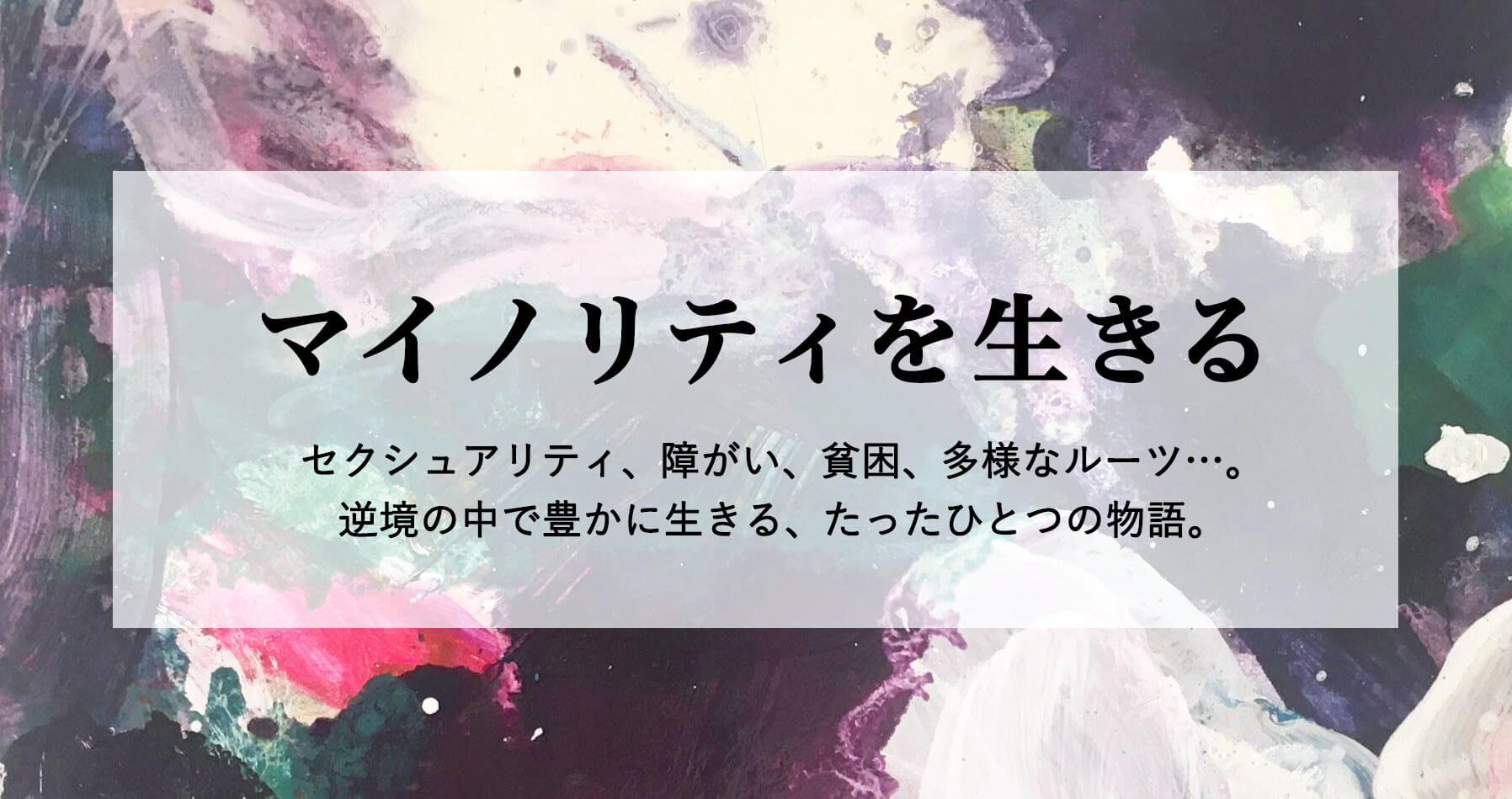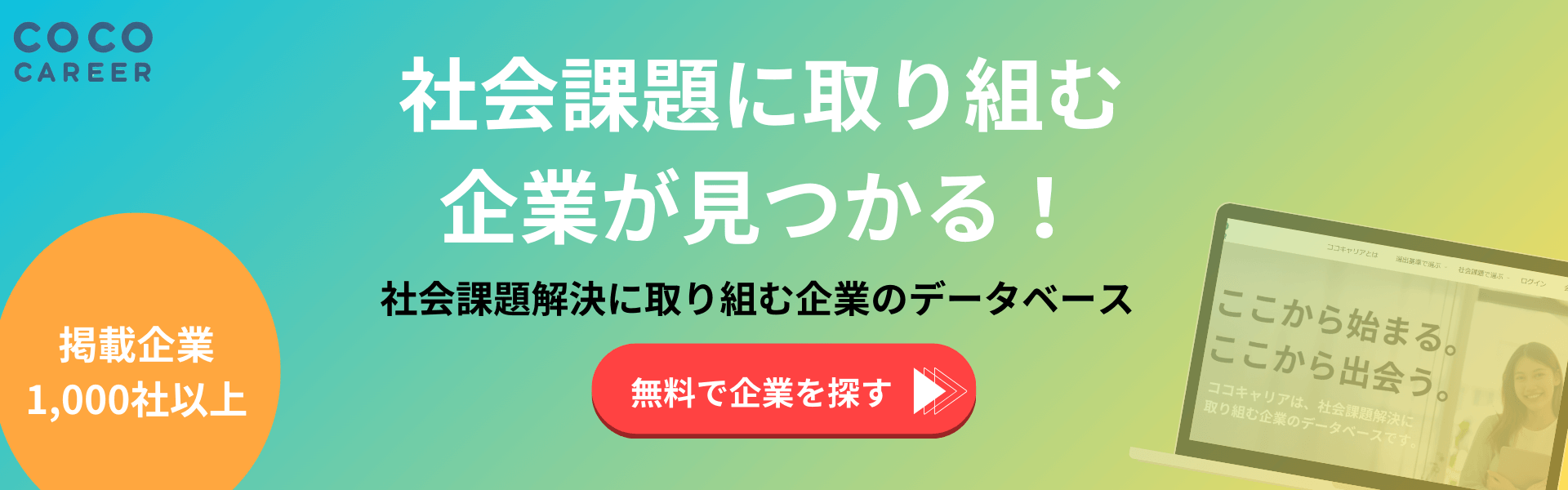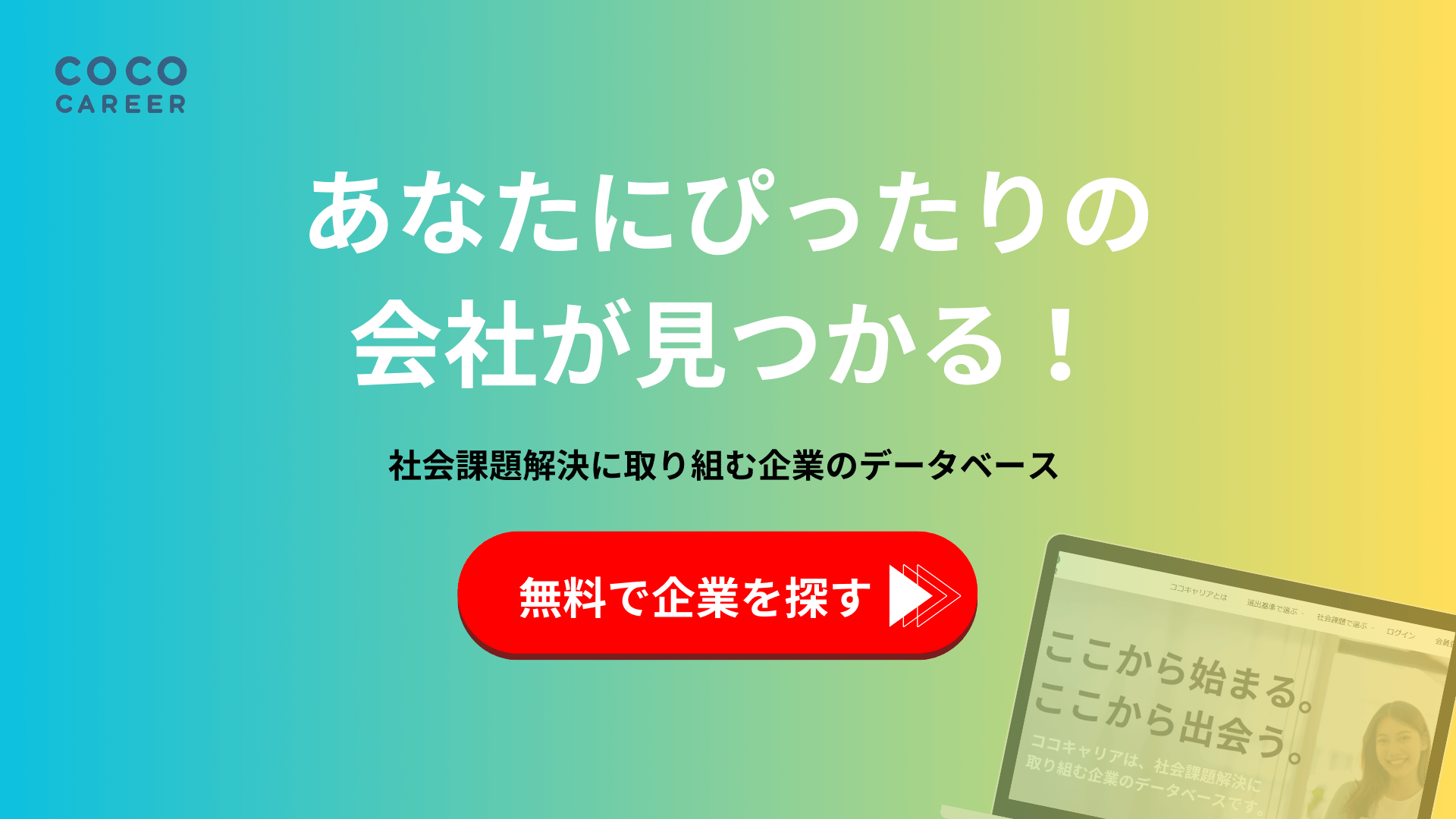「障がいのある子」に対する葛藤

セナは、医師たちが驚くほどのスピードで体重が増え、生後3ヵ月でリコより先に退院した。リコは小さな体で手術に耐え、生後5ヶ月で退院することができた。
退院前の検査でセナの病名が発覚し、退院後もリハビリや治療を続けていた。セナは脳に問題があり、足が突っ張りやすいため、スムーズに歩けるようになることが目標だ。
成長と共に表情が豊かになり、できることも増えていく。リコは、全身を使って意思表示をする。セナは、朝起きると、とびきりの笑顔を見せてくれる。子どもたちはとても可愛く、日々の成長を見るのが楽しみだった。
ただ、自分の子どもたちに「障がい」があるという事実に戸惑いがあった。「命は救われたのだから」と考えても、感情が追いつかない。心のどこかで「セナはきっと喋れるようになる」「自分の子は大丈夫」と信じていたし、障がい者手帳を持つことにもためらいがあった。
周りに「障がい者」だと思われたくない。誰よりも自分が認めたくなかった。これから先、どのくらい病気が改善されるのかも分からない。「できることなら何でもやろう」と、車で約3時間かけて県外の病院に通ったり、鍼灸や漢方を試したりもした。
小学校に入学する頃には、高校卒業後の進路まで考えなくてはならない。サリアは、セナの発達の様子を見て、「大人になっても、軽作業の仕事すら難しいかもしれない」と感じるようになった。
セナが幼い頃は、ニコニコ笑っている穏やかな子だったのに、毎日家で泣きわめいたり、学校で先生を叩いたりすることが増えてきた。同時に、発達遅延の特性を持つリコも、サリアに対して反抗的な態度をとるようになった。
子どもの健康状態や今後の生活を考えると、不安で胸が押しつぶされそうになる。現実が重くのしかかり、逃げられるものなら逃げたかった。
「自分のことは自分でできるようになってほしい。せめてゆっくり寝かせてほしい。家族で穏やかに過ごしたいだけなのに・・・」。そんなつぶやきが、次から次へと溢れ出てくる。
学校から「今日も先生を叩きました」と言われると、セナの特性や困りごとを説明して、頭を下げた。
「あなたなら乗り越えられる」という言葉が辛かった。障がいを持つ子の母親は、本音を言ったらいけないのだろうか。いつも笑顔で、ポジティブでいなくてはいけないのだろうか。
子どもが問題を起こすと、「母親の責任だ」と言われているようで、ますます追い詰められていく。出口の見えないトンネルの中にいるようだった。
視野を広げてくれた福祉施設との出会い

セナが小学校の高学年に上がった頃、18歳以降の進路が具体的に見えてきた。生活介護の事業所に通うのだ。一体、そこはどんな世界なのだろう。
サリアの中では、「身の回りのお世話をしてもらい、単調な日々を過ごすだけ」というイメージだった。きっと学校のような手厚い支援はないし、楽しいイベントも少なく、利用者の意思を汲み取ってくれる優しい人ばかりではないだろう。
「人との交流も少なく、親子だけで孤独に過ごす。それが18歳以降、何十年も続くのか・・・」。そう思うと、目の前が真っ暗になった。
けれどもそのとき、「自分は実際の現場を知らない」という思いも出てきた。
同じ頃、小学校で開かれた事業所説明会で、少し変わった施設に出会った。話を聞くと、生活介護の利用者でも仕事をさせてもらえるらしい。さらに、お菓子や雑貨を作ってただ売るのではなく、デザインも魅力的な商品作りをしているのだそう。そこでは、利用者のことを「仲間」と呼んでいた。
「仲間たちには、障害年金だけでなく、働いた成果としてのお給料を渡したいんです」。職員の話を聞いて、1人の人として尊重してくれる場所なのだと感じた。
しばらく経ったある日、何気なく求人情報を見ていると、その施設の求人広告が目に入った。無資格でも応募できる仕事があったので、早速問い合わせをして面接へ。前職を辞めるまで待ってもらい、トントン拍子にその施設で働くことが決まった。
未経験で不安もあったが、「やってみてダメだったら、そのとき考えればいい」という気持ちで飛びこんだ。実際に経験してみると、楽しいことのほうが多く、毎日が刺激的で勉強になることも多い。サリアにとってはいい選択だった。
施設には、イライラしたりパニックになったりして職員を叩く仲間もいる。
自分の気持ちをうまく表現できず、周りに理解してもらえない。そのもどかしさが、怒りや悲しみとなり、感情が爆発して手を出してしまうのだ。
「きっと、セナやリコもそうなんだ。うまく伝えられないだけで、何かに困っているのかも・・・」。その気づきから、子どもたちを1人の人間として客観的に見るようになっていった。
職員になる前は「セナが周りに迷惑をかけてばかり」と、申し訳ない気持ちでいっぱいだった。しかし、実際に働き始めてからは、「叩かれたら痛いけど、それだけで仲間のことを嫌いになるわけじゃない」と思った。
特性は人によって違うけれど、わがままも愛らしさも持ち合わせた、自分と同じ人間だ。
「本当は私が偏見を持っていただけだったんだ・・・」。
施設で働くうちに、目の前の景色が広がっていった。