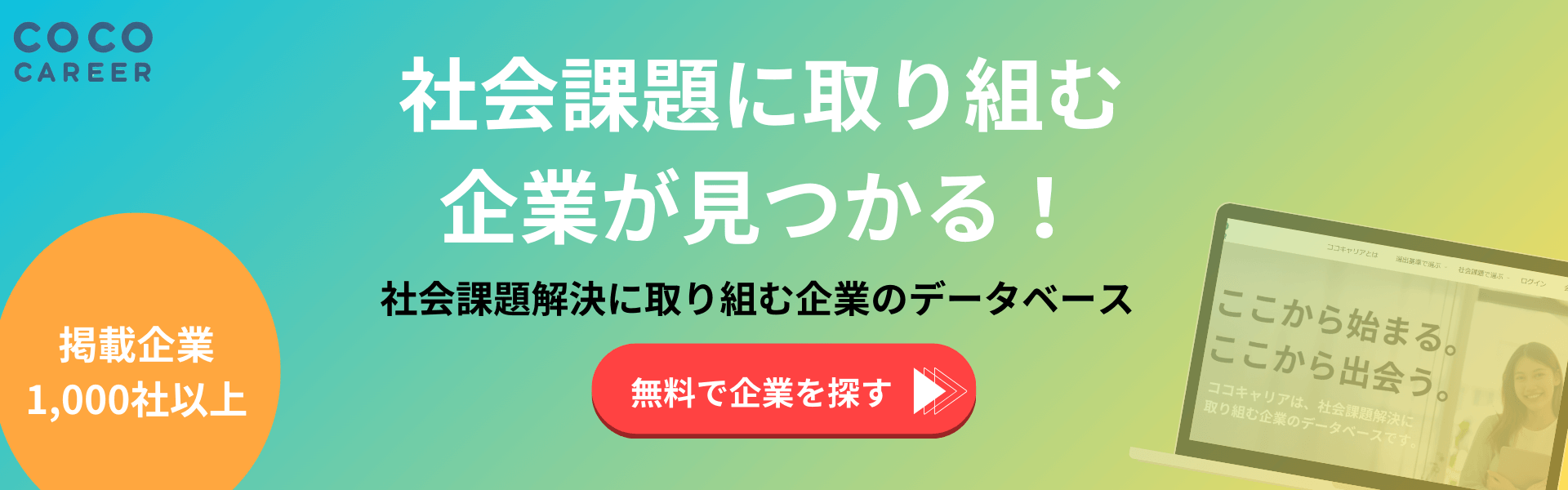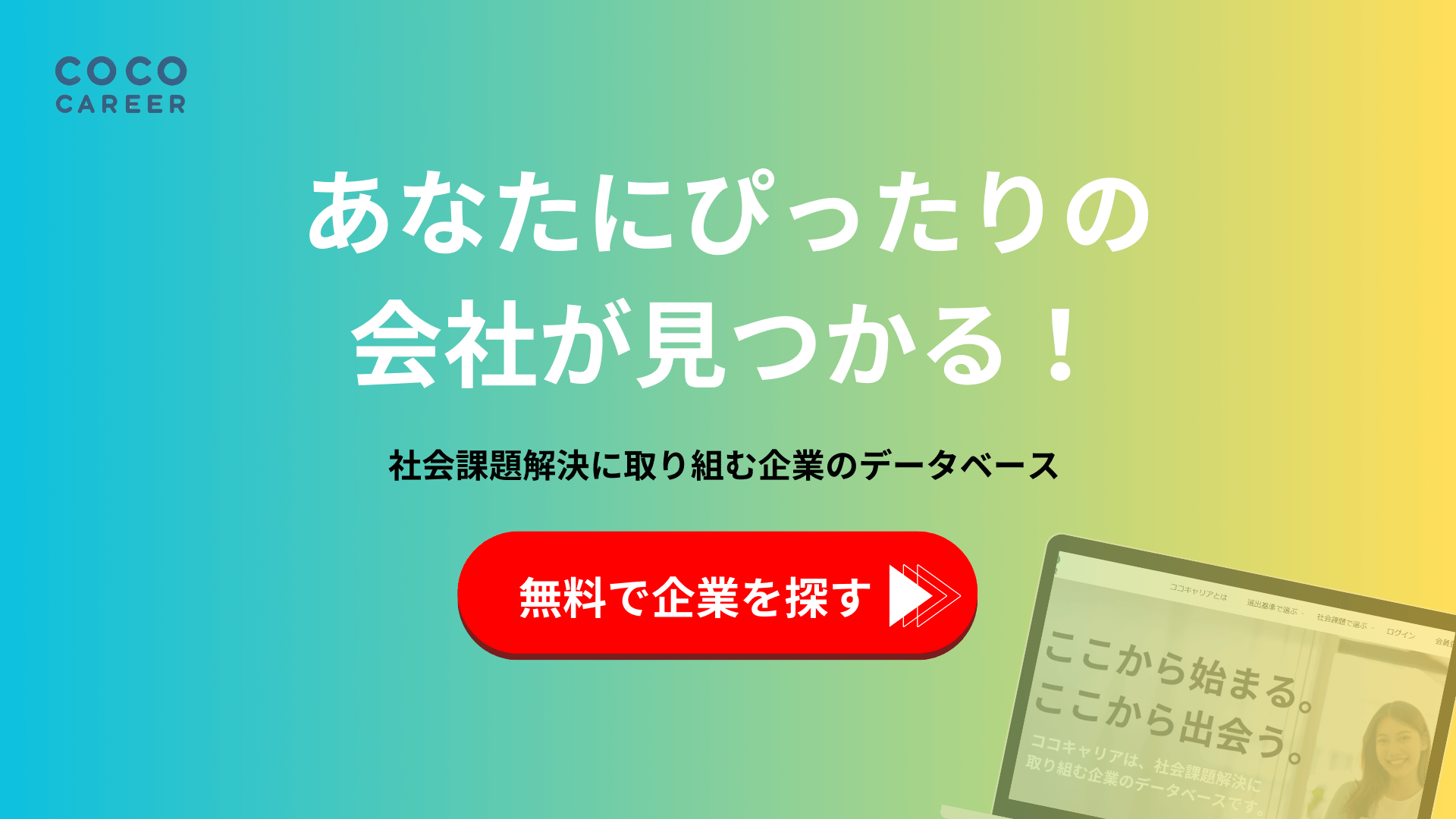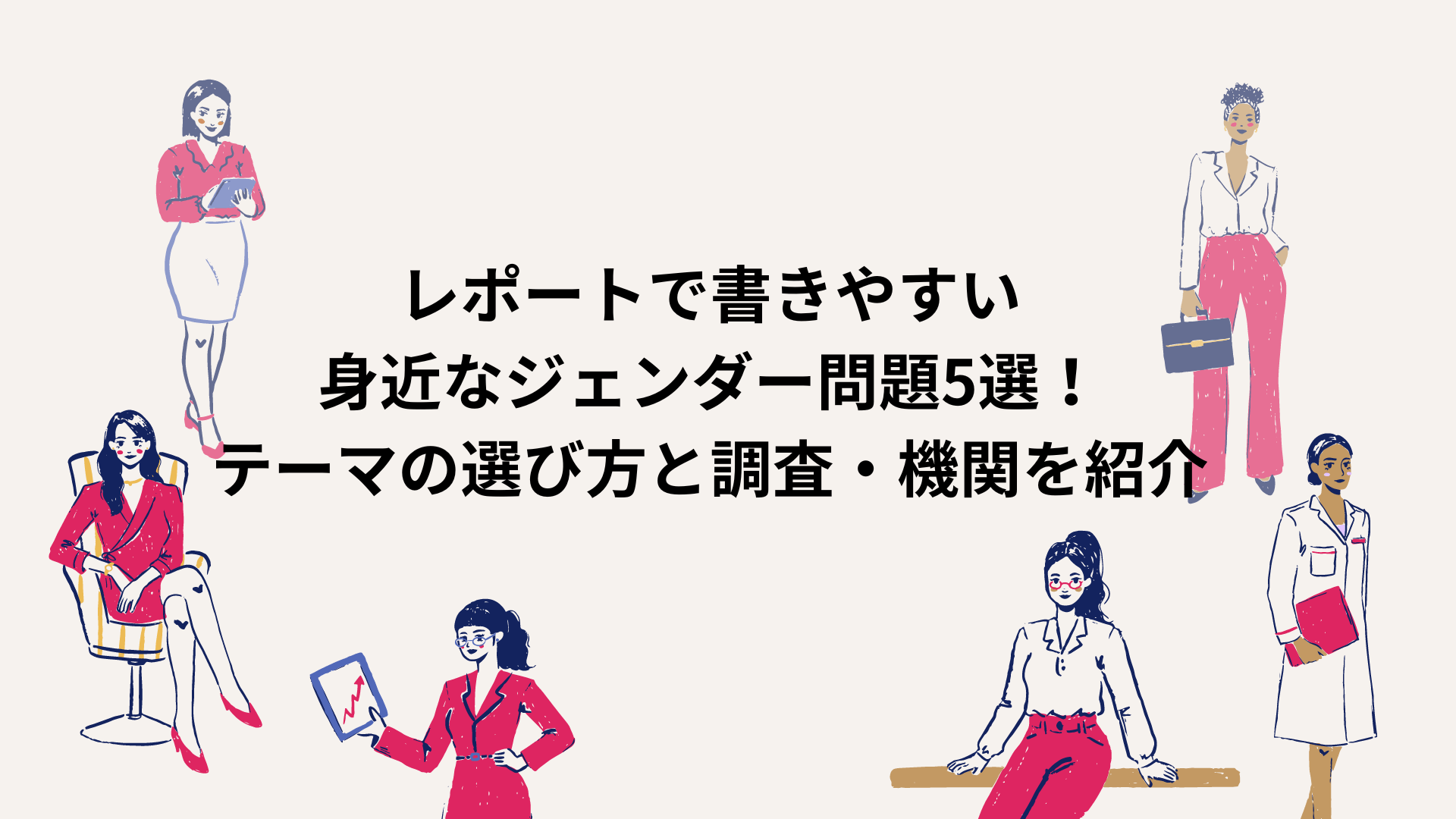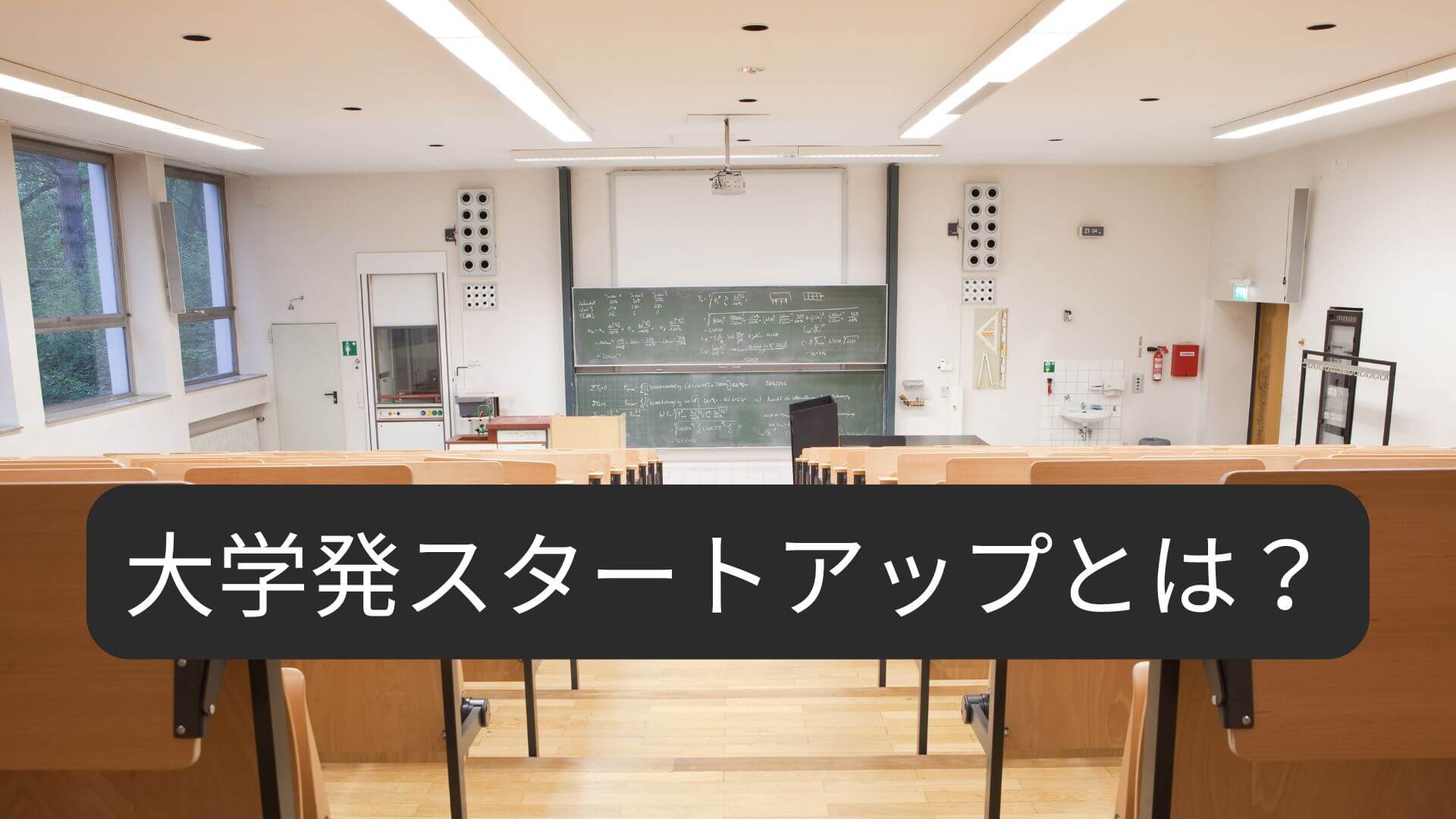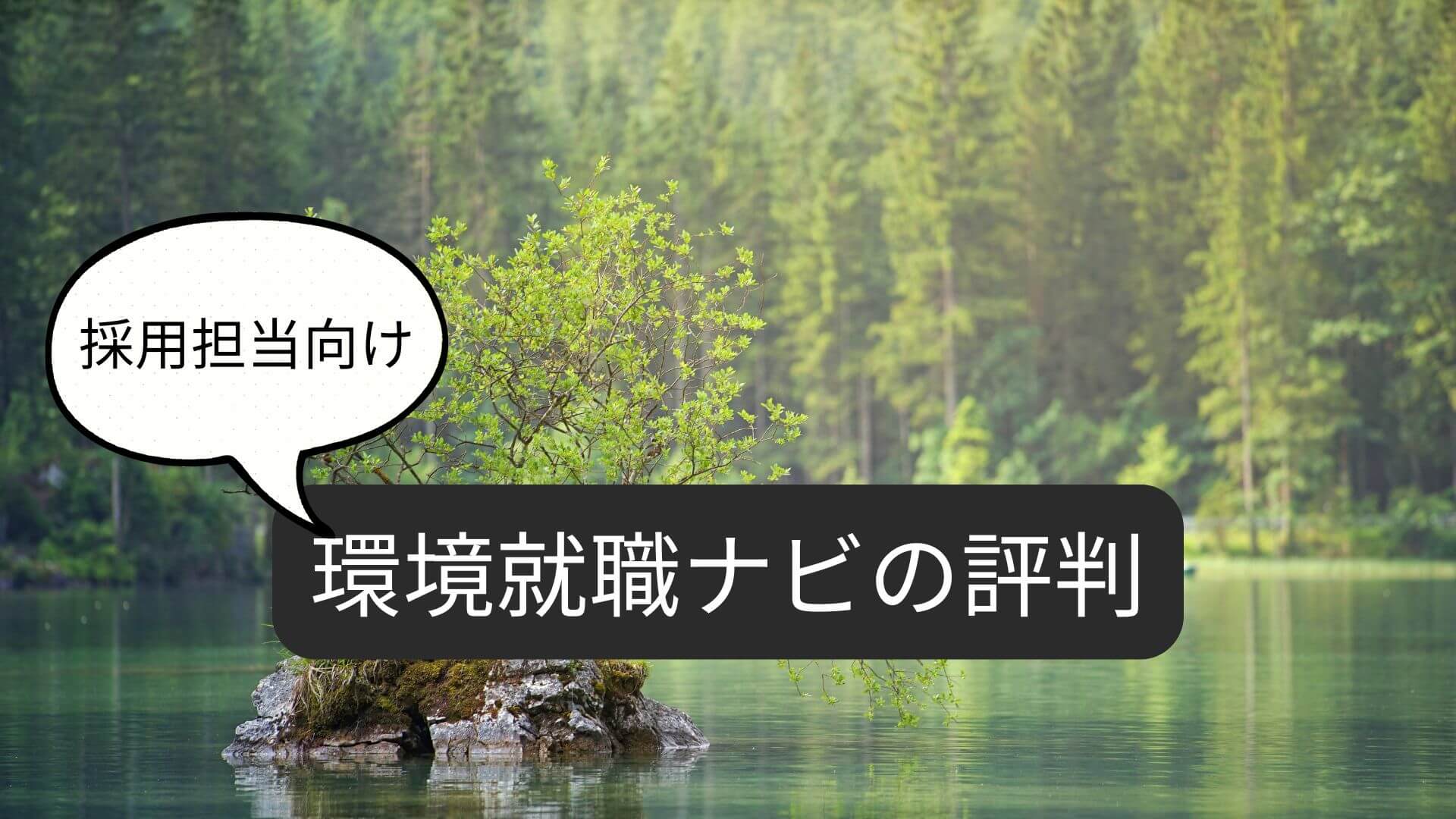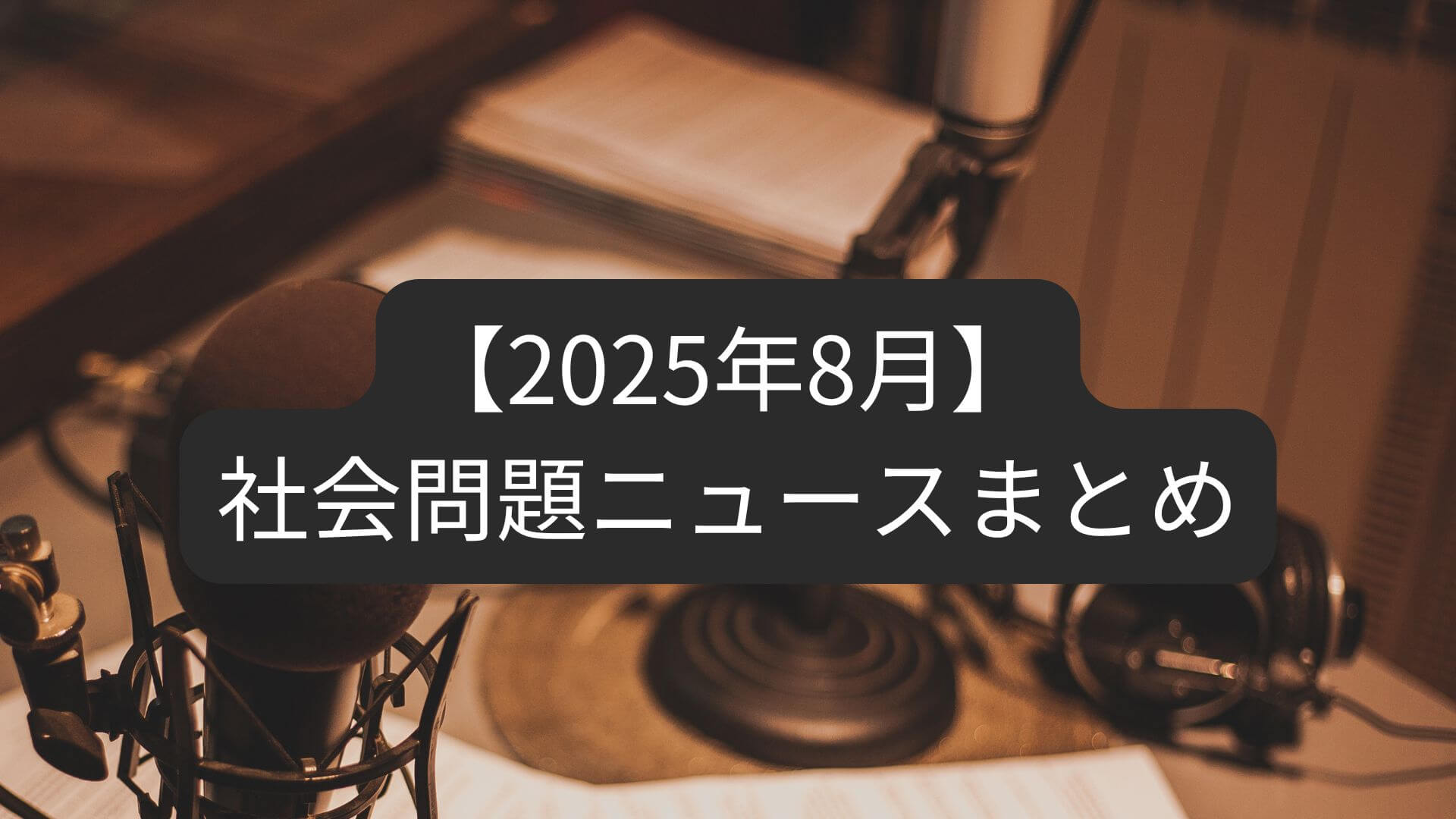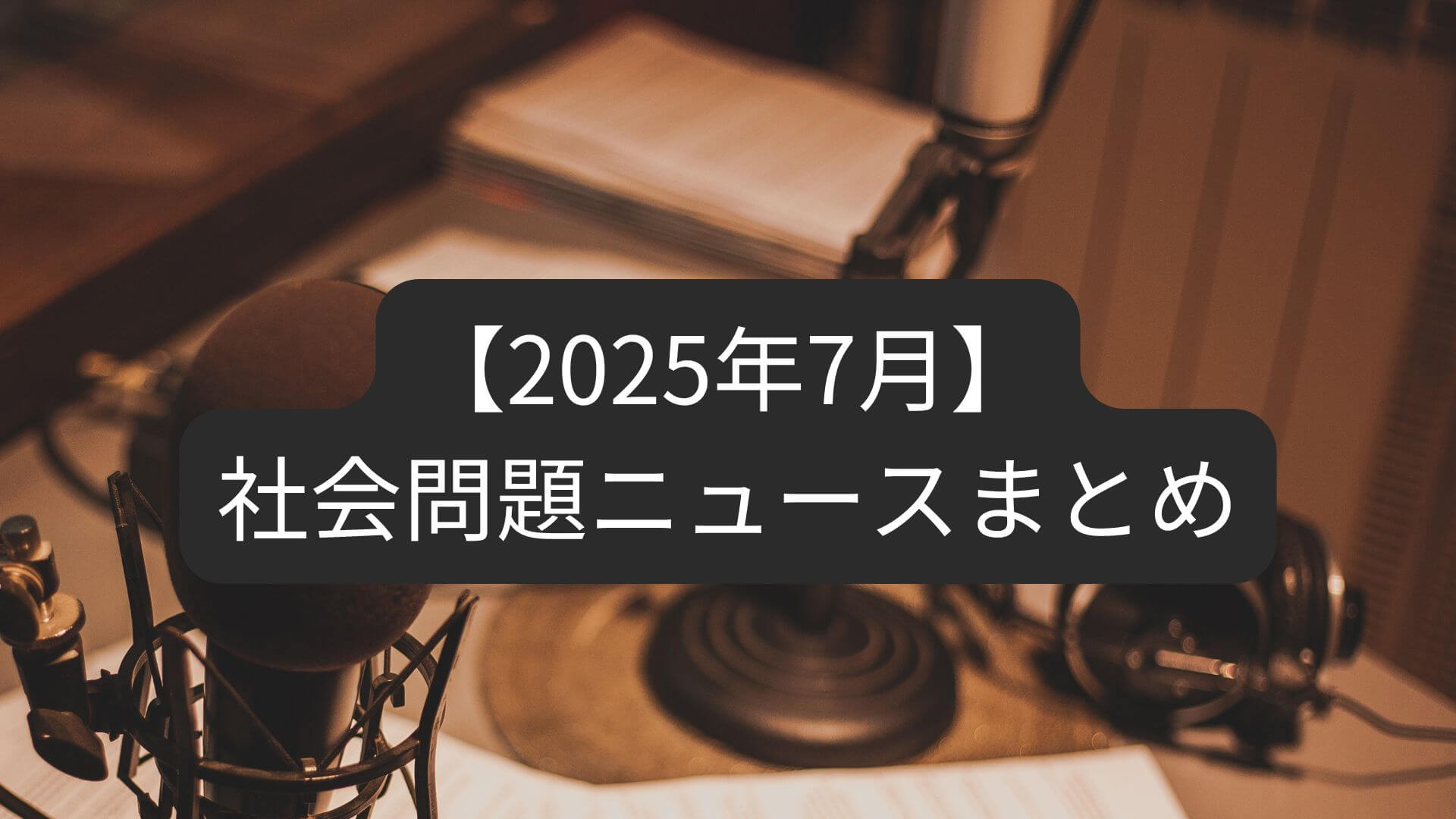皆さんが日々食べている農作物の多くについて、農家の手元から食卓に並ぶまでのプロセスを想像したことがありますか?
ご存知の通り、農家は、皆さんの食卓に並ぶまでに加工、流通、販売などのさまざまなプロセスを経なければなりません。。
もっと言えば、農業には、農家が生産中、もしくは生産前から多くの人たちが関わっています。
例えば、農業機械の製造や品種改良研究などが挙げられます。
このように農業に関するビジネスをまとめてアグリビジネスと言います。
この記事では、アグリビジネスと将来の展望について解説します。
アグリビジネスとは

アグリビジネスはAgriculture (農業)にbusiness(ビジネス)を合わせた言葉で、農業に関連する産業をまとめて捉える用語です。
農業と言っても生産という第一次産業だけでなく、製造業の第二次産業とサービス業の第三次産業まであります。
日本においては、課題も多い農業をいわゆる農家だけのものとして捉えるのではなく、他の産業と繋げて取り組んでゆくものになります。
アグリビジネスが注目されている理由

アグリビジネスは意外にも古い概念で1960年代以前にはアメリカですでに提唱されていました。
しかし、現在注目されている理由はなんでしょうか。
その理由は、日本の農業の持続可能性が危ぶまれており、農業がもつさまざまな役割が失われているためです。
まず、日本の食料自給率は、カロリーベースで令和5年度時点で約38%でした。(日本の食料自給率:農林水産省)
つまり、日本はみなさんが食べる食事の約60%を海外に頼っていることになります。
それに加えて、日本の基幹的農業従事者の平均年齢は、67.8歳となっており、多くがリタイアを控えています。
なお、基幹的農業従事者とは、農業就業人口のうち、普段仕事として農業を行なっている人たちのことを言います。
このように、将来的に農業が衰退していくと、私たちの食に影響が出るのはもちろんですが、カーボンストックや生き物の住み家としての営農地が失われるかもしれません。
そこで、今までの様に個人事業者の農家だけでなく、企業などの参入もあり、より広い範囲で農業を行う意味で注目されています。
アグリビジネスの基本的な構造と実例

アグリビジネスの基本的な構造と実例について解説します。
生産
生産の段階では言うまでもなく、農家が中心となっていますが、企業が生産や新規参入農家の支援を行なっていることがあります。
特に、農地中間管理機構を設けることで、遊休農地等も含めて区画整理を行い、農地の集積化を進めています。
これにより、大規模経営が可能になり、効率よく農業を進めることができるようになるでしょう。
さらに、生産に使われる農業機械や肥料の製造、病気や災害に強い作物を作るために品種改良を行うという研究的な仕事もあります。
加工
もちろん、加工をせずにそのまま流通に乗る野菜や果物もありますが、加工をされる農産物もあります。
また、加工によってフードロスを削減できる点も注目すべきです。
例えば米粉については形やサイズが悪く、廃棄される予定だった米を粉砕し、製造されることもあります。
フードロスとは?削減するために私たちができること | COCOCOLOR EARTH
流通
もちろん国内向けの製品が多くを占めていることは事実ですが、国内市場は成熟しているため海外に輸出されることもあります。
事実、2023年は農産品輸出額が過去最高でした。
海外の市場、比較的近隣で人口も多いアジア市場への輸出が多く、輸出先上位10カ国のうち8カ国はアジアの国でした。
また、アメリカへの輸出も緑茶を中心に回復傾向にあります。
海外に目を向ける一方で、地産地消や直売所を通じて地域の人たちに農作物を販売する取り組みも行われています。
それにより、フードマイレージと呼ばれる輸送距離が減るためコストカットになるだけでなく地域の活性化につながるというのもメリットです。
関連記事
≫ 地産地消のメリット5選!デメリットやSDGs・6次産業との関係も解説
販売
皆さんもよく利用しているであろう、スーパーや直売所だけが販売のチャネルではありません。
例えば、飲食店やホテルで旅行者に地域の食を体験してもらう方法もあります。
筆者が個人的に面白いと思ったのは日本航空(JAL)が成田空港近くで経営している御料鶴というレストランです。
このレストランでは、千葉県内の契約農家や自社農園で採れた作物を古民家で提供しています。
航空会社という全く違う業界の企業が自社農園を経営し、旅行者に味わってもらうというのはとても面白い取り組みだと思いました。
さらに、マーケティングとして農地をブランド化する取り組みもあります。
有名なのは魚沼産のコシヒカリですが、地名と高品質な農産物を結びつけ、販売量の増加を目指す取り組みもあります。
動画でアグリビジネスを知る
動画でもアグリビジネスを紹介しています。
まとめ

アグリビジネスでは農業を盛り上げるために色々なセクターが関わり合っていることがお分かりいただけたでしょうか?
個人的に今後さらに普及すると考えているのは、スマート農業という取り組みです。
スマート農業とはドローンやセンサーのデータを解析し農業に活かすという、いわばデータサイエンスによる農業支援です。
その一方で、このような取り組みが行われているにもかかわらず、農業に課題が多いのも確かです。
例えば、上で触れた高齢化以外にも外来生物も含めた害獣や災害による被害もあります。
既存の取り組みだけでなく、生産の段階でいかにロスを減らしていくかという部分に主眼が置かれていくかもしれません。
関連記事
≫日本の環境問題7選!47都道府県の取り組みや私たちにできること | COCOCOLOR EARTH
≫災害・防災に取り組む企業10選!就職・転職におすすめのベンチャーから大手企業 | COCOCOLOR EARTH

この記事の監修者
吉田宏輝
COCOCOLOREARTH代表、社会活動家。
COCOCOLOREARTHでは、社会課題解決を軸にした就職・転職活動を支援するインタビューメディアの代表として、100人以上の社会活動家にインタビュー、記事執筆やイベント登壇などを行う。