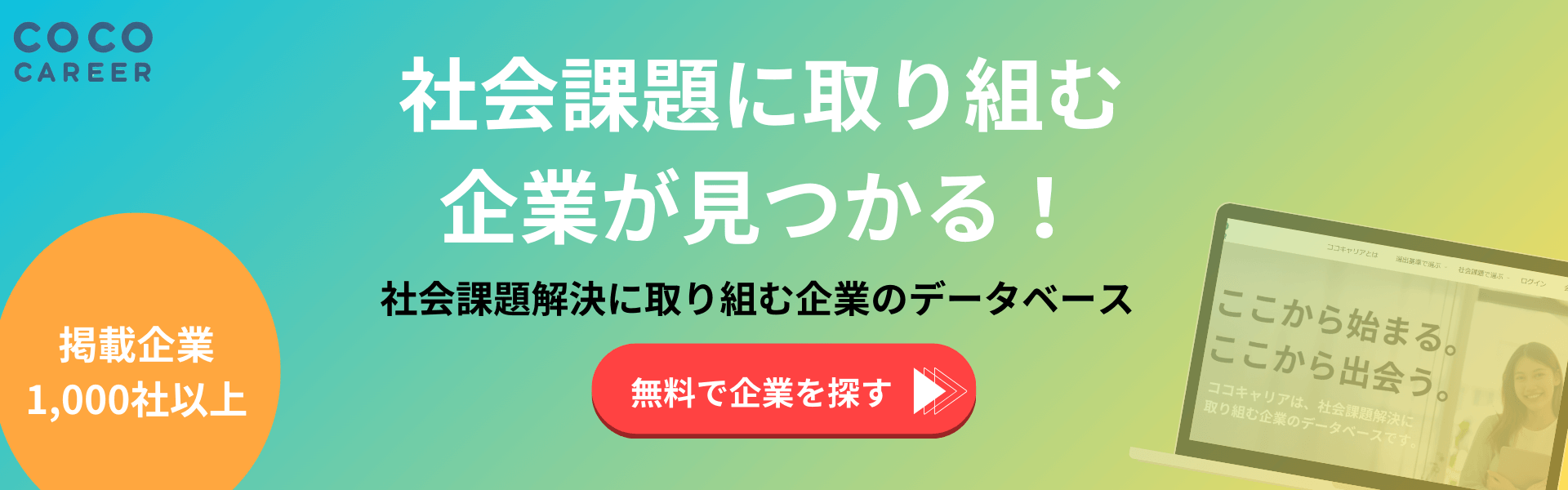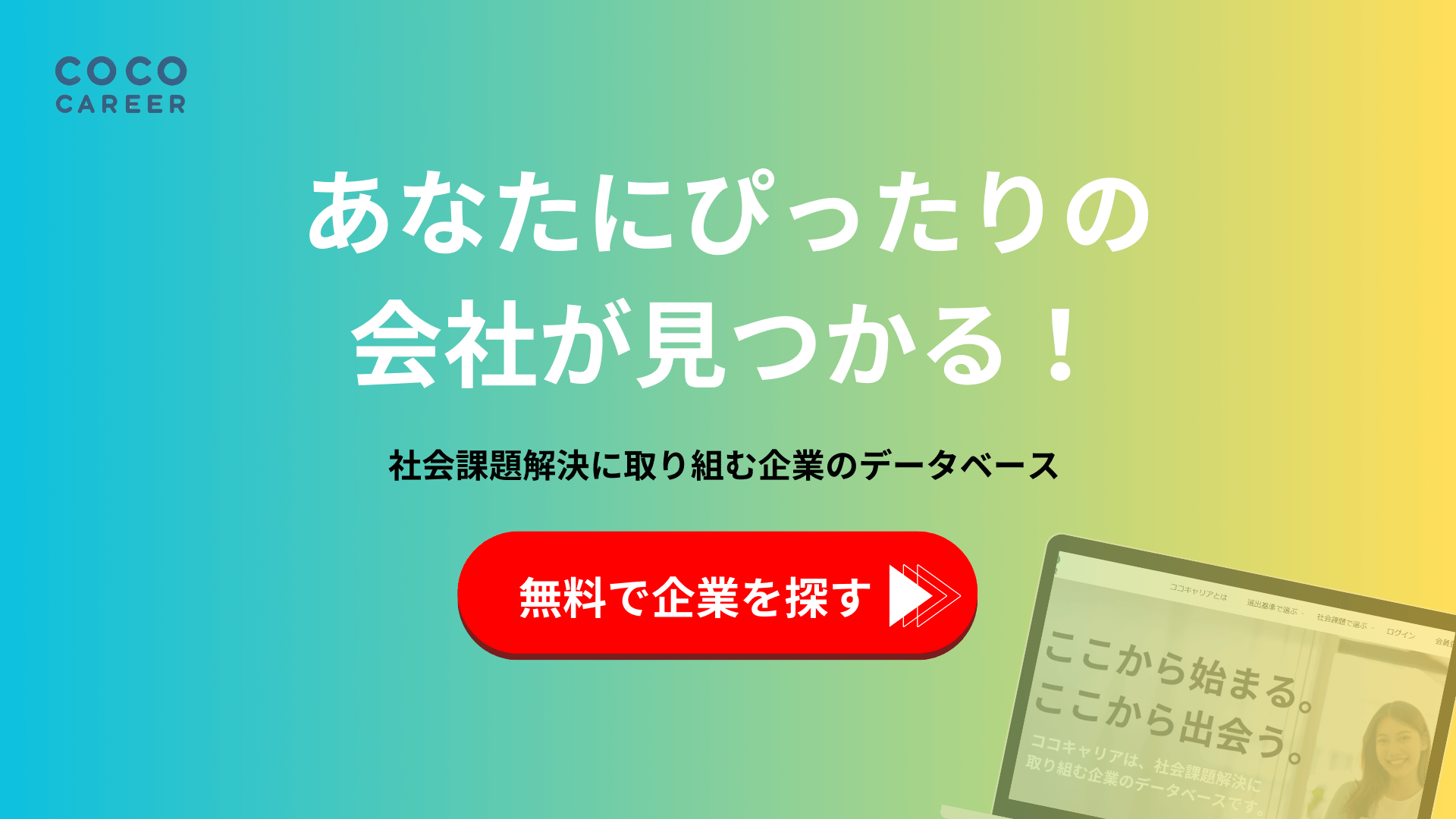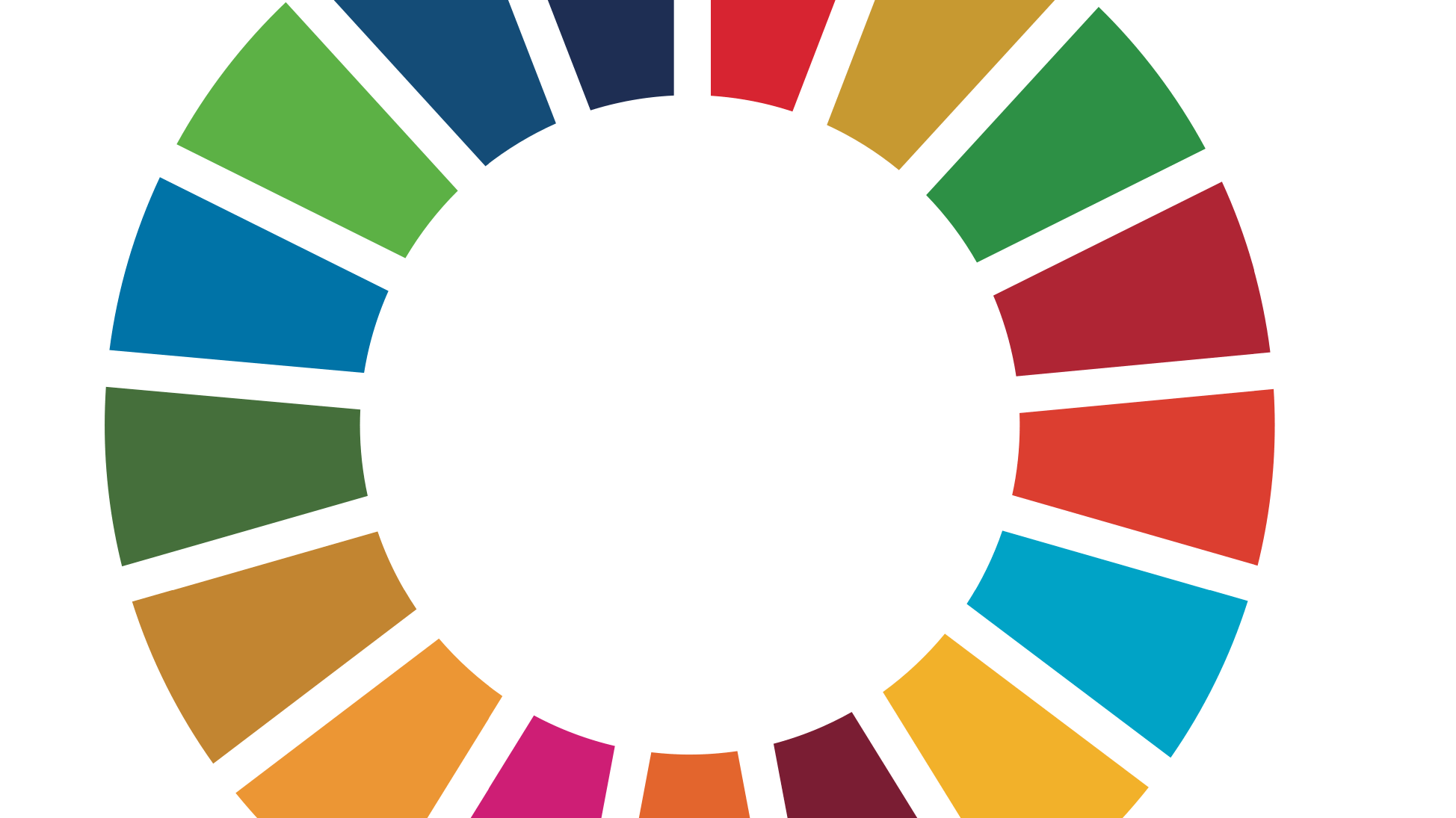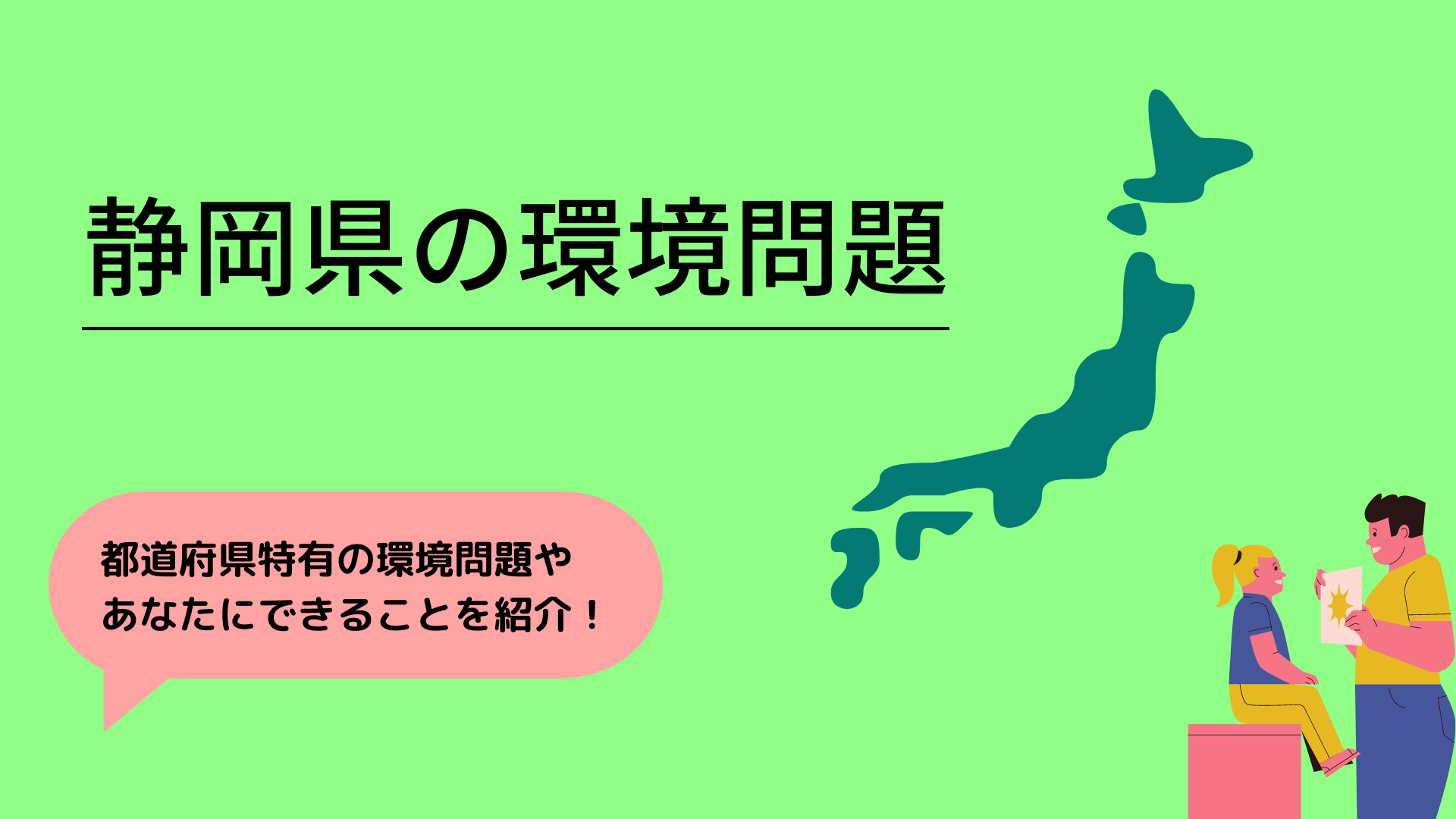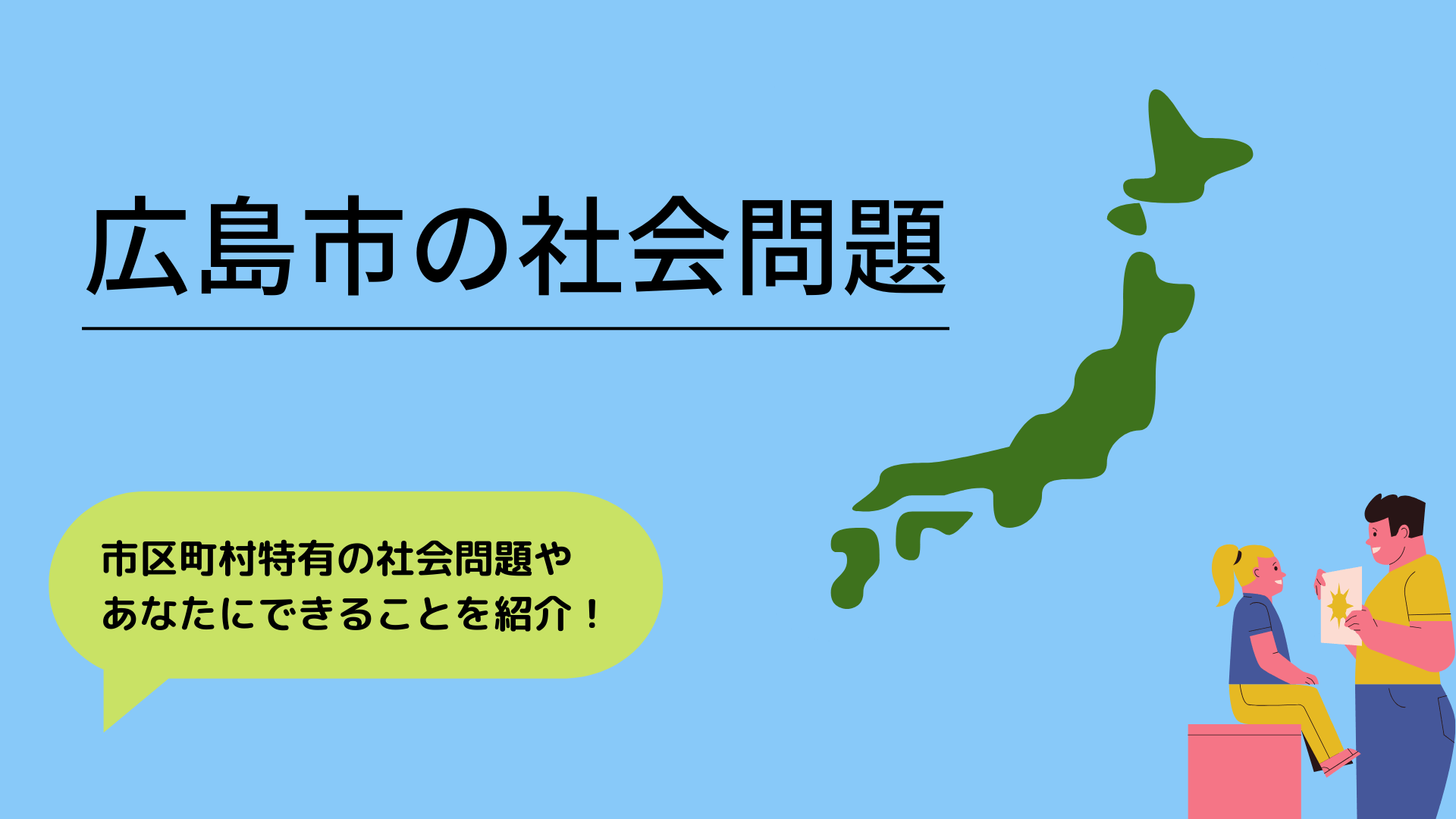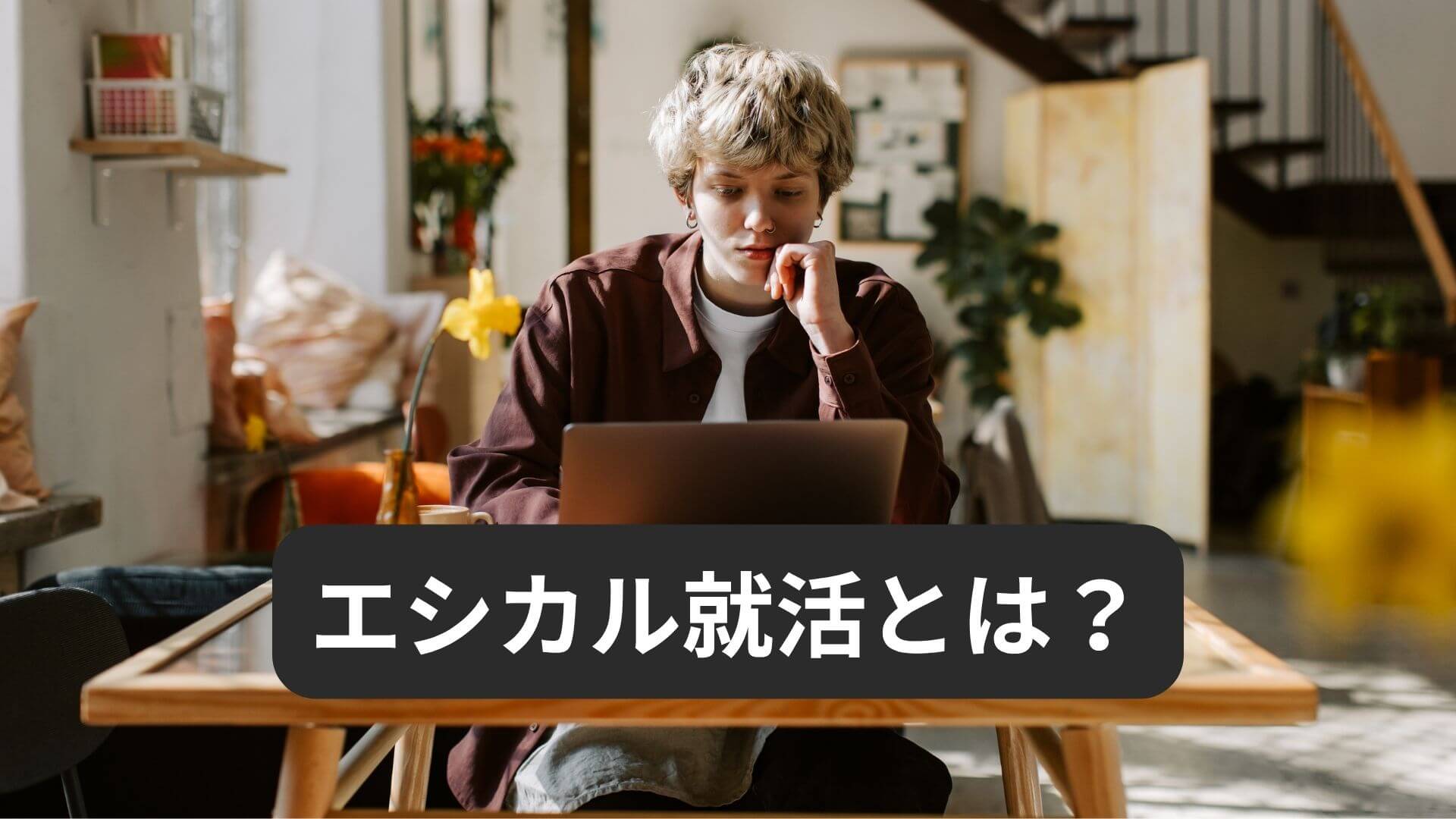現代社会において、「ジェンダー」という言葉は多様な文脈で使用され、様々な議論の中心になっています。
ジェンダーは単に性別を指すのではなく、社会的・文化的に形成される性の役割やアイデンティティについて言及するものです。
そして、このジェンダーの概念は、競争と公平性が重んじられるスポーツの世界においても無視できない問題です。
スポーツにおけるジェンダーの問題は、賞金の格差から、競技のルール、さらにはマネージャーの役割に至るまで多岐にわたります。
本記事では、これらのジェンダーに関連する問題について詳しく解説します。
※【企業様向け】スポーツ又はジェンダーへの取り組みをPRしませんか?
掲載を希望する企業様はこちらをご覧ください
目次
ジェンダーとは

まず、『ジェンダー』という言葉について説明します。
ジェンダーとは、生物学的な性別に対して、社会的・文化的に構築された性差の概念です。
具体的には、「男性は稼いで女性は家事をするべき」という考えや、「男の子はヒーロー、女の子はプリンセスが好き」というステレオタイプなどです。
関連記事
≫ステレオタイプとは?バイアスとの違いや事例、メリット・デメリットを解説
スポーツにおけるジェンダーの問題
スポーツにおけるジェンダーの問題を5つ紹介します。
- 賞金に関する格差
- 距離やセット数に関する格差
- トランスジェンダー選手への対応
- 甲子園のマネージャー問題
- 体育におけるジェンダー問題
スポーツ業界のジェンダー格差問題

賞金に関する格差
賞金に関するジェンダー格差は古くからありました。
格差は近年も残っており、例えば、2018年のサッカー男子ワールドカップの優勝賞金は約 430億円だったのに対し、2019年のサッカー女子ワールドカップの優勝賞金は約32億 5千万円にとどまります。
FIFA のジャンニ・インファンティーノ会長は、2023年に開かれる次の女子ワールドカップでは賞金を倍にすると表明しました。
しかし、同額にはほど遠いものとなっています。
また、テニスの四大大会では、2007年のウィンブルドンを最後に、男女の賞金格差はなくなりました。
この背景には、賞金格差をはじめとする女性差別を訴えたビリー・ジーン・キングの功績が大きく関係しています。
距離やセット数に関する格差
距離やセット数でジェンダー格差があります。
例えば、マラソンでは、女性が42.195キロを走ることは難しいだろうという前提がありました。
そのため、1984年のロサンゼルスオリンピックまで女子マラソンはオリンピック種目として存在しなかったのです。
参考:女性スポーツ選手の賞金額が男性よりも少ない理由
トランスジェンダー選手への対応

2021年に行われた東京オリンピックでは、重量挙げ女子87キロ超級のニュージーランド代表に、トランスジェンダーのローレル・ハバード選手が出場しました。
トランスジェンダーであることを公表する選手が自認する性別のカテゴリーで出場する史上初の大会となりました。
ずっと以前からトランスジェンダー選手はいましたが、東京オリンピックを機に注目が集まりました。
トランスジェンダー選手を「不公平」と排除せず 競技ごとに論議することがスタートしています。
甲子園のマネージャー問題

2016年に行われた甲子園でマネージャー問題が注目を集めました。
グラウンドに出てノックのボール渡しなどの練習を手伝っていた大分高校の女子マネジャーを、大会関係者が慌てて制止しました。
大会規定では、安全面を考慮して「練習補助員は男子部員に限る」と定められていることが理由です。
この対応に、時代錯誤の声が多く集まりました。
このような流れを受けて、2021年の高校女子野球の選手権大会決勝が甲子園球場で開催されたことは大きな変化です。
体育におけるジェンダー問題

学校の体育でも、ジェンダーの問題が見られます。
男女が分かれて授業を行っていたり、取り組む競技が違ったりする学校はいまだ多く残っています。
体育の授業でのパフォーマンスはジェンダー差よりも経験差が大きいと言われており、男女で分ける必要があるのか再考する必要があります。
また、部活動についても女子のみ・男子のみが入部できるものも少なくなく、ジェンダーの問題があると言えるでしょう。
関連記事
≫#MeToo運動とは?きっかけやセクハラや性被害に対する日本や韓国での告発を解説
ジェンダーバイアスにも気を付けよう!

ジェンダーバイアスとは、社会的・文化的な意味での性差に対する固定概念や偏見です。
スポーツの他にも、私たちの身近には、気づかないうちに潜んでいるジェンダーバイアスが数多く存在します。
「女はこうあるべき」
「男はこうあるべき」
これらが重視されるせいで、生きづらさを感じている人が大勢いるのです。
ジェンダーバイアスは、その人らしさを否定して個人の可能性を狭め、自由を奪う原因になります。
そして、私たちは、「女らしさ」「男らしさ」を知らないうちに自分にも他人にも求めてしまうことがあります。
家や学校、職場。あらゆるところにジェンダーバイアスが潜んでいるのが日本社会の現状です。
まずはそのジェンダーバイアスに気づくことが重要だと思います。
関連記事
≫あなたは大丈夫?日本社会に潜む無意識のジェンダーバイアスとは
≫ジェンダーの問題に取り組む企業10選~ベンチャーから大企業まで~
まとめ
スポーツ業界は、上記のようにジェンダー格差も存在しますが、人々に感動や交流、健康をもたらしたりするなど魅力的な環境でもあります。
あなたがもし、こういったジェンダー格差に問題意識があるのなら、情報を発信したり、その業界に就職し、業界を内側から変えていくこともできます。
ぜひ自分なりの取り組み方を探してみてください。
【企業様向け】スポーツ又はジェンダーの問題への取り組みをPRしませんか?

この記事の監修者
吉田宏輝
COCOCOLOREARTH代表、社会活動家。
COCOCOLOREARTHでは、社会課題解決を軸にした就職・転職活動を支援するインタビューメディアの代表として、100人以上の社会活動家にインタビュー、記事執筆やイベント登壇などを行う。