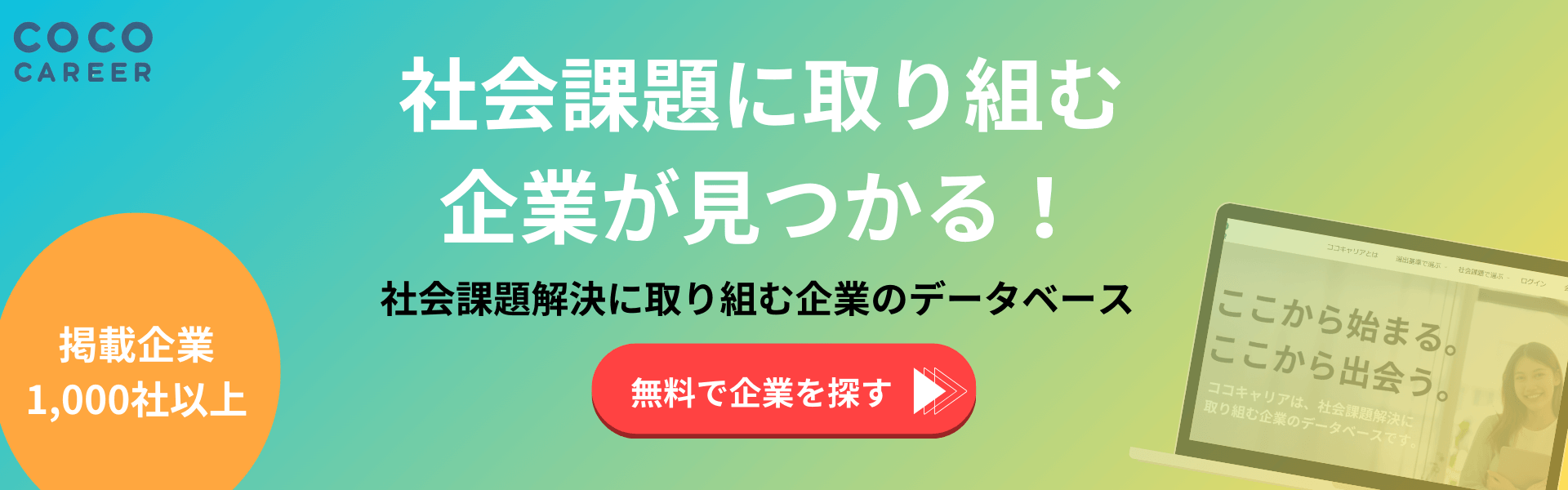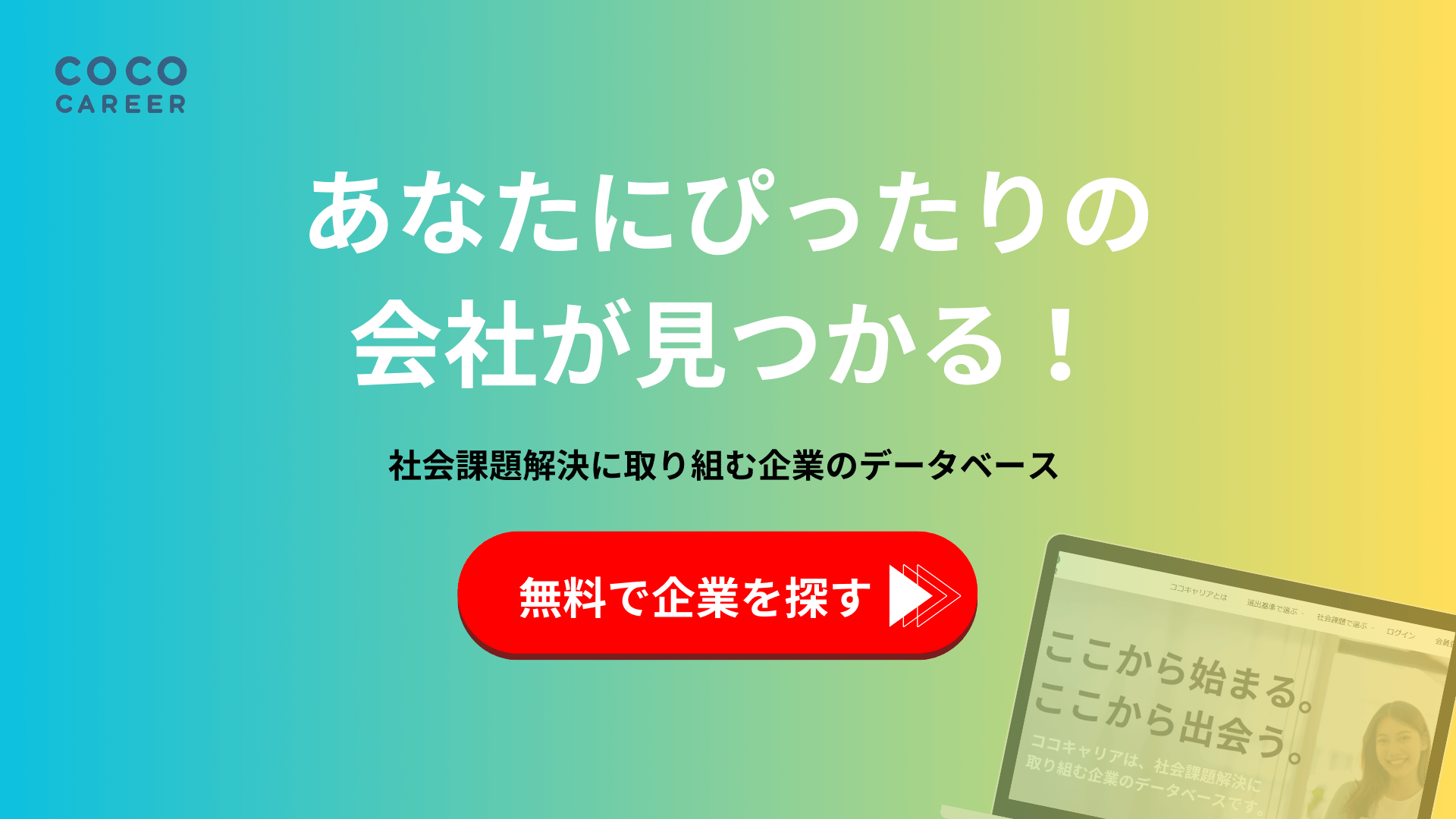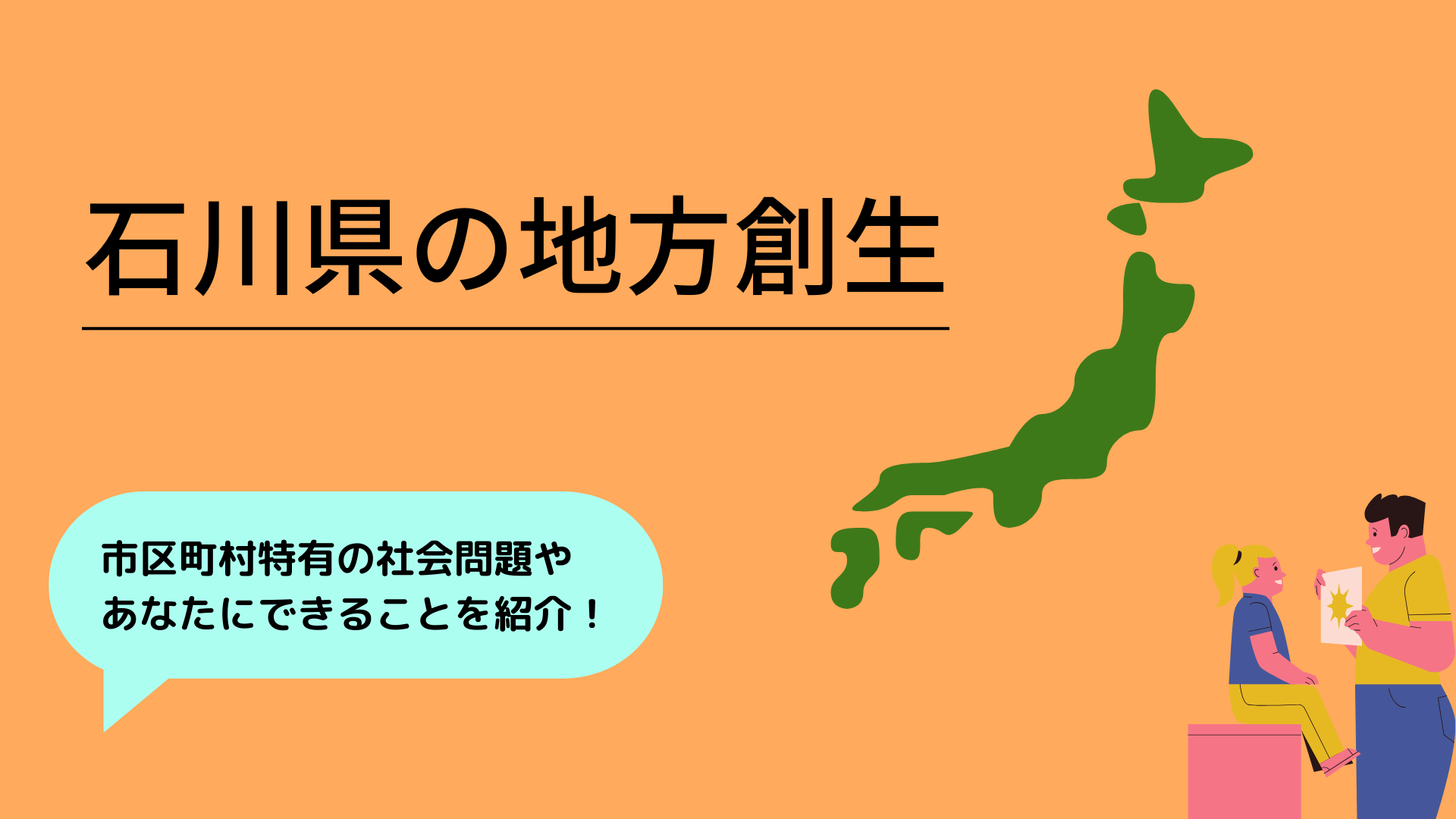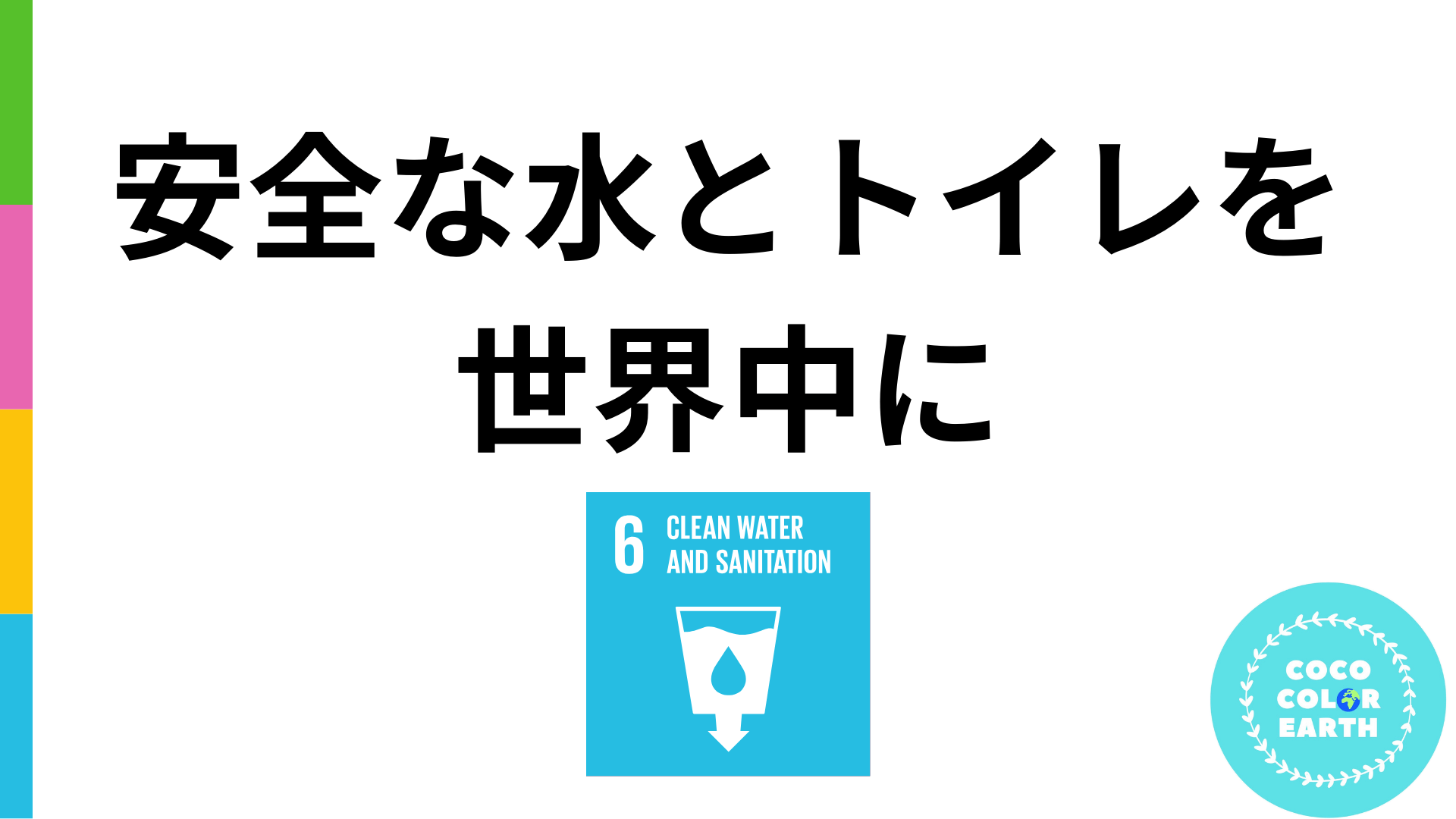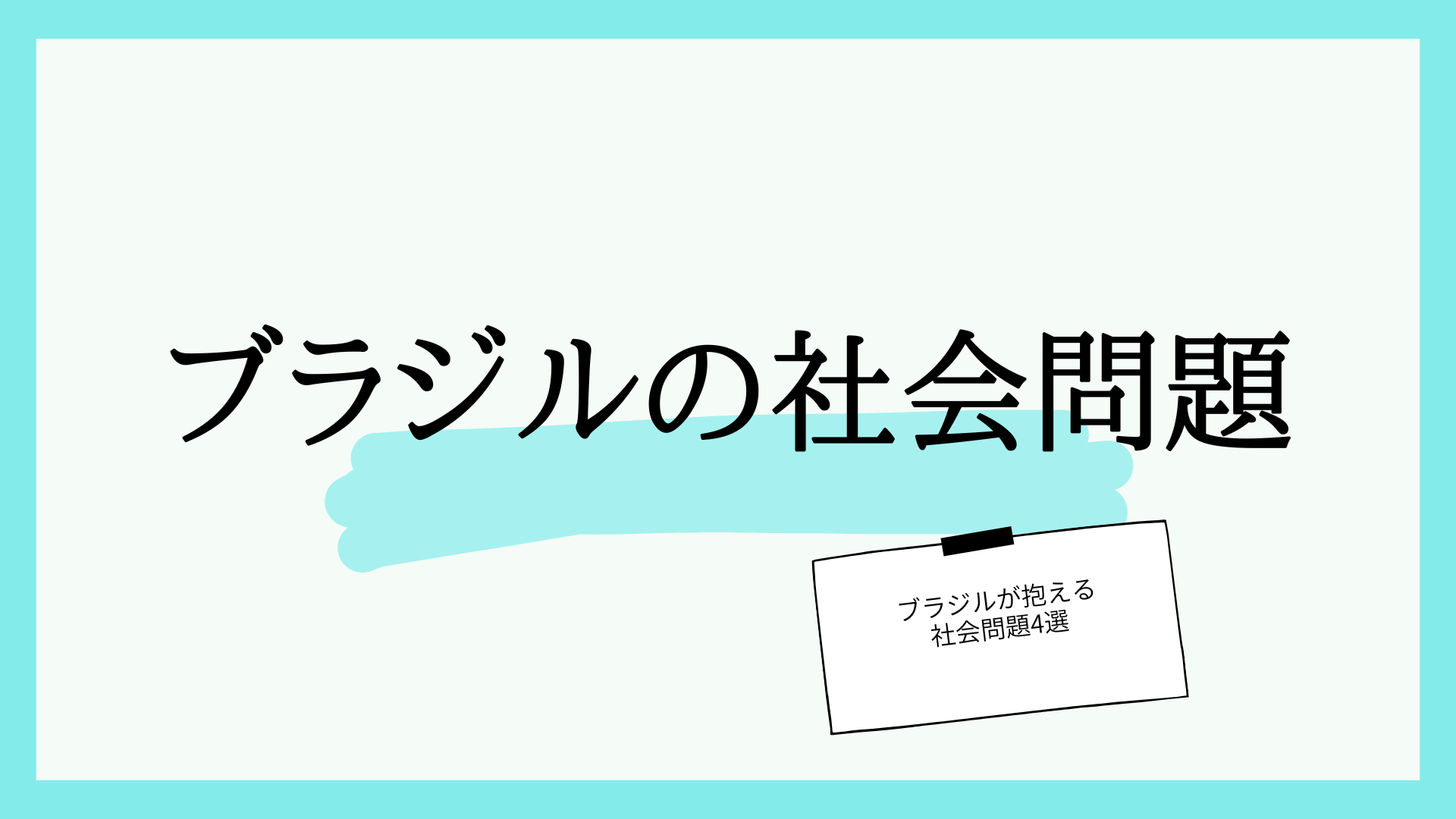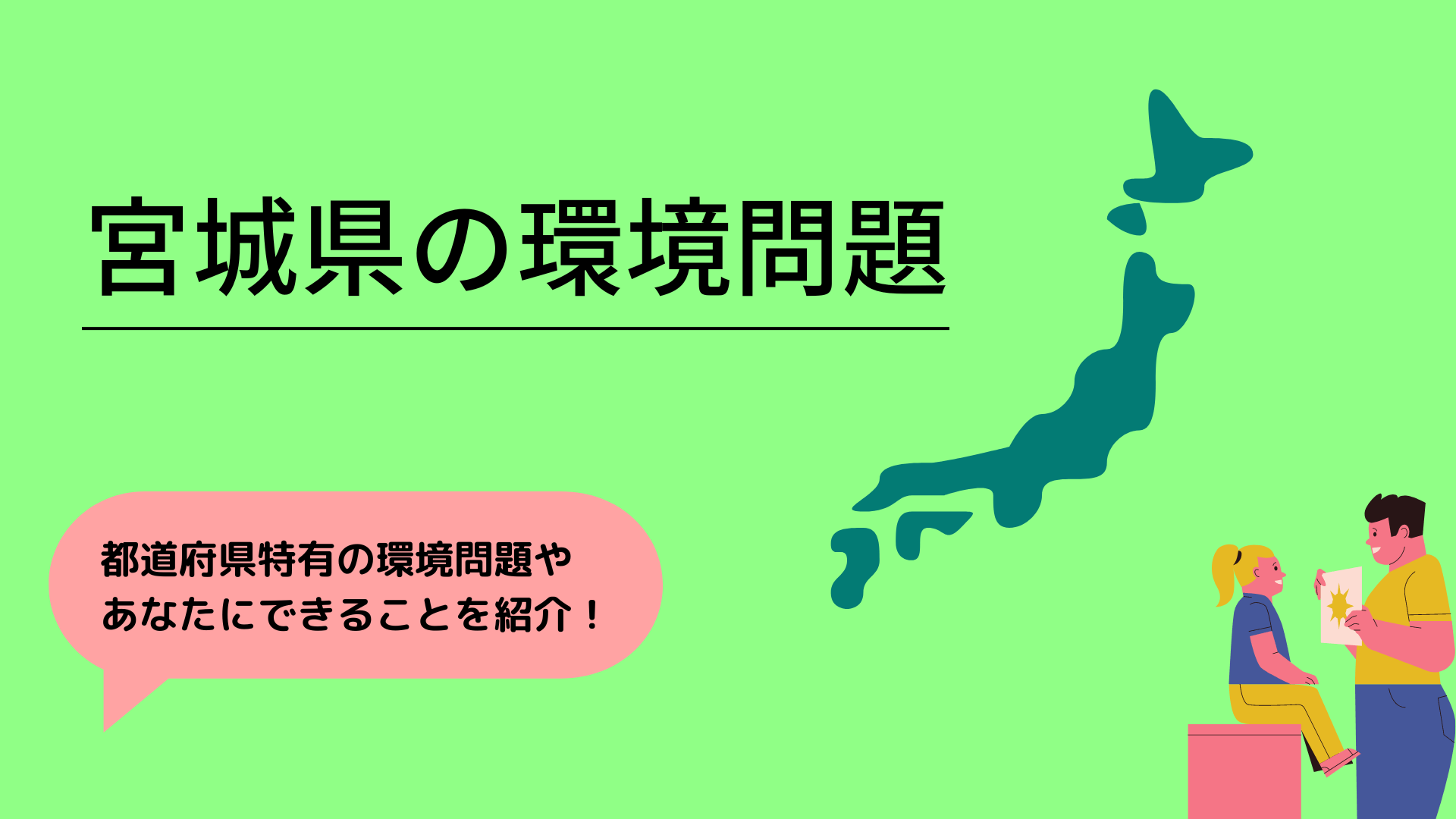環境問題への意識の高まりと共に、「アップサイクル」という言葉がよく耳にするようになりました。
しかし、一体アップサイクルとは何なのでしょうか?
多くの人が「リサイクル」と混同しているかもしれませんが、アップサイクルには独自の定義と価値があります。
本記事では、アップサイクルの基本的な概念から、リサイクルやリメイクとの違い、そして具体的なアップサイクルの例を通して、その魅力と可能性に迫ります。
※【企業様向け】リサイクルの取り組みをPRしませんか?
掲載を希望される企業様はこちらをご覧ください。
目次
アップサイクルとは

アップサイクルとは、使い終わって本来ならそのまま廃棄される製品の一部を再利用して、新たな価値のある製品に生まれ変わらせることです。
「創造的再利用」とも呼ばれており、ただ再利用するだけではなく、アイデアや工夫が大きく関わってきます。
また、サーキュラーエコノミーやリジェネレーションの考え方とも近いでしょう。
例えば、穿かなくなったジーンズからバッグを作ったり、規格外の野菜を使用して別の加工食品を生産したりといったことが当てはまります。
地球環境全体で見ると、循環型経済の一環として資源の廃棄量の減少や、自然環境への負荷を軽減する効果が期待されています。
関連記事
≫環境問題とは?日本と世界の13種類の問題を一覧で簡単に解説
≫【SDGs目標12】つくる責任つかう責任とは?背景や現状、企業の取り組み、私たちにできることを解説
アップサイクルとリサイクルとの違い

アップサイクルとリサイクルの違いは、「一旦資源に戻す」という工程があるかないかです。
リサイクルは、製品を一度資源に戻し、そこから新たなものを作り出します。
例えば、リサイクル原材料を使って新しい製品を作ることや、使用後にリサイクルしやすいように製品を設計することが求められます。
一方、アップサイクルは、製品そのものの特徴や気に入っていた部分を生かしつつ、新たな価値を与えて別のものとして生まれ変わらせます。
資源に戻す必要がなく、アイデア次第でコストもそれほどかかりません。
また、リサイクルの場合は、リサイクル業者に引き取ってもらうことで完結することがほとんどです。
しかし、アップサイクルでは、企業間でそれぞれの強みを生かした開発・製品化が可能です。
これにより、廃棄物をもとにしたビジネスマッチングもできる側面があります。
関連記事
≫リサイクル(3R)とは?例を用いて意味をわかりやすく解説!
≫5Rとは?5つの意味や3Rとの違い、私たちにできることを解説
アップサイクルとリメイクの違い

アップサイクルとリメイクの違いを解説します。
アップサイクルとリメイクの違いは、新たな価値の創出にあります。
リメイクは、何かをモデルにして「新たに作り直す」ことを意味します。
これは様々なジャンルで使用されており、ゲームや映画のリメイクもよく聞く言葉です。
しかし、リメイクには「オリジナルとの差別化」が常につきまとい、場合によってはオリジナルよりも価値が低下することもあります。
例えば、ファッション業界で有名ブランドのスーツのボタンをアクセサリーにリメイクしても、元のスーツ以上の価値が生まれないことがあります。
一方、アップサイクルは「新たな価値を生む」ことに焦点を当てています。
リメイクが元の製品の素材を生かして別のものに作り替える広義な使われ方をするのに対して、アップサイクルは価値が下がるものも含んでいるリメイクとは異なり、新しい価値が追加されることを重視します。
関連記事
≫サーキュラーデザインとは?7つの戦略や事例、PR方法を解説
アップサイクルの具体例5選

アップサイクルの具体例を5つ紹介します。
- アップサイクルが盛んなアパレル業界
- 化粧品メーカーが制服を雑貨にアップサイクル
- 別の業界への参入も可能にしたアップサイクル
- コーヒーの出がらしが消臭剤にアップサイクル
- ブランドの紙袋を活用したアップサイクル
アップサイクルが盛んなアパレル業界
日本を代表するセレクトショップ「ビームス」では、「ビームス クチュール(BEAMS COUTURE)」というアップサイクルのブランドを立ち上げました。そこでは衣服の廃棄ロス削減を目的としてデッドストック品に別のパーツを取り入れてトートバッグにするといった「新たな価値を持った一点モノ」を生み出すことに成功しています。
関連記事
≫スウェットショップとは?人権の搾取が存在する流行の裏側
化粧品メーカーが制服を雑貨にアップサイクル
ヘアケア製品を主力商品として展開しているブランド「ジョンマスターオーガニック」では、従業員の制服をコースターにアップサイクルする取り組みが行われています。廃棄される制服の布や合成皮革からボードを作る技術を活用し、廃棄予定だった700着の制服が約8,000個のコースターに生まれ変わりました。
参考:green beauty action | INTERVIEW:PANECO® / 制服アップサイクル
別の業界への参入も可能にしたアップサイクル
発酵技術を強みにしている株式会社ファーメンステーションでは、カルビー株式会社から提供された規格外のじゃがいもを原料とした発酵アルコールで「じゃがいもとお米の除菌ウエットティッシュ」を商品化しています。
スナック菓子メーカーの廃棄物が日用品に生まれ変わり、別事業への参入も可能にしました。
参考:ファーメンステーションがカルビーのじゃがいもから作る発酵エタノールを配合した「じゃがいもとお米の除菌ウエットティッシュ」を商品化
次に、個人でもできるアップサイクルの具体例を挙げてみましょう。
コーヒーの出がらしが消臭剤にアップサイクル
ドリップした後は捨てるだけだったコーヒーの出がらしは、乾燥すれば消臭剤としてアップサイクルできます。コーヒーメーカーのUCCでは、抽出かすの活用方法として、活性炭以上にアンモニア(におい成分)の脱臭効果が優れているコーヒー抽出かすの再利用方法を公開しています。
ブランドの紙袋を活用したアップサイクル
お買い物をするともらう事の多い紙袋。ご自宅でついついため込んでしまって使い道のないまま捨てることになる場合が多いのではないでしょうか。アップサイクルジャパンの公式Youtubeチャンネルでは、そういった紙袋を実用的でかわいいポーチに変身させる方法を公開しています。
https://www.youtube.com/@user-ho7gh6bo7n
関連記事
≫サーキュラーエコノミーに取り組む企業10選!就職・転職におすすめの大企業からベンチャー
≫リサイクルに取り組む企業10選!就職・転職におすすめの大企業からベンチャー
≫ごみ問題に取り組む企業10選!就職・転職におすすめの大企業からベンチャー
日本におけるアップサイクル

日本は基本的に天然資源が乏しい国です。
そのため、再利用の文化は古くから根付いていました。「もったいない」は、今や世界の共通言語です。
江戸時代は資源を再利用する「循環型社会」だったと言われています。衣服のみならず、あらゆる日用品を再利用しており、鍋釜などの貴重な金属類はいうまでもなく、「灰」もリサイクルの対象だったという記録が残ってるそうです。
日本のエネルギー自給率の低さもアップサイクルの加速に関連しているといえるかもしれません。
東日本大震災後全ての原子力発電所が停止したこともあり、2014年度には、日本のエネルギー自給率は急激に下がっています。
リサイクルで発生する再生エネルギーよりも効率の高いアップサイクルを選択することも将来的に有効なことは間違いありません。
足元は揺らぎつつあるとはいえ日本はまだまだ技術大国。
新しい技術で、アップサイクルやそれをサポートするビジネスを展開する企業の動きも出てきていますし、環境省でも「サステナブルファッション」を通してアップサイクルの普及に取り組んでいます。
まとめ
大量生産して大量消費・大量廃棄という現代社会に代わり、持続可能な社会への転換が叫ばれている今、アップサイクルが注目されています。
アップサイクル製品は廃棄物を再利用することで、新たな価値を生み出し天然資源の消費抑制効果が期待できるだけでなく、新たなビジネスやライフスタイルまで生み出しています。
SDGsのように消費者にも広まっていってみんながアップサイクルを意識し始めると、さらにアップサイクルを導入する企業も増えていくことが予想されます。
「アップサイクル」はビジネスだけでなく、様々な分野で今後の成長が期待されている取り組みです。

この記事の監修者
吉田宏輝
COCOCOLOREARTH代表、社会活動家。
COCOCOLOREARTHでは、社会課題解決を軸にした就職・転職活動を支援するインタビューメディアの代表として、100人以上の社会活動家にインタビュー、記事執筆やイベント登壇などを行う。