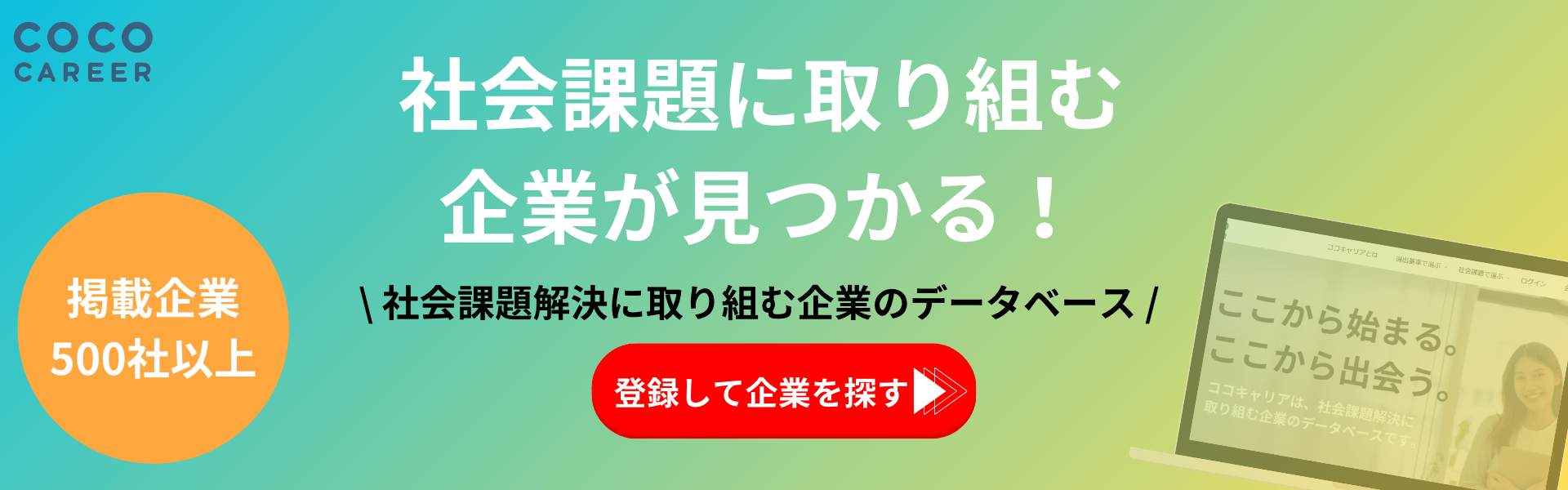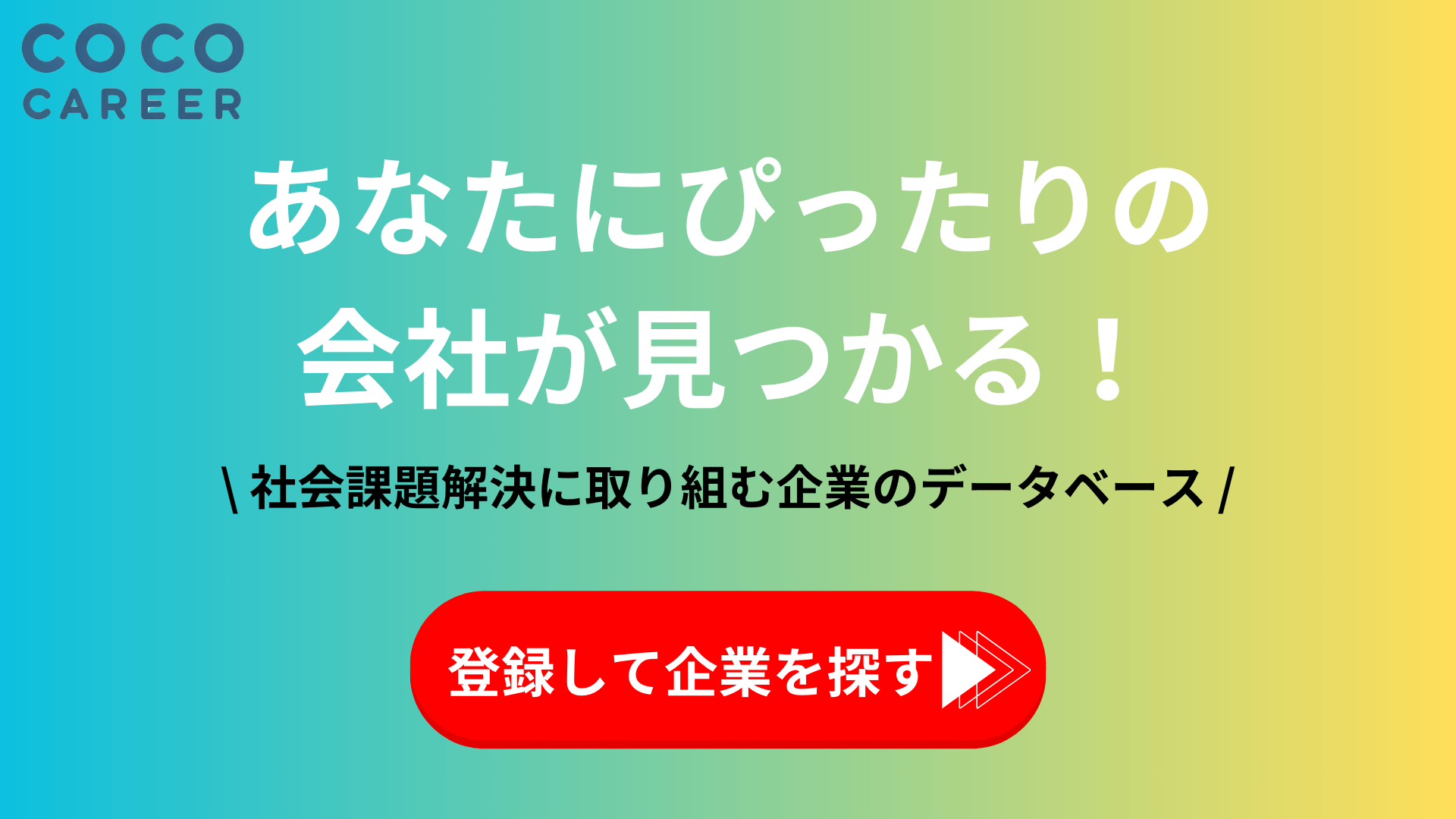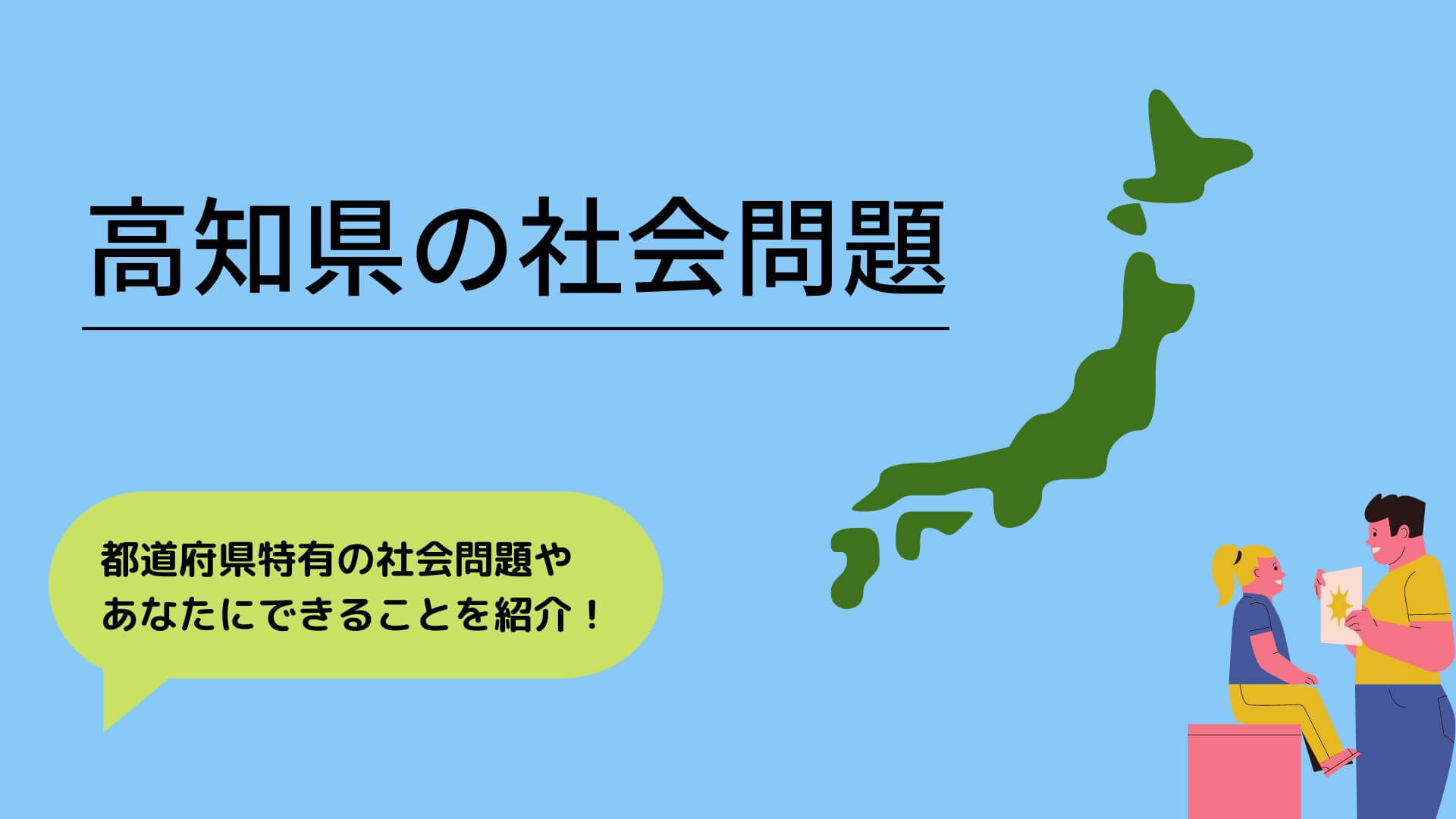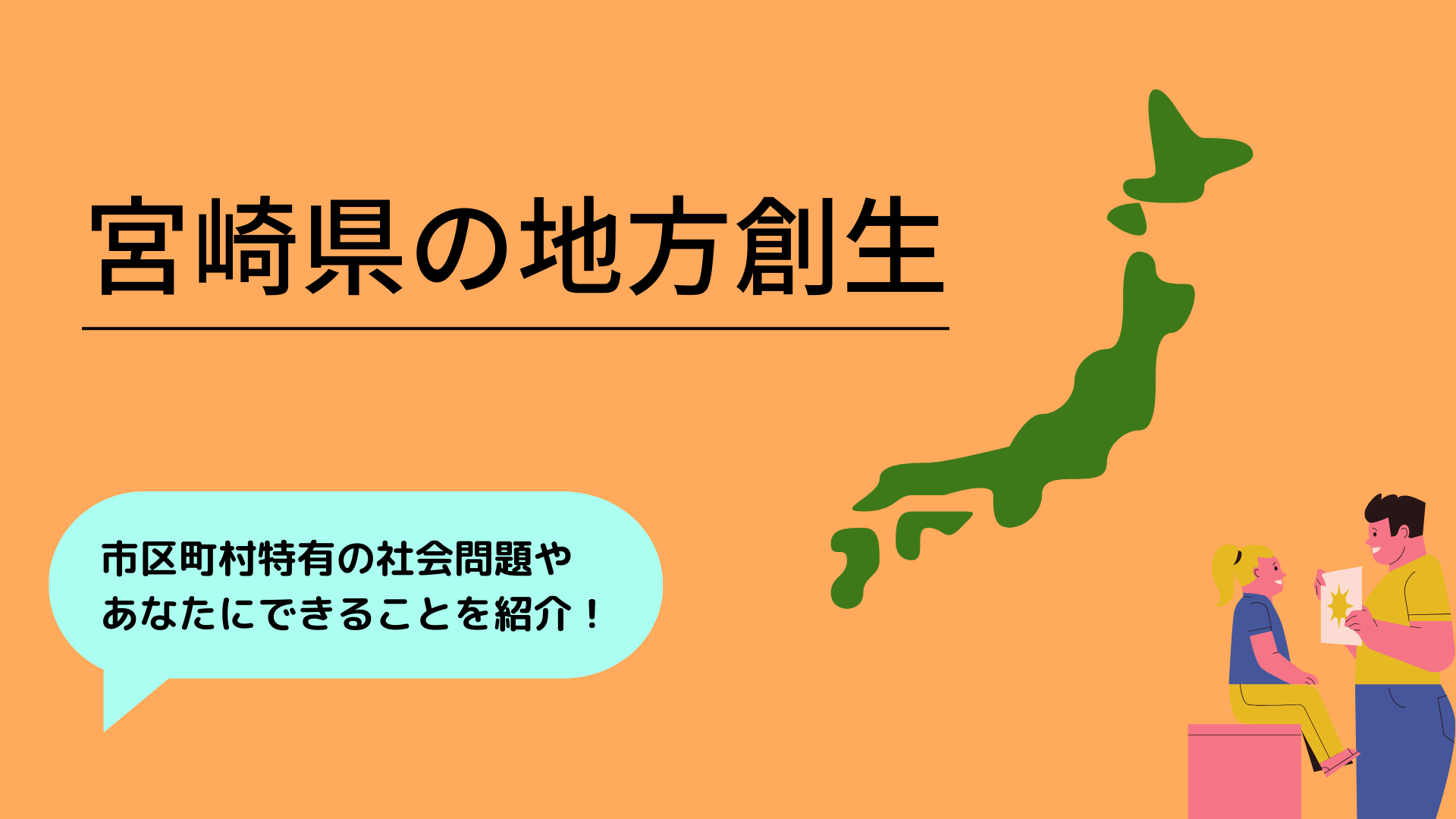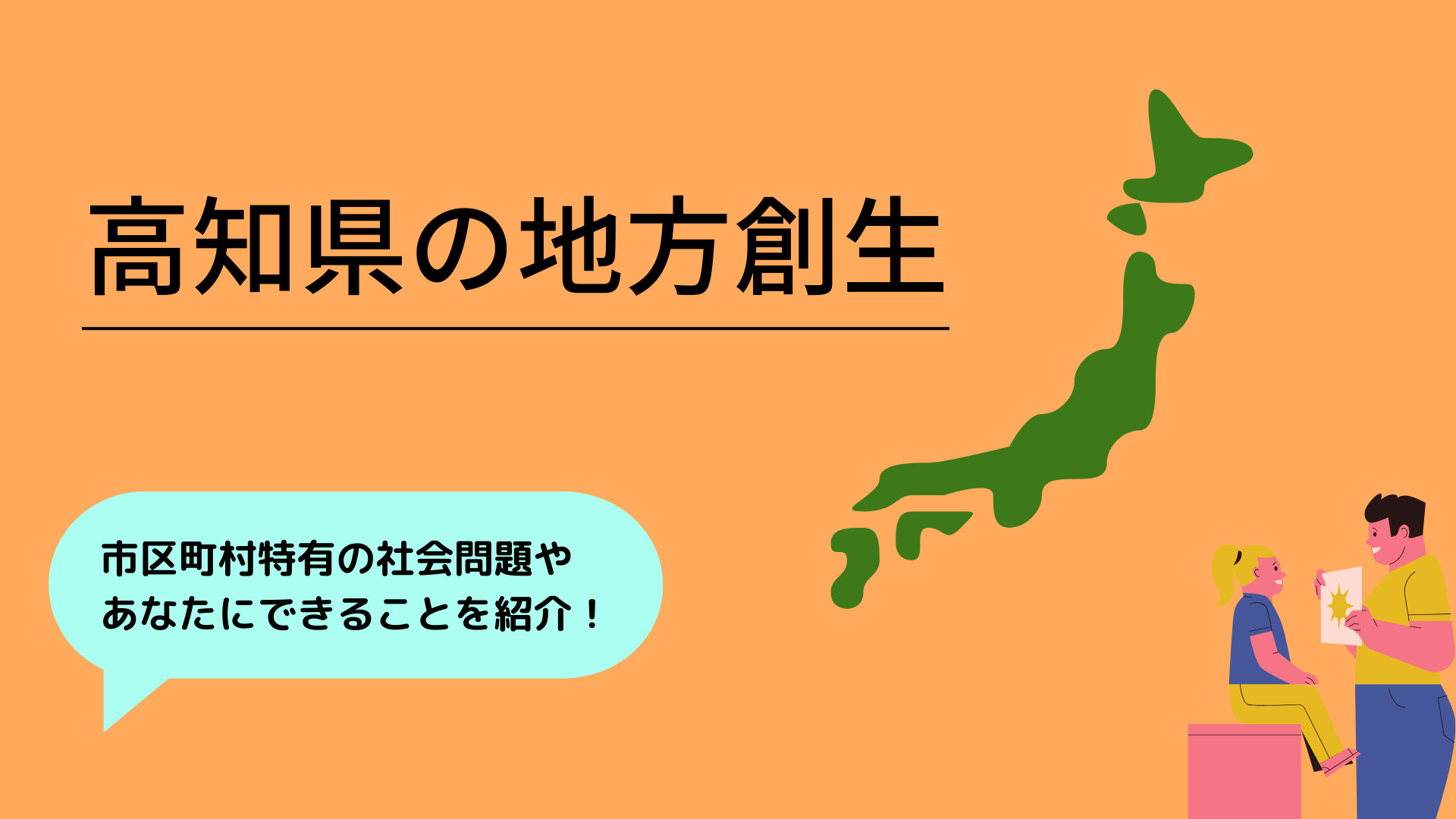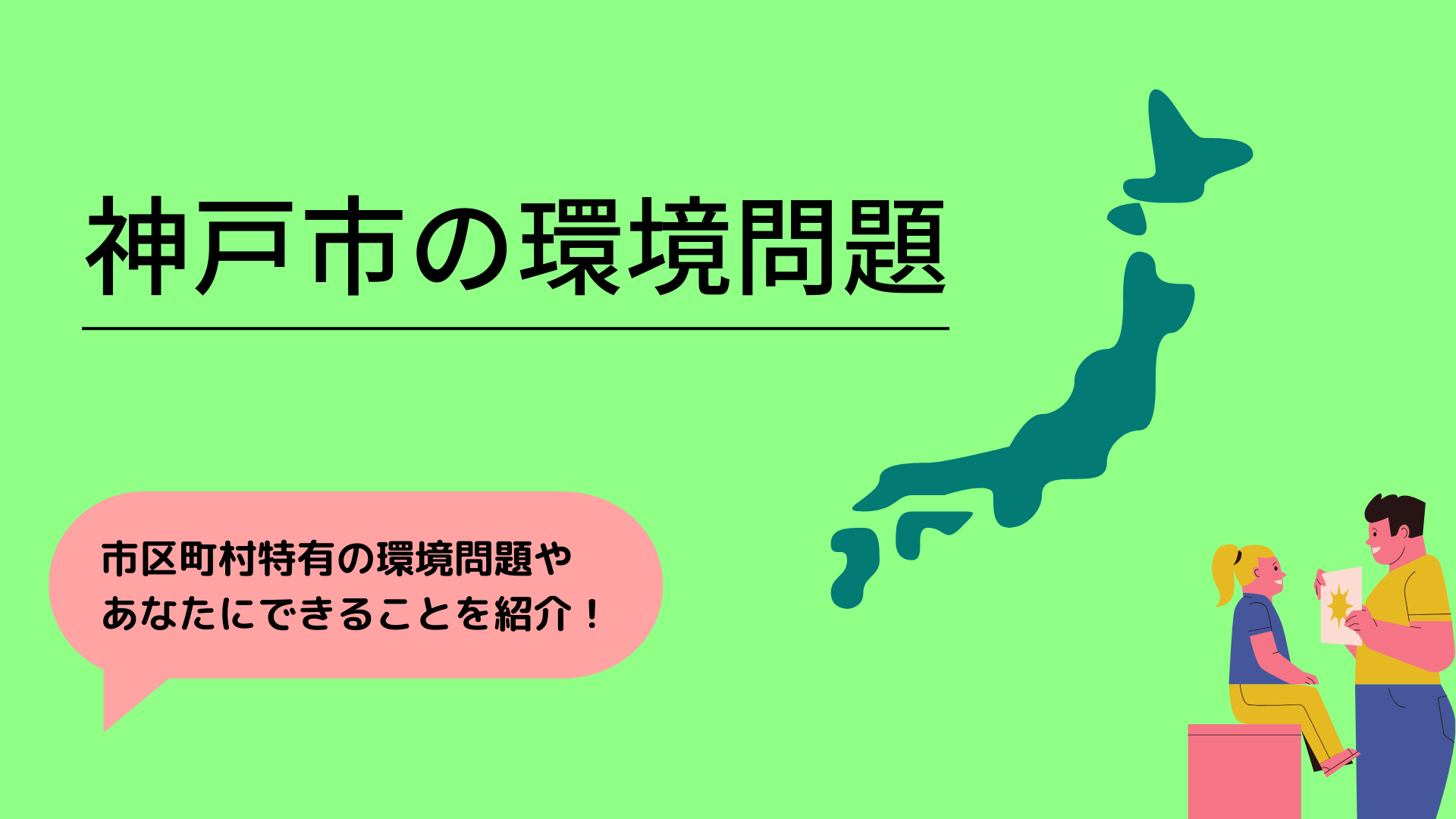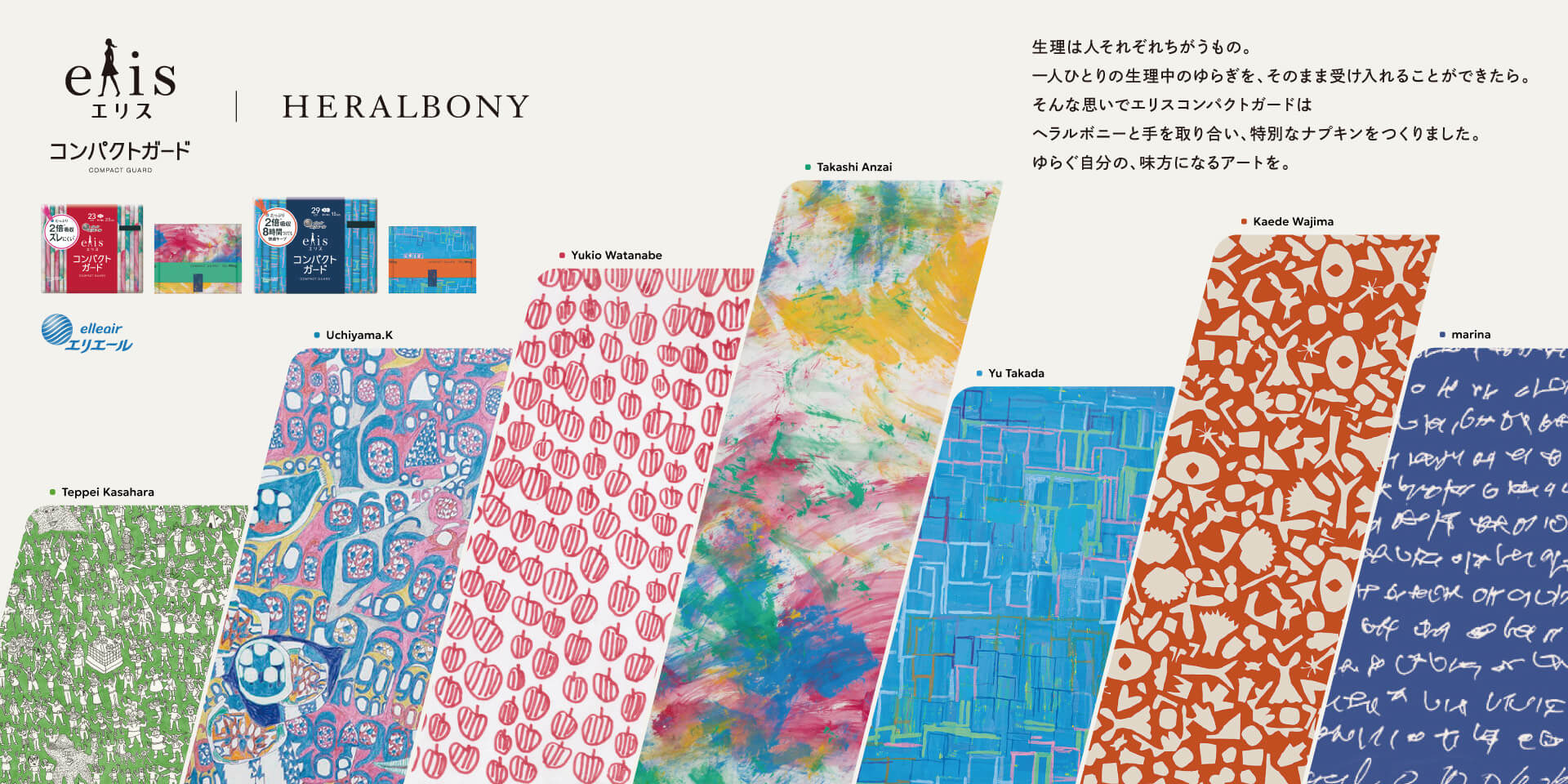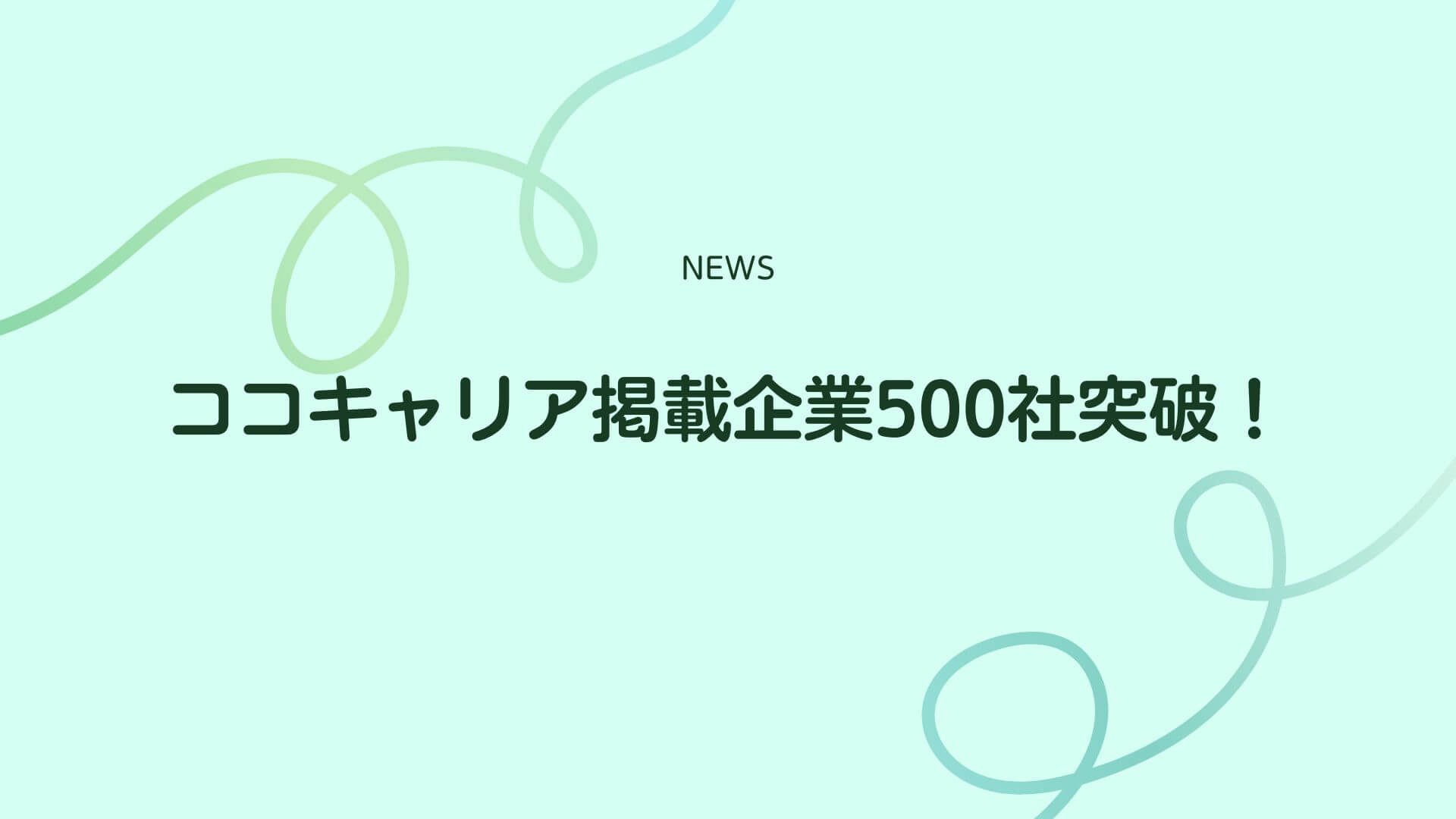フードファディズムとは、ある食べ物や栄養成分が健康に与える影響を過度に信じたり評価する現象です。
具体的には、「○○を食べるとやせる」「○○という成分は体に悪い」などの情報が過度に広まることです。
この概念は、1950年代にアメリカで生まれ、現代でも頻繁に起こっています。
この記事では、フードファディズムに関する事例や問題点、解決策について解説します。
≫フードロスとは?削減するために私たちができること
≫食品ロスとは?フードロスとの違いや日本の現状、取り組む企業を解説
※【企業様向け】フードロスへの取り組みをPRしませんか?
掲載を希望される企業様はこちら
目次
フードファディズムの事例
日本でもたくさんのフードファディズムが起こっています。
2000年以降に起こったフードファディズムの事例を紹介します。
寒天

2005年に放送されたテレビ番組の影響で観点ブームが起こりました。
低カロリーで満足感を得られることからダイエットの良いと評判になりました。
寒天メーカーは、大幅な需要の増加に対応するため、増産に追われました。
しかし、ブームが去ると、売上は大幅に減少に製造メーカーへの負担は大きかったです。
納豆

2007年に放送されたテレビ番組で、納豆に含まれる成分にがダイエット効果があると取り上げられ流行。
日本中のスーパーから納豆が消えました。
しかし、のちにテレビ番組の捏造であったことが発覚しました。
さらに、2020年には納豆が新型コロナウイルス感染症に有効であると噂が広がりました。
実際には、根拠のないデマでありましたが、一時的に品薄となっています。
バナナ

2008年には、あるテレビ番組がきっかけで、朝バナナダイエットが流行しました。
朝食をバナナと水にするだけで痩せられると話題に。
売り場からバナナが消えてしまうスーパーまでありました。
牛乳

2005年ごろから、牛乳は体に悪いと主張をする記事や書籍が話題になりました。
その結果、右肩上がりの成長を続けていた牛乳の生産量は減少。
それからは、上昇することなく右肩下がりを続けています。
フードファディズムの問題点

フードロスにつながる
フードファディズムによって、悪いうわさが流れれば、その商品は売れ残り廃棄となってしまいます。
また、爆発的に売れたとしても、フードロスにつながる可能性が高いです。
多くの企業は「対前年比で○%増」を売り上げ目標にしているため、高めの目標設定になることが多いです。
しかし、現実では、そこまで売れず、フードロスとなってしまいます。
生産者への負担
企業や生産者にとって、売上が増えることはありがたいですが、社員や生産者への負担は大きくなります。
また、ブームが終わると、以前よりも需要が落ち込むことが多く、最悪の場合には経営難にまでなってしまいます。
実際に、寒天ブームでは、立て直すまでに数年もかかったそうです。
届くべき人に行きわたらなくなる可能性も
何かしらの理由で、その商品が必要な方にも行きわたらなくなってしまう可能性があります。
コロナ禍でマスクやアルコールが、病院に行きわたらなくなってしまったようなことが今後起きないとは限りません。
フードファディズムの解決策

フードファディズムを見抜くにはどうすれば良いのでしょうか?
ここでは2つの対策をご紹介します。
食に関する正しい知識を身につける
まずは、食と健康に対するしっかりとした知識を身につけましょう。
基本的な栄養素の役割や効果は知っておくことをおすすめします。
家庭科の授業で習う程度で構いませんので、復習しておきましょう。
また、偏りのない食事が、健康維持に役立ちます。
健康に良いからと言って偏った食事をするのは危険です。
バランスよく色々なものを食べましょう。
情報を正しく読み解く
フードファディズム、企業による過度な広告や、メディアによる情報の切り取り方が原因となることが多いです。
そのため、情報を正しく読み解く必要があります。
情報を飲みにせず客観的に判断しましょう。
特に、科学的根拠があるのか、複数の情報から総合的に判断することがポイントです。
まとめ
いかがでしたでしょうか?
フードファディズムとは、ある食べ物や栄養成分が健康に与える影響を過度に信じたり評価する現象です。
食に関する正しい知識を身につけることと、情報を正しく読み解くことが対策のカギになります。
メディアの情報に流されず、自ら情報の信ぴょう性について確かめてみましょう。
≫フードロスに取り組む企業10選~ベンチャー企業を中心に紹介~
その他の○○ズムも知ってみよう!
≫ルッキズムとは?社会問題として注目される背景や現状、事例を解説
≫フードファディズムとは?事例や3つの問題点、解決策について解説!
≫レイシズムとは?歴史や現在の問題、日本のレイシズムを簡単に解説
≫エイジズム(年齢差別)とは?具体例や問題点、私たちにできることを解説
≫アニミズムとは?特徴や歴史、日本・世界の事例を簡単に解説
【企業様向け】フードロスの取り組みをPRしませんか?

この記事の監修者
吉田宏輝
COCOCOLOREARTH代表、社会活動家。
COCOCOLOREARTHでは、社会課題解決を軸にした就職・転職活動を支援するインタビューメディアの代表として、100人以上の社会活動家にインタビュー、記事執筆やイベント登壇などを行う。