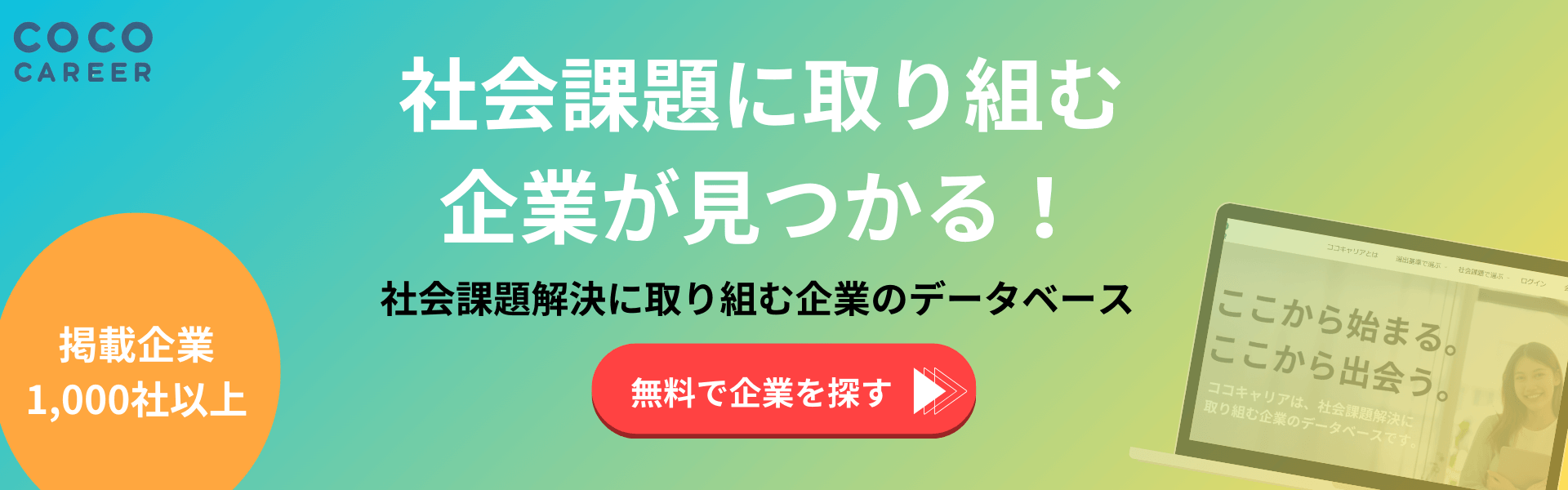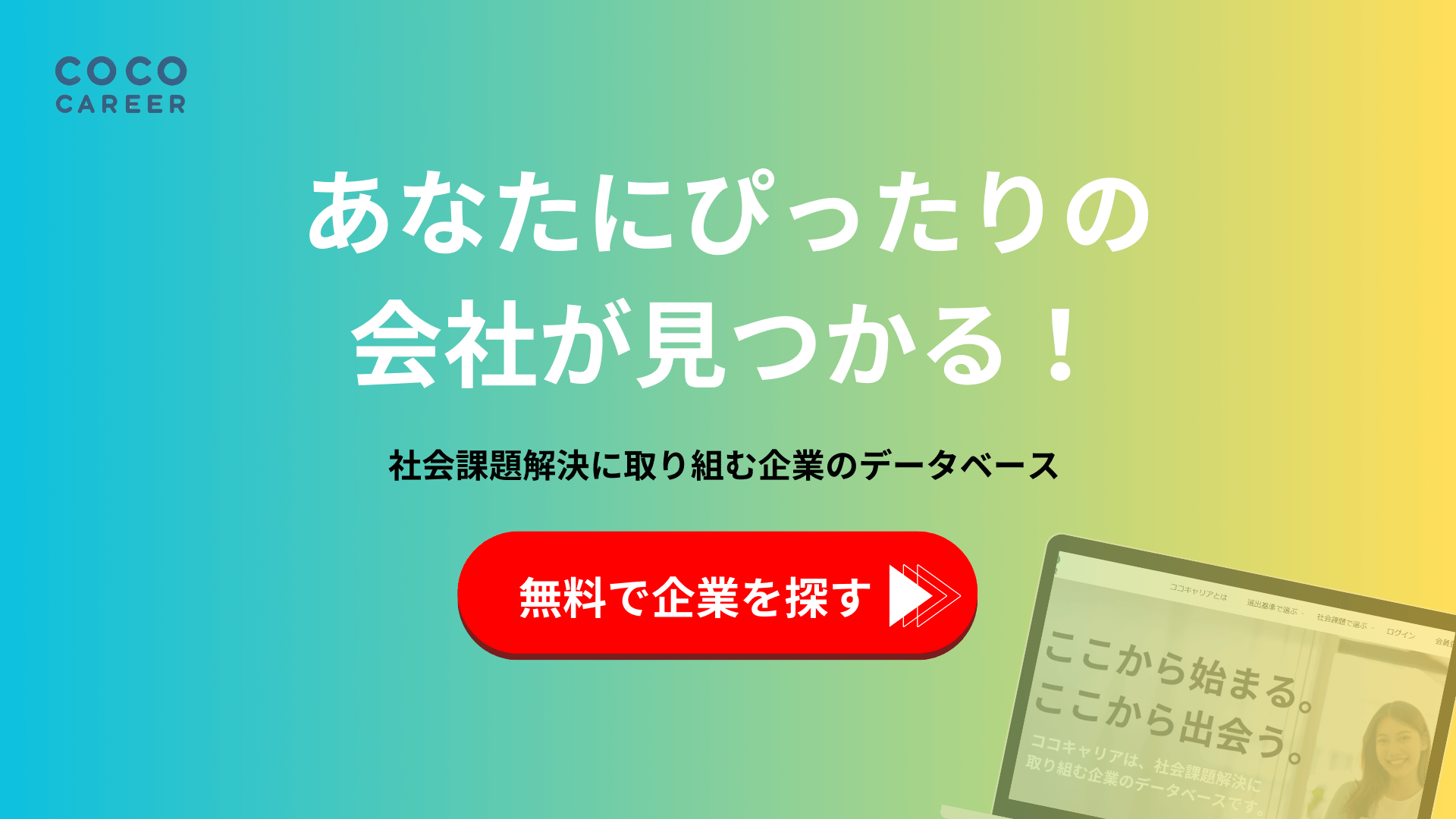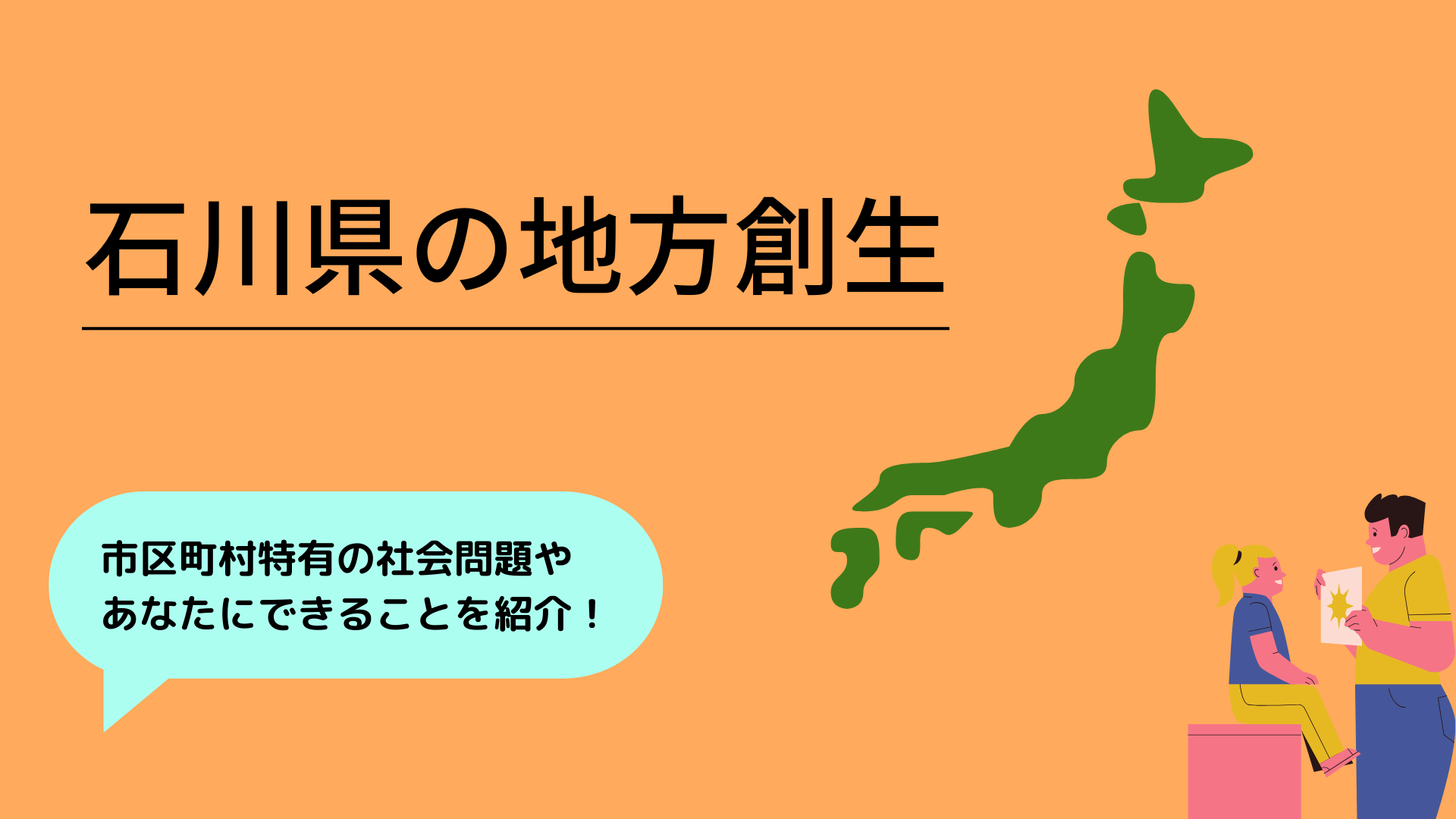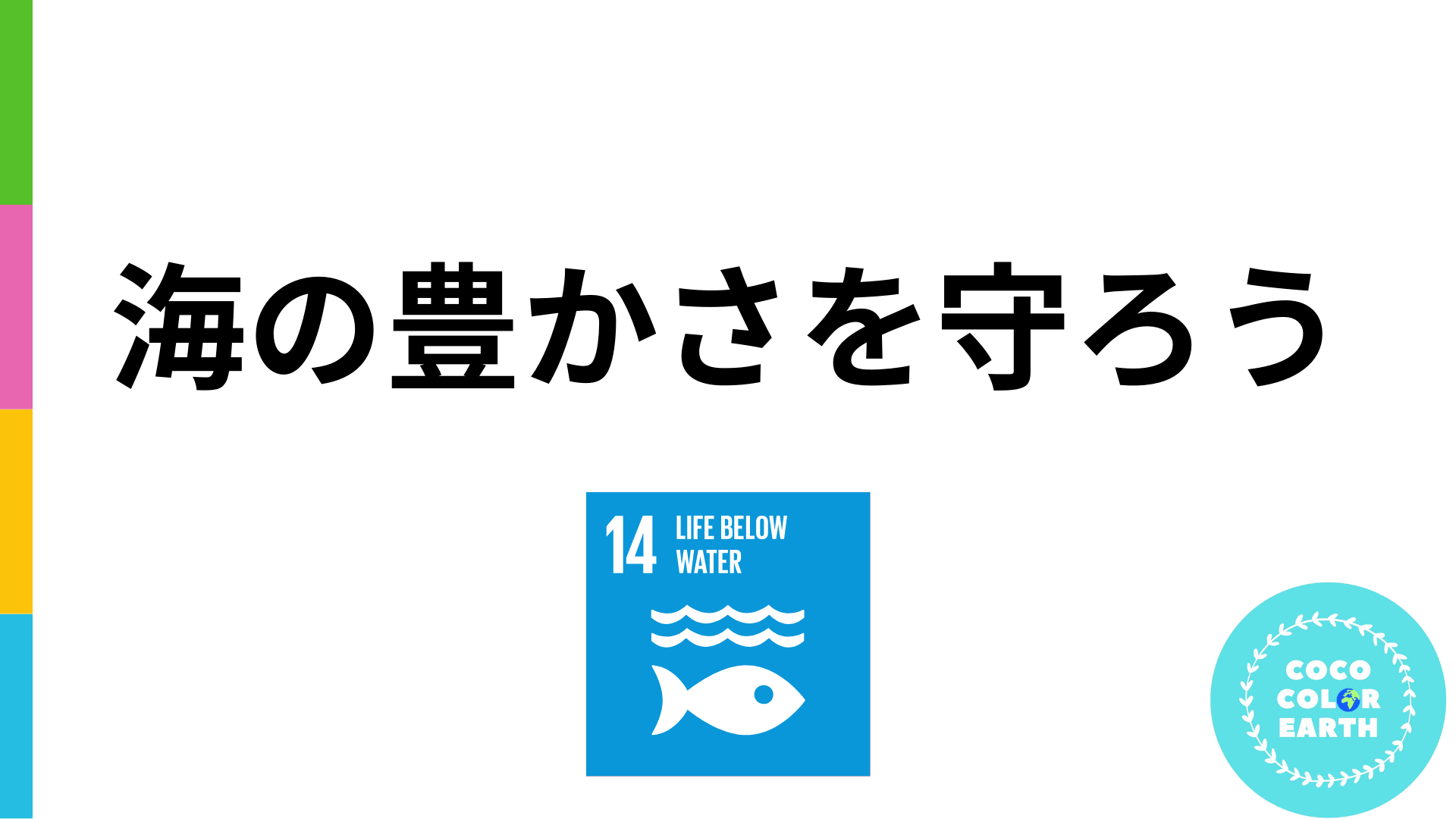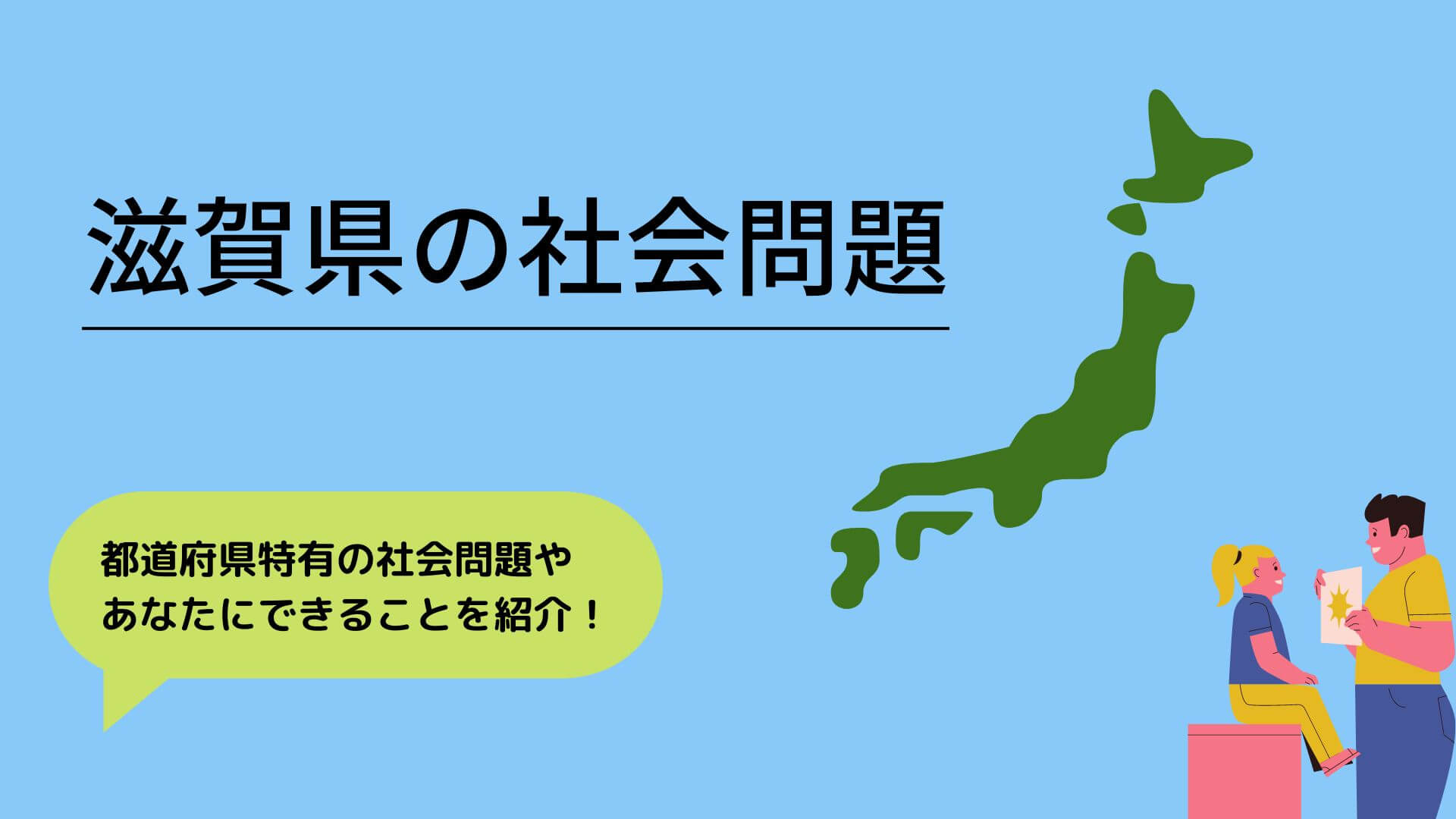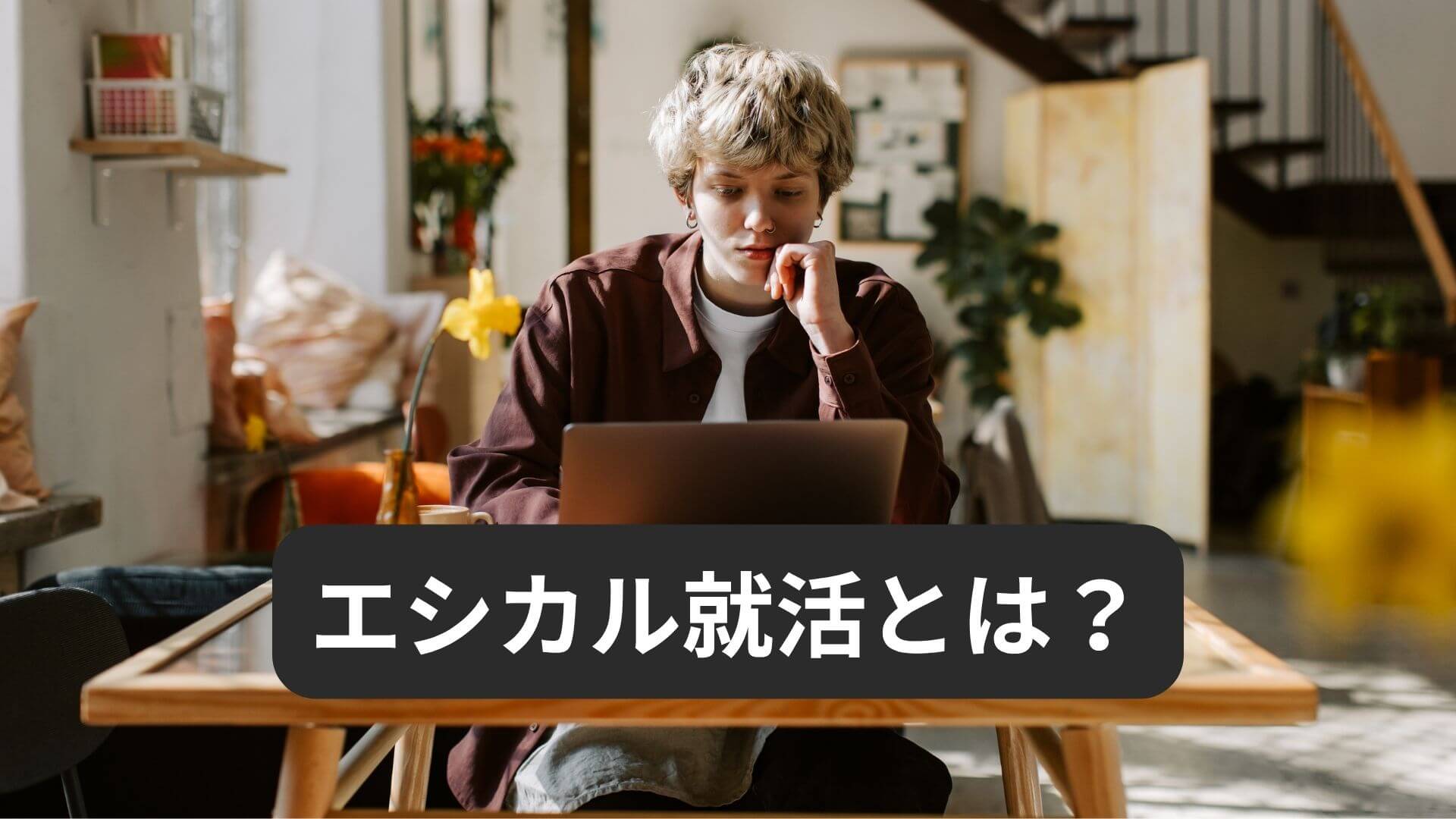私たちの日常生活には、多くの見えない水が関わっていることをご存知でしょうか?
この見えない水、つまり「バーチャルウォーター」という概念は、私たちが消費する食品や製品の生産過程で使われる水の量を表しています。
特に、食糧の生産には膨大な量の水が必要であり、その影響は私たちの生活と切り離せないものです。
本記事では、バーチャルウォーターの基本的な概念から、私たちが普段口にするカレーライス、ケーキ、コーヒーなどの具体的な例、日本のバーチャルウォーター輸入量やその問題点、そしてそれに対する解決策について詳しく解説します。
私たちが普段気づかないこの重要な問題について、一緒に考えてみましょう。
※【企業様向け】環境問題への取り組みをPRしませんか?
このページに掲載を希望する企業様はこちらをご覧ください
目次
バーチャルウォーターとは
バーチャルウォーター(virtual water/仮想水)とは、輸入食糧を生産するのに必要な水の量を推定したもので、ロンドンのアンソニー・アラン教授によって示された概念です。
例えば、牛1頭分のバーチャルウォーターは約12,000トンです。
牛の飼料となるトウモロコシは、1kgあたり1,800リットルの水が必要で、牛はこれを大量に消費しているため、大きな数字になります。
他にも、私たちが普段食べている食品にどのくらいのバーチャルウォーターが含まれているかは、環境省のバーチャルウォーター量自動計算から調べることができます。
身近なバーチャルウォーターの具体例
身近なバーチャルウォーターの具体例を解説します。
- カレーライスのバーチャルウォーター
- ケーキのバーチャルウォーター
- コーヒーのバーチャルウォーター
カレーライスのバーチャルウォーター
カレーライス一人前のバーチャルウォーターは、約1516Lです。
内訳
米100g=388.5L
牛肉50g=1030L
人参1本=41.175L
ジャガイモ1個=18.5L
玉ねぎ1個=37.92L
ケーキのバーチャルウォーター
ケーキのバーチャルウォーターは、約619.55Lです。
内訳
小麦粉100g=210L
卵2個=358.4L
イチゴ5個=51.15L
コーヒーのバーチャルウォーター
コーヒーのバーチャルウォーターは、約210Lです。
日本のバーチャルウォーター輸入量

https://globe.asahi.com/article/11614201
日本のバーチャルウォーターの輸入量を解説します。
バーチャルウォーターの輸入量は「年間約640億トン」であり、なんと琵琶湖の貯水量の約2.5倍に相当します。
日本は、国内の年間総水資源使用量900億トンのほかに、その3分の2以上の水を海外から輸入していることになります。
関連記事
≫日本にもあるの!?水問題の現状と最新の取り組み
バーチャルウォーターの問題点

バーチャルウォーターの問題点を解説します。
日本は多くの食糧を輸入していますが、仮にそれらを国内で生産しようとすると大量の水が必要です。
つまり、食糧輸入によって日本は水資源を節約できますが、その代わりに輸出国では水資源が消費されたことになります。
結果として、バーチャルウォーター輸出国であるインド、エチオピア、パキスタンでは、深刻な水不足が発生しています。
インドでは、2019年時点で全土の4割が干ばつ状態になっています。
エチオピアでは、子どもたちが1日中水汲みに行きますが、得られるのは泥水の地域も少なくありません。
バーチャルウォーター輸出国ほど水不足に陥り、住民は劣悪な環境下での生活を強いられているのです。
また、バーチャルウォーター輸入国の日本にとって、輸出国の水不足や汚染水の問題は決して他人事ではありません。
輸出国が水不足により食糧を作れなくなれば、当然日本も輸入できないためです。
参考:深刻化するインドの水不足とモディ政権の取り組み(1)インド全土の4割以上が干ばつ状態に
関連記事
≫【途上国一覧付き!】途上国って結局どこなの?様々な定義と分類を解説!
≫日本にもあるの!?水問題の現状と最新の取り組み
≫水不足の原因とは?考えられる8つの原因と私たちができること
バーチャルウォーターに関わる問題の解決策
バーチャルウォーターに関わる問題の解決策について解説します。
実は、もともとバーチャルウォーターに関する議論は、「水資源の地域的な偏りは、食糧の輸出入を媒体とする地域間の移動により緩和することが可能である」という仮説から始まりました。
しかし、上記の通り、食糧の輸出入が水資源の最も合理的な再配分にはなっていないのが現状のようです。
私たちにできることとして、まずバーチャルウォーターを減らす行動が挙げられます。
すなわち、食糧は必要な分だけ購入し、廃棄しないことや、できるだけ国内産の食糧を選択することです。
さらに、世界の水問題の解決に取り組むNPO・NGOの活動に参加したり、寄付をしたりすることも問題解決策のひとつと言えるでしょう。
関連記事
≫フードファディズムとは?事例や3つの問題点、解決策について解説!
≫ブルーエコノミーとは?ブルーファイナンスやグリーンエコノミーとの違いを解説
≫サーキュラーエコノミーとは? アメリカで話題の「LOOP」や江戸時代の事例を解説
さいごに
私たち日本人は、蛇口をひねれば水が出る生活に慣れています。
しかし、世界は深刻な水不足にあることや、日本も間接的に海外の水に頼っていることを理解し、食糧や水をムダにしないよう心掛けなくてはいけません。
節水は、渇水や今後想定される水不足の緩和のために大切です。
蛇口の締め忘れ防止やお風呂の水の洗濯利用、シャワーではなく桶で貯めてお風呂に入るなど、簡単なことから始めましょう。
当サイトは、社会課題をキャリアにしたいと考える方のお手伝いをしています。
他にもご興味のある記事があれば是非ご覧ください。
関連記事
≫ウォーターフットプリントとは?バーチャルウォーターとの違いや原因、私たちにできることを解説
【企業様向け】環境問題への取り組みをPRしませんか?

この記事の監修者
吉田宏輝
COCOCOLOREARTH代表、社会活動家。
COCOCOLOREARTHでは、社会課題解決を軸にした就職・転職活動を支援するインタビューメディアの代表として、100人以上の社会活動家にインタビュー、記事執筆やイベント登壇などを行う。