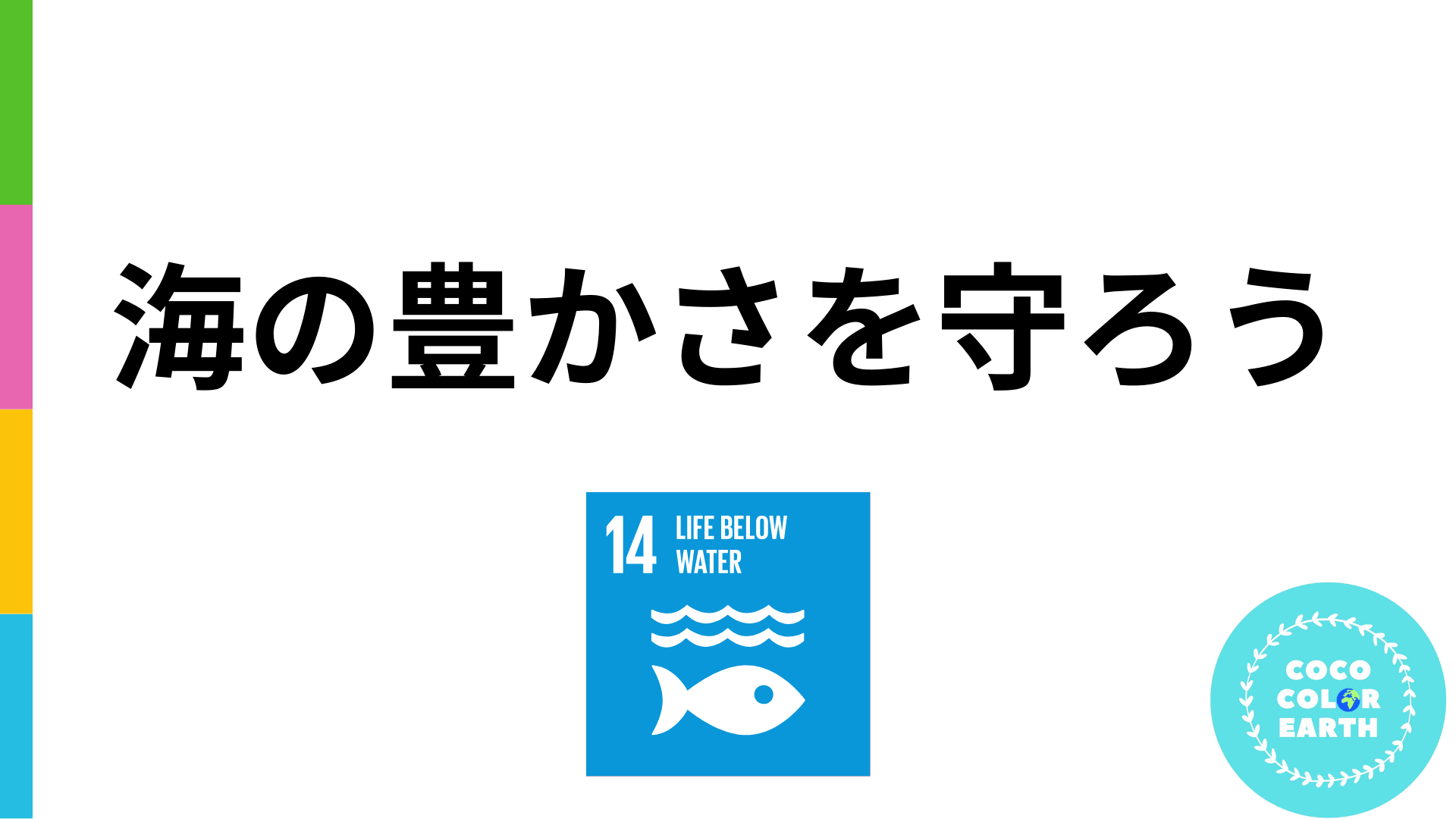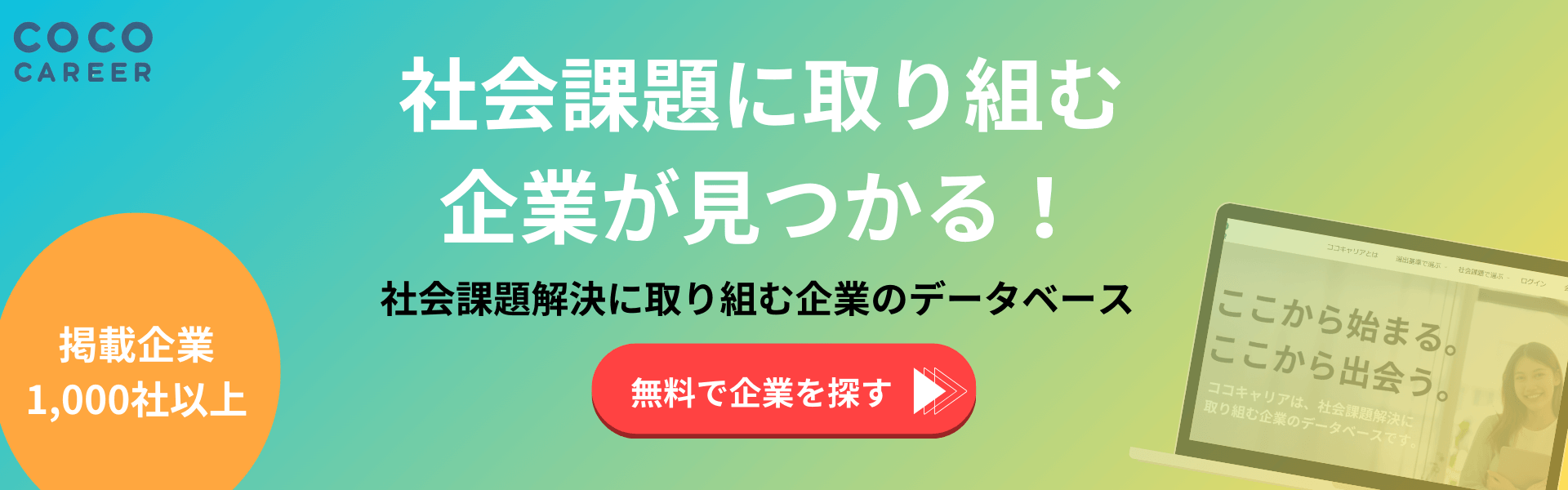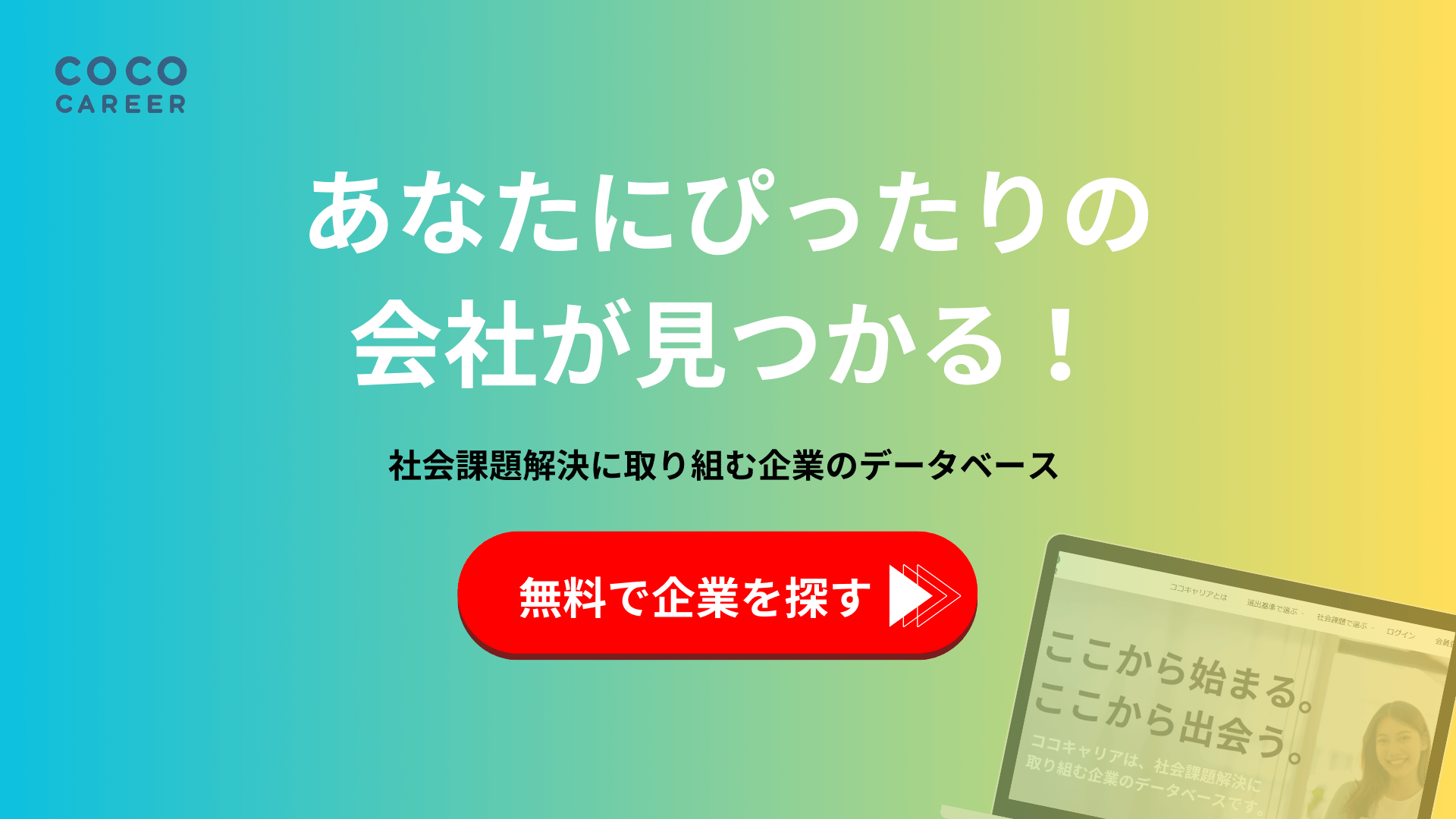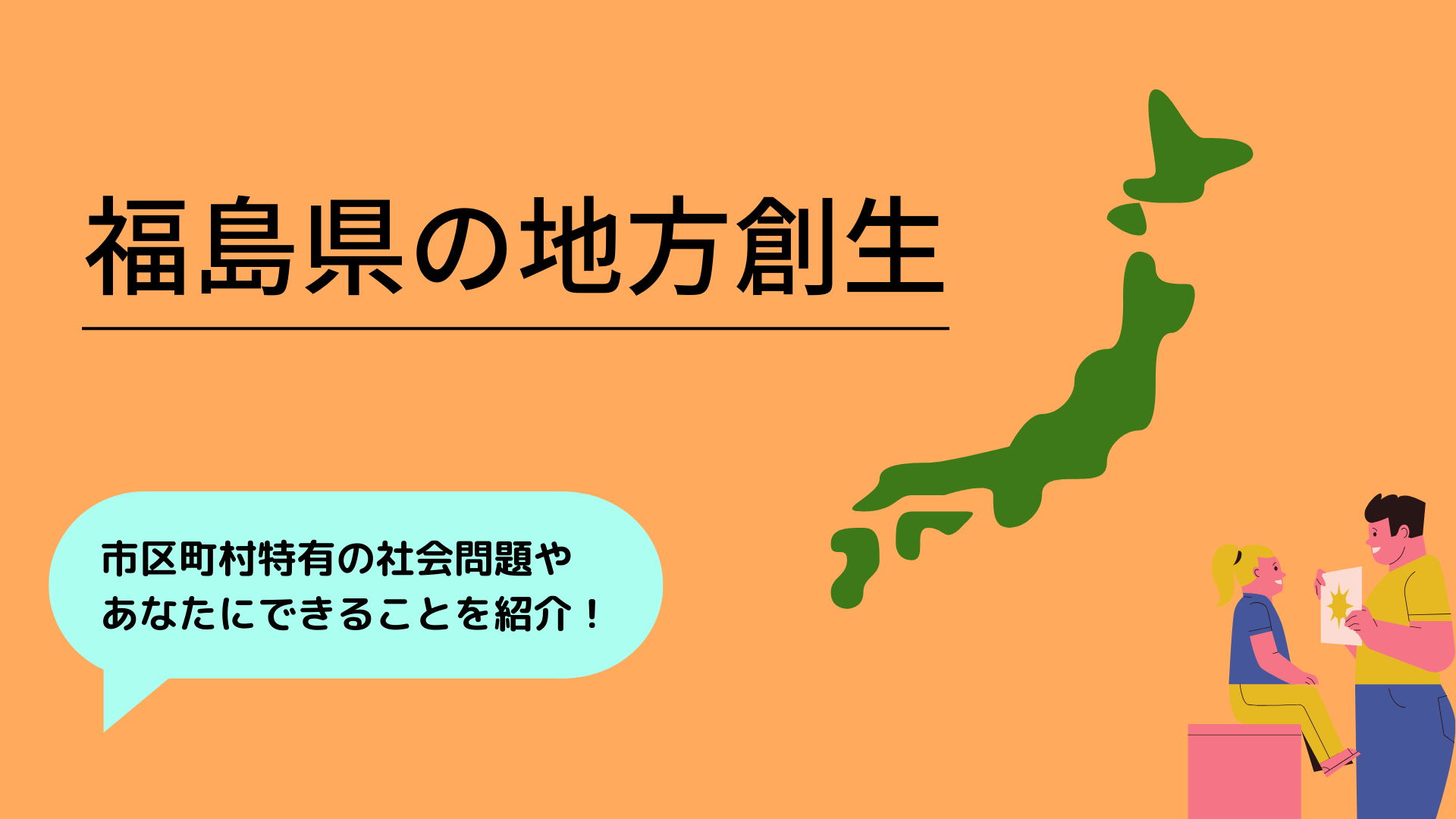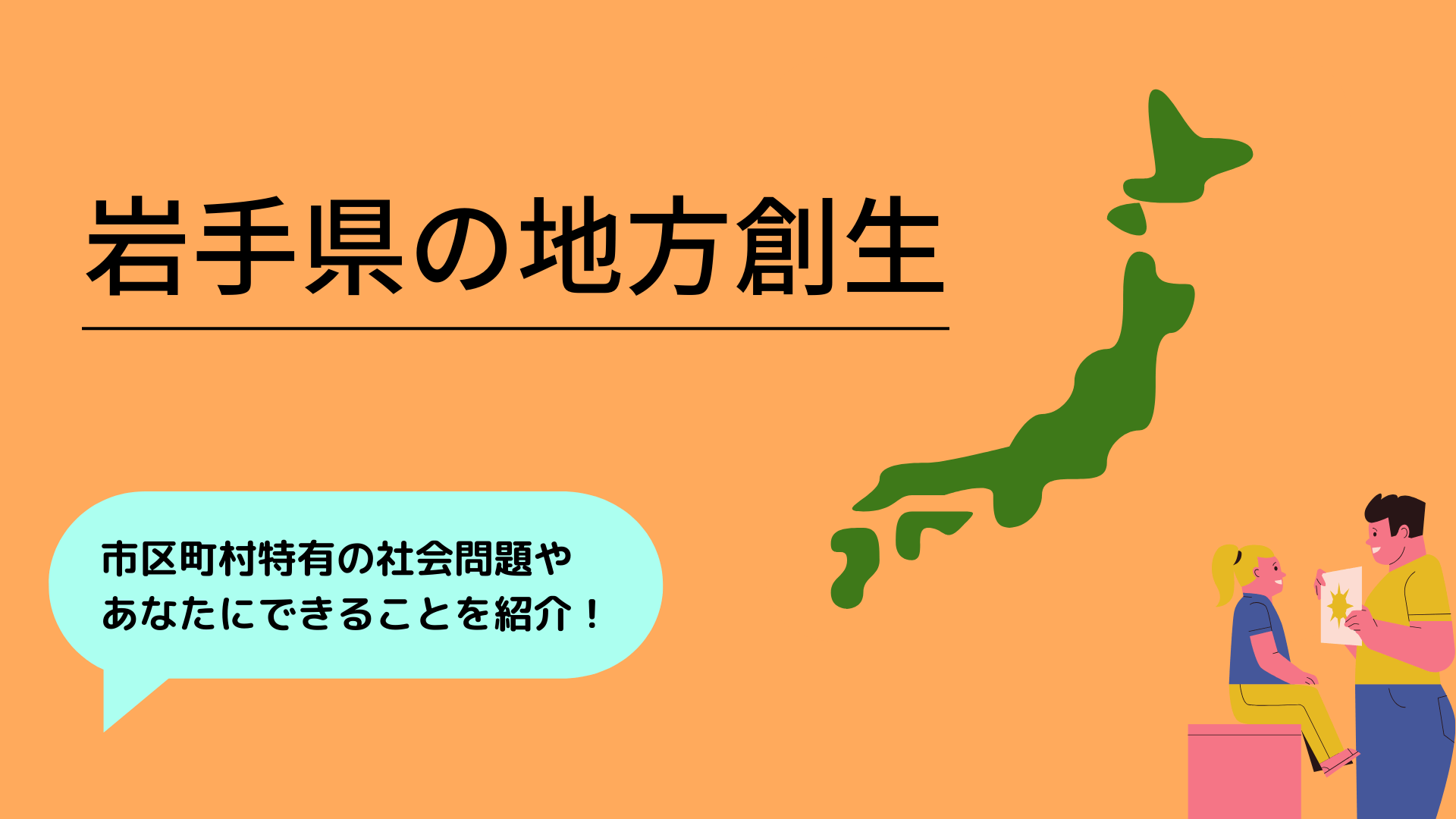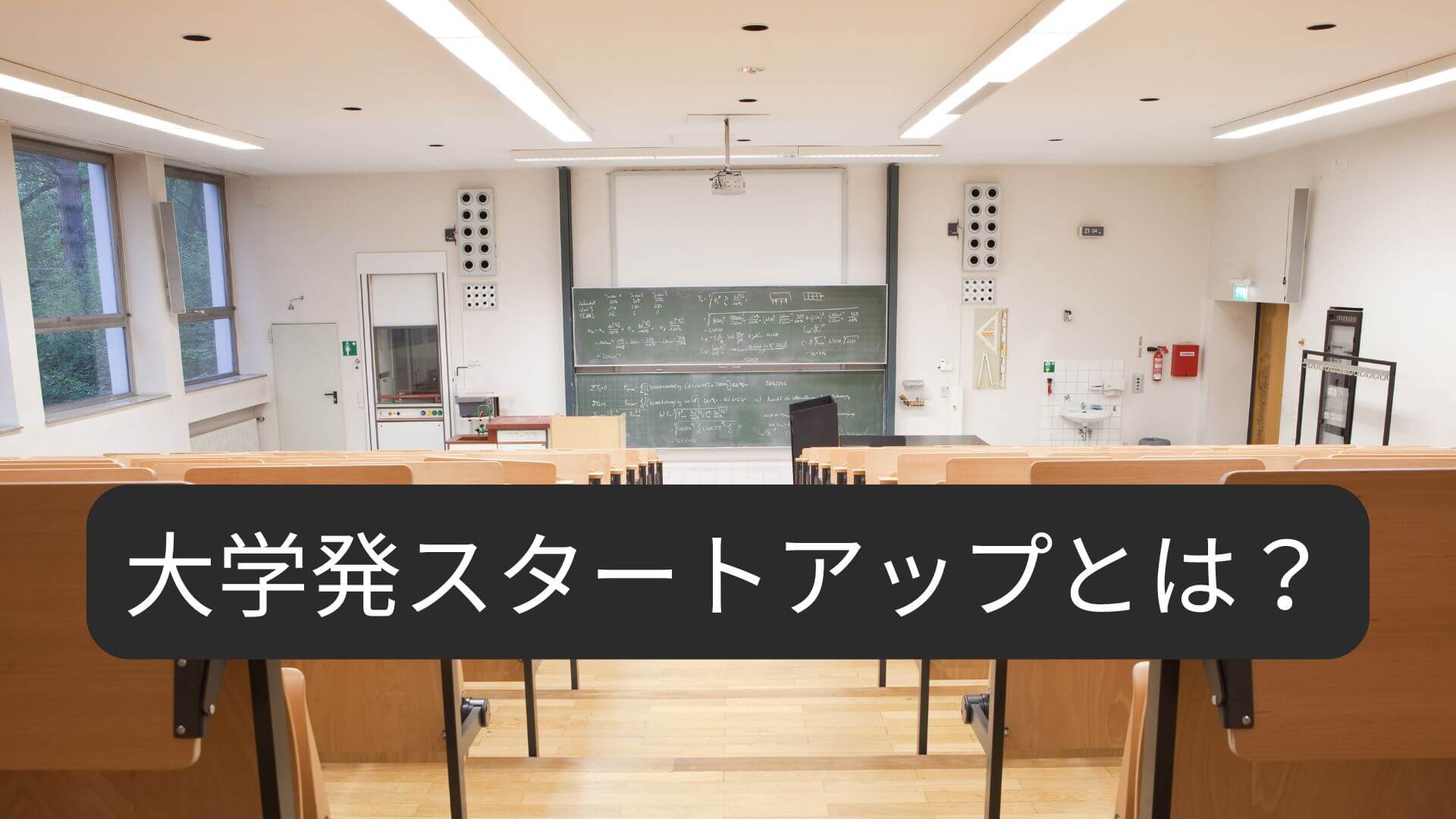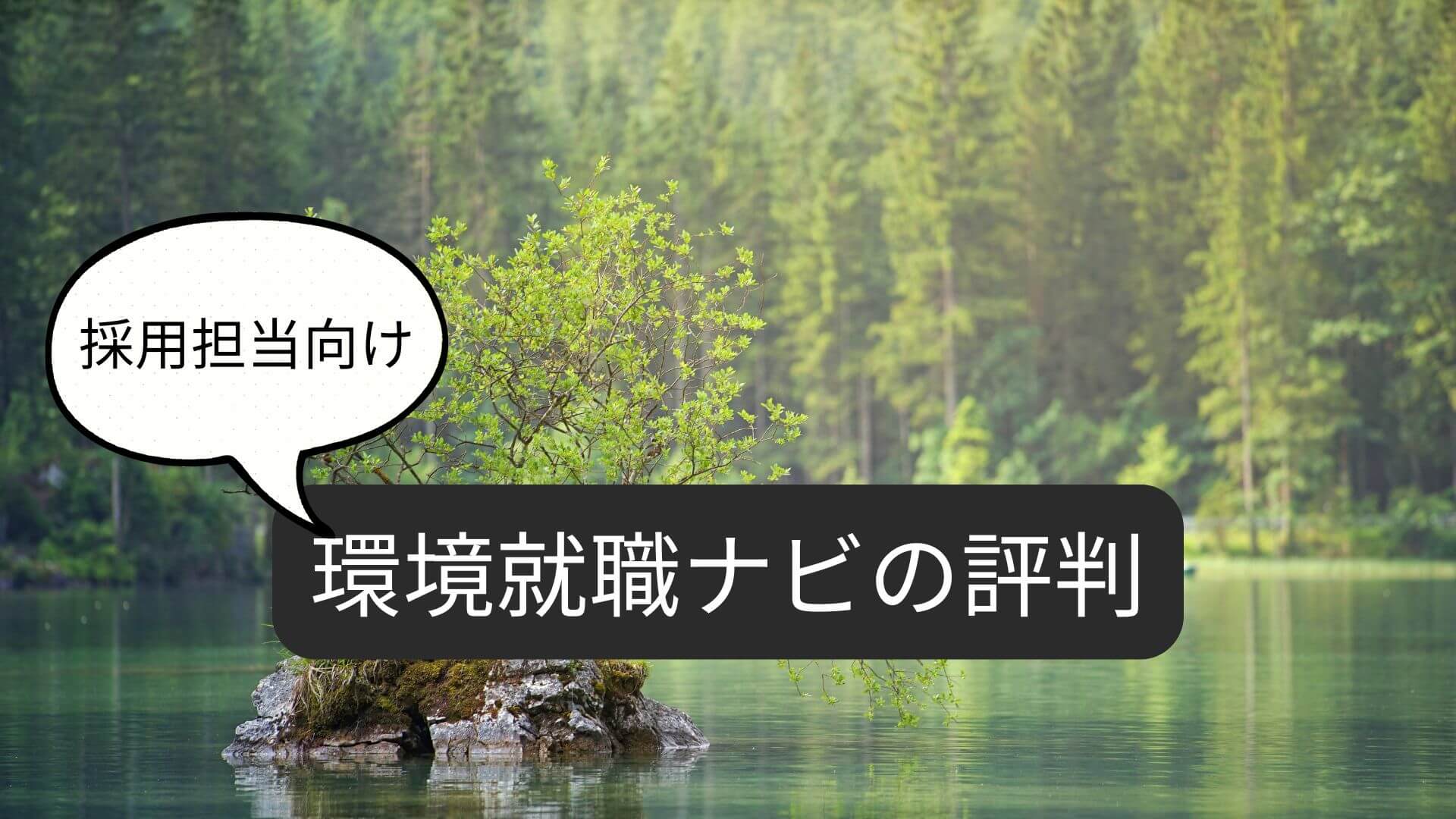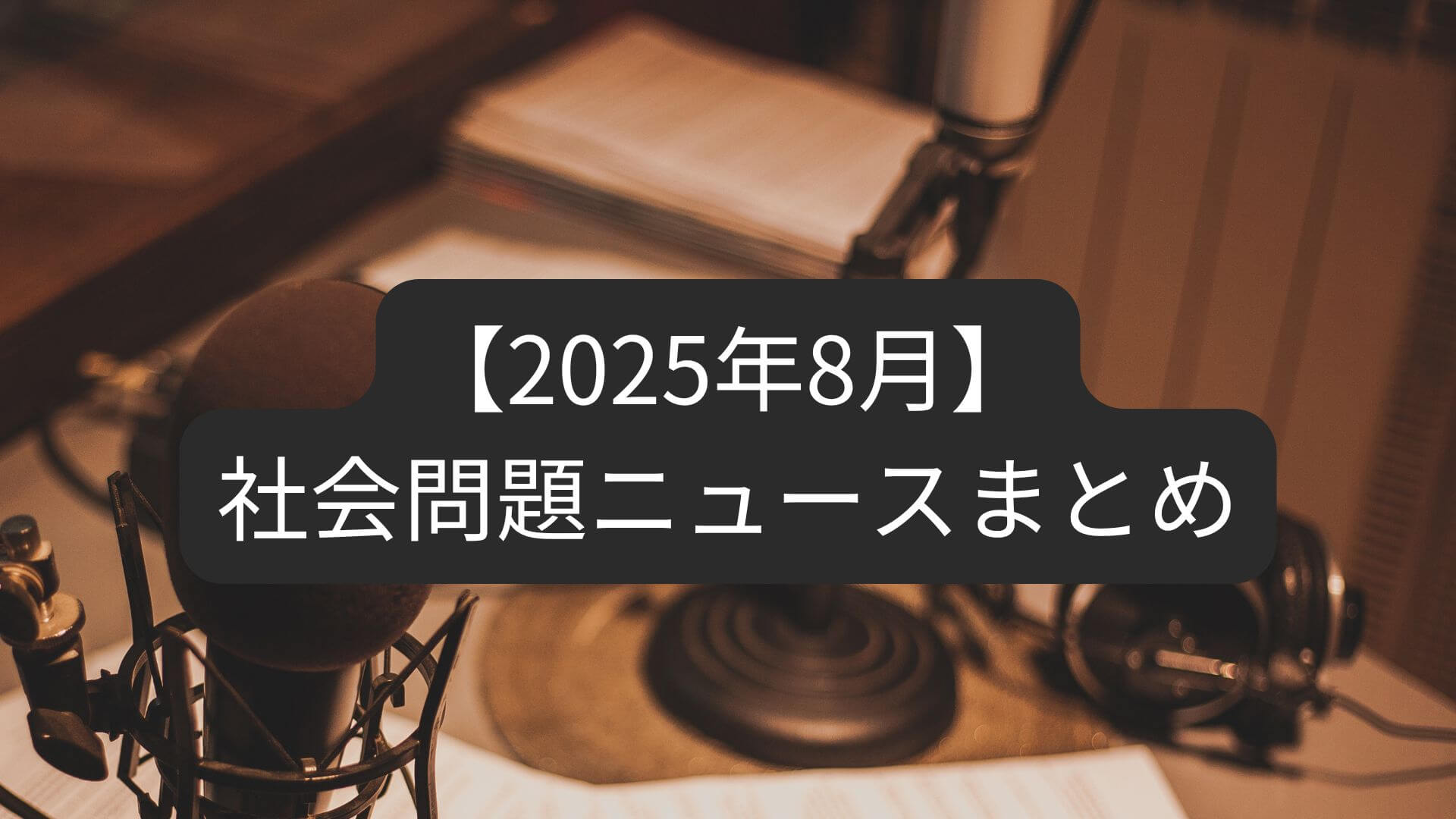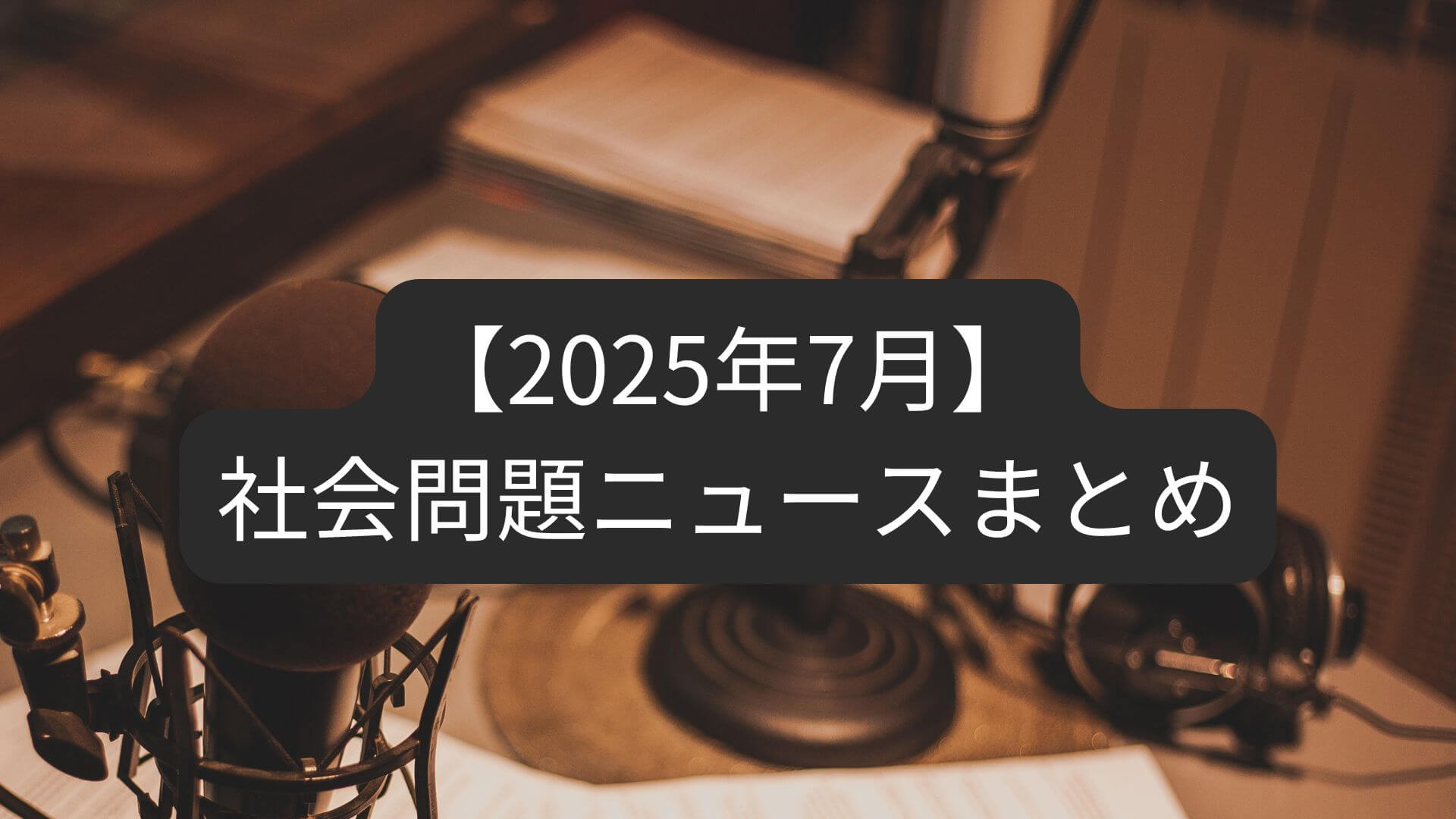近年、SDGs(持続可能な開発目標)という言葉を耳にする機会が増えています。
その中でも「海の豊かさを守ろう」は、私たちの生活と密接に関わる重要なテーマです。
海は地球の約70%を占め、気候調節や食料供給など、私たちの生存に欠かせない役割を果たしています。
しかし、現在、海は深刻な危機に直面しています。
この記事では、SDGsの目標14「海の豊かさを守ろう」について、基本的な情報から現状、課題、そして私たちにできることをわかりやすく解説します。
目次
海の豊かさを守ろうとは

「海の豊かさを守ろう」は、SDGsの17の目標のうち、目標14として設定されています。
この目標は、海洋と沿岸生態系を持続可能な形で管理し、海洋資源を保全することを目指しています。
具体的には、海洋汚染の防止、過剰漁業の規制、海洋生態系の保護などが含まれます。
海は地球の生命維持システムの一部であり、その豊かさを守ることは、私たちの未来を守ることにつながります。
SDGsとは
SDGs(Sustainable Development Goals)は、2015年に国連で採択された「持続可能な開発目標」です。
2030年までに達成すべき17の目標と169のターゲットから構成されています。
SDGsは、貧困や飢餓の撲滅、教育や医療の普及、気候変動対策など、地球上の誰一人取り残さないことを目指しています。
その中で、目標14「海の豊かさを守ろう」は、海洋資源の持続可能な利用と保全に焦点を当てています。
海の豊かさを守ろうを構成するターゲット
目標14「海の豊かさを守ろう」は、以下のような具体的なターゲットで構成されています。
| 14.1 | 2025年までに、海洋ごみや富栄養化を含む、特に陸上活動による汚染など、あらゆる種類の海洋汚染を防止し、大幅に削減する。 |
| 14.2 | 2020年までに、海洋及び沿岸の生態系に関する重大な悪影響を回避するため、強靱性(レジリエンス)の強化などによる持続的な管理と保護を行い、健全で生産的な海洋を実現するため、海洋及び沿岸の生態系の回復のための取組を行う。 |
| 14.3 | あらゆるレベルでの科学的協力の促進などを通じて、海洋酸性化の影響を最小限化し対処する。 |
| 14.4 | 水産資源を、実現可能な最短期間で少なくとも各資源の生物学的特性によって定められる最大持続生産量のレベルまで回復させるため、2020年までに、漁獲を効果的に規制し、過剰漁業や違法・無報告・無規制(IUU)漁業及び破壊的な漁業慣行を終了し、科学的な管理計画を実施する。 |
| 14.5 | 2020年までに、国内法及び国際法に則り、最大限入手可能な科学情報に基づいて、少なくとも沿岸域及び海域の10パーセントを保全する。 |
| 14.6 | 開発途上国及び後発開発途上国に対する適切かつ効果的な、特別かつ異なる待遇が、世界貿易機関(WTO)漁業補助金交渉の不可分の要素であるべきことを認識した上で、2020年までに、過剰漁獲能力や過剰漁獲につながる漁業補助金を禁止し、違法・無報告・無規制(IUU)漁業につながる補助金を撤廃し、同様の新たな補助金の導入を抑制する**。 **現在進行中の世界貿易機関(WTO)交渉およびWTOドーハ開発アジェンダ、ならびに香港閣僚宣言のマンデートを考慮。 |
| 14.7 | 2030年までに、漁業、水産養殖及び観光の持続可能な管理などを通じ、小島嶼開発途上国及び後発開発途上国の海洋資源の持続的な利用による経済的便益を増大させる。 |
| 14.a | 海洋の健全性の改善と、開発途上国、特に小島嶼開発途上国および後発開発途上国の開発における海洋生物多様性の寄与向上のために、海洋技術の移転に関するユネスコ政府間海洋学委員会の基準・ガイドラインを勘案しつつ、科学的知識の増進、研究能力の向上、及び海洋技術の移転を行う。 |
| 14.b | 小規模・沿岸零細漁業者に対し、海洋資源及び市場へのアクセスを提供する。 |
| 14.c | 「我々の求める未来」のパラ158において想起されるとおり、海洋及び海洋資源の保全及び持続可能な利用のための法的枠組みを規定する海洋法に関する国際連合条約(UNCLOS)に反映されている国際法を実施することにより、海洋及び海洋資源の保全及び持続可能な利用を強化する。 |
海の豊かさを守ろうが生まれた背景
「海の豊かさを守ろう」が生まれた背景には、海洋環境が直面する深刻な問題があります。
プラスチックごみや化学物質による海洋汚染は、海洋生物に大きな影響を与え、過剰漁業により多くの魚種が絶滅の危機に瀕しています。
さらに、気候変動による海水温の上昇や海洋酸性化は、サンゴ礁の白化や生態系の崩壊を引き起こしています。
これらの問題を解決し、持続可能な形で海洋資源を利用するため、国際社会はSDGsの目標14「海の豊かさを守ろう」を設定しました。
この目標は、未来の世代に豊かな海を引き継ぐための重要な取り組みです。
≫気候変動とは?原因と考えられる具体例、私たちができることを解説
≫海面上昇の対策とは?日本や海外の現状、私たちにできること
海の豊かさを守ろうの現状

現在、海洋環境は以下のような状況にあります。
プラスチック汚染
現在、年間800万トン以上のプラスチックごみが海に流れ込んでいます。
これにより、海洋生物がプラスチックを誤飲したり、絡まったりする事例が後を絶ちません。
特にマイクロプラスチック(5mm以下の微小なプラスチック粒子)は、食物連鎖を通じて魚や貝類に蓄積され、最終的には人間の健康にも影響を及ぼす可能性が指摘されています。
また、プラスチックごみは海洋生態系を破壊し、沿岸地域の観光業や漁業にも悪影響を与えています。
≫海洋プラスチックごみ問題の現状、日本と世界の取り組み・テクノロジーを解説
参考:環境省_令和2年版 環境・循環型社会・生物多様性白書 状況第1部第1章第3節
魚資源の減少
世界の魚資源の約3分の1が過剰漁獲により持続不可能な状態にあります。
特にマグロやサバなどの人気魚種は、その生息数が激減しています。
過剰漁業は、生態系のバランスを崩し、食物連鎖を混乱させる原因となります。
さらに、違法・無報告・無規制(IUU)漁業が横行している地域もあり、これが問題をさらに深刻化させています。
このままでは、将来的に海から持続可能な形で食料を確保することが難しくなるでしょう。
サンゴ礁の危機
世界のサンゴ礁の約50%が既に失われ、残りの多くも危機にさらされています。
サンゴ礁は「海の熱帯雨林」とも呼ばれ、多様な生物の生息地として重要な役割を果たしています。
しかし、海水温の上昇による白化現象や、海洋酸性化、さらには観光開発や汚染による直接的な破壊が進んでいます。
サンゴ礁の減少は、海洋生物の多様性を失うだけでなく、沿岸地域の防災機能(津波や高潮の緩和)も弱めることにつながります。
≫絶滅危惧種とは?2024年最新版!26種類の動物を一覧で解説
≫レッドリストとは?絶滅危惧種のIUCN・環境省による評価基準やカテゴリーを解説
海の豊かさを守ろうの課題
目標14を達成するためには、以下のような課題があります。
国際協力の不足
海洋問題は国境を越えるため、各国が協力して取り組む必要がありますが、現状では国際的な連携が十分ではありません。
例えば、違法・無報告・無規制(IUU)漁業は、特定の国や地域だけでなく、広範な海域で行われており、これを根絶するためには国際的な監視体制や情報共有が不可欠です。
また、海洋保護区の設置や管理においても、各国の利害が対立し、合意形成が難しい場合があります。
さらに、気候変動や海洋酸性化のような地球規模の問題に対処するためには、先進国と開発途上国が協力して技術や資金を共有する必要がありますが、その枠組みがまだ不十分です。
≫国際協力とは?15種類の問題と日本の取り組み、キャリアについて簡単に解説!
資金と技術の不足
海洋環境の保全と持続可能な利用には、莫大な資金と先進技術が必要です。
特に開発途上国では、海洋保護区の設置や管理、持続可能な漁業の推進に必要な資金や技術が不足しています。
例えば、衛星監視システムやデータ分析技術は、違法漁業の防止や漁獲量の管理に有効ですが、これらの技術を導入するためのコストが障壁となっています。
また、海洋汚染の防止やサンゴ礁の修復には、長期的な投資が必要ですが、短期的な経済利益を優先する傾向が強いため、資金が十分に確保されていないのが現状です。
一般市民の意識の低さ
海洋問題に対する一般市民の関心が低く、行動に結びついていないことも大きな課題です。
多くの人々が、海洋汚染や過剰漁業の問題を「遠い海の話」として捉え、自分たちの生活と直接関連があると認識していません。
例えば、プラスチックごみの問題は、個人の消費行動や廃棄物管理の改善によって大きく軽減できるにもかかわらず、その重要性が十分に理解されていません。
また、持続可能な魚介類を選ぶ「エコラベル」の認知度も低く、消費者が適切な選択をするための情報が不足しています。
海の豊かさを守ろうに取り組む企業3選

海の豊かさを守ろうに取り組む企業を紹介します。
≫【SDGs目標14】海の豊かさを守ろうに取り組む企業10選!就職・転職におすすめの大企業からベンチャー
株式会社ライトハウス
株式会社ライトハウスは、船舶へのITとデータ活用を通じて海洋資源探索の最適化を目指すIT企業です。
まき網漁やひき網漁におけるコミュニケーションの課題を解決し、漁業の効率化を実現する「ISANA」の研究開発と運用を通じて、日本の漁業に大きく貢献していることが特徴です。
自律的に内部構造を変化させ、未知の領域に柔軟に適応していく「探索型組織」を採用することで、急速に変化する市場や技術動向に迅速に対応し、新たな機会を捉えることが可能としているのもまた、特筆すべき個性の一つです。
HP:https://lighthouse-frontier.tech/
株式会社ベンナーズ
株式会社ベンナーズは、未利用魚を活用した商品開発などに取り組む福岡県福岡市にある会社です。
「日本の食と水産業界を守る」を経営理念に掲げ、食の三方よし「作り手、使い手、社会を豊かにすること」を目指しています。
総水揚げ量の30%といわれる規格外魚介類の価値を再発見し、海の生態系のバランス保持と日本の水産業の持続可能な発展に貢献しています。
HP:https://www.benners.co.jp/
合同会社シーベジタブル
合同会社シーベジタブルは、海藻を採取・研究し、食用として加工・販売する会社です。
収穫量が減少し供給量が不足していた海藻を栽培することで、安定的に供給することが可能になりました。
多様なスペシャリストが集い、社外の研究者などとも連携して、分野を横断して海藻の基礎研究から栽培技術の確立まで取り組んでいます。
HP:https://seaveges.com/
海の豊かさを守ろうに対して私たちができること5選

海の豊かさを守ろうに対して私たちができることを紹介します。
プラスチック使用の削減
プラスチックごみは海洋汚染の主要な原因の一つです。
私たちは日常生活でプラスチックの使用を減らすことで、海へのごみの流入を防ぐことができます。
具体的には、レジ袋の代わりにエコバッグを使う、プラスチックストローを避ける、使い捨て容器ではなく再利用可能な容器を選ぶなどが挙げられます。
また、プラスチック製品をリサイクルする習慣を身につけることも重要です。
これにより、プラスチックごみが海に流れ込むリスクを大幅に減らすことができます。
持続可能な魚介類の選択
過剰漁業や違法漁業を防ぐため、持続可能な方法で獲られた魚介類を選ぶことが重要です。
MSC(海洋管理協議会)やASC(水産養殖管理協議会)などのエコラベルが付いた商品を選ぶことで、持続可能な漁業や養殖業を支援することができます。
また、地元で獲られた魚や旬の魚を選ぶことも、過剰な漁獲圧力を減らす一助となります。
消費者が意識的に選択することで、市場全体が持続可能な方向に変わっていくことが期待されます。
海洋保護活動への参加
地域で行われているビーチクリーンや植林活動に参加することで、直接的に海洋環境の保全に貢献できます。
ビーチクリーンは、海岸に漂着したごみを回収し、海洋生物の誤飲や絡まりを防ぐ効果があります。
また、マングローブや海草の植林は、沿岸生態系を回復させ、生物多様性を守るために有効です。
これらの活動に参加することで、海洋問題に対する理解を深め、地域社会との連帯感も高まります。
情報の発信と共有
SNSやブログなどを活用して、海洋問題に関する情報を発信し、周囲の意識を高めることも重要です。
例えば、プラスチックごみの問題や持続可能な魚介類の選び方について発信することで、多くの人々が問題を理解し、行動を起こすきっかけを作ることができます。
また、海洋保護団体の活動やイベント情報を共有することで、より多くの人々が参加する機会を増やすことができます。
情報の発信は、個人でも簡単にできる効果的なアクションです。
≫レポートで書きやすいSDGsのテーマ10選!テーマの選び方や参考になる調査を解説
≫レポートで書きやすい貧困問題のテーマ5選!テーマの選び方の例や調査・機関を解説
≫【2024年最新版】社会課題やSDGs、サステナブルについて発信するメディア30選!
政策への関与
海洋保護に関する政策に注目し、署名活動や投票を通じて意見を反映させることも重要です。
例えば、プラスチック規制や漁業管理に関する法律が制定される際には、その内容を確認し、支持または改善を求める声を届けることができます。
また、選挙では海洋環境を重視する政治家や政党を支持することで、政策レベルでの変化を促すことができます。
市民の声が集まることで、政府や企業が海洋保護に向けた取り組みを強化する可能性が高まります。
まとめ
「海の豊かさを守ろう」は、SDGsが掲げる重要な目標の一つです。
海は私たちの生活に欠かせない資源であり、その豊かさを守ることは、未来の世代への責任でもあります。
現状は厳しいですが、一人ひとりの小さな行動が大きな変化につながります。
まずは身近なことから始めて、海の豊かさを守るための一歩を踏み出しましょう。
【その他のSDGsの目標を詳しく知りたい】
【SDGs目標1】貧困をなくそうとは?背景や現状、企業の取り組み、私たちにできることを解説
【SDGs目標2】飢餓をゼロにとは?背景や現状、企業の取り組み、私たちにできることを解説
【SDGs目標3】すべての人に健康と福祉をとは?背景や現状、企業の取り組み、私たちにできることを解説
【SDGs目標4】質の高い教育をみんなにとは?背景や現状、企業の取り組み、私たちにできることを解説
【SDGs目標5】ジェンダー平等を実現しようとは?背景や現状、企業の取り組み、私たちにできることを解説
【SDGs目標6】安全な水とトイレを世界中にとは?背景や現状、企業の取り組み、私たちにできることを解説
【SDGs目標7】エネルギーをみんなに そしてクリーンにとは?背景や現状、企業の取り組み、私たちにできることを解説
【SDGs目標8】働きがいも経済成長もとは?背景や現状、企業の取り組み、私たちにできることを解説
【SDGs目標9】産業と技術革新の基盤を作ろうとは?背景や現状、企業の取り組み、私たちにできることを解説
【SDGs目標10】人や国の不平等をなくそうとは?背景や現状、企業の取り組み、私たちにできることを解説
【SDGs目標11】住み続けられるまちづくりをとは?背景や現状、企業の取り組み、私たちにできることを解説
【SDGs目標12】つくる責任つかう責任とは?背景や現状、企業の取り組み、私たちにできることを解説
【SDGs目標13】気候変動に具体的な対策をとは?背景や現状、企業の取り組み、私たちにできることを解説
【SDGs目標14】海の豊かさを守ろうとは?背景や現状、企業の取り組み、私たちにできることを解説
【SDGs目標15】陸の豊かさも守ろうとは?背景や現状、企業の取り組み、私たちにできることを解説
【SDGs目標16】平和と公正をすべての人にとは?背景や現状、企業の取り組み、私たちにできることを解説
【SDGs目標17】パートナーシップで目標を達成しようとは?背景や現状、企業の取り組み、私たちにできることを解説

この記事の監修者
吉田宏輝
COCOCOLOREARTH代表、社会活動家。
COCOCOLOREARTHでは、社会課題解決を軸にした就職・転職活動を支援するインタビューメディアの代表として、100人以上の社会活動家にインタビュー、記事執筆やイベント登壇などを行う。