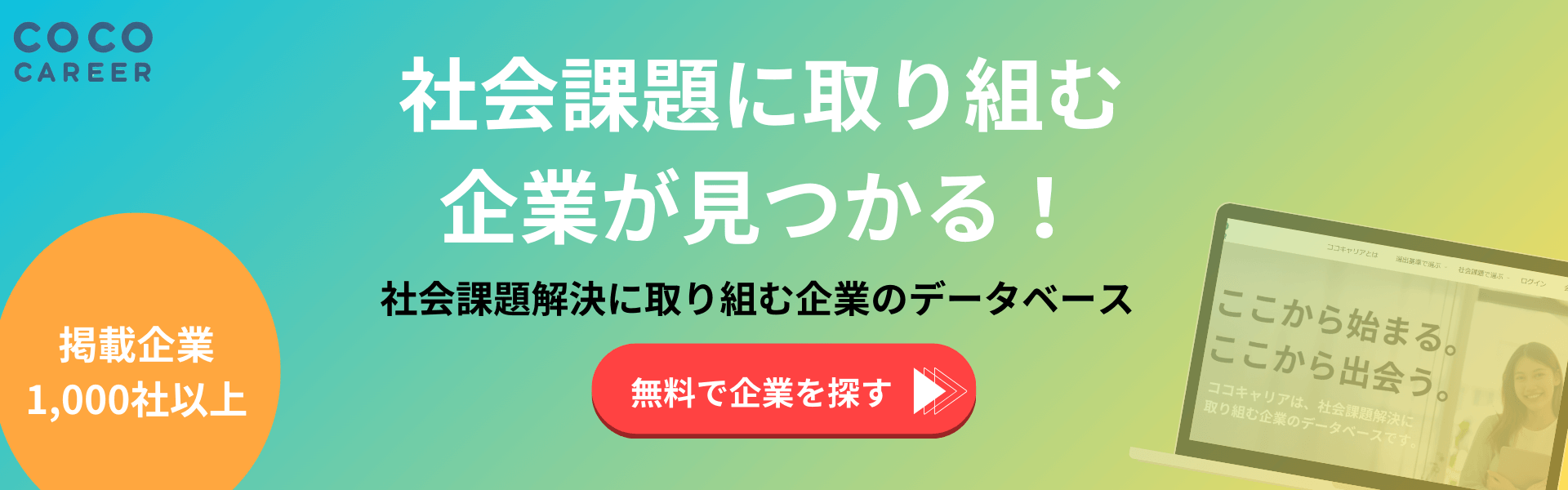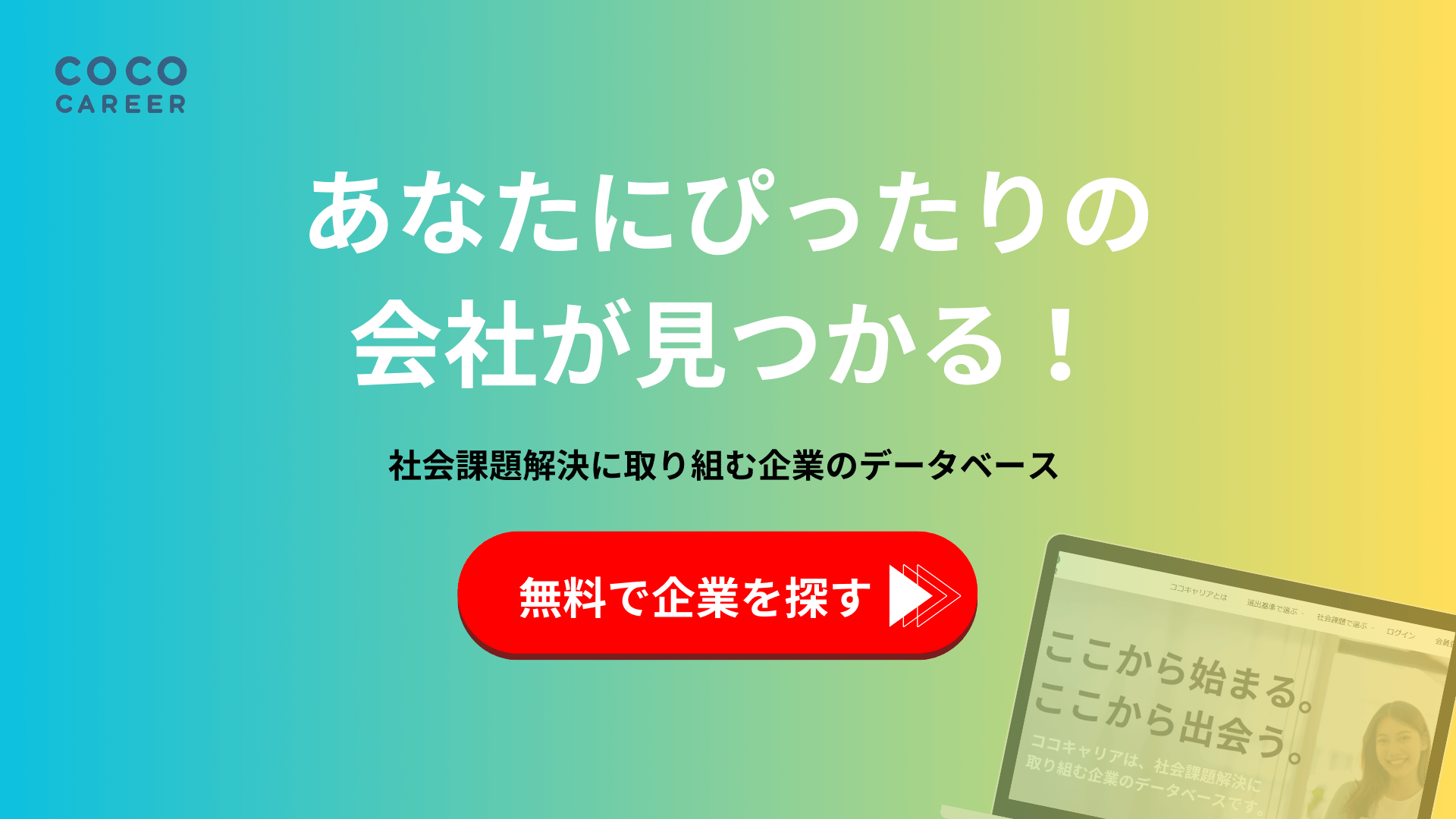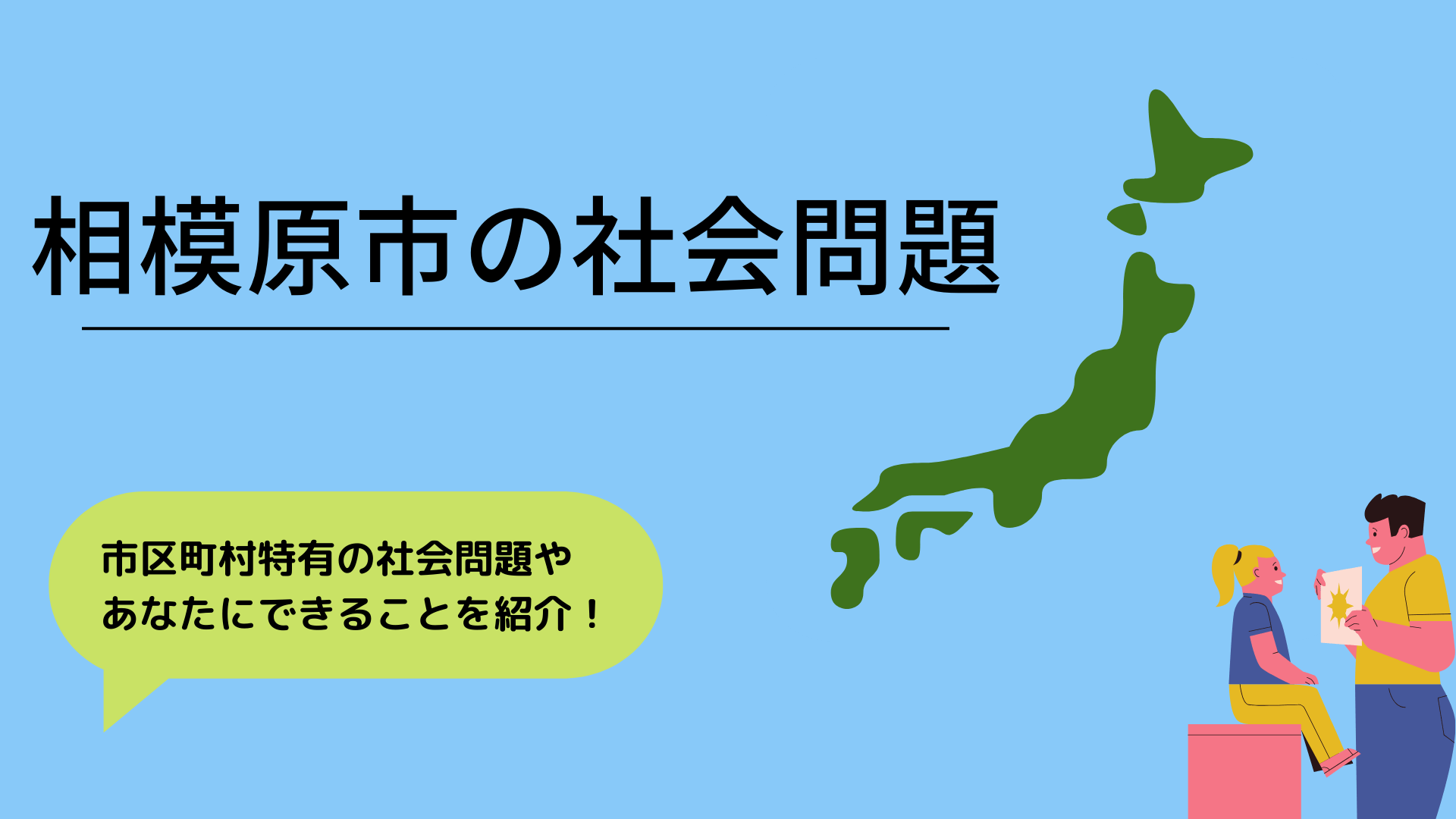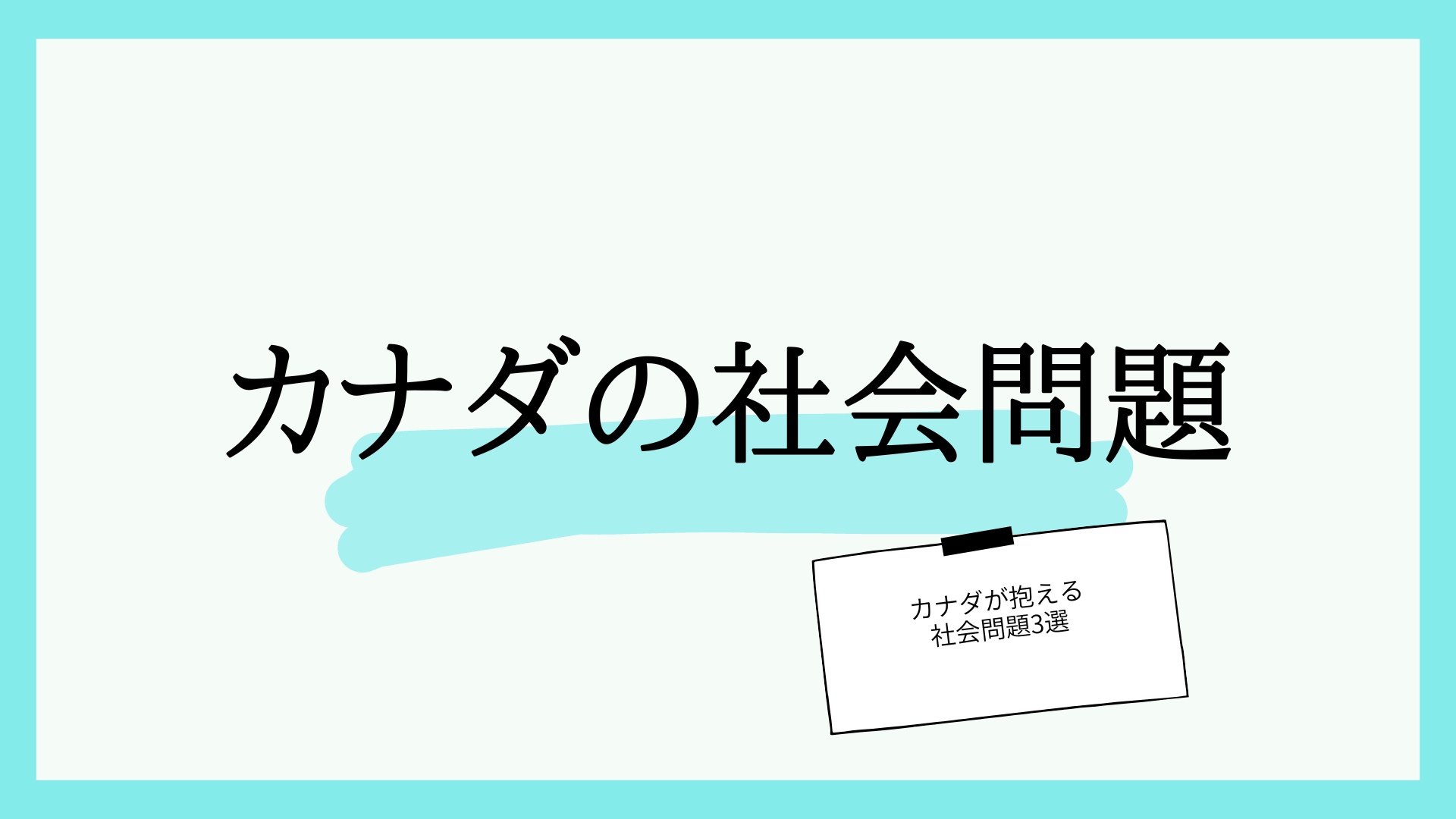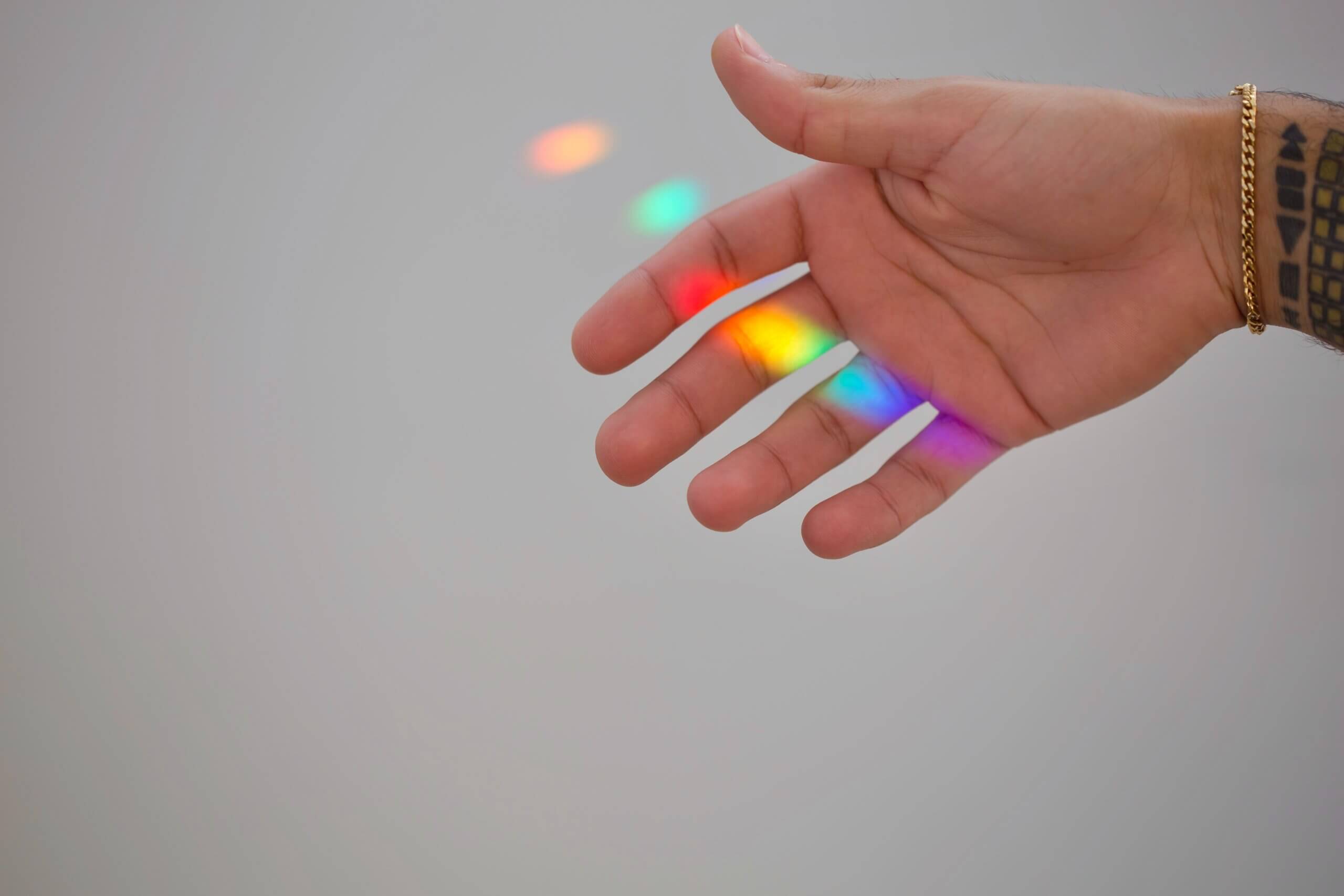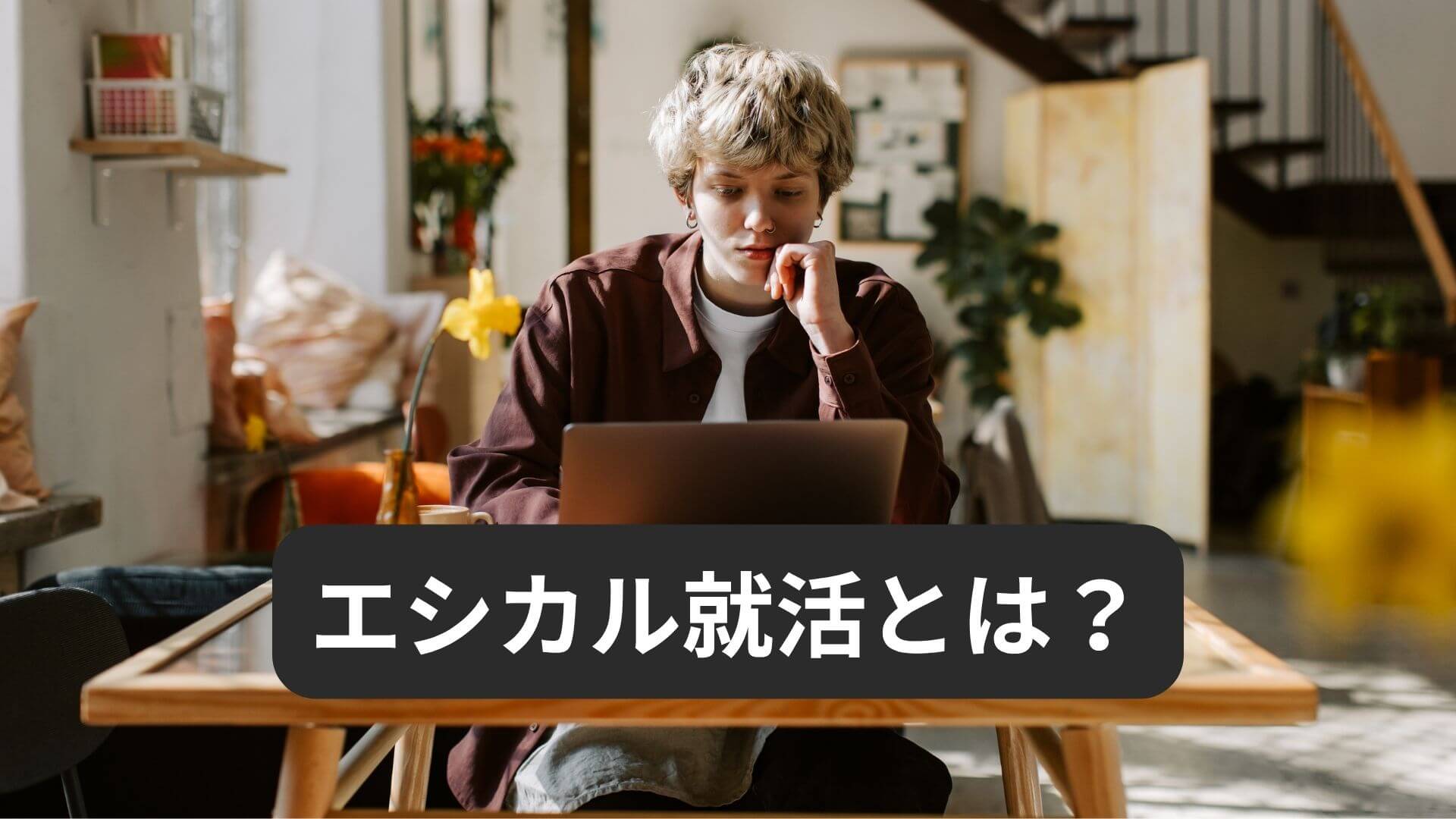南北問題という言葉は、誰しも歴史の授業などで耳にしたことがあると思います。
しかし、問題の背景や現在起きている世界の問題との結びつきについて深く知っていることは少ないのではないでしょうか。
この記事では、南北問題について解説していきます。
南北問題について知ることで、現在起きている様々な問題に目を向けるためのヒントも得られると思います。
※【企業様向け】国際協力への取り組みをPRしませんか?
掲載を希望される企業様はこちら
目次
南北問題とは

南北問題とは、一言で言うと先進国と開発途上国の間で経済格差が生じている問題です。
地図上で見た際に途上国は南側、先進国は北側に多く位置していることからこのように呼ばれています。
実際に、経済的格差を見てみると、先進国と呼ばれる欧米などは北の方に位置し,アジアやアフリカ・南米などの発展途上国南に位置しています。
そして、先進国と途上国の間の格差は未だ解決していません。
≫紛争とは?戦争、内戦は何が違う?現在起こっている事例をもとに解説
南北問題と南南問題の違い
南北問題と南南問題の違いは、「国際的な経済格差」(南北問題)と「発展途上国間の格差」(南南問題)に焦点を当てている点です。
南南問題とは、南北問題において「南」といわれる発展途上国の中に生じてきた、「南北問題」とは違う新たな経済格差の問題です。
そのため、より南に位置する国が貧しい訳ではなく、総称として使われている言葉です。
発展途上国の中でも、経済発展に成功した国は、新興工業経済地域(NIEs)など工業化の進んだ国、または石油輸出国機構(OPEC)など資源を保有する国です。
一方、発展途上国の中でも特に経済発展が遅れている国は、後発発展途上国と呼ばれています。
≫南南問題とは?どこの国?背景や現状、南北問題との違いをわかりやすく解説
≫発展途上国とはどこ?途上国一覧と様々な定義、企業の取り組みを解説!
≫国際協力とは?15の問題と日本の取り組み、キャリアについて簡単に解説!
南北問題はいつから?歴史を解説

1960年代:南北問題の始まり
「南北問題」という言葉は1960年に当時イギリスのロイド銀行会長であったオリバー・フランクス氏の「東西問題に匹敵する問題として南北問題に目を向けるべきだ」という発言がきっかけで使われるようになりました。
しかし、この背景となる南北の経済格差はずっと昔から存在しています。
産業革命をきっかけに19世紀末には世界経済が確立し、国際分業体制が出来上がりました。
その中で工業国、農業国と分化していくことでヨーロッパの植民地であった国々では特定の作物に依存する経済形態に転換せざるを得なくなりました。
これが南北間の国々の格差が広まる原因となります。
1970年代:第一次オイルショック
先ほど述べたように1960年に南北問題が注目されるようになりましたが、1970年代になるとその状況に変化が生じます。
1973年の第一次オイルショックで原油価格が高騰したことがきっかけで、石油をはじめ天然資源が豊富な発展途上国は保有する天然資源が国際社会で大きな力となるという認識が広まりました。
こうして、産出した天然資源を先進国の支配から取り戻し、自国主権で開発を行おうとする資源ナショナリズムの動きが盛んになったのです。
1980年代:国際機関が多額の借金を
1970年代には国際機関が多額の借金を負うようになりました。
これが原因で1980年代になると、アフリカや中南米の国々は元利の返済に追われるようになり、短期間で物価が異常に高騰し経済が混乱しました。
石油産出国や新興工業国の所得が向上していった一方で、最貧国が衰退していき南南問題が顕著になったのもこの頃です。
1990年代:東西冷戦が終結
1989年に東西冷戦が終結したことにより、「発展途上国に対する援助を通じて、それらの国々を支配下につなぎ止めておく」考え方が通用しなくなりました。
これにより、非軍事的な考え方を含む開発や援助の方法が模索され始めたのです。
≫グローバルサウスとは?G7やウクライナ危機で存在感が増す「グローバルサウス」の意味
現在起きている南北問題の具体例

経済格差
経済格差による貧困問題は今でも存在しており、世界銀行が定義している国際貧困ライン(1日1.9ドル未満)以下で暮らす人々もいるのが現実です。
また、世界の人口の80%が発展途上国に集中しているにも関わらず、食料不足に陥っている一方で先進国では食料が余っている事態も生じています。
この背景には歴史が大きく関係しています。
そのため、現在でも発展途上国は貧困から抜け出すのが難しい状況が続いているのです。
教育格差
経済格差のみならず、教育格差も深刻です。
UNICEFが発表した「世界子供白書2023」によれば、若者(15~24歳)の識字率は世界平均で男子が93%、女子が91%である一方で後発開発途上国の多いサハラ以南のアフリカでは男子が79%、女子が74%となっています。
教育が十分に受けられない原因としては、そもそも教育を受けられる学校がない、金銭的に貧しい、戦争や紛争が起きているなどが挙げられます。
情報格差(デジタルデバイド)
発展途上国と先進国との間でインターネット普及率やIT人材の確保などに格差が生まれています。
実際、2020年でもインターネットを使う人の比率は、先進国では87.8%なのに対し、発展途上国では57.8%と大きな開きがあります。
参考:Committed to connecting the world
≫デジタルデバイド(情報格差)とは?日本の現状や原因、企業の取り組みを紹介
南北問題に対する取り組み

国際機関による取り組み
国際社会における南北問題への取り組みが始まったのは1960年代前半のことでした。
1961年に国連が発表した「第1次国連開発10年のための国際開発戦略」は開発途上国の発展に寄与するためでした。
これにより、開発途上国全体の国内総生産(GDP)年平均成長率を5%以上に引き上げることを目標に掲げ、60年代後半には5.3%にまで上昇させることに成功しました。
更に、資源産出国の自国の資源の主権を守るための「天然の富と資源に対する永久主権」や開発途上国の貿易拡大のための機関「UNCTAD」の設立など様々な取り組みが行われてきました。
その後も「国連開発の10年」は10年ごとに見直しが行われ、1990年の第4次戦略まで続くことになります。
そして、現在では「持続可能な開発目標(SDGs)」という世界共通の目標設定をすることで、今もなお取り組みがなされているのです。
日本の取り組み
日本の南北問題に対する取り組みは、1954年の南アジア諸国へのODA(政府開発援助)による支援への参加が始まりです。
この頃は援助国が南アジアに限られていましたが、1974年にはJICAの前身となる国際協力事業団を設立し、ODAを拡大していきました。
また近年では、APECやASEANといった機関と連携したり、アフリカ地域との協力体制も強化するなど積極的に開発途上国への援助に取り組んでいます。
≫SDGsに取り組む企業10選~ベンチャーから大企業まで~
≫開発コンサルに取り組む企業10選!就職・転職におすすめの大企業からベンチャー
≫国際協力に取り組む企業10選~ソーシャルビジネスと開発コンサルを中心に~
≫ヘルスケアに取り組む企業10選~ベンチャーから大企業まで~
南北問題は日本でも起こっている
南北問題は国の中でも起こりうるのです。
この記事では、日本で起こっている南北問題も取り上げます。
千葉県の南北問題
千葉県では、人口の3/4が県全体の30%の面積に偏り、残りの約70%の面積には人口の1/4しかいないのが現状です。
また、大型商業施設の開業などで県北部や東京湾岸は商圏を広げた一方で、県南部や外房地域では縮小傾向にあります。
そのため、人口だけでなく、商業についても南北問題があります。
参考:平成30年度消費者購買動向調査報告書 – 千葉県
:千葉県の集客力、南北差ひらく 18年度県調査
≫千葉県の社会問題とは?南北問題の課題や独自の取り組みを解説
兵庫県の南北問題
人口や経済活動は南部の瀬戸内海沿岸域に集中し、北部の中山間地域や日本海沿岸域は、人口減少や高齢化が深刻です。
そのため、北部での雇用の創出や子育て支援、健康寿命対策などが求められます。
参考:兵庫県の現状と課題
:兵庫県の魅力を生かす 求められる大阪・京都との連携 | 2019年9月号 | 事業構想オンライン
≫兵庫県の社会問題とは?地域格差がある南北問題や人口減少の課題を解説
千葉県と兵庫県以外でも、茨城県や三重県でも南北問題は起きています。
私たちにできること
寄付をする
寄付をすることで、あなたが課題に感じている問題に取り組むことができます。
例えば、Give Oneでは寄付先を300以上紹介しています。
独自の審査で選ばれた寄付先なので安心して募金活動ができます。
≫【12選】クリック募金とは?サイト一覧や仕組み、やり方、メリットを解説
フェアトレード商品の購入
最近では、多くのお店でフェアトレード商品が見られるようになりました。
商品には公式のラベルがついており、オンラインでの購入も可能です。
例えば、フェアトレードオンラインショップのfair selectでは世界中からフェアトレード商品を取り寄せてオンラインで販売しています。
≫エシカル消費とは?企業が取り組む重要性やメリット、事例を解説!
≫エシカル消費に取り組む企業10選!ベンチャー企業を中心にご紹介
誰かと議論してみる
あなたが誰かに世界の社会問題を発信し、議論していくことで、周りの行動や意識が変わるかもしれません。
話す内容は、何でも大丈夫です。
もしかするとあなたの家族や友人は、その問題の存在すら知らないかもしれません。
≫ソーシャルグッドとは?個人ができることや取り組む企業を解説
まとめ
この問題を遠い国のことだと思わずに、更に気になった点を調べてみることで知識を自分のものにし、周りの人に広めてみてください。
また、調べることで他の問題にも関心を持ち、知識を深めることも社会問題に対するアプローチ方法を見つけるヒントになります。
ぜひ、これをきっかけに様々な問題に目を向け「自分ごと化」してみてください。
≫【留学エージェント10選】おすすめ留学サイトを比較ランキングで紹介!
【企業様向け】国際協力の取り組みをPRしませんか?

この記事の監修者
吉田宏輝
COCOCOLOREARTH代表、社会活動家。
COCOCOLOREARTHでは、社会課題解決を軸にした就職・転職活動を支援するインタビューメディアの代表として、100人以上の社会活動家にインタビュー、記事執筆やイベント登壇などを行う。