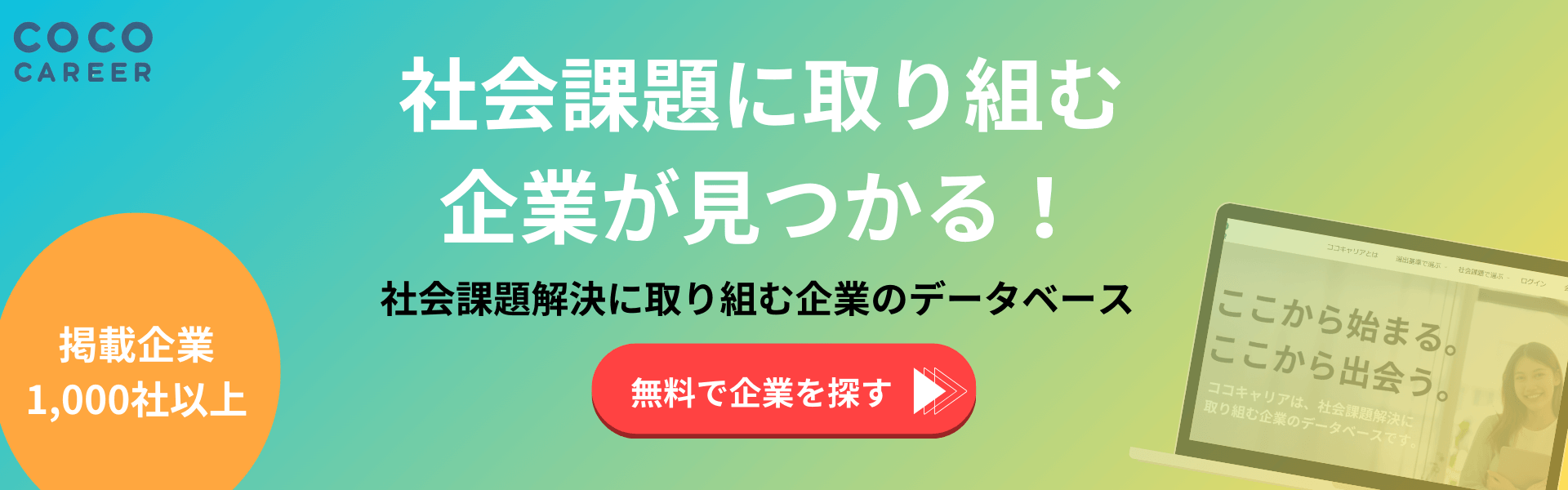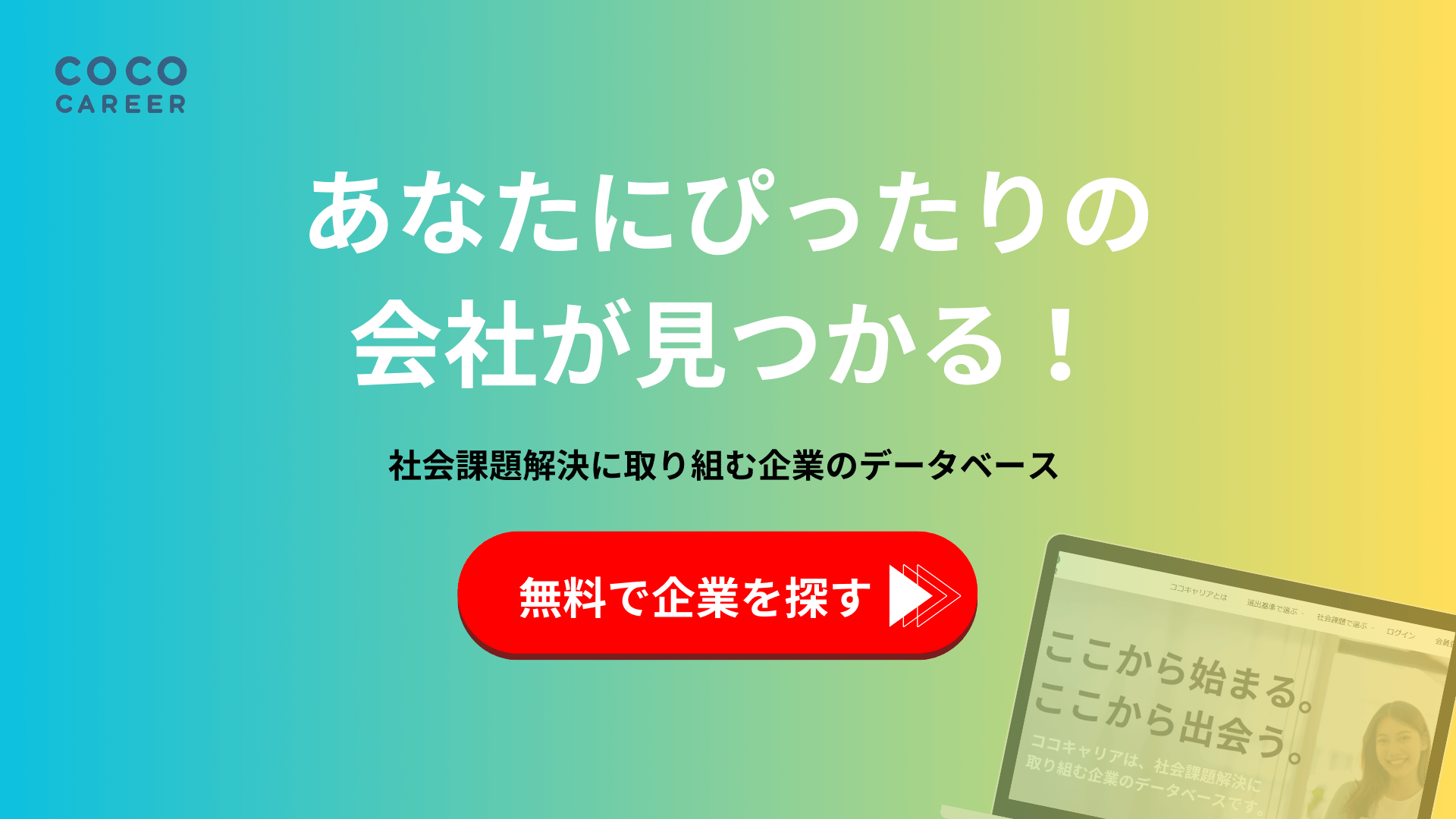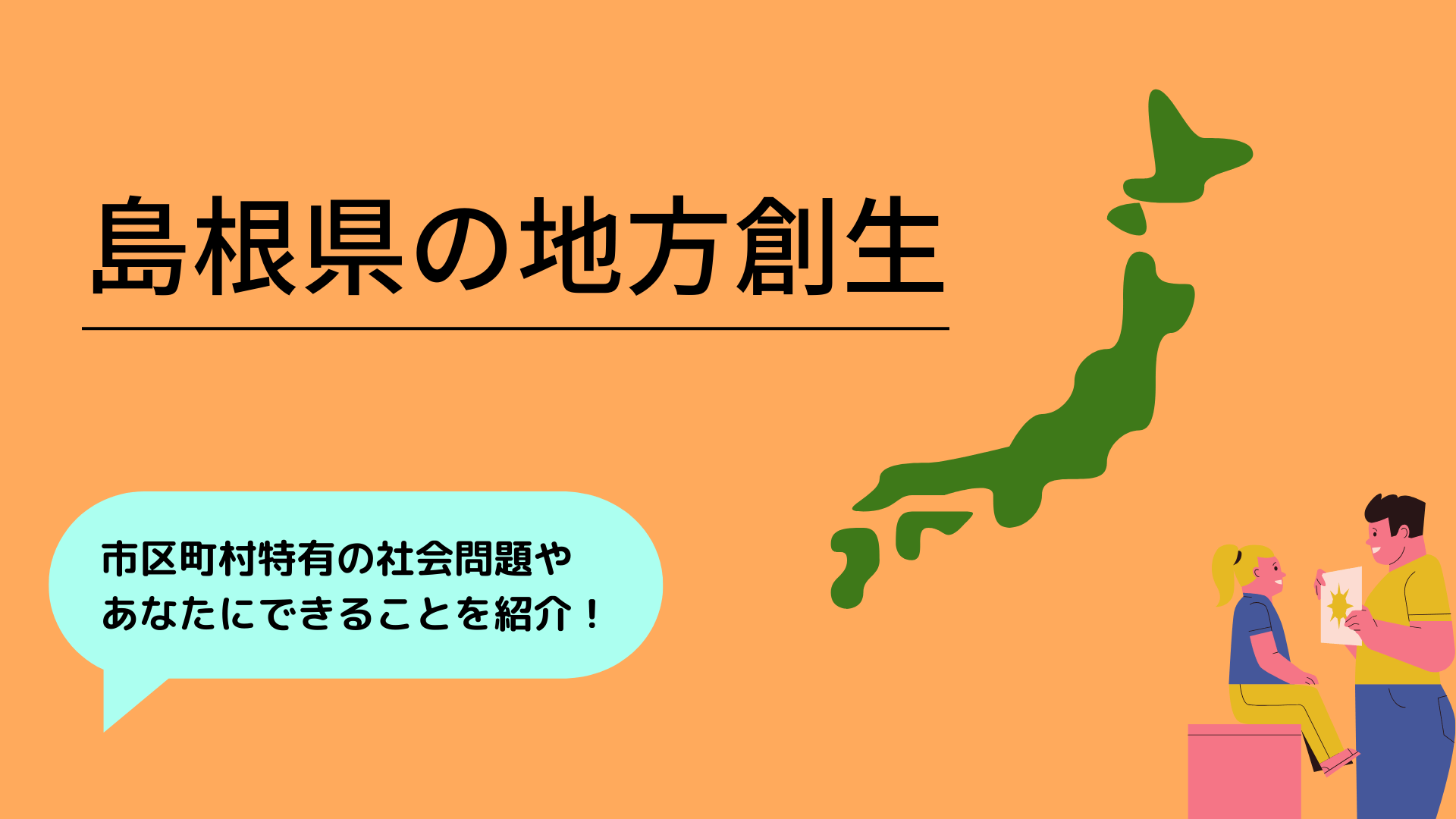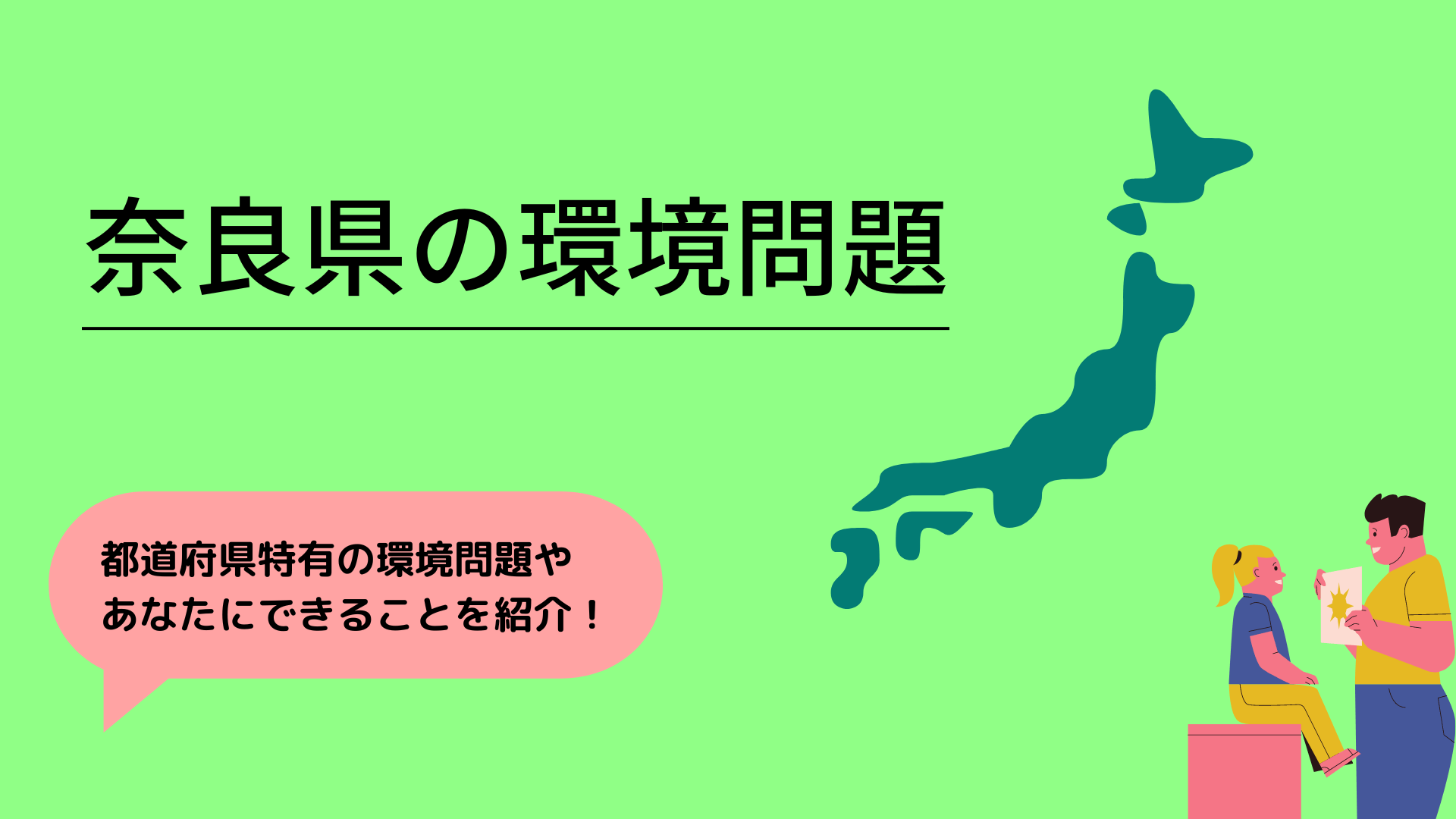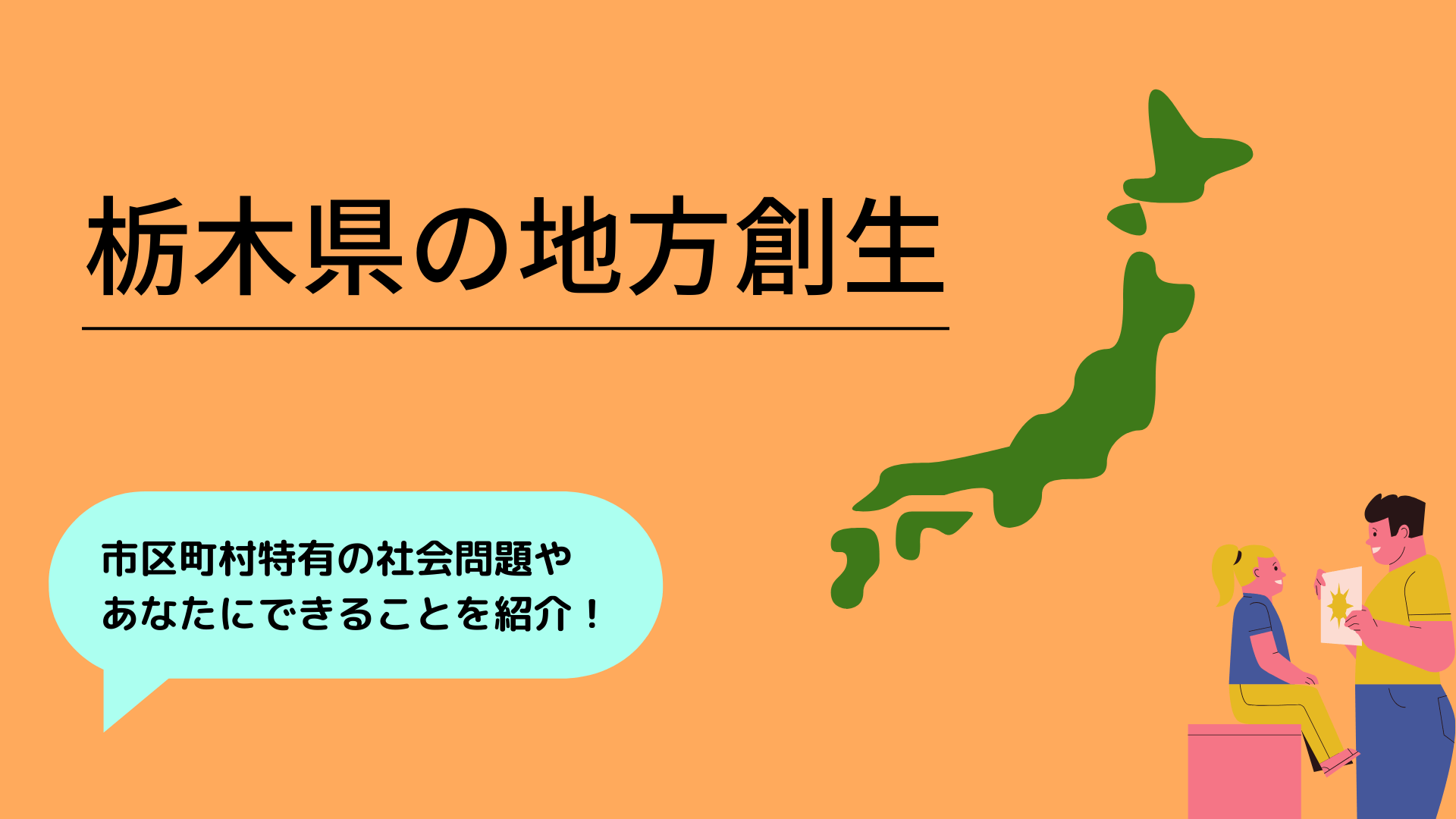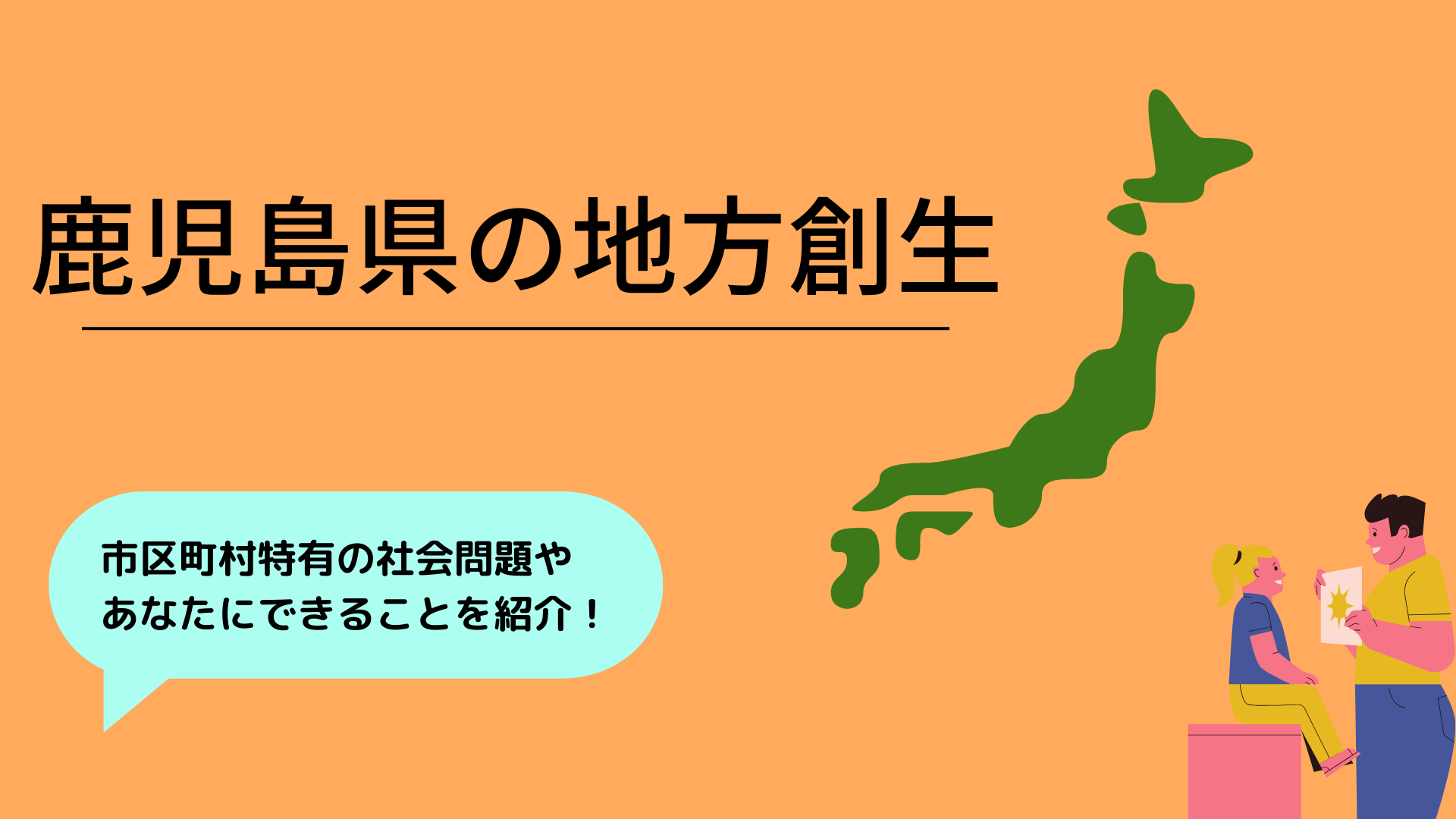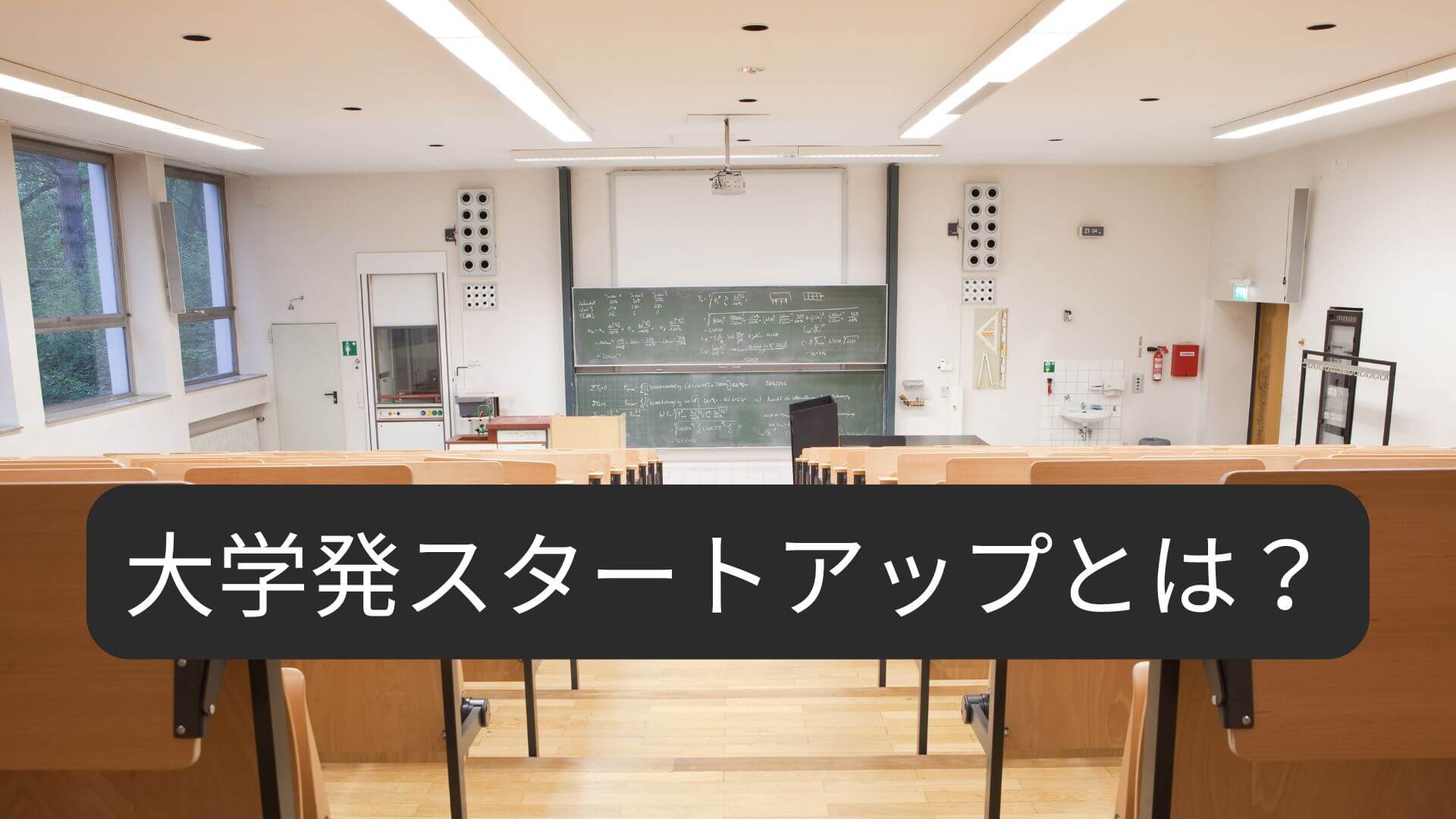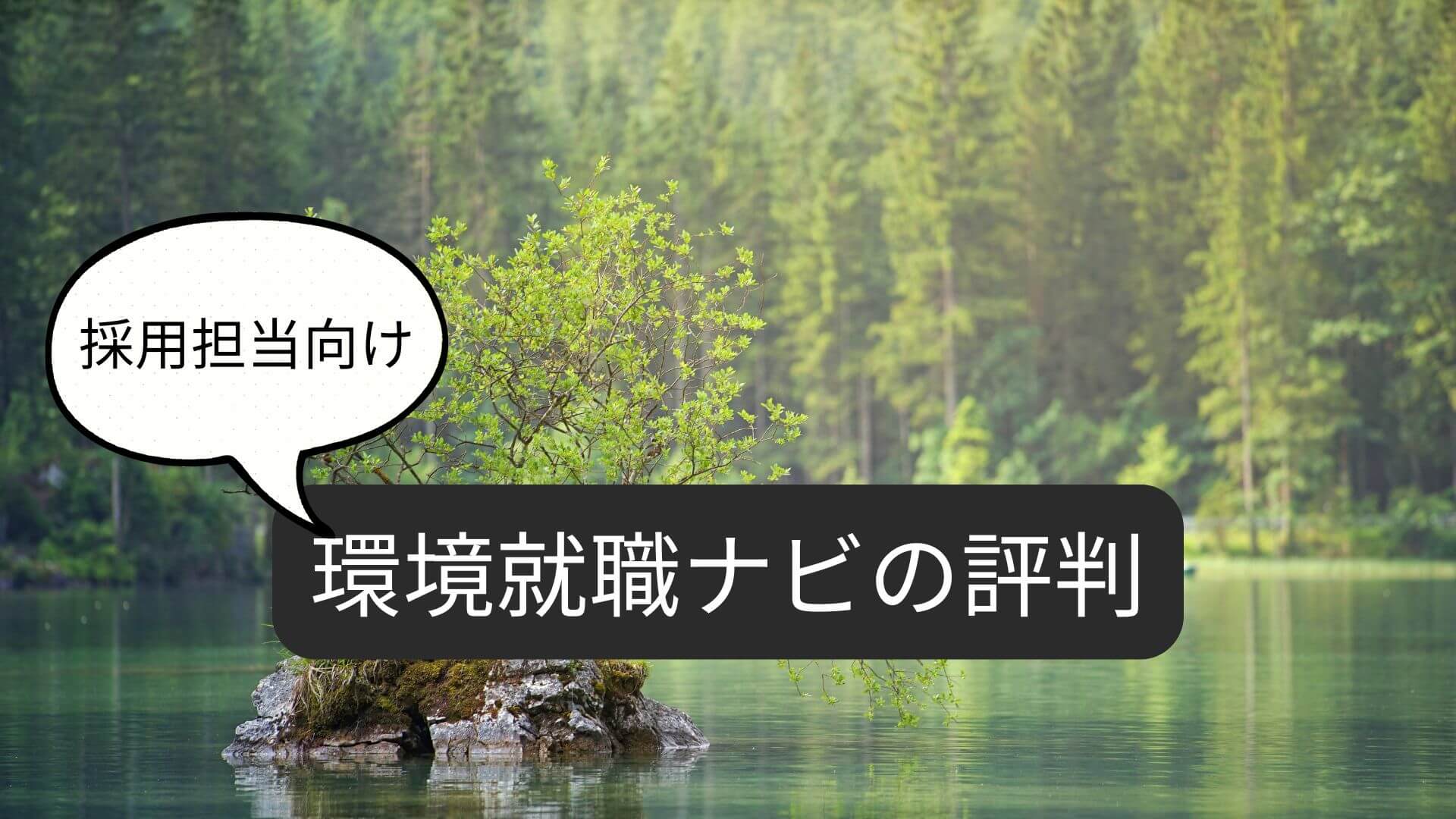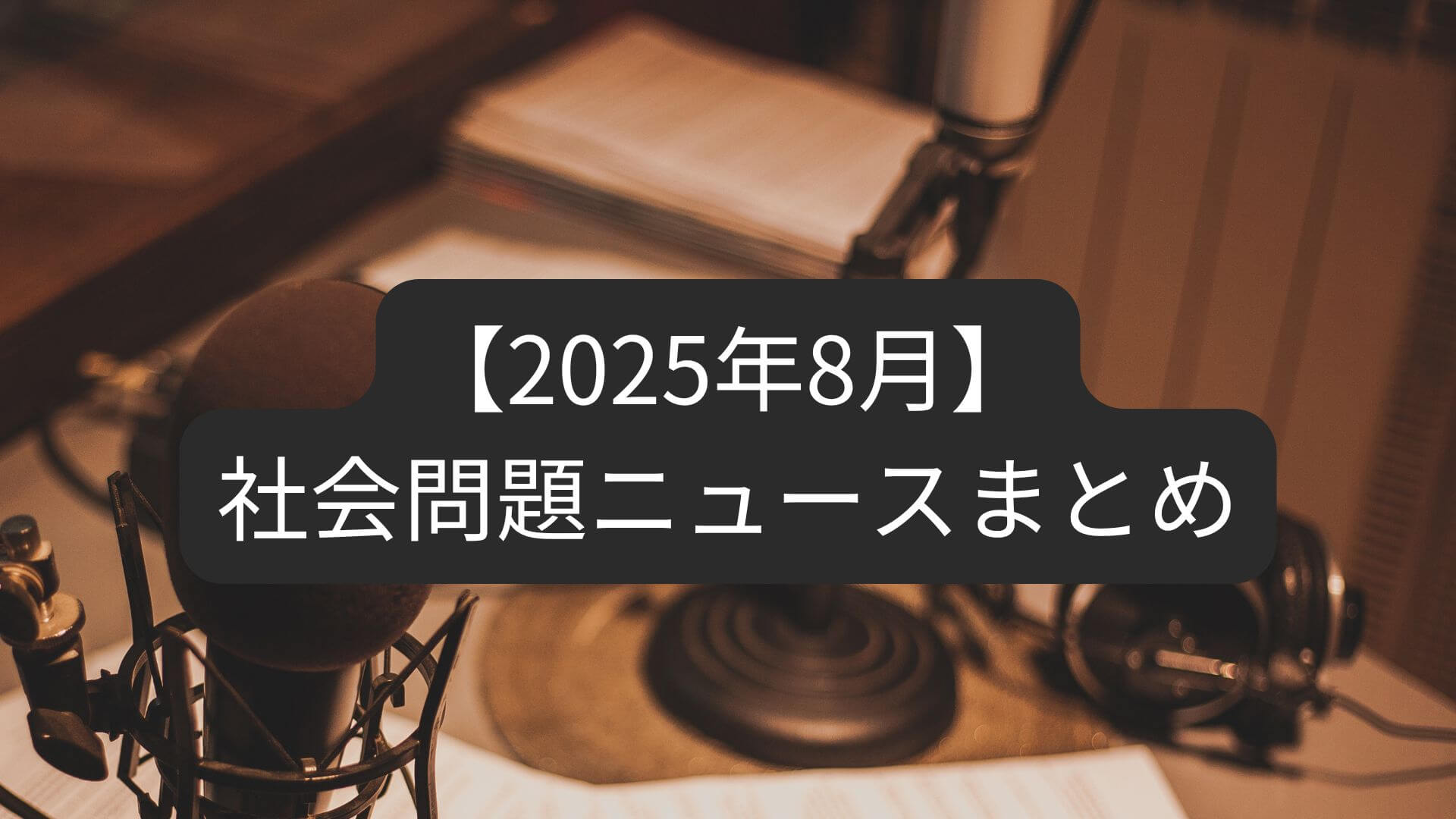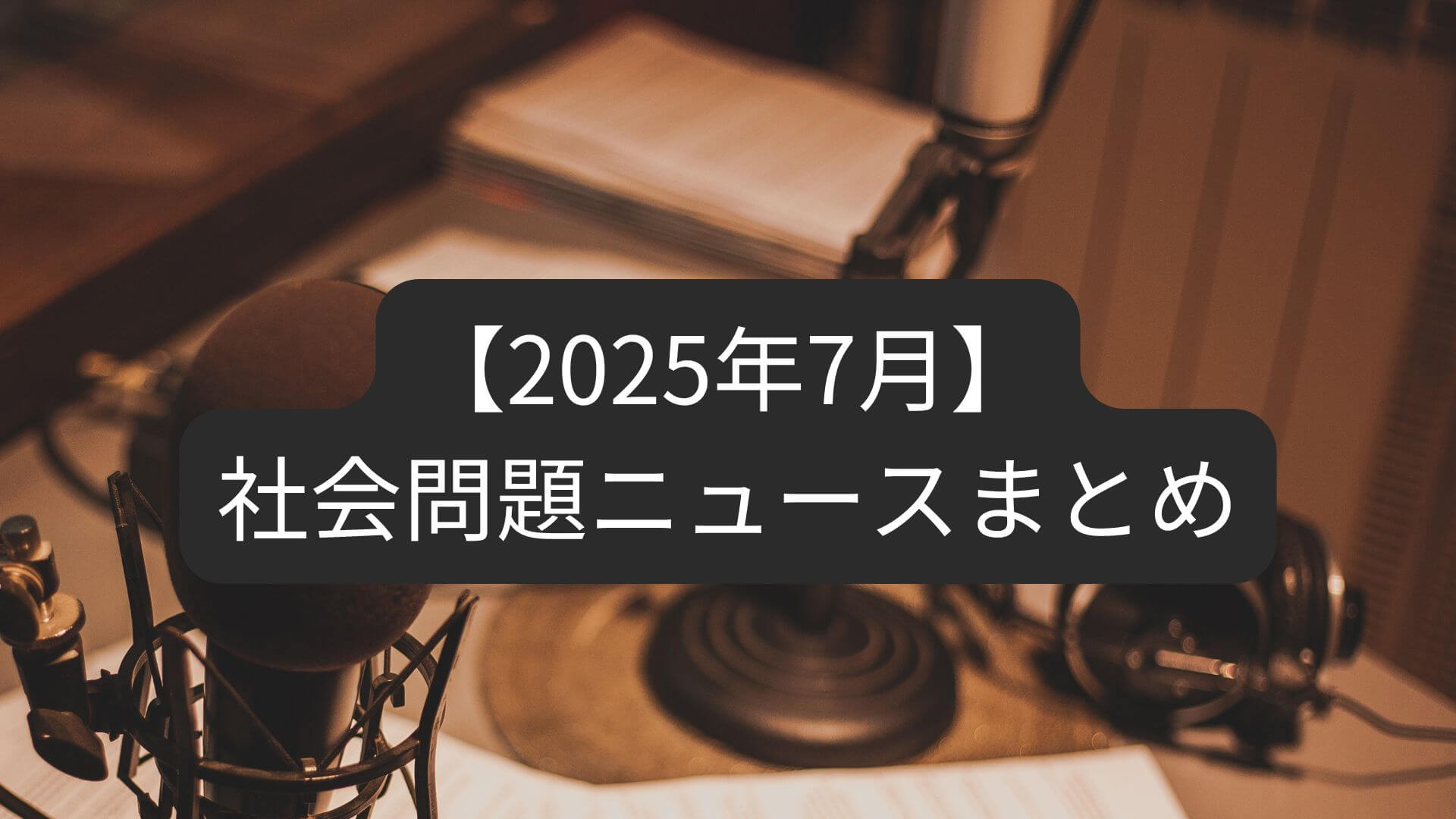近年、SDGs(持続可能な開発目標)という言葉を耳にする機会が増えています。
その中でも「つくる責任、つかう責任」は、私たちの日常生活に直結する重要なテーマです。
この記事では、初めてSDGsに関心を持った方に向けて、「つくる責任、つかう責任」の基本的な情報をわかりやすく解説します。
持続可能な社会を実現するために、私たち一人ひとりがどのような役割を果たせるのか、一緒に考えていきましょう。
目次
つくる責任、つかう責任とは

「つくる責任、つかう責任」は、SDGsの目標12「持続可能な消費と生産パターンを確保する」に関連する概念です。
これは、生産者(つくる側)と消費者(つかう側)の双方が、環境や社会に配慮した行動を取ることを求めています。
具体的には、資源の効率的な利用、廃棄物の削減、環境負荷の軽減などが含まれます。
SDGsとは
SDGs(Sustainable Development Goals)は、2015年に国連で採択された「持続可能な開発のための2030アジェンダ」に記載された17の目標です。
これらの目標は、貧困、飢餓、健康、教育、気候変動、平和と公正など、多岐にわたる課題を包括的に解決することを目指しています。
SDGsは、先進国と開発途上国が協力して達成すべき普遍的な目標であり、地球上の「誰一人取り残さない」ことを誓っています。
つくる責任、つかう責任を構成するターゲット
目標12には、以下のような具体的なターゲットが設定されています。
| 12.1 | 開発途上国の開発状況や能力を勘案しつつ、持続可能な消費と生産に関する 10 年計画枠組み(10YFP)を実施し、先進国主導の下、全ての国々が対策を講じる。 |
| 12.2 | 2030年までに天然資源の持続可能な管理及び効率的な利用を達成する。 |
| 12.3 | 2030年までに小売・消費レベルにおける世界全体の一人当たりの食料の廃棄を半減させ、 収穫後損失などの生産・サプライチェーンにおける食品ロスを減少させる。 |
| 12.4 | 2020年までに、合意された国際的な枠組みに従い、製品ライフサイクルを通じ、環境上適正な化学物質や全ての廃棄物の管理を実現し、人の健康や環境への悪影響を最小化するため、化学物質や廃棄物の大気、水、土壌への放出を大幅に削減する。 |
| 12.5 | 2030年までに、廃棄物の発生防止、削減、再生利用及び再利用により、廃棄物の発生を大幅に削減する。 |
| 12.6 | 特に大企業や多国籍企業などの企業に対し、持続可能な取り組みを導入し、持続可能性に関する情報を定期報告に盛り込むよう奨励する。 |
| 12.7 | 国内の政策や優先事項に従って持続可能な公共調達の慣行を促進する。 |
| 12.8 | 2030年までに、人々があらゆる場所において、持続可能な開発及び自然と調和したライフ スタイルに関する情報と意識を持つようにする。 |
| 12.a | 開発途上国に対し、より持続可能な消費・生産形態の促進のための科学的・技術的能力の強化を支援する。 |
| 12.b | 雇用創出、地方の文化振興・産品販促につながる持続可能な観光業に対して持続可能な開発がもたらす影響を測定する手法を開発・導入する。 |
| 12.c | 開発途上国の特別なニーズや状況を十分考慮し、貧困層やコミュニティを保護する形で開発に関する悪影響を最小限に留めつつ、税制改正や、有害な補助金が存在する場合はその環境 への影響を考慮してその段階的廃止などを通じ、各国の状況に応じて、市場のひずみを除去することで、浪費的な消費を奨励する化石燃料に対する非効率な補助金を合理化する。 |
つくる責任、つかう責任が生まれた背景
「つくる責任、つかう責任」が生まれた背景には、地球規模の環境問題や資源の枯渇があります。
20世紀以降、工業化が進み、大量生産・大量消費が当たり前となりました。
その結果、資源の過剰利用や廃棄物の増加が深刻化し、地球環境に大きな負荷がかかっています。
また、開発途上国では、貧困や不平等が拡大し、持続可能な開発が妨げられています。
これらの問題を解決するために、持続可能な消費と生産のパターンを確立することが急務となっています。
つくる責任、つかう責任の現状

「つくる責任、つかう責任」の現状は、深刻な課題とともに、解決に向けた動きも始まっています。
以下に、重要な3つのポイントを解説します。
食品ロスとプラスチック廃棄物の深刻化
世界では年間約13億トンの食料が廃棄されており、これは生産される食料の3分の1に相当します。
また、年間800万トン以上のプラスチックが海に流れ込み、海洋生態系に深刻な影響を与えています。
これらの問題は、資源の無駄遣いや環境汚染を引き起こし、持続可能な社会の実現を妨げています。
先進国では消費者の過剰な購入や厳しい品質基準が、開発途上国ではインフラ不足が主な原因です。
≫フードロスとは?削減するために私たちができること
≫食品ロスとは?フードロスとの違いや日本の現状、取り組む企業を解説
≫海洋プラスチック問題とは?解決策と私たちにできること
≫ごみ問題とは?このままだとどうなる?現状や問題点、企業の取り組みを解説
参考:食品ロスの現状を知る:農林水産省
海洋プラスチック問題について |WWFジャパン
企業と消費者の意識変化
企業側では、リサイクル素材を使用した製品の開発やサプライチェーン全体での環境配慮が進んでいます。
また、ESG(環境・社会・ガバナンス)投資の拡大により、持続可能性を重視する企業が増えています。
消費者側でも、環境や社会に配慮した商品を選ぶ「エシカル消費」が広がりつつあります。
特に若い世代を中心に、プラスチックフリー製品やオーガニック食品への関心が高まっています。
しかし、価格や利便性を優先する消費者も多く、持続可能な消費が主流になるにはまだ時間がかかると見られています。
≫ESGとは?意味やSDGsとの違い、ESG投資、企業のPR方法を解説
≫エシカル消費とは?企業の取り組み事例や私たちができることを解説
政策と技術革新の進展
各国政府は、持続可能な消費と生産を促進するための政策を導入しています。
例えば、EUでは循環型経済行動計画を推進し、使い捨てプラスチックの禁止やリサイクル目標の設定を行っています。
日本でも食品ロス削減推進法が制定されるなど、法整備が進んでいます。
また、技術の進歩も持続可能な消費と生産を支える重要な要素です。再生可能エネルギー技術やリサイクル技術の進化により、資源の効率的な利用が可能になっています。
しかし、これらの政策や技術を広く普及させるためには、さらなる投資や国際協力が必要です。
つくる責任、つかう責任の課題
「つくる責任、つかう責任」を実現するためには、以下の3つの主要な課題を解決する必要があります。
≫【2024年最新】日本の社会問題一覧!30の社会課題とランキングを解説!
環境負荷の軽減と資源の効率的利用
生産者側では、製造業や農業において、生産過程で大量の資源やエネルギーが消費され、温室効果ガスや廃棄物が発生しています。
特に、化石燃料の使用や化学物質の過剰利用が環境に大きな負荷をかけています。
一方、消費者側では、過剰な消費や食品ロスが資源の無駄遣いを引き起こしています。
先進国では、厳しい品質基準や大量購入が食品ロスの主な原因となっています。
この課題を解決するためには、生産者がクリーンエネルギーやリサイクル技術を導入し、消費者が必要な分だけ購入し、食品ロスを減らす意識を持つことが重要です。
≫カーボンプライシングとは?日本の導入はいつから?価格や現状をわかりやすく解説
≫カーボンリサイクルとは?メリットや企業の取り組み事例、今後の課題を解説!
≫ブルーカーボンとは?メカニズムやJブルークレジットとの関係、取り組み事例をわかりやすく解説
サプライチェーンの透明化とエシカル消費の普及
生産者側では、グローバルなサプライチェーンにおいて、労働環境や環境影響の監視が難しく、透明性の確保が課題です。
特に、開発途上国での労働条件や環境規制の不備が問題視されています。
一方、消費者側では、環境や社会に配慮した商品を選ぶ「エシカル消費」がまだ主流とは言えません。
価格が高い場合や選択肢が少ない場合、消費者が持続可能な製品を選びにくい状況です。
この課題を解決するためには、企業がサプライチェーンの透明性を高め、消費者がエシカルな製品を積極的に選ぶことで、持続可能な消費を促進することが求められています。
≫外国人労働者問題とは?日本の現状や問題点、原因をわかりやすく解説
≫カンボジアの社会問題は何がある?教育問題や児童労働、環境問題について解説
政策と技術革新の不足
生産者側では、持続可能な生産を実現するためには、新たな技術や設備の導入が必要ですが、特に中小企業では資金や技術力が不足しています。
また、持続可能な製品を開発するための政策支援が不十分な場合もあります。
一方、消費者側では、リサイクルや廃棄物管理に関するインフラが整備されていない地域が多く、消費者が適切に行動しにくい状況です。
また、持続可能な消費を促進するための政策や制度が不十分な場合があります。
この課題を解決するためには、政府が持続可能な生産と消費を後押しするための政策を強化し、企業や消費者が行動しやすい環境を整える必要があります。
つくる責任つかう責任に取り組む企業3選

つくる責任つかう責任に取り組む企業を紹介します。
≫【SDGs目標12】つくる責任つかう責任に取り組む企業10選!就職・転職におすすめの大企業からベンチャー
≫リサイクルに取り組む企業10選!就職・転職におすすめの大企業からベンチャー
≫サーキュラーエコノミーに取り組む企業10選!就職・転職におすすめの大企業からベンチャー
日本リユースシステム株式会社
日本リユースシステム株式会社は、リユース事業を基盤とした企業です。
不要になった衣類や家電製品など、さまざまなものを海外に輸出することで、資源の有効活用と新たな価値創造を目指しています。
また、社会貢献活動にも積極的に取り組んでおり、その一つである「古着deワクチン」は、不要な衣類をリサイクルすることで、開発途上国の子どもたちにワクチンを届けるという斬新な取り組みです。
HP:https://www.nrscorp.jp/
日本リユースシステム株式会社の事業内容や創業理由を詳しく見る
株式会社土屋鞄製造所
株式会社土屋鞄製造所は、1965年の創業以来、革製品を中心としたランドセル、鞄、財布などの小物を企画・製造・販売している日本の老舗ブランドです。
特にランドセルは、その品質の高さから多くの顧客に支持されており、日本を代表するランドセルメーカーとして知られています。
購入後のメンテナンスや修理にも注力しており、不用になった商品を引き取って、専任の職人の手で修理・クリーニング・補色を施すリユースにも取り組んでいます。
HP:https://tsuchiya-kaban.jp/
リバー株式会社
リバー株式会社は、120年以上の歴史を持つ、廃棄物処理とリサイクルを専門とする総合環境企業です。
東証プライム上場企業・TREホールディングスの一員として、国内の廃棄物処理業界において大きな事業規模を誇っています。
「地球を資源だらけの星にしよう。」という企業理念のもと、長年培ってきたリサイクル技術とネットワークで、廃棄物を資源として有効活用し、循環型社会の実現を目指しています。
HP:https://www.re-ver.co.jp/
つくる責任、つかう責任に対して私たちができること5選

「つくる責任、つかう責任」を実現するためには、生産者だけでなく、消費者である私たち一人ひとりの行動が重要です。
以下に、私たちが日常生活で実践できる5つの具体的な取り組みを解説します。
エコフレンドリーな製品を選ぶ
持続可能な消費を実践する第一歩は、環境に優しい製品を選ぶことです。
例えば、リサイクル素材を使用した商品や、オーガニック認証を受けた食品を選ぶことで、資源の有効利用や環境負荷の軽減に貢献できます。
また、プラスチックフリーの製品や詰め替え可能な商品を選ぶことで、廃棄物の削減にも繋がります。
消費者が環境に配慮した商品を選ぶことで、企業も持続可能な製品の開発をさらに進めるインセンティブが生まれます。
≫エシカル消費に取り組む企業10選!就職・転職におすすめのベンチャーを中心に紹介
≫エシカル・サステナブルファッションに取り組む企業10選!就職・転職におすすめの大企業からベンチャー
≫サステナブルシャンプー10選!環境に優しいエシカルなシャンプーを紹介
食品ロスを減らす
食品ロスは、世界的に深刻な問題です。
私たちができることとして、買い物の際に必要な分だけ購入し、食べ残しを減らすことが挙げられます。
また、賞味期限や消費期限を確認し、計画的に食材を使い切ることも重要です。
家庭での調理方法を見直し、余った食材を活用するレシピを試すことで、食品ロスをさらに減らすことができます。
さらに、外食時には食べきれる量を注文し、持ち帰りを活用するのも有効な手段です。
≫フードファディズムとは?事例や3つの問題点、解決策について解説!
リサイクルを徹底する
リサイクルは、資源の循環を促進するための重要な取り組みです。
私たちができることとして、家庭や職場での分別回収を徹底することが挙げられます。
プラスチック、紙、ガラス、金属など、リサイクル可能な資源を正しく分別し、適切に廃棄することで、廃棄物の削減と資源の再利用に貢献できます。
≫リサイクル(3R)とは?例を用いて意味をわかりやすく解説!
≫5Rとは?5つの意味や3Rとの違い、私たちにできることを解説
省エネを心がける
エネルギー消費を減らすことも、持続可能な社会を実現するための重要な取り組みです。
私たちができることとして、電気や水の使用量を減らすことが挙げられます。
例えば、LED電球への切り替えや、使わない電化製品のコンセントを抜くことで、エネルギー消費を削減できます。
情報を共有し、意識を高める
持続可能な消費と生産に関する情報を家族や友人と共有し、意識を高めることも重要です。
例えば、SNSやブログでエコフレンドリーなライフスタイルを発信したり、地域の環境イベントに参加したりすることで、周囲の人々に影響を与えることができます。
また、学校や職場で持続可能な取り組みについて話し合い、具体的な行動を促すことも有効です。
情報を共有し、意識を高めることで、持続可能な社会を実現するためのムーブメントを広げることができます。
≫レポートで書きやすいSDGsのテーマ10選!テーマの選び方や参考になる調査を解説
≫【2024年最新版】社会課題やSDGs、サステナブルについて発信するメディア30選!
まとめ
「つくる責任、つかう責任」は、持続可能な社会を実現するために不可欠な概念です。
生産者と消費者が協力して、資源の効率的な利用や廃棄物の削減に取り組むことで、地球環境を守り、未来の世代に豊かな地球を引き継ぐことができます。
私たち一人ひとりができることは小さくても、その積み重ねが大きな変化をもたらします。今日からできることを始めてみませんか?
【その他のSDGsの目標を詳しく知りたい】
【SDGs目標1】貧困をなくそうとは?背景や現状、企業の取り組み、私たちにできることを解説
【SDGs目標2】飢餓をゼロにとは?背景や現状、企業の取り組み、私たちにできることを解説
【SDGs目標3】すべての人に健康と福祉をとは?背景や現状、企業の取り組み、私たちにできることを解説
【SDGs目標4】質の高い教育をみんなにとは?背景や現状、企業の取り組み、私たちにできることを解説
【SDGs目標5】ジェンダー平等を実現しようとは?背景や現状、企業の取り組み、私たちにできることを解説
【SDGs目標6】安全な水とトイレを世界中にとは?背景や現状、企業の取り組み、私たちにできることを解説
【SDGs目標7】エネルギーをみんなに そしてクリーンにとは?背景や現状、企業の取り組み、私たちにできることを解説
【SDGs目標8】働きがいも経済成長もとは?背景や現状、企業の取り組み、私たちにできることを解説
【SDGs目標9】産業と技術革新の基盤を作ろうとは?背景や現状、企業の取り組み、私たちにできることを解説
【SDGs目標10】人や国の不平等をなくそうとは?背景や現状、企業の取り組み、私たちにできることを解説
【SDGs目標11】住み続けられるまちづくりをとは?背景や現状、企業の取り組み、私たちにできることを解説
【SDGs目標12】つくる責任つかう責任とは?背景や現状、企業の取り組み、私たちにできることを解説
【SDGs目標13】気候変動に具体的な対策をとは?背景や現状、企業の取り組み、私たちにできることを解説
【SDGs目標14】海の豊かさを守ろうとは?背景や現状、企業の取り組み、私たちにできることを解説
【SDGs目標15】陸の豊かさも守ろうとは?背景や現状、企業の取り組み、私たちにできることを解説
【SDGs目標16】平和と公正をすべての人にとは?背景や現状、企業の取り組み、私たちにできることを解説
【SDGs目標17】パートナーシップで目標を達成しようとは?背景や現状、企業の取り組み、私たちにできることを解説

この記事の監修者
吉田宏輝
COCOCOLOREARTH代表、社会活動家。
COCOCOLOREARTHでは、社会課題解決を軸にした就職・転職活動を支援するインタビューメディアの代表として、100人以上の社会活動家にインタビュー、記事執筆やイベント登壇などを行う。