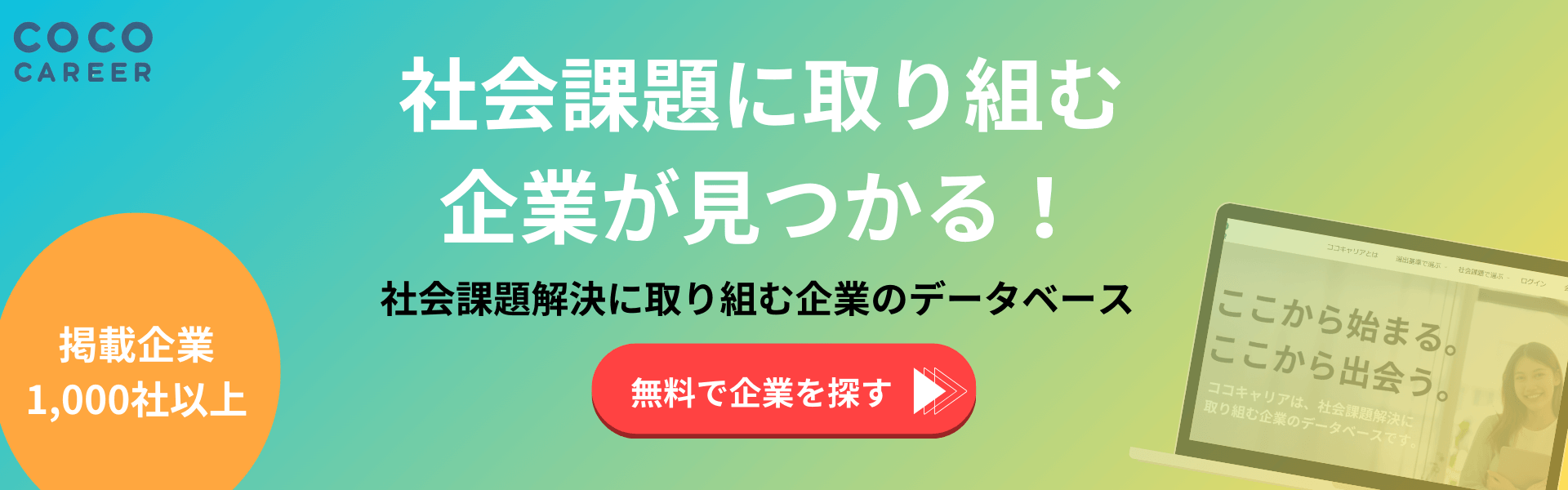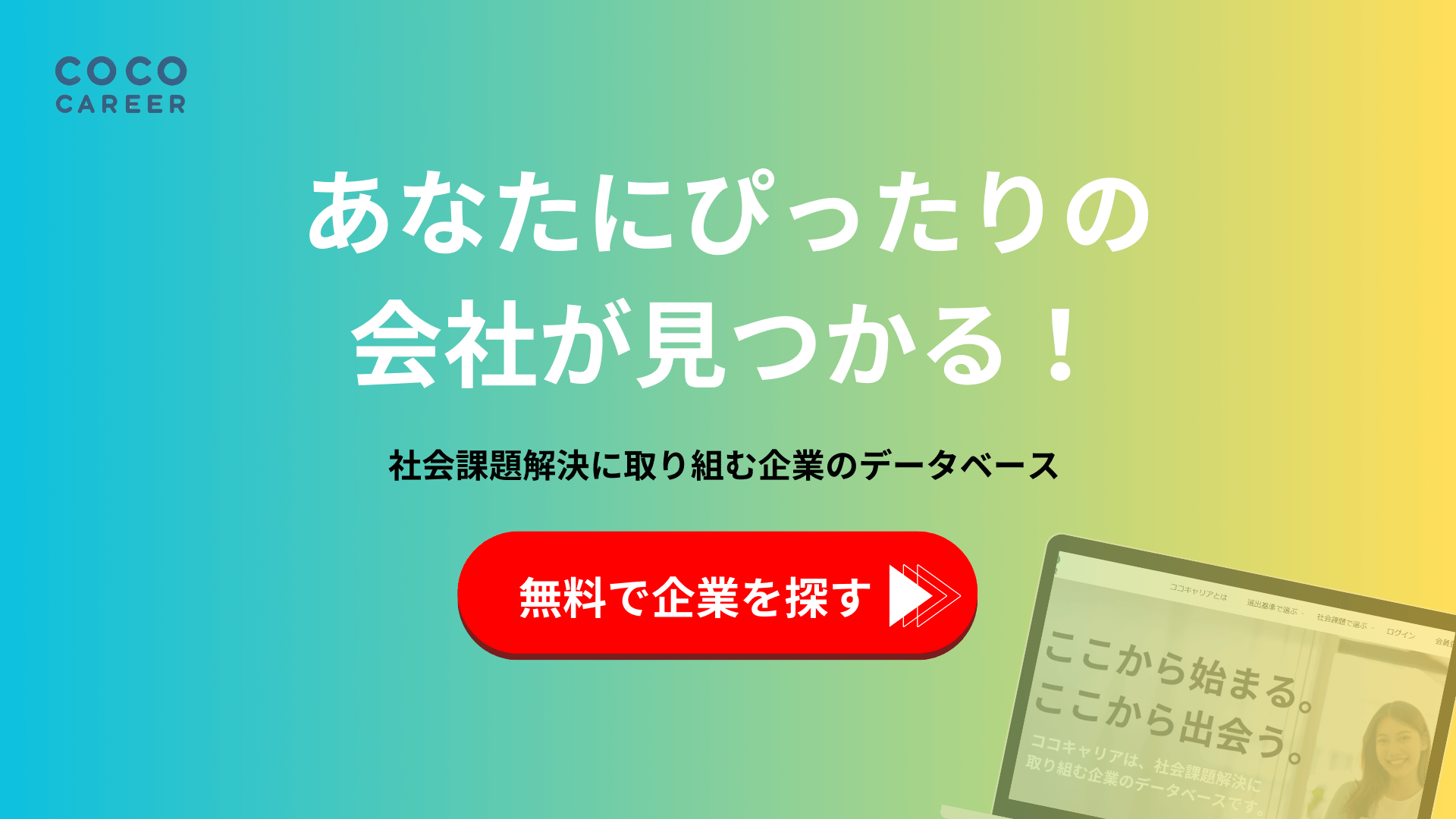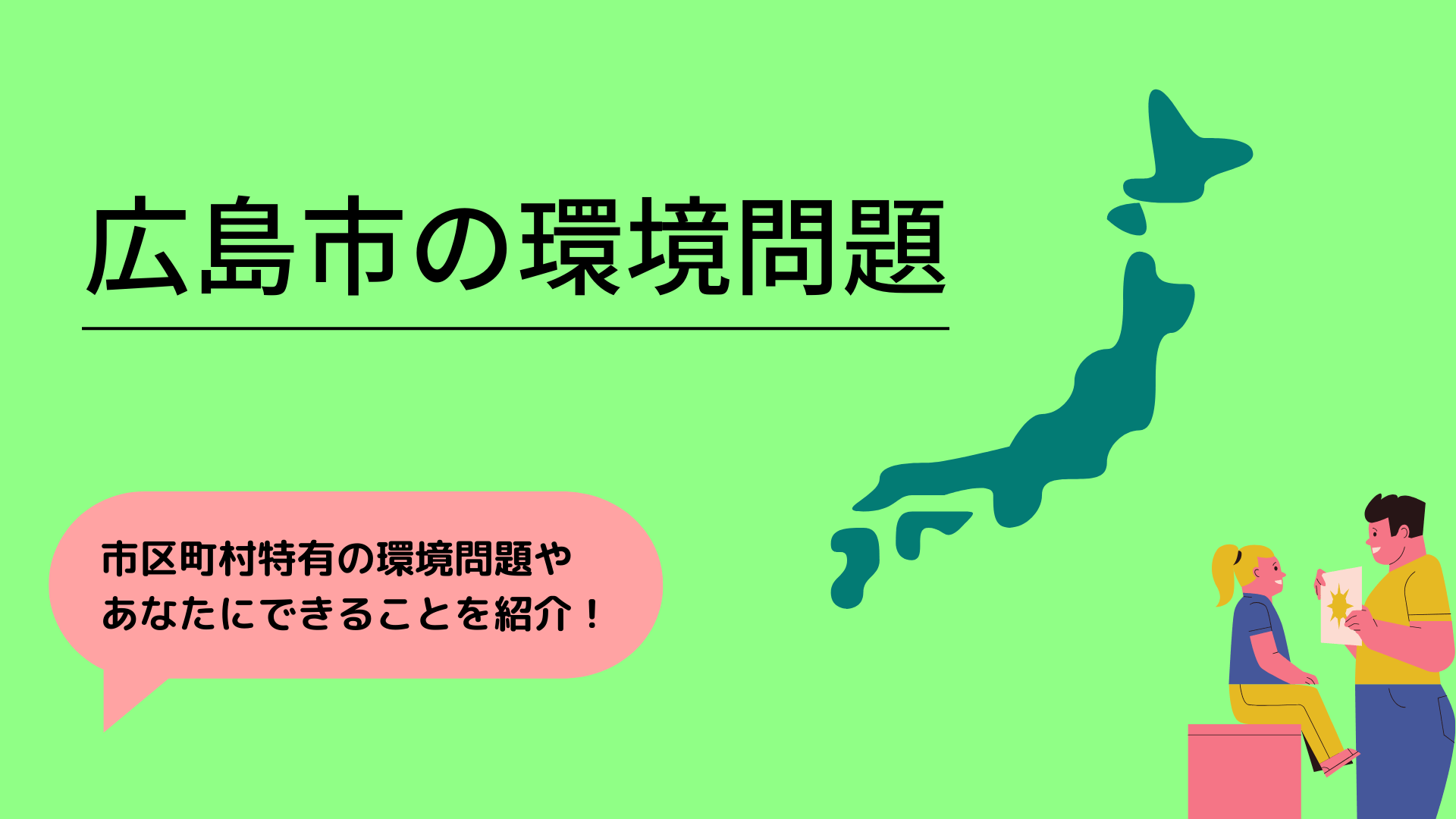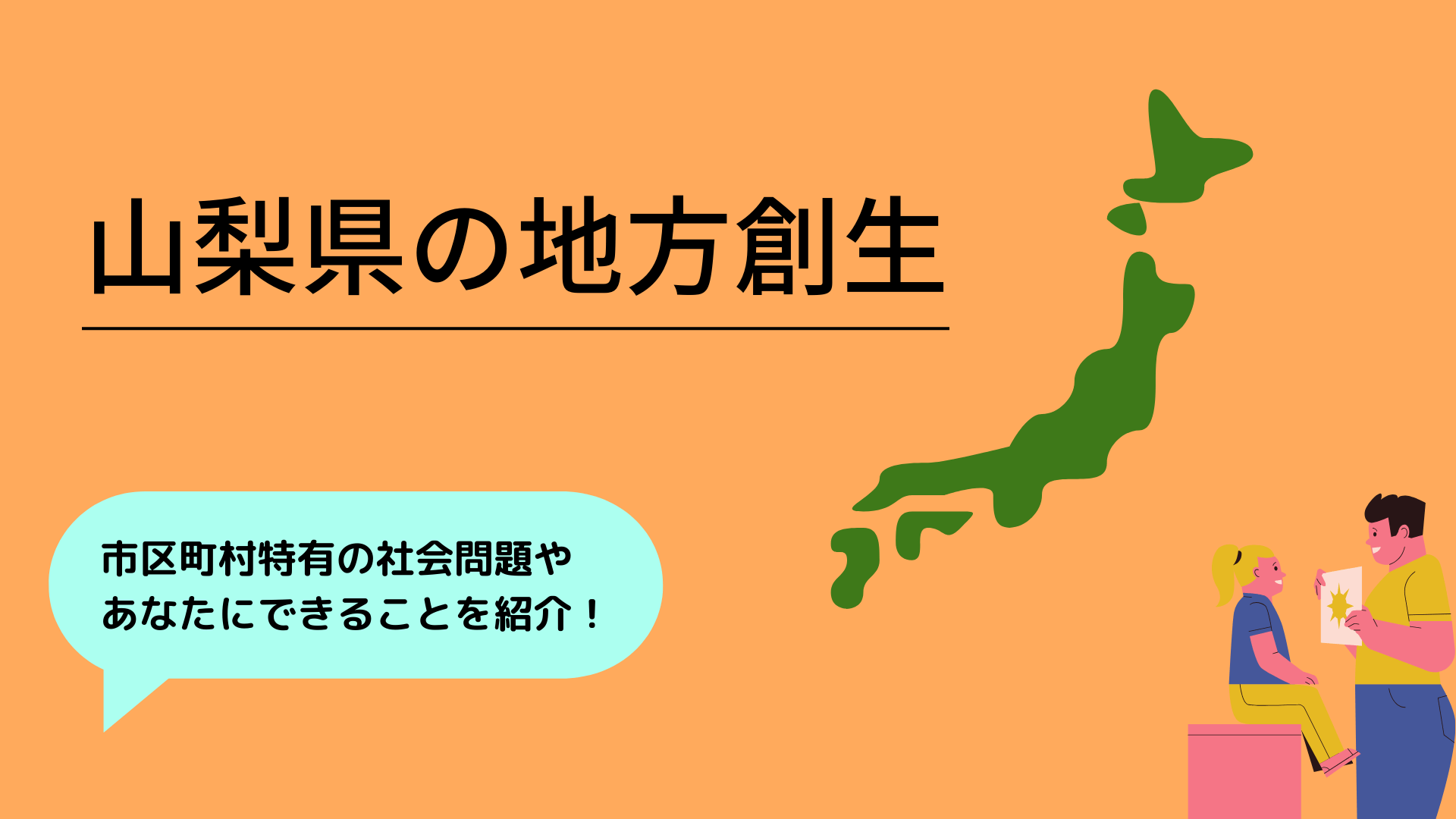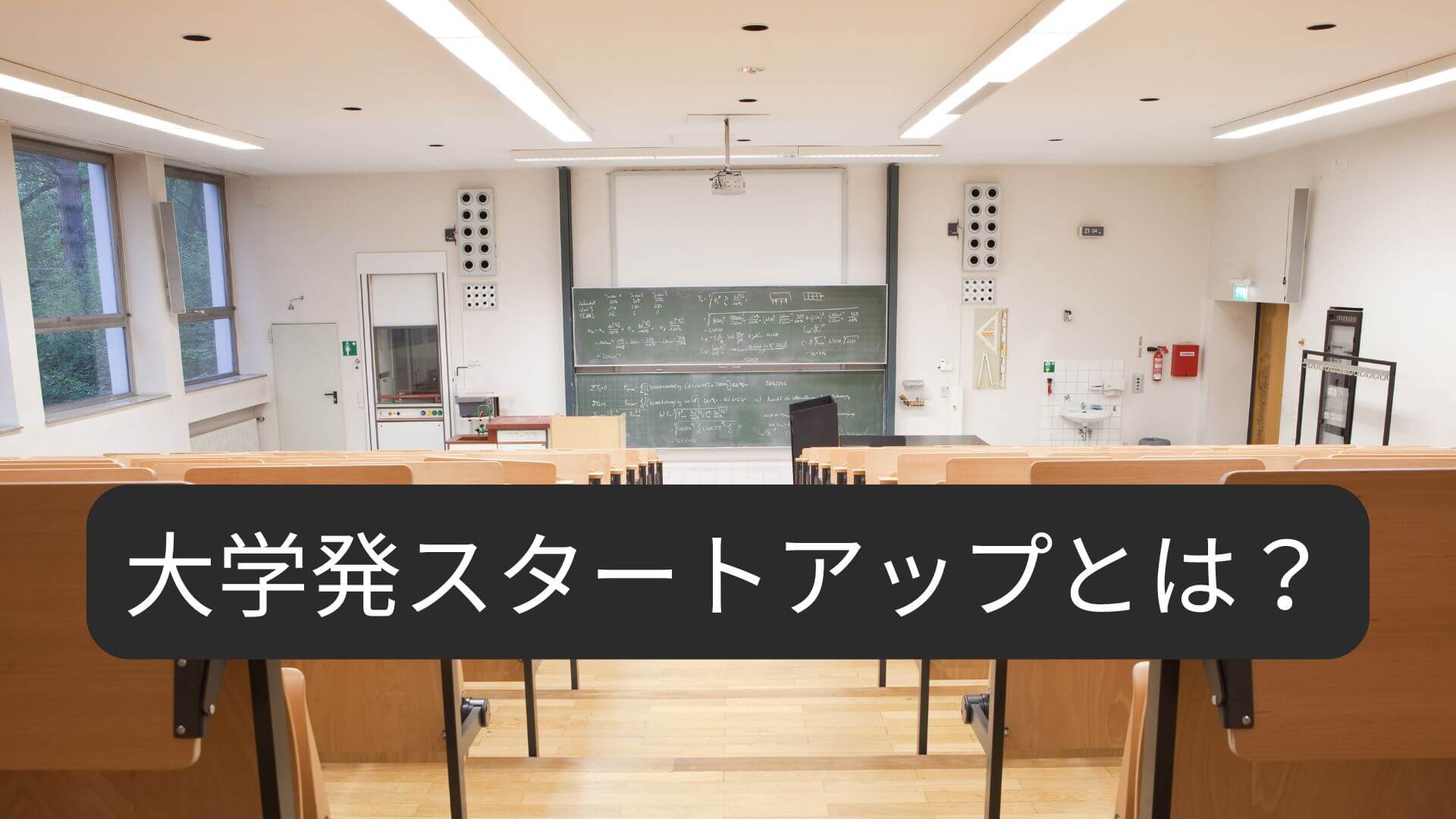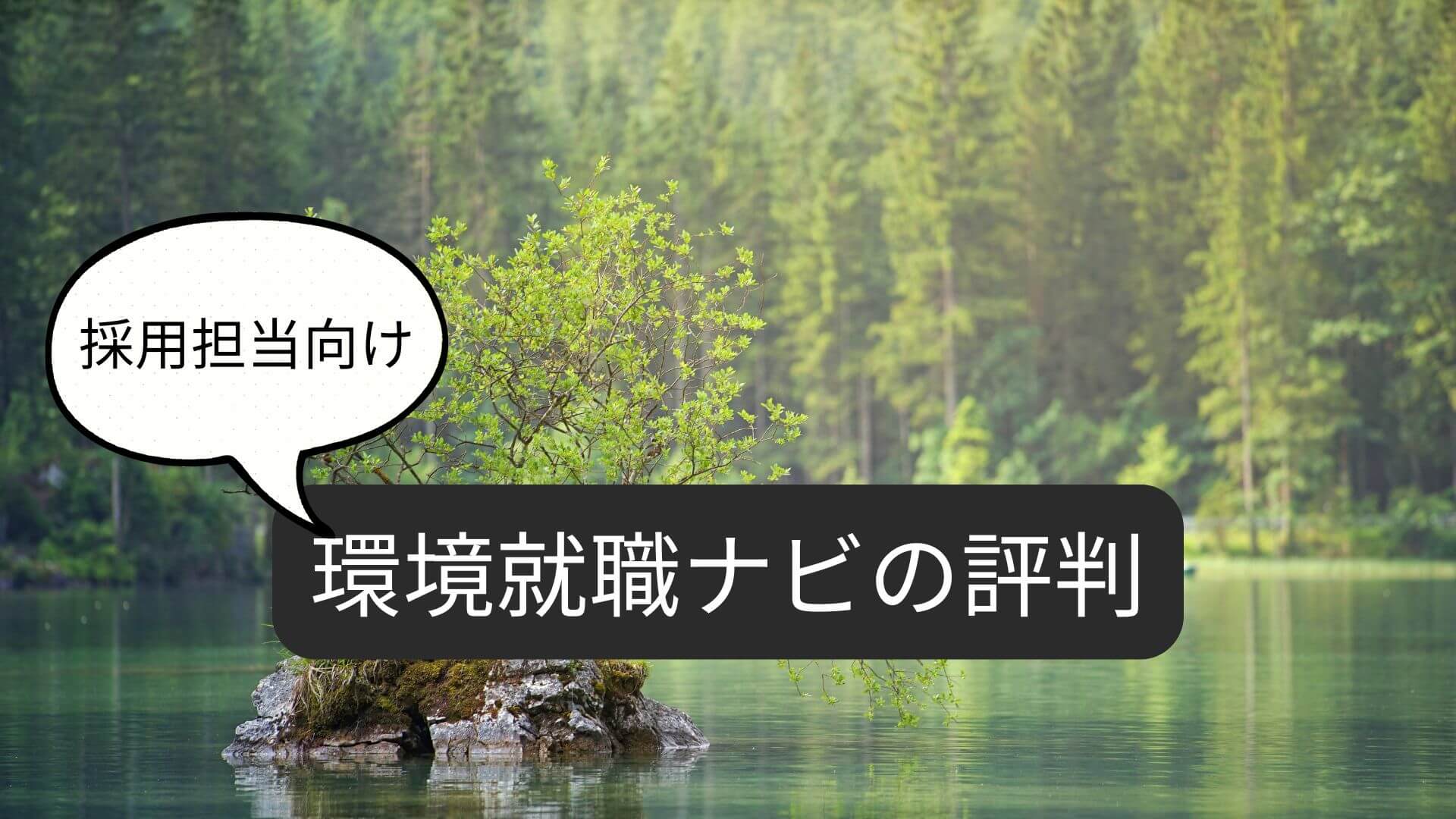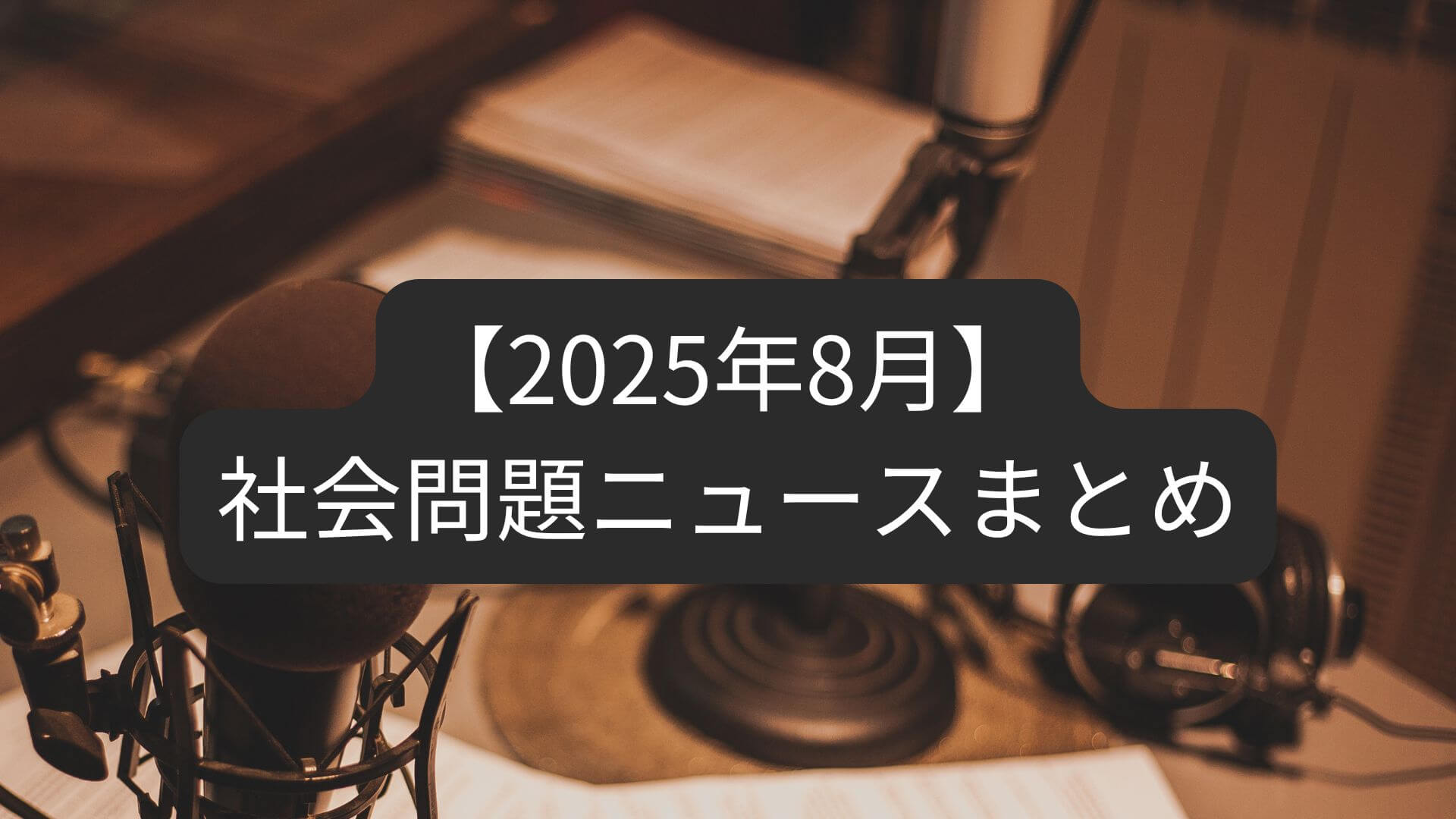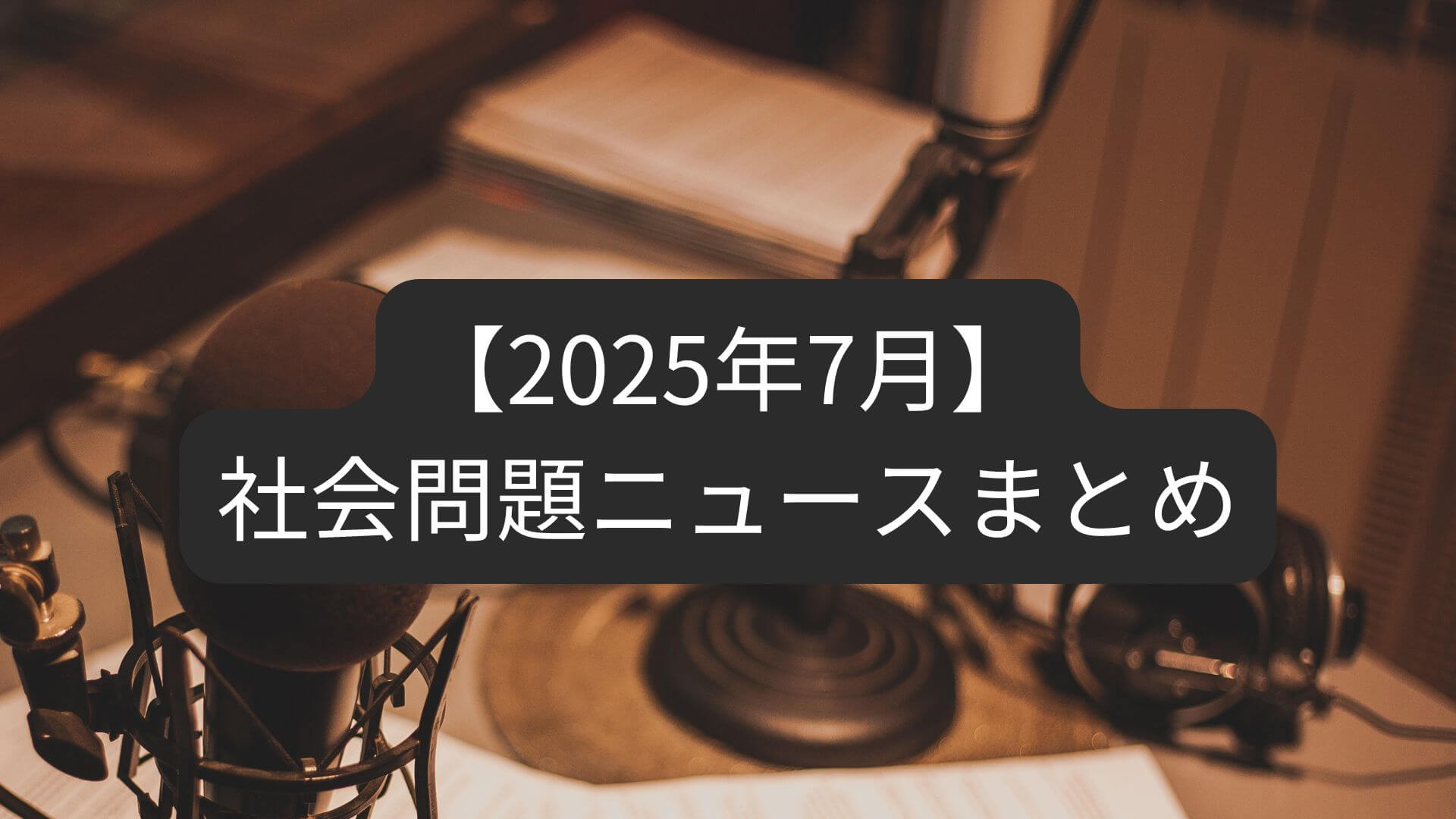日本では、少子高齢化や気候変動など、数多くの社会問題があります。
その深刻化は年々増しており、特に2040年にはあらゆる問題が顕著に現れます。
今後、日本で起こりうる問題はどのようなものでしょうか。
日本はどのような対策考え、取り組んでいるのでしょうか。
※【企業様向け】介護への取り組みをPRしませんか?
掲載を希望される企業様はこちら
目次
2040年問題とは

2040年問題とは、日本が2040年に直面すると考えられる問題の総称です。
総人口に占める高齢者の割合が増えることで、あらゆる業種での人手不足や医療、福祉、社会保障の懸念が考えられます。
2040年になると、1971年~1974年の第二次ベビーブームに生まれた団塊ジュニア世代が65歳以上となります。
総人口に対する高齢者の割合は、36.2%となることが予測され、約2.8人に1人が高齢者という計算になります。
このように、総人口に占める高齢者の割合が増えることで、あらゆる業種での人手不足や医療、福祉、社会保障の懸念が考えられます。
参考:平成の30年間と、2040年にかけての社会の変容|厚生労働省
2040問題と2025問題の違い
2040問題と2025問題は、どちらも高齢者の増加により起こる問題です。
大きな違いは、深刻さにあります。
2025年問題は、財源の不足が心配されていますが、2040年問題は、財源の不足はもちろんインフラの老朽化や人材不足など、問題がより深刻になります。
2054年問題も問題視されるように
2054年問題とは、生産年齢人口が激減する反面、団塊世代の75歳以上の人口が2054年まで増え続けるという問題です。
2054年には、75歳以上の人口は2,449万人になると推測されており、人口の25%が75歳以上の高齢者となる予想がされています。
2040年問題に関する課題
2040年問題に関する課題はどのようなものがあるでしょうか。
現役世代の負担増加

現役世代は、2040年に約6000万人と推定されています。
これは、1人の高齢者を1.5人の現役世代で支える計算となり、現役世代に対する負担がこれまで以上に大きくなります。
特に、医療・介護の社会保障費が急増することが考えられます。
2040年問題に向けて、国も働き方や社会制度の改革を進めています。
≫肩車型社会とは?超高齢社会で迎える4つの問題と私たちにできること
労働人口の減少

少子化により、現役世代の人口が減少することで多くの産業で人手不足が予測されます。
特に、医療や建設、運輸業の労働力不足は、深刻な社会問題となっています。
実際、医療関係者の不足はコロナ以前から深刻化しています。
特に都市部は多くの高齢者がいるため、医療の需要が高まっています。
この需給ギャップは、2025年時点で37.7万人と推計されており、2040年にはさらに拡大するでしょう。
≫外国人労働者問題とは?日本の現状や問題点、原因をわかりやすく解説
≫留学生アルバイト問題とは?増えた背景や留学生を取り巻く問題を解説
インフラの老朽化

日本では、高度経済成長期以降、地方から都市部に人口が流入し、都市部を中心に多くの建物ができました。
その建物の多くは、2040年には築50年を超えます。
一般に、建設から50年が経過した建物は、老朽化問題が発生します。
また、築50年の建物には、エレベーターや手すりがないものも多く、高齢者にとって不便です。
老朽化した建物が多くなりすぎたために、改修作業が追いついていません。
参考:社会インフラの老朽化
≫インフラ整備とは?日本と世界の現状やメリット、SDGsとの関係を紹介
2040年問題の対策
2040年問題に関する課題への対策はあるのでしょうか。
ここでは、政府による社会保障と働き方改革について見ていきます。
政府は、2040年を展望し、誰もがより長く元気に活躍できるよう、以下の取り組みを進めています。
多様な働き方と社会参加の環境整備
現役世代の急減が考えられる一方、平均寿命の増加など医療の向上に伴う高齢者の若返りが見られます。
そのため、より多くの人が意欲や能力に応じ、社会の担い手として活躍できるよう取り組みが行われています。
具体的には、副業や兼業の促進、中途採用の拡大、地域共生への働きが進んでいます。
個人の意思や能力、事情に応じた多様で柔軟な働き方を選択可能とする社会が目指されています。
参考:70歳以上でも働ける仕事9選!働き方のかたちや仕事の探し方も解説
健康寿命の延伸

日本政府は、2016年から2040年にかけて健康寿命を男女ともに3年以上延伸することを目指しています。
健康寿命とは、心も体も日常生活をする上で支障なく、健康的に生活できる期間のことです。
目標達成のために政府は、健康無関心層も含めた予防、健康づくりの推進、保険者間の格差の解消に向けた取り組みを行っています。
ワクチン接種への対応もその1つです。
緊急時の対応を急速に行えるよう、医療機関で整備が進んでいます。
医療・福祉サービスの改革と生産性の向上

2040年までに、医療・福祉の単位時間サービス提供量について5%(医師については7%)以上の改善を目指しています。
なお、単位時間サービス提供量とは、サービス提供量÷労働時間で算出される指標です。
テクノロジーの活用や業務の適切な分担により、医療・福祉の現場全体で必要なサービスがより効率的に提供されることが求められます。
具体的には、ロボットやICTの実用化、シニア人材の活用が推進されています。
このように政府や医療機関を中心に、2040年問題を見据えた対策がされています。
また、民間セクターも2040年問題に対して取り組んでいます。
例えば、Panasonicでは、医療技術として介護ロボットの生産を積極的に行っています。
参考:2040年を展望した社会保障・働き方改革本部のとりまとめについて
:パナソニックがご提案する解決策 | Panasonic
2040年問題に対する取り組み

2040年問題に対して多くの組織が推進している事例があります。
それはDX(デジタルトランスフォーメーション)です。
経済産業省は、DXについて次のように定義しています。
「データとデジタル技術を活用して、顧客や社会のニーズを基に、製品やサービス、ビジネスモデルを変革するとともに、業務そのものや、組織、プロセス、企業文化・風土を変革し、競争上の優位性を確立すること」
言い換えると、DXはITを手段として利用し、組織やビジネスモデルの変革を進めることです。
企業のみならず、都市部の公共団体でも取り組みが進んでいます。
≫サステナビリティ・トランスフォーメーション(SX)とは?生まれた背景やメリットを解説!
〇福祉関連の企業を紹介!
・福祉問題に取り組む企業10選!
・ヘルスケアに取り組む企業10選!
・教育問題に取り組む企業10選!
・保育の問題に取り組む企業10選!
・介護の問題に取り組む企業10選!
・ジェンダーの問題に取り組む企業10選!
・高齢化社会の問題に取り組む企業10選!
・ケアテックに取り組む企業10選!
さいごに
2040年は、遠いようで近い未来です。
2040年問題は大きな問題だからこそ、大きなインパクトが必要です。
そのため、1人の行動のインパクトは小さいかもしれません。
しかし、政府や企業だけが対策するだけでなく、すべての人の協力が不可欠です。
1人1人の行動が集まれば、それは大きなインパクトになります。
ぜひ、できることから輪を広げていきましょう。
【企業様向け】介護への取り組みをPRしませんか?

この記事の監修者
吉田宏輝
COCOCOLOREARTH代表、社会活動家。
COCOCOLOREARTHでは、社会課題解決を軸にした就職・転職活動を支援するインタビューメディアの代表として、100人以上の社会活動家にインタビュー、記事執筆やイベント登壇などを行う。