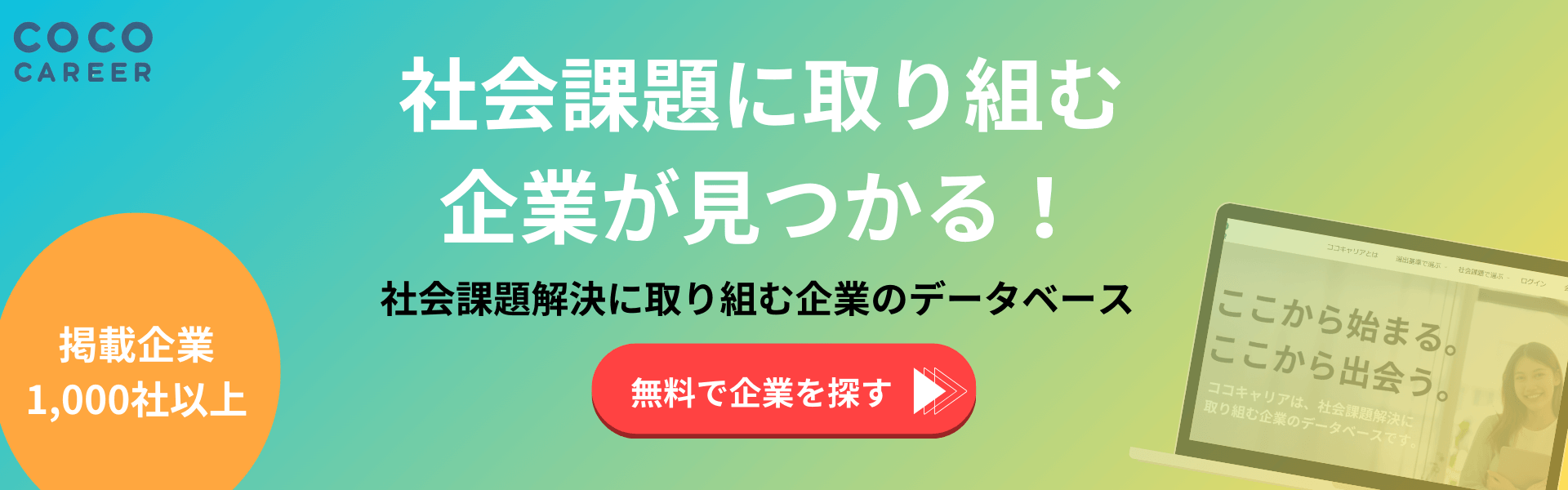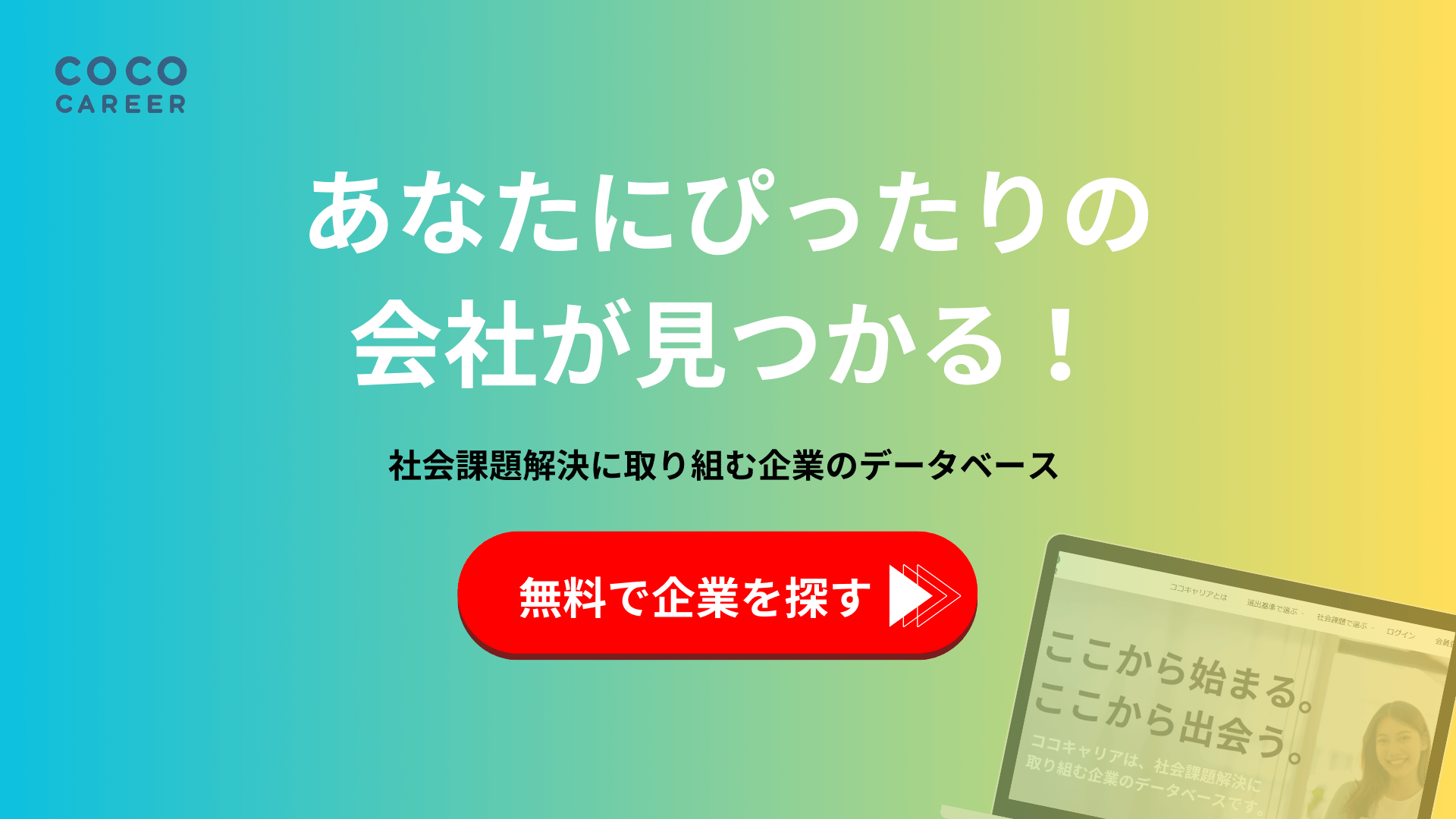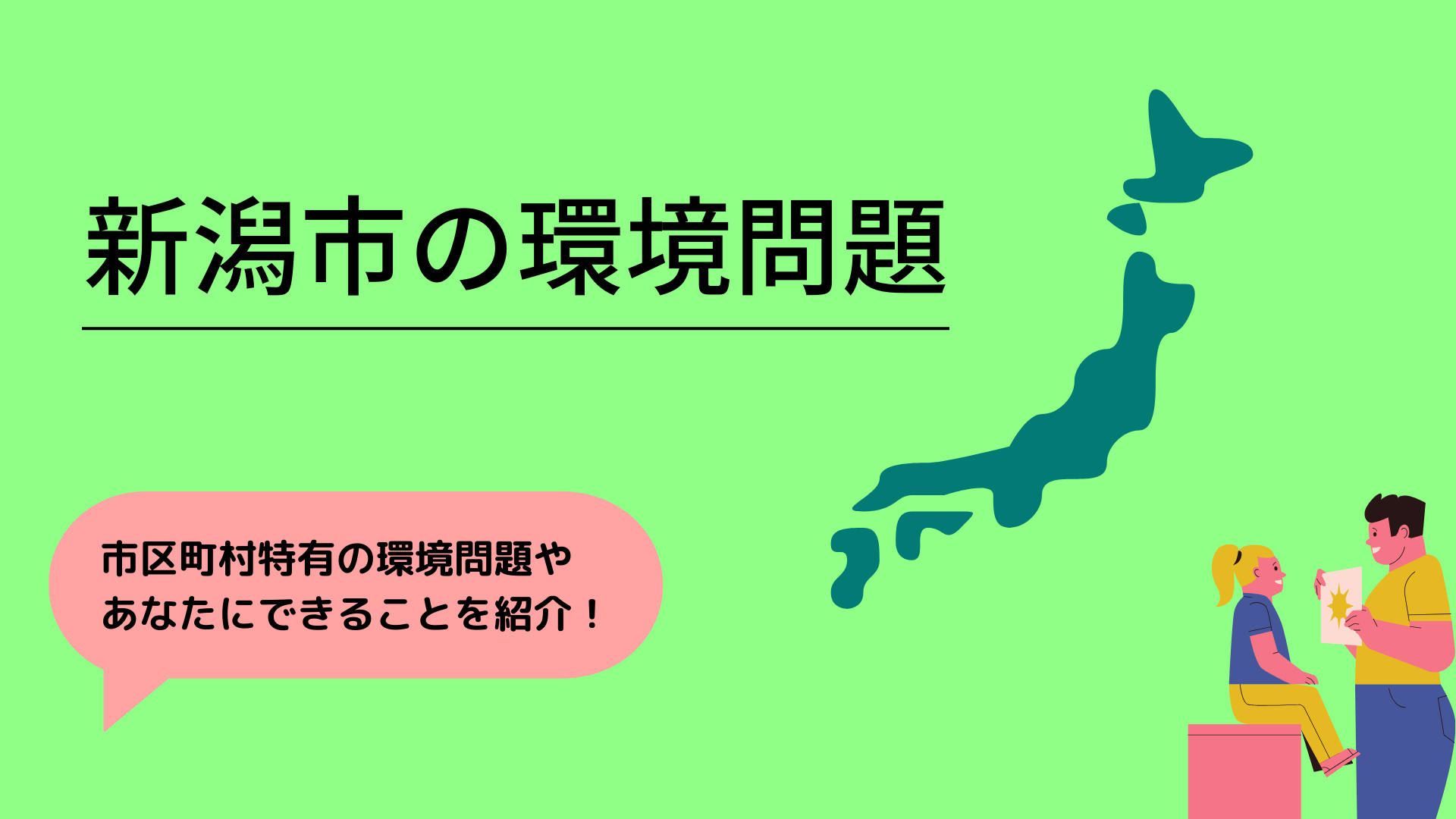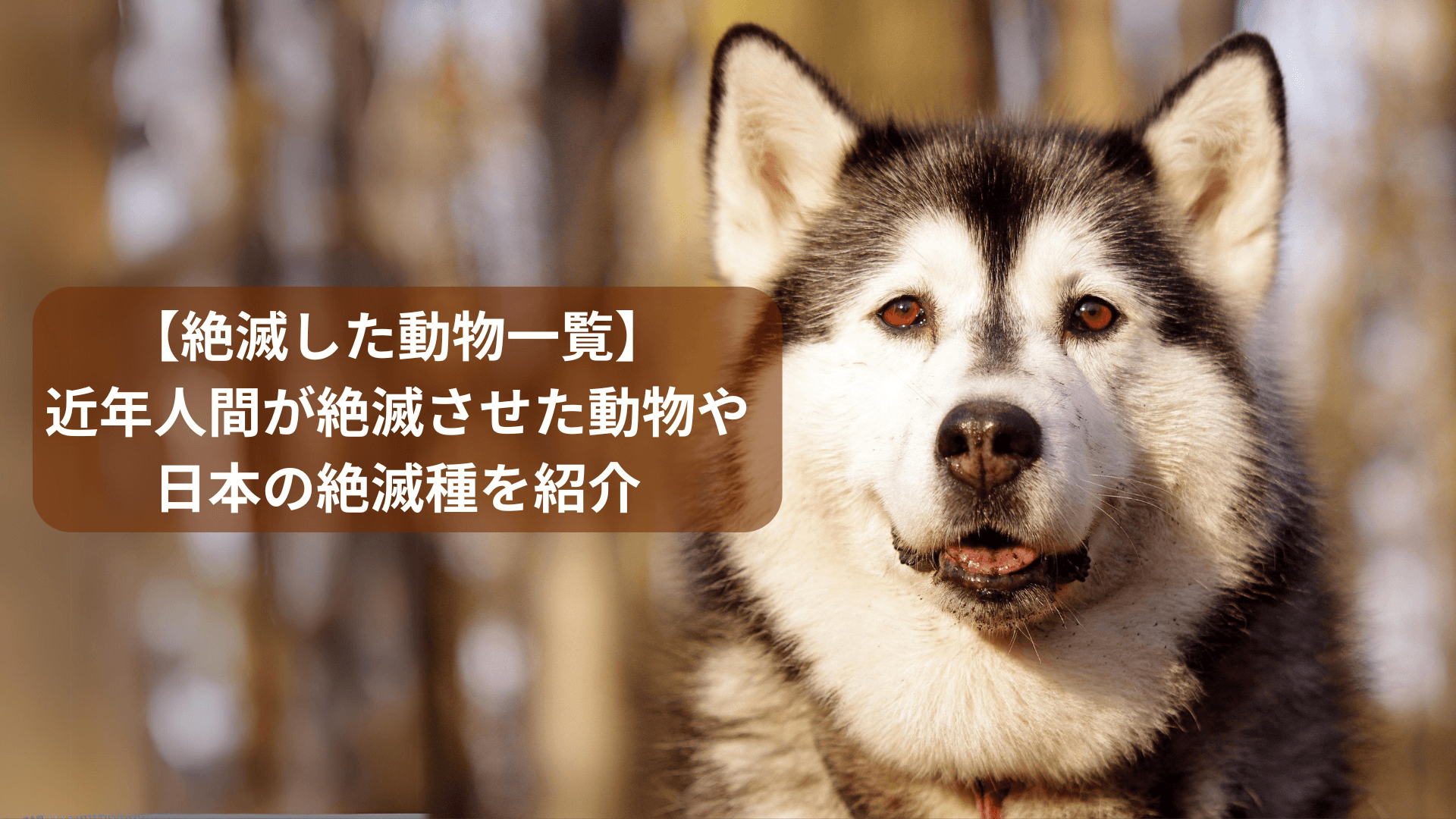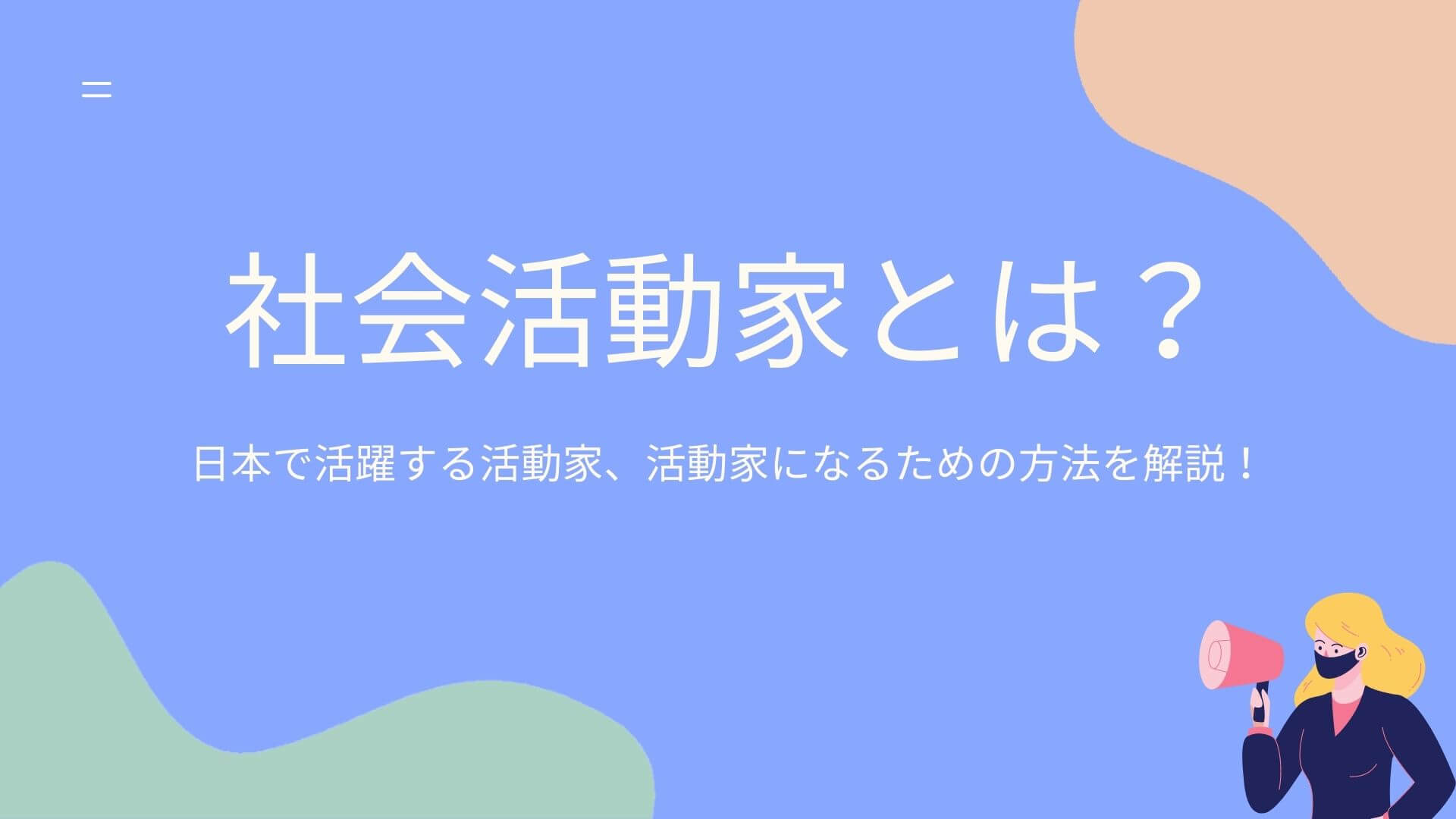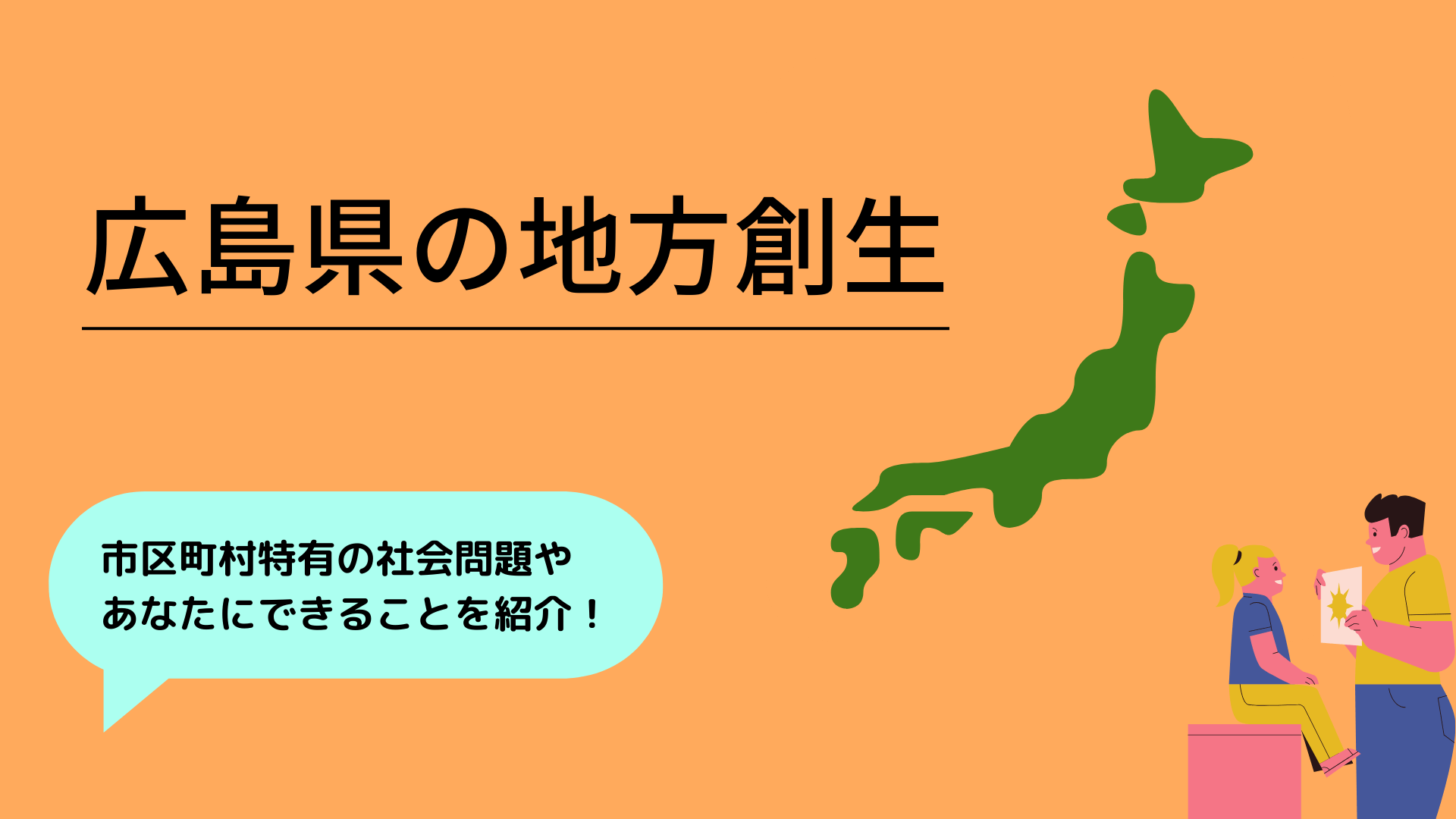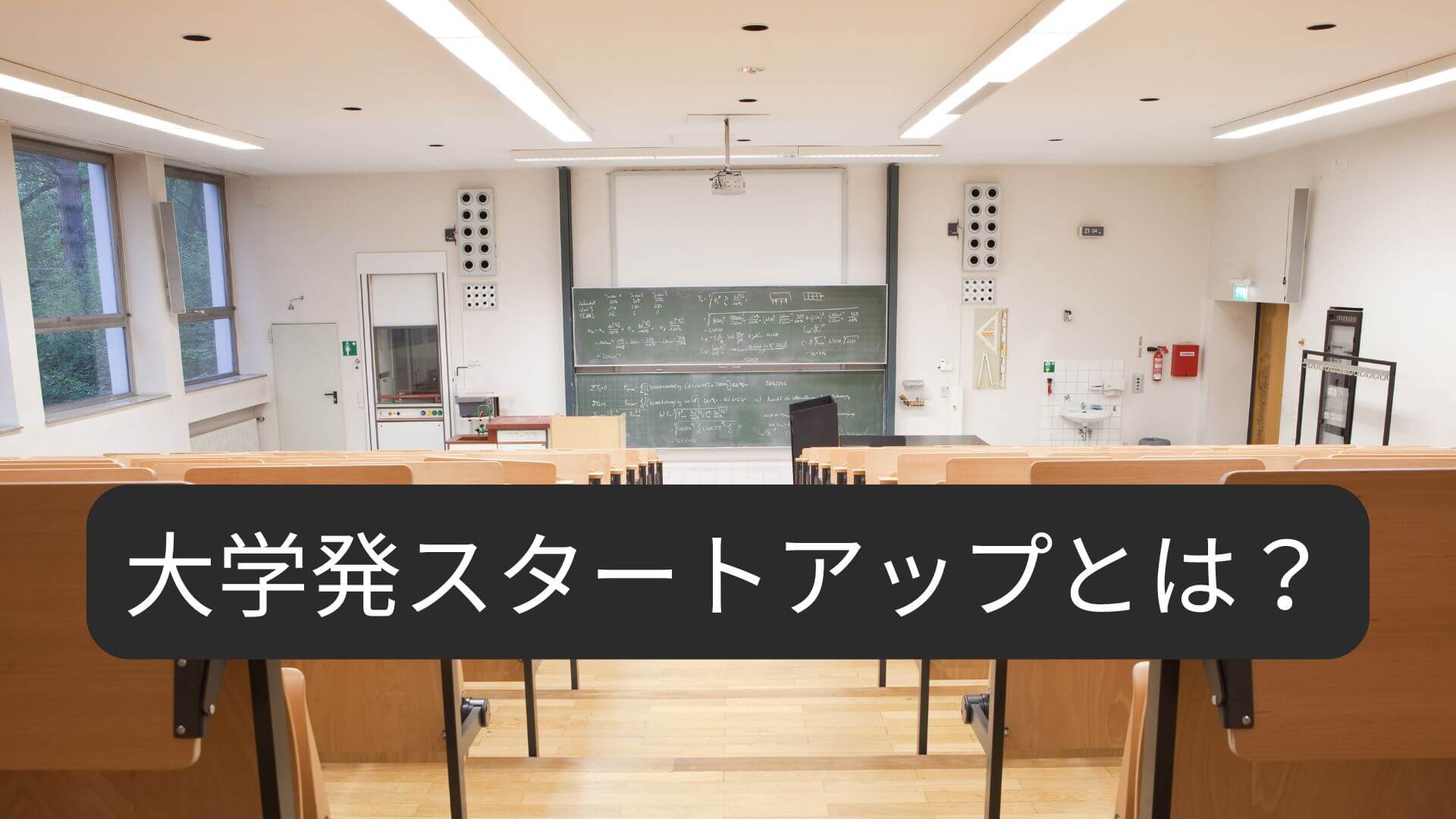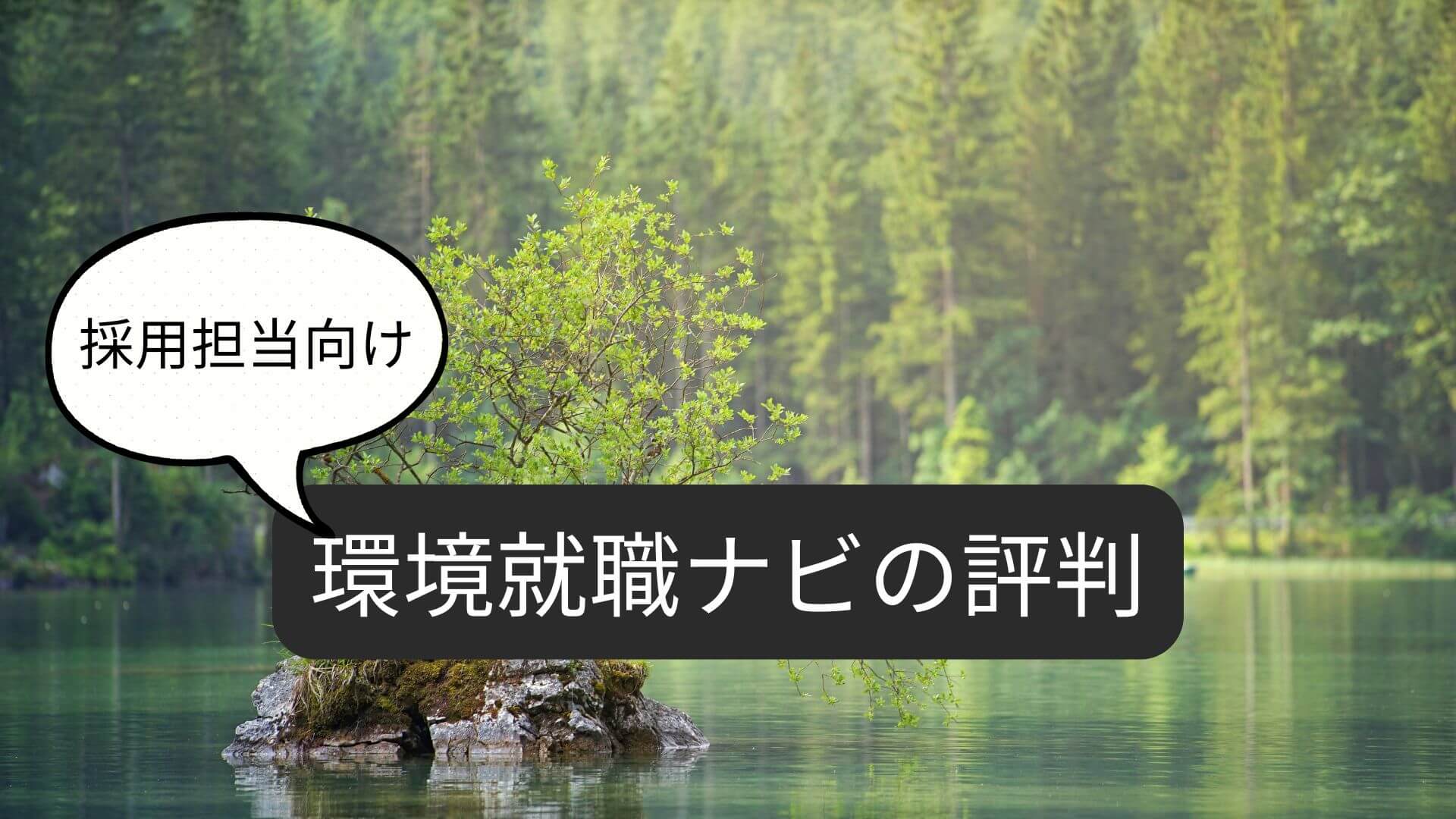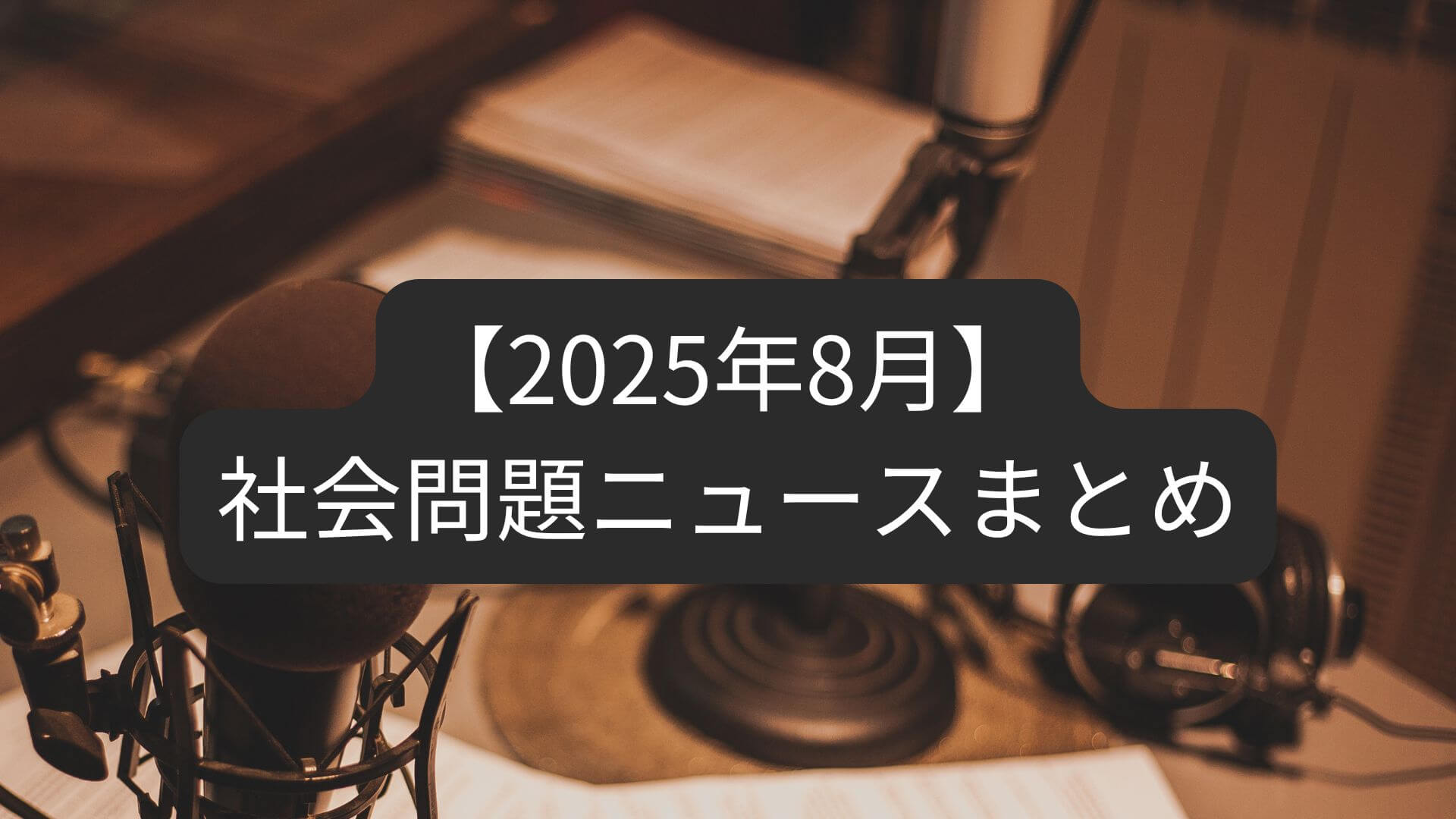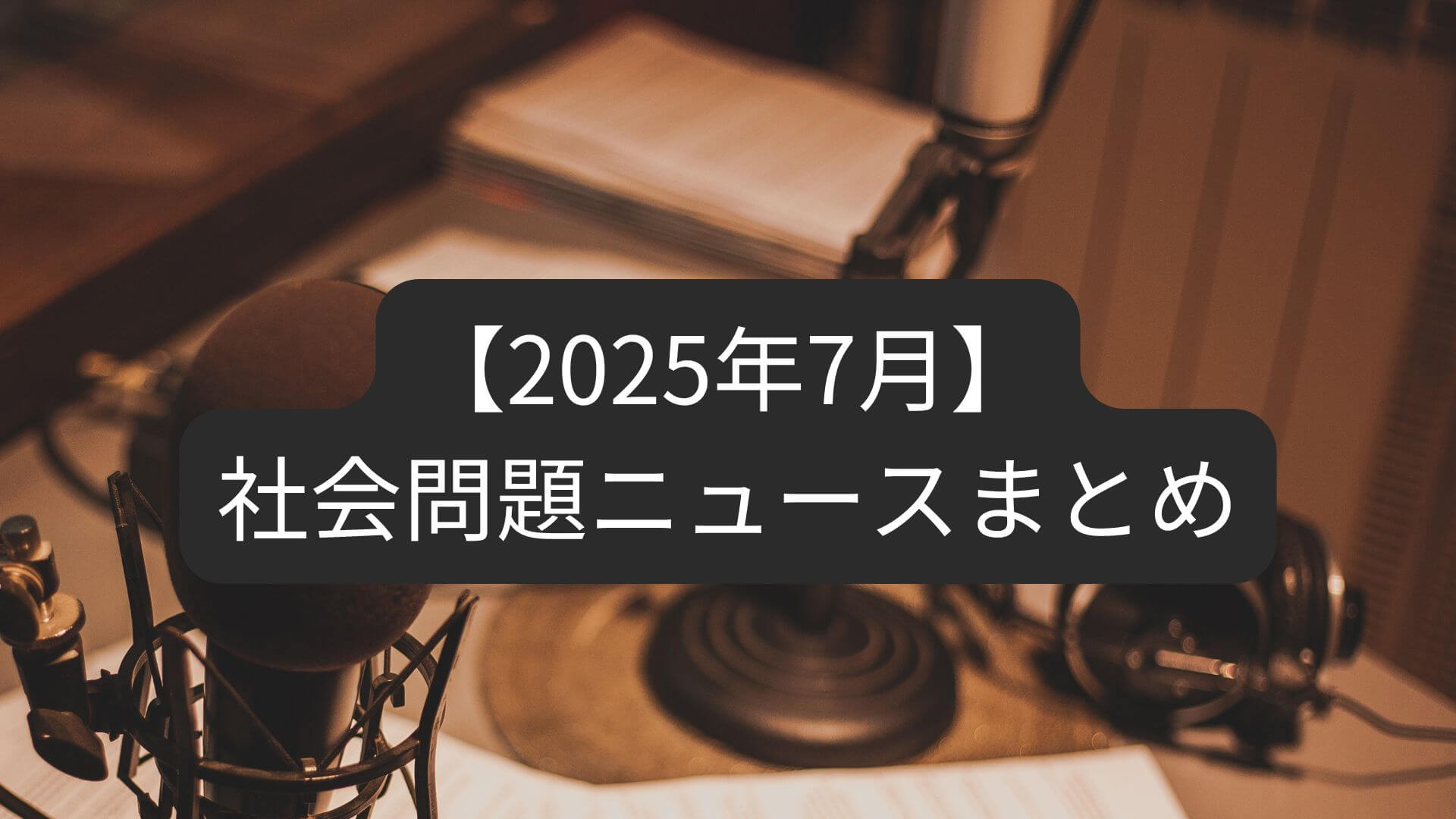近年、SDGs(持続可能な開発目標)という言葉を耳にする機会が増えています。
特に「住み続けられるまちづくり」は、私たちの日常生活に直結する重要なテーマです。
この記事では、SDGsの基本的な情報を踏まえながら、住み続けられるまちづくりの意義や現状、課題について解説します。
さらに、私たち一人ひとりができる具体的なアクションも紹介します。
初めてSDGsに関心を持った方にもわかりやすくお伝えしますので、ぜひ最後までお読みください。
目次
住み続けられるまちづくりとは

「住み続けられるまちづくり」とは、誰もが安全で快適に暮らせる持続可能な都市やコミュニティを目指す取り組みです。
具体的には、災害に強いインフラの整備、環境に配慮した都市計画、多様な人々が共生できる社会の実現などが含まれます。
このコンセプトは、SDGsの目標11「住み続けられるまちづくりを」に明確に示されており、世界中で注目されています。
SDGsとは
SDGs(Sustainable Development Goals)は、2015年に国連で採択された「持続可能な開発目標」です。2030年までに達成すべき17の目標と169のターゲットから構成されています。
これらの目標は、貧困や飢餓の撲滅、教育の普及、気候変動対策など、多岐にわたる課題を包括的に解決することを目指しています。
SDGsは、政府や企業だけでなく、個人も含めたすべての人が参加するグローバルな取り組みです。
住み続けられるまちづくりを構成するターゲット
SDGsの目標11「住み続けられるまちづくりを」には、以下のような具体的なターゲットが設定されています。
| 11.1 | 2030年までに、全ての人々の、適切、安全かつ安価な住宅及び基本的サービスへのアクセスを確保し、スラムを改善する。 |
| 11.2 | 2030年までに、脆弱な立場にある人々、女性、子供、障害者及び高齢者のニーズに特に配慮 し、公共交通機関の拡大などを通じた交通の安全性改善により、全ての人々に、安全かつ安価で容易に利用できる、持続可能な輸送システムへのアクセスを提供する。 |
| 11.3 | 2030年までに、包摂的かつ持続可能な都市化を促進し、全ての国々の参加型、包摂的かつ持続可能な人間居住計画・管理の能力を強化する。 |
| 11.4 | 世界の文化遺産及び自然遺産の保護・保全の努力を強化する。 |
| 11.5 | 2030年までに、貧困層及び脆弱な立場にある人々の保護に焦点をあてながら、水関連災害などの災害による死者や被災者数を大幅に削減し、世界の国内総生産比で直接的経済損失を大幅 に減らす。 |
| 11.6 | 2030年までに、大気の質及び一般並びにその他の廃棄物の管理に特別な注意を払うことによるものを含め、都市の一人当たりの環境上の悪影響を軽減する。 |
| 11.7 | 2030年までに、女性、子供、高齢者及び障害者を含め、人々に安全で包摂的かつ利用が容易な緑地や公共スペースへの普遍的アクセスを提供する。 |
| 11.a | 各国・地域規模の開発計画の強化を通じて、経済、社会、環境面における都市部、都市周辺部及び農村部間の良好なつながりを支援する。 |
| 11.b | 2020年までに、包含、資源効率、気候変動の緩和と適応、災害に対する強靱さ(レジリエン ス)を目指す総合的政策及び計画を導入・実施した都市及び人間居住地の件数を大幅に増加させ、仙台防災枠組2015-2030に沿って、あらゆるレベルでの総合的な災害リスク管理の策定 と実施を行う。 |
| 11.c | 財政的及び技術的な支援などを通じて、後発開発途上国における現地の資材を用いた、持続可能かつ強靱(レジリエント)な建造物の整備を支援する。 |
住み続けられるまちづくりが生まれた背景
「住み続けられるまちづくり」という考え方が生まれた背景には、急速な都市化とそれに伴う問題があります。
20世紀以降、世界中で都市への人口集中が進み、特に発展途上国ではスラムの拡大やインフラ不足が深刻化しました。また、先進国でも都市部の過密化による生活環境の悪化が問題となっています。
さらに、気候変動や自然災害のリスクが高まっていることも大きな要因です。
例えば、海面上昇による沿岸部の浸水や、豪雨による洪水被害など、都市の脆弱性が浮き彫りになっています。
こうした状況を踏まえ、持続可能なまちづくりが国際的な課題として認識されるようになりました。
住み続けられるまちづくりの現状

現在、世界各国で住み続けられるまちづくりに向けた取り組みが進んでいます。
例えば、北欧諸国では環境に配慮した都市計画が進み、公共交通機関の利用が促進されています。
また、日本でも災害に強いまちづくりや、高齢者が住みやすいバリアフリー設計が進められています。
しかし、まだ多くの課題が残されています。
特に発展途上国では、インフラ整備が遅れており、災害時の被害が大きくなりがちです。
また、先進国でも都市部の過密化や環境問題が深刻化しています。
住み続けられるまちづくりの課題
住み続けられるまちづくりを実現するためには、以下のような課題を克服する必要があります。
≫【2024年最新】日本の社会問題一覧!30の社会課題とランキングを解説!
インフラ整備の遅れ
都市部に人口が集中することで、既存のインフラが過剰に利用され、老朽化や機能不全が起こりやすくなっています。
また、農村部ではインフラそのものが整備されていない地域も多く、都市と地方の格差が拡大しています。
≫インフラ整備とは?日本と世界の現状やメリット、SDGsとの関係をわかりやすく解説
≫発展途上国とはどこ?途上国一覧と様々な定義、企業の取り組みを解説!
環境負荷の増大
都市化に伴い、エネルギー消費や廃棄物の増加が深刻な問題となっています。
特に大気汚染や水質汚濁は、住民の健康や生態系に悪影響を及ぼしています。
また、都市部のヒートアイランド現象や緑地の減少も、環境負荷を高める要因です。
≫典型7公害とは?7つの種類や最新の公害状況、対策をわかりやすく解説
≫都市問題とは?人口移動による世界と日本の都市化の課題と解決策
災害リスクの高まり
気候変動の影響により、自然災害が頻発化・激甚化しています。
特に都市部では、人口密度が高いため、災害時の被害が大きくなるリスクがあります。
また、災害に弱いインフラや建物が多いことも課題です。
社会的格差の拡大
都市部と地方、富裕層と貧困層の間で、生活環境や機会の格差が広がっています。
特に都市部では、高額な住宅費や生活費が貧困層の生活を圧迫し、スラムの形成やホームレス問題を引き起こしています。
≫限界集落とはどこ?定義や3つの原因、対策をわかりやすく解説
≫消滅集落とは?原因と増え続ける理由
≫スラムとは?どこの国にある?定義やなくすためにできることを解説
コミュニティの弱体化
地域社会のつながりが薄れ、災害時の共助や日常的な支え合いが難しくなっています。
特に都市部では、匿名性が高く、近隣住民との交流が少ないため、孤立する人々が増えています。
財政的・制度的な制約
持続可能なまちづくりを進めるためには、莫大な資金と長期的な計画が必要です。
しかし、特に財政基盤の弱い自治体では、予算不足や人材不足が大きな障壁となっています。
住み続けられるまちづくりをに取り組む企業3選

住み続けられるまちづくりをに取り組む企業を紹介します。
≫【SDGs目標11】住み続けられるまちづくりをに取り組む企業10選!就職・転職におすすめの大企業からベンチャー
≫まちづくりに取り組む企業10選!就職・転職におすすめのベンチャーから大企業
株式会社さとふる
株式会社さとふるは、ふるさと納税ポータルサイト「さとふる」の運営する企業です。
「ふるさとを元気に。」を企業理念とし、ITの力を活用した地域活性化に取り組んでいます。
ふるさと納税に係る負担を軽減することで、地域や事業者は新しい取り組みへの挑戦を援助。地域の魅力が増し、地域に興味を持つ人や、応援する人が増え、地域産業が活性化されるきっかけを創出しています。
HP:https://www.satofull.jp/static/company/
ANAあきんど株式会社
ANAあきんど株式会社は、航空セールス事業に加え、地域創生事業に注力しているANAグループの会社です。
「地域と世界をつなぐ翼で地域とともに日本の未来を創る」をミッションに掲げ、ANAグループのネットワークを生かした人流・商流を創出。
観光振興や産業振興などを通じ、地域、顧客、ANAグループの「三方よし」を目指しています。
HP:https://www.ana-akindo.co.jp/
株式会社テイラーワークス
株式会社テイラーワークスは、信頼と共感を核に、地域や業種を越えたコラボレーションを促進するソーシャルコミュニティプラットフォーム「Tailor Works」を運営しています。
このプラットフォームは、新たな出会い、つながり、そしてアイデアやプロジェクトの拡散を可能にする三つの特長を持ち、共通の興味を持つ仲間と繋がることができます。
多様なバックグラウンドを持つ人々が共感とビジョンで結びつき、社会を変革するアイデアを現実のものにするための共創体験を提供しています。
HP:https://tailorworks.com/
住み続けられるまちづくりに対して私たちができること5選

「住み続けられるまちづくり」を実現するためには、政府や企業だけでなく、私たち一人ひとりの行動が重要です。
以下に、具体的にできることを5つ詳しく解説します。
省エネ・節電を心がける
家庭や職場でのエネルギー消費を減らすことは、持続可能なまちづくりに直接貢献する行動です。
まずは、日常生活で使う電気やガスの量を減らすことを意識しましょう。
例えば、LED電球や省エネ家電を活用することで、電力消費を大幅に削減できます。
冷暖房の設定温度を適切に調整することも重要です。
夏は28℃、冬は20℃を目安にすることで、無駄なエネルギー消費を抑えられます。
公共交通機関を利用する
車ではなく、電車やバス、自転車などの環境に優しい交通手段を選ぶことで、CO2排出量を削減できます。
特に都市部では、自動車の利用が大気汚染や交通渋滞の原因となっています。
通勤や買い物に公共交通機関を利用するだけでなく、自転車や徒歩で移動できる距離は車を使わないようにしましょう。
また、カーシェアリングやライドシェアを活用することで、車の台数を減らすことができます。
地域活動に参加する
地域のイベントやボランティア活動に参加することで、コミュニティの絆を強め、持続可能なまちづくりを支えることができます。
例えば、防災訓練や清掃活動に参加することで、災害に強いまちづくりや美しい街並みの維持に貢献できます。
また、地域の祭りやイベントに積極的に参加することで、住民同士のつながりを深めることができます。
高齢者や障害者を支援するボランティアに参加することも、地域社会の包摂性を高める重要な行動です。
≫地域貢献とは?社会貢献との違いや企業の取り組み事例・メリットを解説!
≫町おこしとは?成功事例と失敗事例、成功に必要なポイントを解説
≫地域活性化とは?なぜ必要?メリットや具体事例を簡単に解説
地元の商品を購入する
地元産の食材や製品を選ぶことで、地域経済を支え、環境負荷を軽減することができます。
地元の農産物や特産品を購入することで、輸送に伴うCO2排出量を削減できます。
また、地元の商店や市場で買い物をすることで、地域の産業や雇用を守ることにつながります。
地元の飲食店を利用することも、地域経済の活性化に貢献します。さらに、地元の工芸品や伝統工芸品を選ぶことで、地域の文化や歴史を守ることもできます。
≫地産地消のメリット5選!デメリットやSDGs・6次産業との関係も解説
情報を発信・共有する
SNSやブログなどを活用して、持続可能なまちづくりに関する情報を発信・共有することで、周囲の人々の意識を高めることができます。
例えば、SDGsや持続可能なまちづくりに関する情報をSNSでシェアすることで、より多くの人々が関心を持つきっかけとなります。
また、地域の取り組みや成功事例を紹介することで、他の地域にも良い影響を与えることができます。
環境保護や省エネに関するアイデアを発信することも、具体的な行動を促す有効な手段です。
さらに、地域の課題について議論するオンラインコミュニティに参加することで、新しい解決策を見つけることができるかもしれません。
≫レポートで書きやすい地域課題のテーマ5選!都道府県ごとの課題やテーマの選び方を解説
≫【2024年最新版】社会課題やSDGs、サステナブルについて発信するメディア30選!
まとめ
住み続けられるまちづくりは、SDGsの重要な目標の一つです。
急速な都市化や気候変動、社会的不平等といった課題を解決するためには、持続可能な都市計画やインフラ整備が不可欠です。
しかし、その実現には政府や企業だけでなく、私たち一人ひとりの努力も必要です。
省エネやリサイクル、地域活動への参加など、身近なことから始めることで、住み続けられるまちづくりに貢献できます。
ぜひ今日からできることを見つけて、行動に移してみてください。
【その他のSDGsの目標を詳しく知りたい】
【SDGs目標1】貧困をなくそうとは?背景や現状、企業の取り組み、私たちにできることを解説
【SDGs目標2】飢餓をゼロにとは?背景や現状、企業の取り組み、私たちにできることを解説
【SDGs目標3】すべての人に健康と福祉をとは?背景や現状、企業の取り組み、私たちにできることを解説
【SDGs目標4】質の高い教育をみんなにとは?背景や現状、企業の取り組み、私たちにできることを解説
【SDGs目標5】ジェンダー平等を実現しようとは?背景や現状、企業の取り組み、私たちにできることを解説
【SDGs目標6】安全な水とトイレを世界中にとは?背景や現状、企業の取り組み、私たちにできることを解説
【SDGs目標7】エネルギーをみんなに そしてクリーンにとは?背景や現状、企業の取り組み、私たちにできることを解説
【SDGs目標8】働きがいも経済成長もとは?背景や現状、企業の取り組み、私たちにできることを解説
【SDGs目標9】産業と技術革新の基盤を作ろうとは?背景や現状、企業の取り組み、私たちにできることを解説
【SDGs目標10】人や国の不平等をなくそうとは?背景や現状、企業の取り組み、私たちにできることを解説
【SDGs目標11】住み続けられるまちづくりをとは?背景や現状、企業の取り組み、私たちにできることを解説
【SDGs目標12】つくる責任つかう責任とは?背景や現状、企業の取り組み、私たちにできることを解説
【SDGs目標13】気候変動に具体的な対策をとは?背景や現状、企業の取り組み、私たちにできることを解説
【SDGs目標14】海の豊かさを守ろうとは?背景や現状、企業の取り組み、私たちにできることを解説
【SDGs目標15】陸の豊かさも守ろうとは?背景や現状、企業の取り組み、私たちにできることを解説
【SDGs目標16】平和と公正をすべての人にとは?背景や現状、企業の取り組み、私たちにできることを解説
【SDGs目標17】パートナーシップで目標を達成しようとは?背景や現状、企業の取り組み、私たちにできることを解説

この記事の監修者
吉田宏輝
COCOCOLOREARTH代表、社会活動家。
COCOCOLOREARTHでは、社会課題解決を軸にした就職・転職活動を支援するインタビューメディアの代表として、100人以上の社会活動家にインタビュー、記事執筆やイベント登壇などを行う。