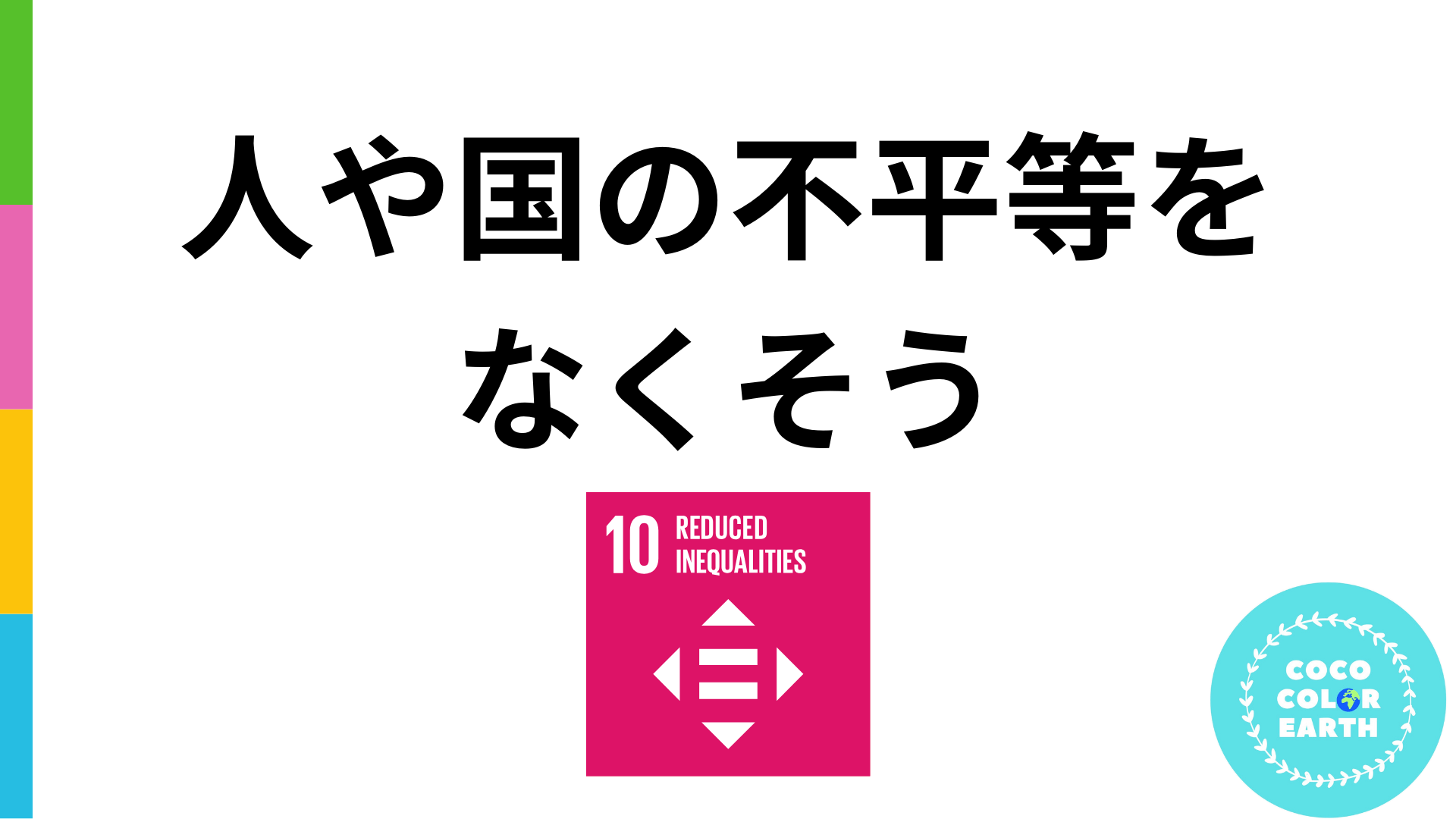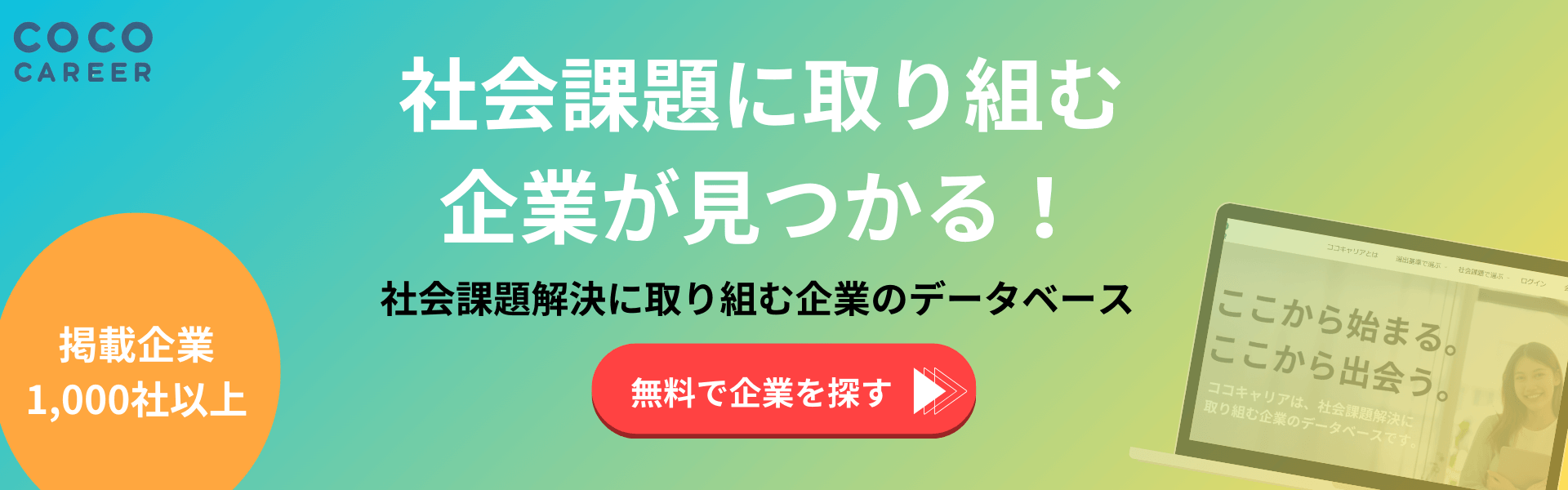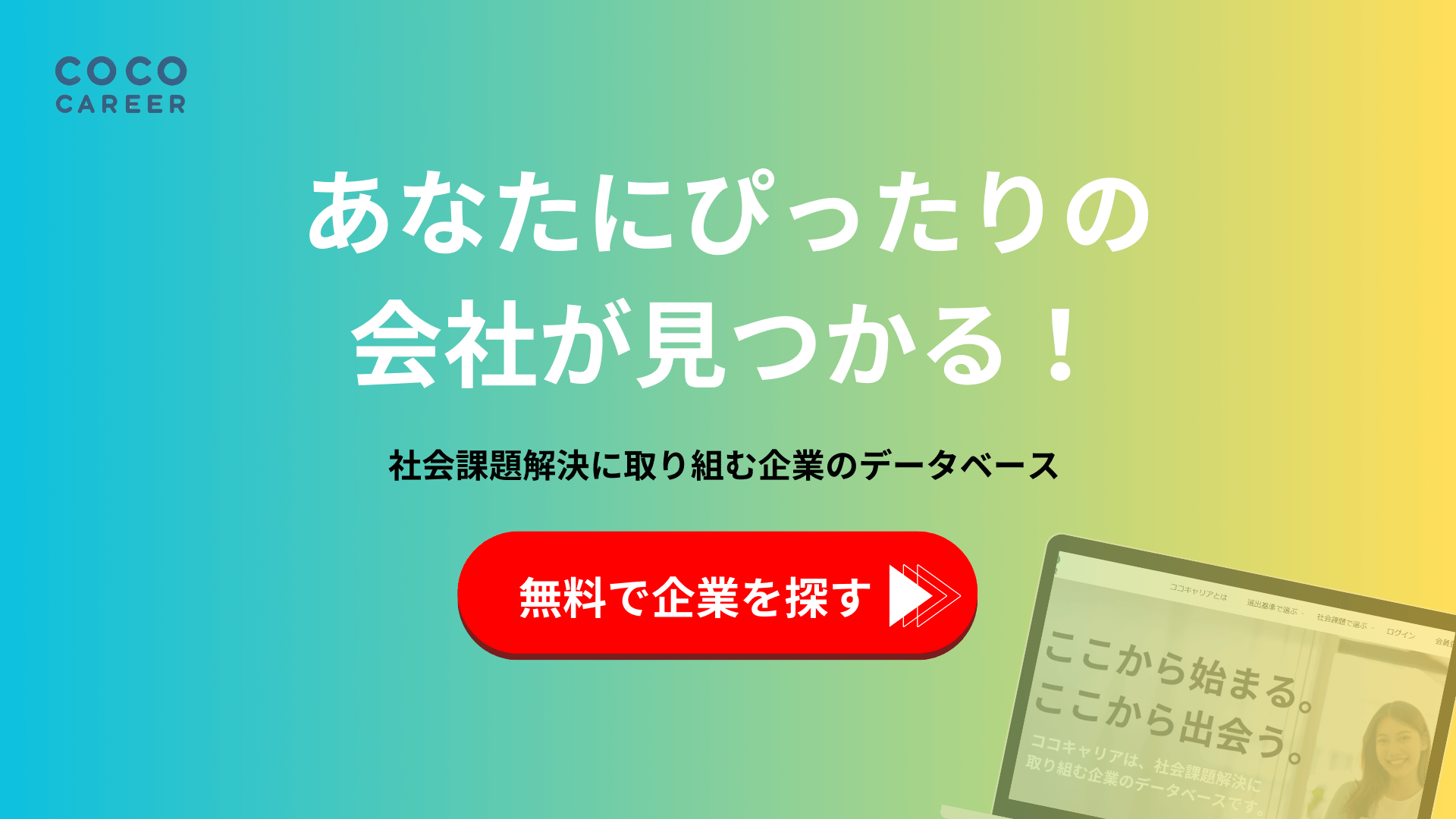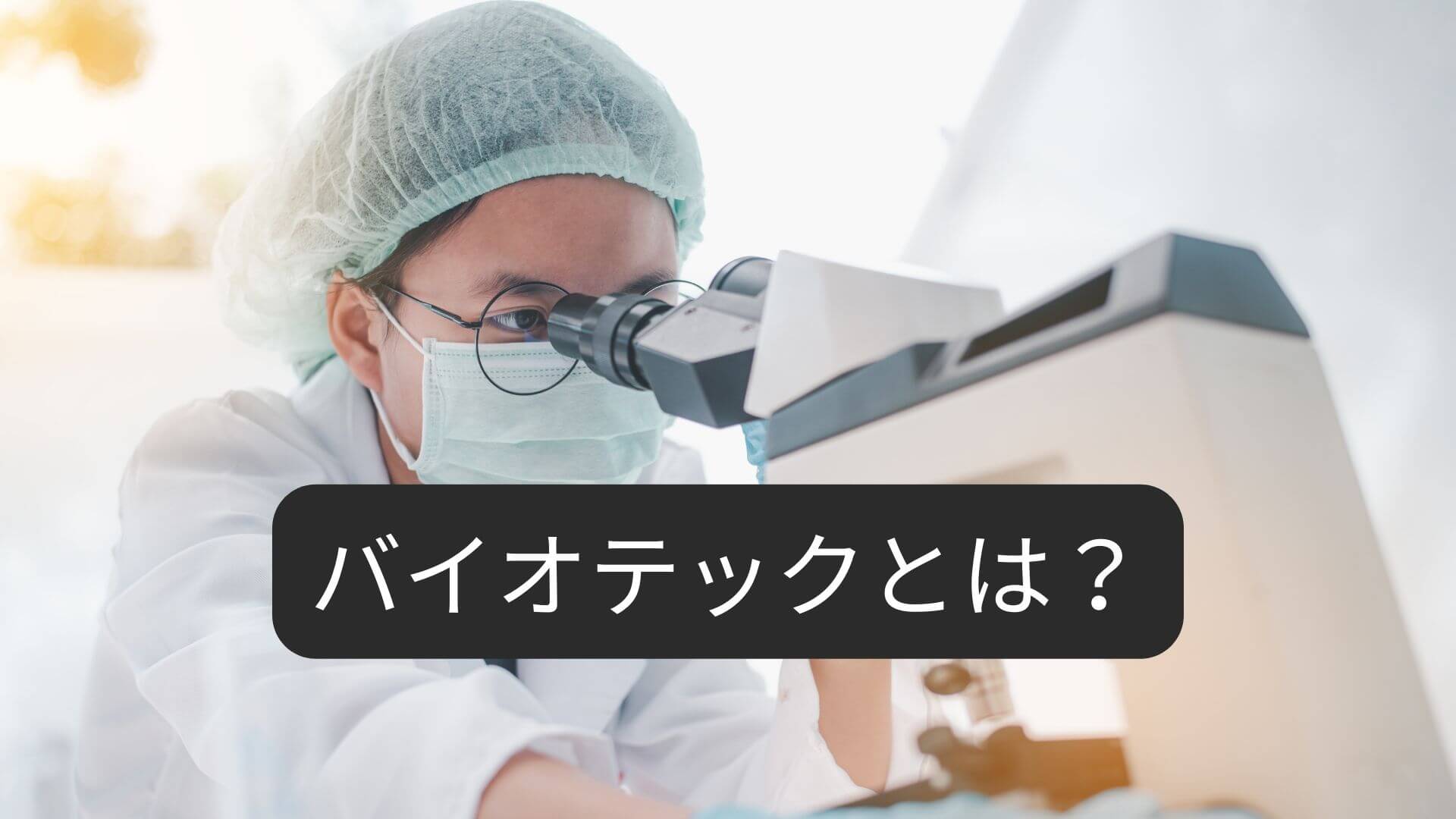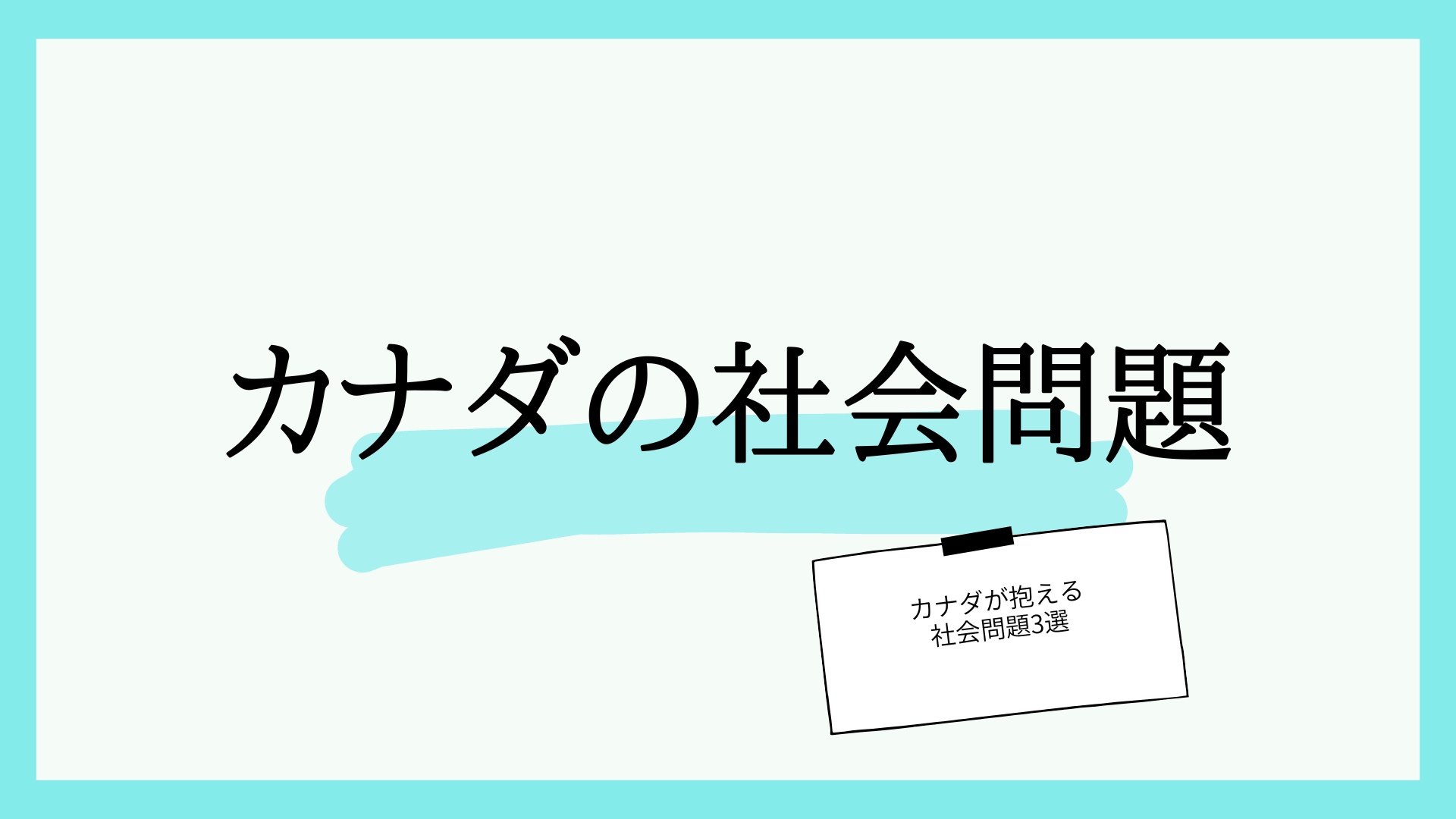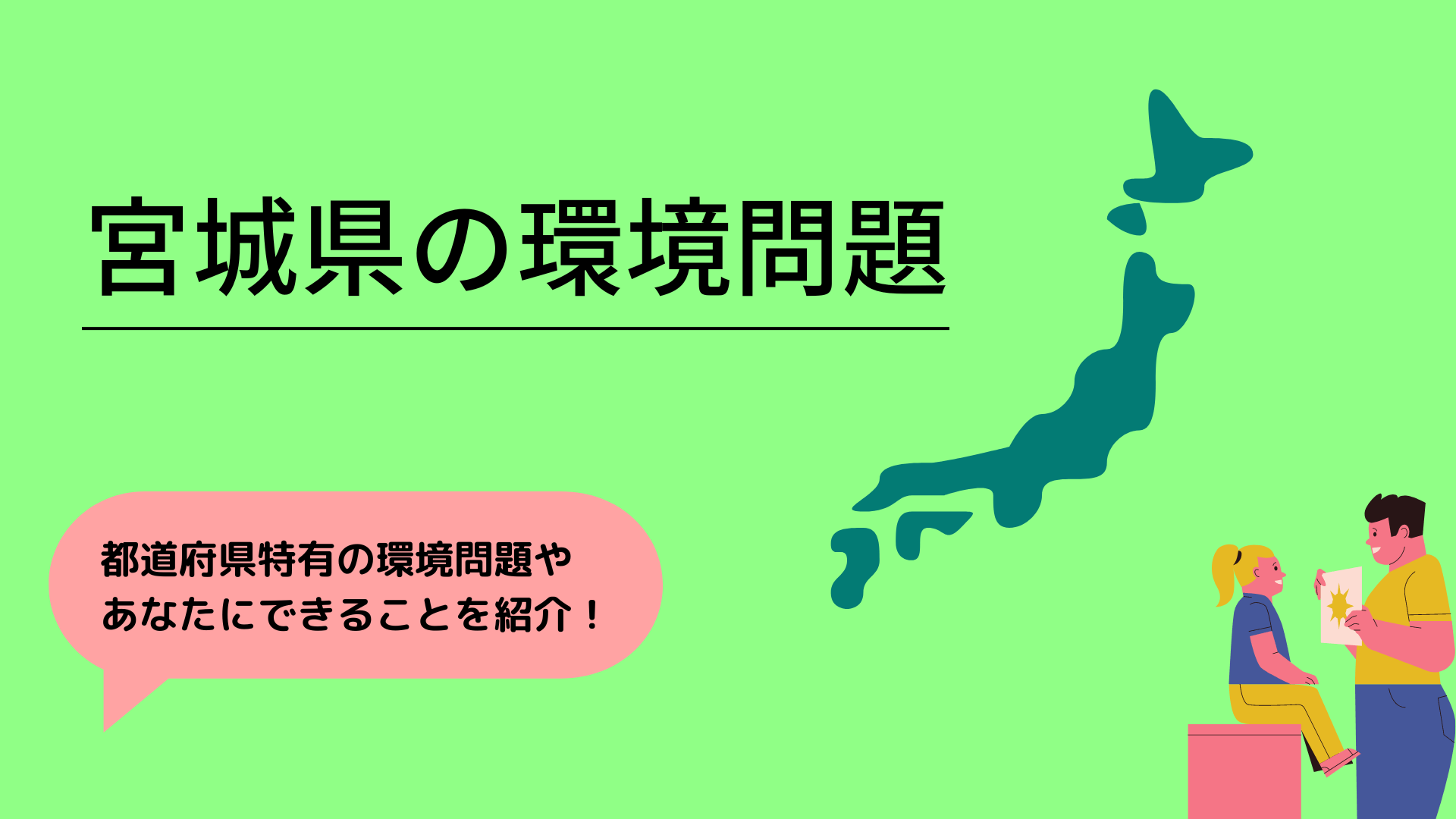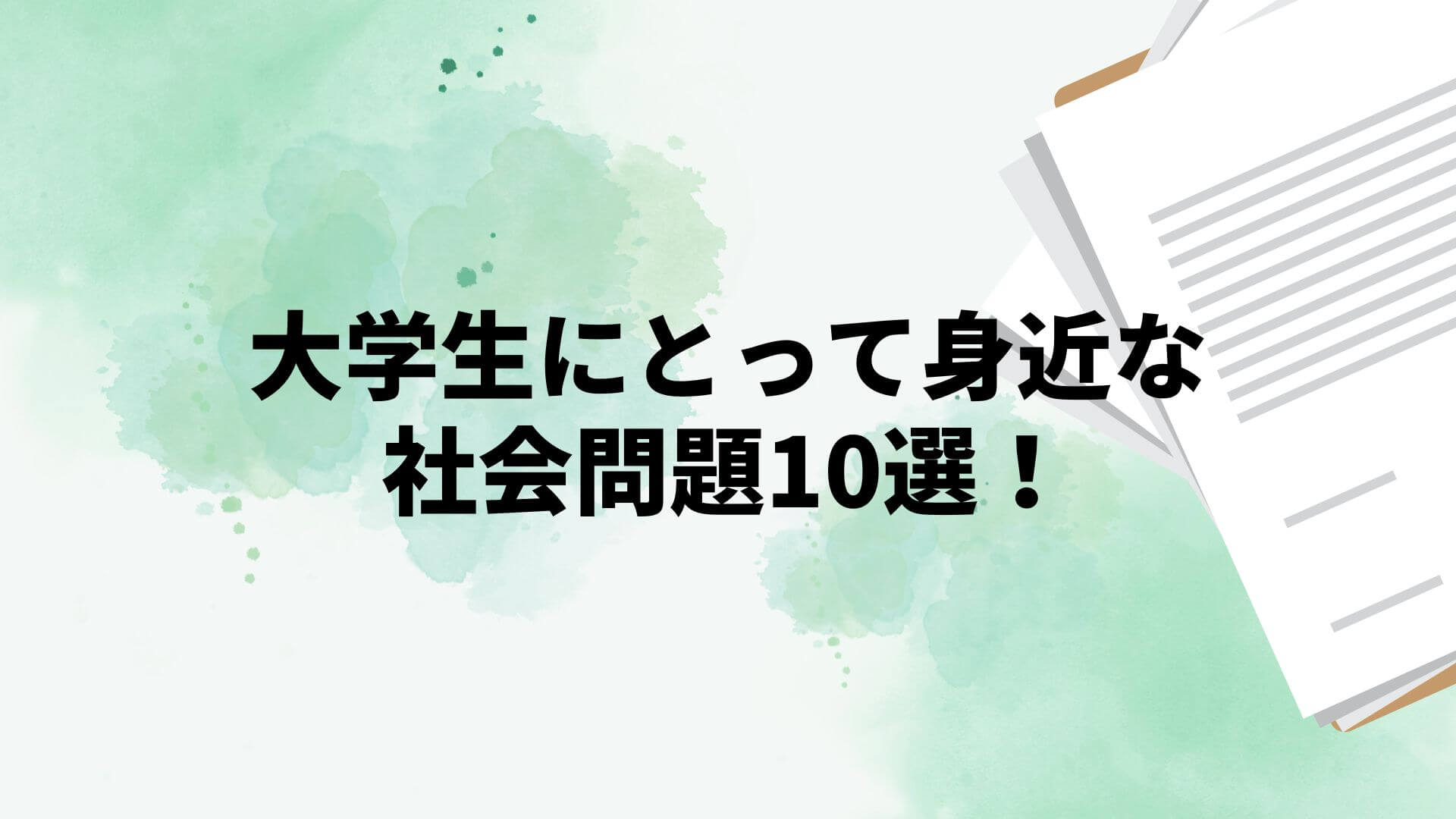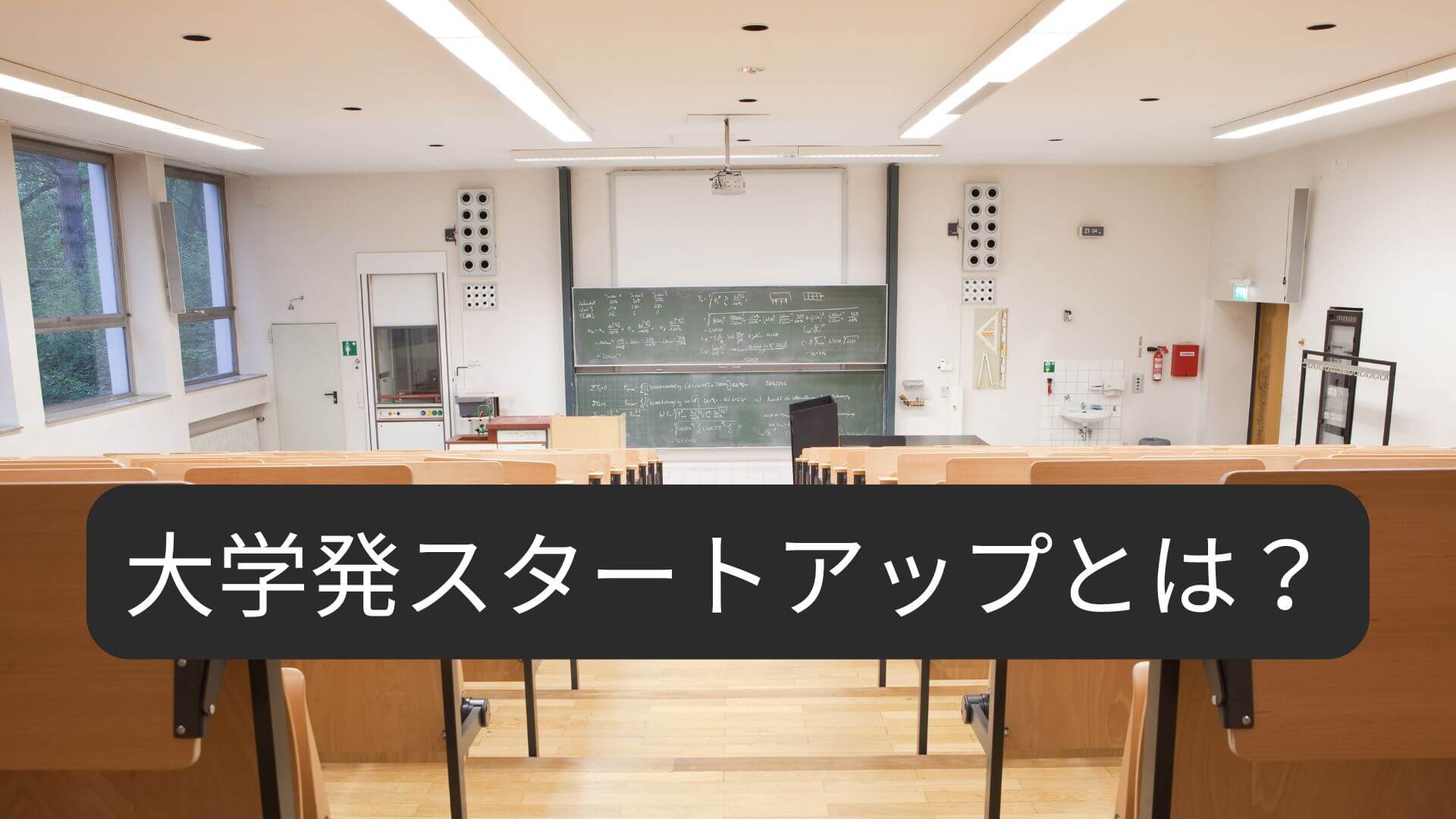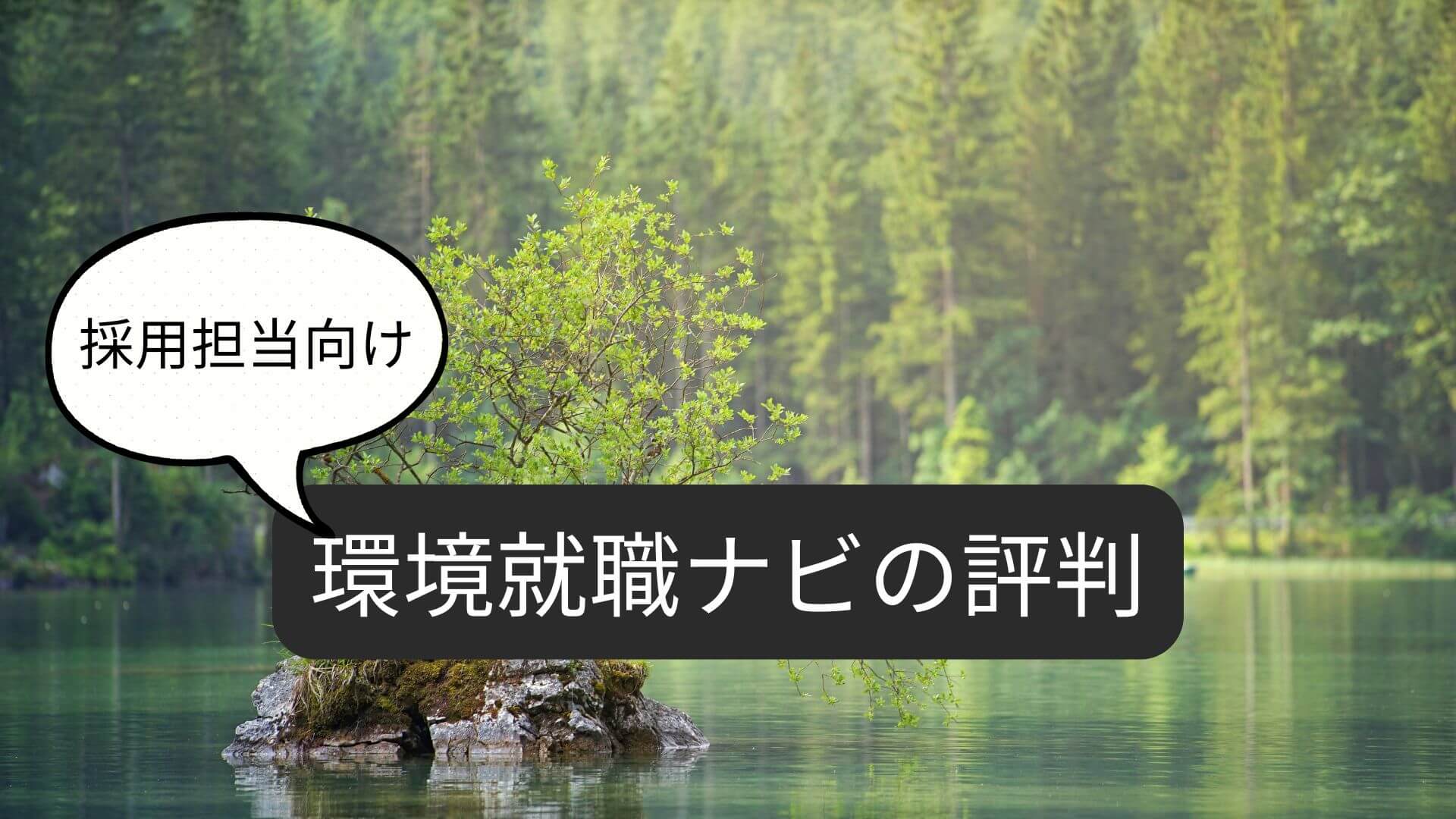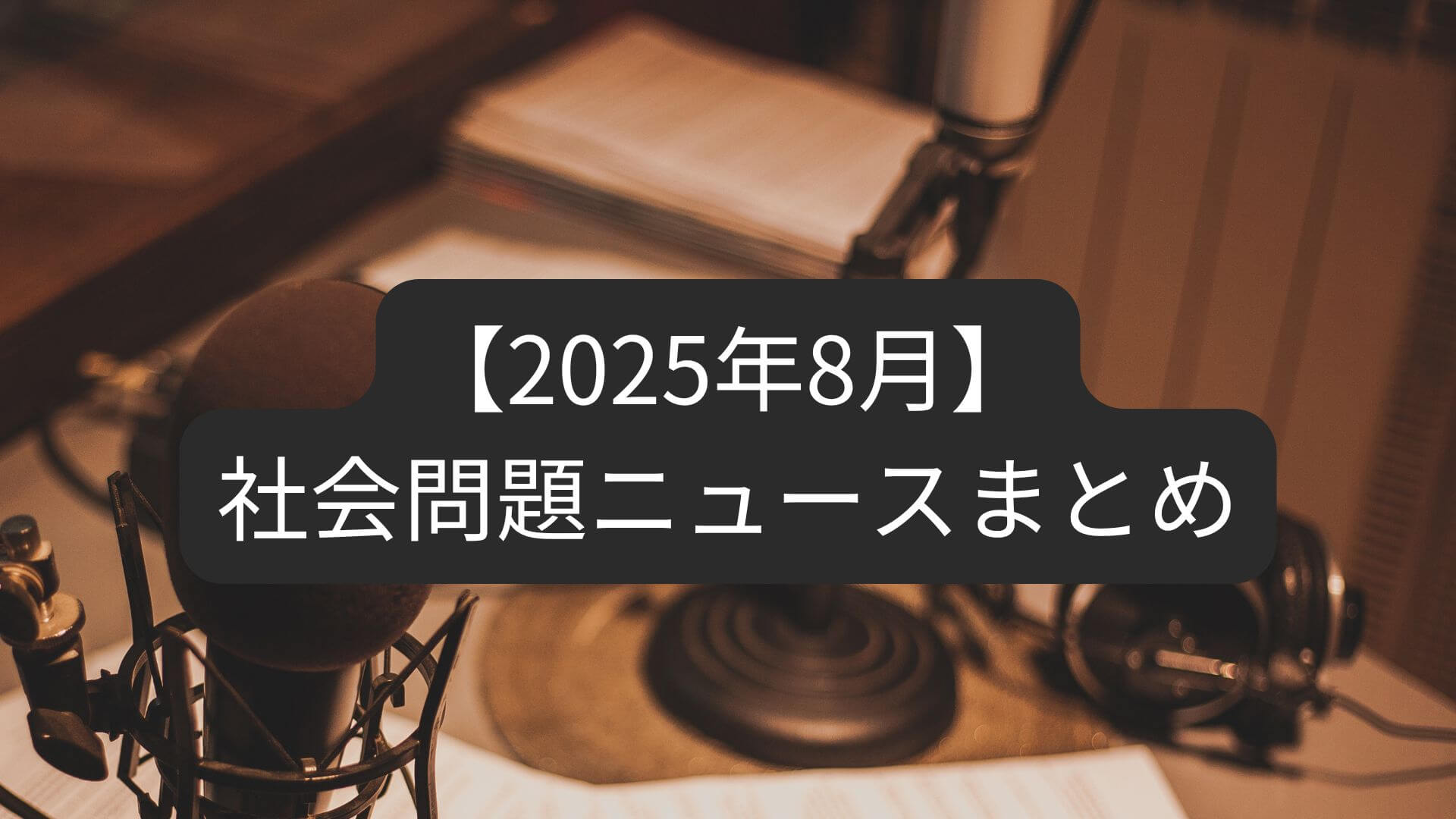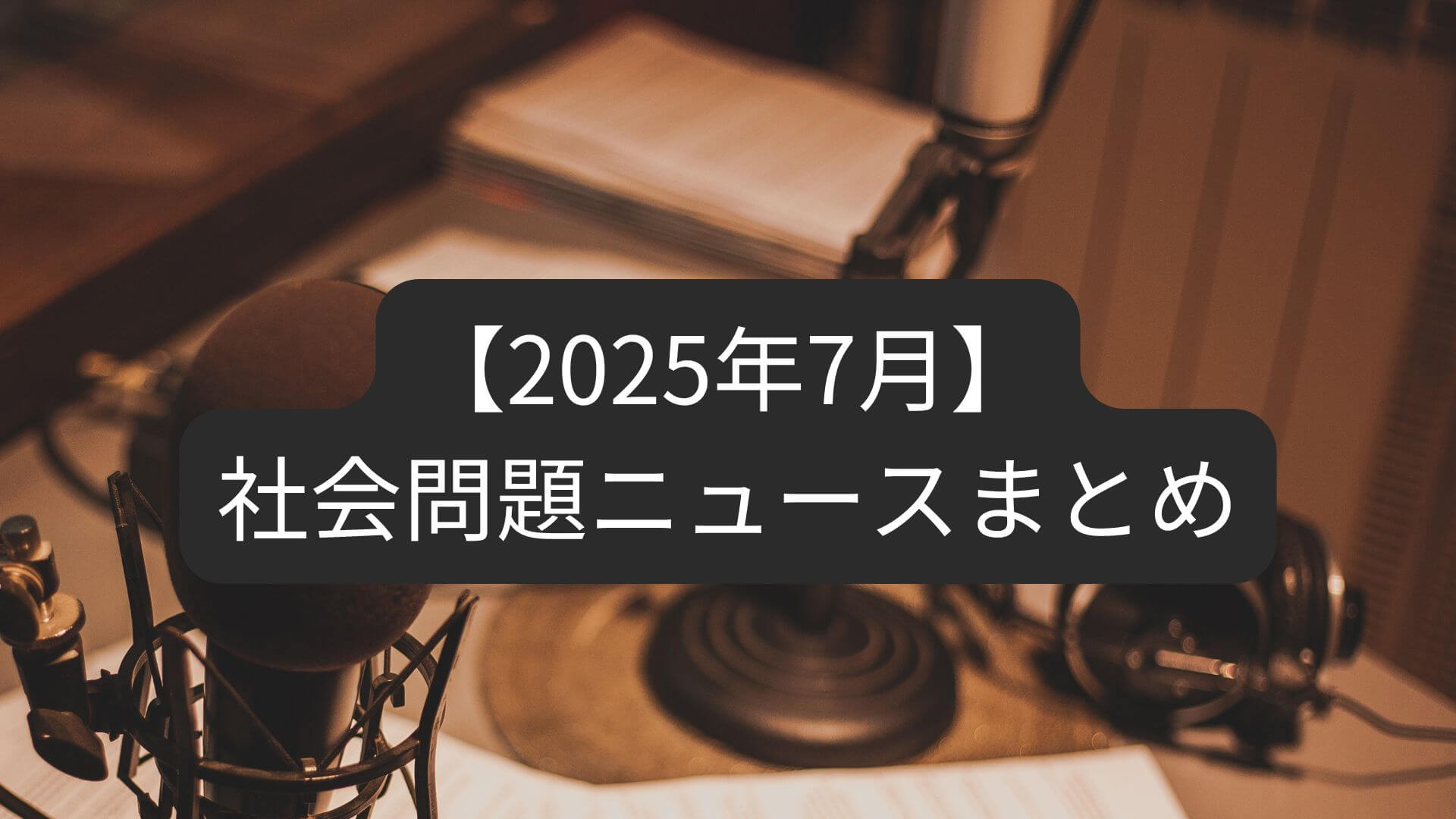近年、SDGs(持続可能な開発目標)という言葉を耳にする機会が増えています。
特に「人や国の不平等をなくそう」という目標は、誰もが公平な機会を得られる社会を目指す重要なテーマです。
しかし、なぜこの目標が掲げられたのか、その背景や現状、私たちに何ができるのかを理解している人は少ないかもしれません。
この記事では、初めてSDGsに関心を持った人に向けて、「人や国の不平等をなくそう」の基本的な情報をわかりやすく解説します。
目次
人や国の不平等をなくそうとは

「人や国の不平等をなくそう」は、SDGsの17の目標のうちの10番目に位置付けられています。
この目標は、世界中のあらゆる形態の不平等を減らし、誰もが公平な機会を得られる社会を実現することを目指しています。
具体的には、所得格差、性別や年齢による差別、地域間の経済格差など、多岐にわたる問題に取り組むことが求められています。
SDGsとは
SDGs(Sustainable Development Goals)は、2015年に国連で採択された「持続可能な開発目標」です。
2030年までに達成すべき17の目標と169のターゲットから構成されており、貧困や飢餓、気候変動、不平等など、世界が抱える課題を解決するための国際的な枠組みです。
SDGsは「誰一人取り残さない」を理念としており、すべての国や地域、企業、個人が協力して取り組むことが求められています。
人や国の不平等をなくそうを構成するターゲット
「人や国の不平等をなくそう」には、具体的な10のターゲットが設定されています。以下にその一部を紹介します。
| 10.1 | 2030 年までに、各国の所得下位 40%の所得成長率について、国内平均を上回る数値を漸進的に達成し、持続させる。 |
| 10.2 | 2030 年までに、年齢、性別、障害、人種、民族、出自、宗教、あるいは経済的地位その他の状況に関わりなく、全ての人々の能力強化及び社会的、経済的及び政治的な包含を促進する。 |
| 10.3 | 差別的な法律、政策及び慣行の撤廃、並びに適切な関連法規、政策、行動の促進などを通じて、機会均等を確保し、成果の不平等を是正する。 |
| 10.4 | 税制、賃金、社会保障政策をはじめとする政策を導入し、平等の拡大を漸進的に達成する。 |
| 10.5 | 世界金融市場と金融機関に対する規制とモニタリングを改善し、こうした規制の実施を強化する。 |
| 10.6 | 地球規模の国際経済・金融制度の意思決定における開発途上国の参加や発言力を拡大させることにより、より効果的で信用力があり、説明責任のある正当な制度を実現する。 |
| 10.7 | 計画に基づき良く管理された移民政策の実施などを通じて、秩序のとれた、安全で規則的かつ責任ある移住や流動性を促進する。 |
| 10.a | 世界貿易機関(WTO)協定に従い、開発途上国、特に後発開発途上国に対する特別かつ異なる待遇の原則を実施する。 |
| 10.b | 各国の国家計画やプログラムに従って、後発開発途上国、アフリカ諸国、小島嶼開発途上国及び内陸開発途上国を始めとする、ニーズが最も大きい国々への、政府開発援助(ODA)及び海外直接 投資を含む資金の流入を促進する。 |
人や国の不平等をなくそうが生まれた背景
不平等は、長年にわたって人類が直面してきた問題です。
特に、経済のグローバル化が進む中で、富裕層と貧困層の格差が拡大し、地域間や国家間の経済的不平等が深刻化しました。また、性別や人種、宗教による差別も根強く残っています。
こうした状況を改善するため、国際社会はSDGsを通じて不平等の解消に取り組むことを決めたのです。
人や国の不平等をなくそうの現状

「人や国の不平等をなくそう」という目標は、SDGsの重要なテーマの一つですが、現状では依然として多くの課題が残されています。
経済格差の拡大
世界では、富裕層と貧困層の間の経済格差が拡大しています。
特に、世界の富裕層1%が持つ資産は、残り99%の資産を上回っていると言われています。
開発途上国では、貧困層の生活水準が向上せず、経済的な機会が限られているため、格差がさらに深刻化しています。
また、先進国でも低所得層の生活が苦しくなり、中間層が減少する「格差社会」が問題となっています。
≫南北問題とは?歴史や現状、南南問題との違い、私たちができることを解説
≫南南問題とは?どこの国?背景や現状、南北問題との違いをわかりやすく解説
≫発展途上国とはどこ?途上国一覧と様々な定義、企業の取り組みを解説!
教育と医療へのアクセス格差
教育や医療へのアクセスは、人々の生活の質を左右する重要な要素ですが、その機会は不平等に分配されています。
開発途上国では、特に農村部や紛争地域で、子どもたちが学校に通えない状況が続いています。
また、医療サービスが受けられないために、予防可能な病気で命を落とす人々も少なくありません。
先進国でも、低所得層やマイノリティグループが十分な教育や医療を受けられないケースが多く見られます。
≫子どもの貧困とは?日本の現状や原因、私たちにできることを解説
性別や人種による差別
性別や人種、民族による差別は、依然として世界中で根強く残っています。
女性は男性に比べて賃金が低く、リーダーシップの機会も限られています。
また、マイノリティグループは、就職や住居の選択において差別を受けることが多く、社会的な排除に直面しています。
このような差別は、個人の可能性を制限し、社会全体の成長を阻む要因となっています。
≫マイノリティとは?マジョリティとの違いや使い方、5つの具体例を簡単に解説
≫ジェンダーとは?10種類のジェンダー問題を例を用いてわかりやすく解説!
移民と難民の保護不足
紛争や気候変動、経済的不安定により、移民や難民の数が増加していますが、彼らは移動先の国で適切な保護や支援を受けられないことが多くあります。
移民労働者は低賃金で過酷な労働を強いられ、難民は基本的な人権さえ保障されない状況に置かれています。
また、移民労働者が家族に送金する際のコストが高く、生活を圧迫する要因となっています。
≫紛争とは?戦争、内戦は何が違う?現在起こっている事例をもとに解説
≫移民問題とは?SDGsとの関係や現状、日本の政策を解説
≫日本の難民問題とは?現状や受け入れない理由、私たちにできること
国際的な意思決定における不均衡
国際的な経済や金融の意思決定の場では、開発途上国の声が十分に反映されていない現状があります。
先進国や多国籍企業が主導権を握ることで、開発途上国が不利な立場に置かれることが多く、経済的な不平等がさらに拡大しています。
このような不均衡は、国際社会全体の安定と発展を阻む要因となっています。
≫国際協力とは?15種類の問題と日本の取り組み、キャリアについて簡単に解説!
人や国の不平等をなくそうの課題
「人や国の不平等をなくそう」という目標を達成するためには、多くの課題が存在します。
以下に、その主な課題を見出し分けして説明します。
≫【2024年最新】日本の社会問題一覧!30の社会課題とランキングを解説!
経済格差の是正
経済格差は、先進国と開発途上国の間だけでなく、各国の国内でも深刻な問題です。
富裕層と貧困層の間の所得格差が拡大し、低所得層が経済的な機会を得ることが難しくなっています。
特に、開発途上国では貧困の連鎖が続き、経済的自立が困難な状況が続いています。
このような格差を是正するためには、包括的な経済政策と国際協力が必要です。
社会保障制度の不備
多くの国では、貧困層や社会的弱者に対する社会保障が不十分です。
特に開発途上国では、医療や教育、住宅などの基本的なサービスが行き届かず、貧困層が生活の基盤を築くことが難しい状況です。
また、先進国でも、低所得層や高齢者、障害者に対する支援が不十分なケースが多く見られます。
≫肩車型社会とは?超高齢社会で迎える4つの問題と私たちにできること
差別と偏見の根絶
性別、人種、民族、宗教、障害などによる差別は、依然として世界中で根強く残っています。
差別は、教育や雇用、住居の選択など、人々の生活のあらゆる面に影響を及ぼし、社会的な不平等を生み出しています。
差別をなくすためには、法律や政策の改正だけでなく、人々の意識を変えるための教育や啓発活動が不可欠です。
≫エイジズム(年齢差別)とは?具体例や問題点、私たちにできることを解説
≫レイシズム(人種主義)とは?歴史や現在の問題、日本のレイシズムを簡単に解説
移民と難民の保護
紛争、気候変動、経済的不安定により、移民や難民の数が増加していますが、彼らは移動先の国で適切な保護や支援を受けられないことが多くあります。
移民労働者は低賃金で過酷な労働を強いられ、難民は基本的な人権さえ保障されない状況に置かれています。
移民と難民の権利を保護し、社会に統合するための政策と国際協力が必要です。
国際的な協力の不足
不平等を解消するためには、国際社会全体の協力が不可欠です。
しかし、各国の利害が対立し、協力が進まない場合があります。
特に、開発途上国が国際的な意思決定の場で十分な発言権を持てないことが、経済的不平等をさらに深刻化させています。
国際的な協力を強化し、開発途上国の声を反映させる仕組みが必要です。
データとモニタリングの不足
不平等の問題を正確に把握し、効果的な政策を実施するためには、信頼性の高いデータと継続的なモニタリングが必要です。
しかし、多くの国では、所得や資産の分布、差別の実態などに関するデータが不足しており、政策の効果を評価することが難しい状況です。
データ収集と分析の体制を整備し、政策の効果を検証する仕組みを構築することが重要です。
人や国の不平等をなくそうに取り組む企業3選

人や国の不平等をなくそうに取り組む企業を紹介します。
≫【SDGs目標10】人や国の不平等をなくそうに取り組む企業10選!就職・転職におすすめの大企業からベンチャー
株式会社デジリハ
株式会社デジリハは「リハビリを、アソビに」をビジョンに、デジタルリハビリツールの開発や普及に取り組んでいます。
大学や病院、リハビリテーションセンターなどと共同で研究を進め、国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO)の2023年度SBIR推進プログラムに採択されたことにより、オリジナルデバイスの開発にも着手。
数々の賞を受賞し、注目を集めています。
HP:https://www.digireha.com/
合同会社Ledesone
合同会社Ledesoneは、発達障害をはじめとする周囲からは見えづらい困りごとや特性を持つ当事者と共創するインクルーシブデザインを展開する会社です。
Ledesoneという名称は、イタリア語で「アイディアは無限大」という意味のLe idee sono infiniteが由来で、どんな人にも可能性は無限にあるという意味が込められています。
ミッションは「ひとりひとりが過ごしやすい社会をともにつくる」です。
HP:https://ledesone.com/
株式会社バオバブ
株式会社バオバブは、AI学習データの作成やアノテーションを事業とする会社です。
住んでいる地域に関わらず、障がいのある人、育児・介護中などさまざまな事情で通勤が困難な人や働きづらさを抱える人に在宅での就労の機会を提供しています。
ていねいなコミュニケーションと独自のサポート体制で、未経験者も安心して取り組むことが可能。
社会とつながり、貢献しているという自己有用感を高めています。
HP:https://baobab-trees.com/
人や国の不平等をなくそうに対して私たちができること5選

「人や国の不平等をなくそう」という目標は、国際社会全体で取り組むべき重要な課題ですが、私たち個人にもできることがたくさんあります。
以下に、具体的な5つの行動とその解説を紹介します。
フェアトレード商品を選ぶ
フェアトレードとは、開発途上国の生産者が適正な報酬を得られるよう支援する貿易の仕組みです。
フェアトレード商品を選ぶことで、生産者の生活水準が向上し、経済的な不平等を解消する一助となります。
例えば、コーヒーやチョコレート、衣類など、日常的に購入する商品の中にはフェアトレード認証を受けたものが多くあります。
消費者が意識的にこれらの商品を選ぶことで、持続可能な経済活動を支援できます。
≫レインフォレストアライアンスとは?意味や他の認証との違いをわかりやすく解説
寄付やボランティアに参加する
貧困層や社会的弱者を支援する団体に寄付をしたり、ボランティア活動に参加したりすることも、不平等を解消するための有効な手段です。
寄付は、教育や医療、食料支援など、直接的に人々の生活を改善するために使われます。
また、ボランティア活動に参加することで、現地の状況を理解し、問題解決に向けた具体的な行動を起こすことができます。
例えば、地域のフードバンクや教育支援プログラムに参加するなど、身近なところから始めることができます。
差別や偏見をなくす意識を持つ
日常生活の中で差別や偏見に気づいたら、声を上げて是正を促すことが重要です。
性別、人種、宗教、障害などによる差別は、社会的な不平等を生み出す大きな要因です。
私たち一人ひとりが差別や偏見に対して敏感になり、それを許さない態度を示すことで、社会全体の意識を変えることができます。
例えば、職場や学校で差別的な発言や行動を見かけたら、それを指摘し、正しい方向に導くことが大切です。
情報を発信する
SNSやブログなどを活用して、不平等の問題について発信し、周囲の関心を高めることも重要な行動です。
情報を発信することで、多くの人々に問題の存在を知らせ、解決に向けた行動を促すことができます。
例えば、特定の地域やグループが直面している不平等な状況についての記事をシェアしたり、自分が参加したボランティア活動の体験を発信したりすることで、問題の認知度を高めることができます。
≫【2024年最新版】社会課題やSDGs、サステナブルについて発信するメディア30選!
≫レポートで書きやすいSDGsのテーマ10選!テーマの選び方や参考になる調査を解説
持続可能な消費を心がける
環境や社会に配慮した商品を選び、持続可能な消費を実践することも、不平等を解消するための一歩です。
持続可能な消費とは、資源を無駄にせず、環境や社会に悪影響を与えない商品やサービスを選ぶことです。
例えば、リサイクル製品を選ぶ、地元の生産者から直接購入する、過剰包装を避けるなど、小さな行動が大きな変化につながります。
持続可能な消費を心がけることで、経済的・社会的な不平等を減らすことができます。
≫地産地消のメリット5選!デメリットやSDGs・6次産業との関係も解説
≫エシカル消費とは?企業の取り組み事例や私たちができることを解説
≫リサイクル(3R)とは?例を用いて意味をわかりやすく解説!
まとめ
「人や国の不平等をなくそう」は、SDGsが掲げる重要な目標の一つです。
世界中で依然として深刻な不平等が存在していますが、私たち一人ひとりが意識を変え、行動を起こすことで、この問題を解決することができます。
フェアトレード商品を選ぶ、寄付やボランティアに参加する、差別や偏見をなくす意識を持つなど、日常生活でできることから始めてみましょう。
誰もが公平な機会を得られる社会を実現するために、私たちの力が必要です。
【その他のSDGsの目標を詳しく知りたい】
【SDGs目標1】貧困をなくそうとは?背景や現状、企業の取り組み、私たちにできることを解説
【SDGs目標2】飢餓をゼロにとは?背景や現状、企業の取り組み、私たちにできることを解説
【SDGs目標3】すべての人に健康と福祉をとは?背景や現状、企業の取り組み、私たちにできることを解説
【SDGs目標4】質の高い教育をみんなにとは?背景や現状、企業の取り組み、私たちにできることを解説
【SDGs目標5】ジェンダー平等を実現しようとは?背景や現状、企業の取り組み、私たちにできることを解説
【SDGs目標6】安全な水とトイレを世界中にとは?背景や現状、企業の取り組み、私たちにできることを解説
【SDGs目標7】エネルギーをみんなに そしてクリーンにとは?背景や現状、企業の取り組み、私たちにできることを解説
【SDGs目標8】働きがいも経済成長もとは?背景や現状、企業の取り組み、私たちにできることを解説
【SDGs目標9】産業と技術革新の基盤を作ろうとは?背景や現状、企業の取り組み、私たちにできることを解説
【SDGs目標10】人や国の不平等をなくそうとは?背景や現状、企業の取り組み、私たちにできることを解説
【SDGs目標11】住み続けられるまちづくりをとは?背景や現状、企業の取り組み、私たちにできることを解説
【SDGs目標12】つくる責任つかう責任とは?背景や現状、企業の取り組み、私たちにできることを解説
【SDGs目標13】気候変動に具体的な対策をとは?背景や現状、企業の取り組み、私たちにできることを解説
【SDGs目標14】海の豊かさを守ろうとは?背景や現状、企業の取り組み、私たちにできることを解説
【SDGs目標15】陸の豊かさも守ろうとは?背景や現状、企業の取り組み、私たちにできることを解説
【SDGs目標16】平和と公正をすべての人にとは?背景や現状、企業の取り組み、私たちにできることを解説
【SDGs目標17】パートナーシップで目標を達成しようとは?背景や現状、企業の取り組み、私たちにできることを解説

この記事の監修者
吉田宏輝
COCOCOLOREARTH代表、社会活動家。
COCOCOLOREARTHでは、社会課題解決を軸にした就職・転職活動を支援するインタビューメディアの代表として、100人以上の社会活動家にインタビュー、記事執筆やイベント登壇などを行う。